ふるさと納税をするたびに、楽天ポイントがつくのを楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか?
楽天グループが「ふるさと納税でのポイント付与を禁止する総務省の告示は違法だ」として、ついに東京地裁へ訴訟を起こしました。
総務省が2025年10月からポイント制度を全面禁止すると発表したことに対し、楽天は「制度の普及を支えてきたのに!」と真っ向から反論。
この記事では、この制度変更が何を意味するのか、ふるさと納税の未来や地方経済への影響まで、わかりやすく解説していきます。
はじめに
楽天が行政訴訟を提起した背景とは?
ふるさと納税を利用したことがある方なら、「楽天ふるさと納税」というサービス名を聞いたことがあるかもしれません。
楽天の特徴は、寄付時に楽天ポイントが付与されるという点で、多くの利用者にとって“お得感”のある仕組みとして親しまれてきました。
しかし2024年6月、総務省が制度の見直しを行い、「寄付に対するポイント付与は禁止する」と告示。
この告示が2025年10月から施行されることを受け、楽天グループは「これは違法だ」として東京地裁に訴えを起こしました。
楽天側は「ポイント制度がふるさと納税の普及に貢献してきた」と主張し、ネット上では支援の署名活動も活発化しています。
単なる経済的対立というよりも、国と企業、地方自治体と市民の関係性が問われる事態となっています。
ふるさと納税制度と民間企業の関わり
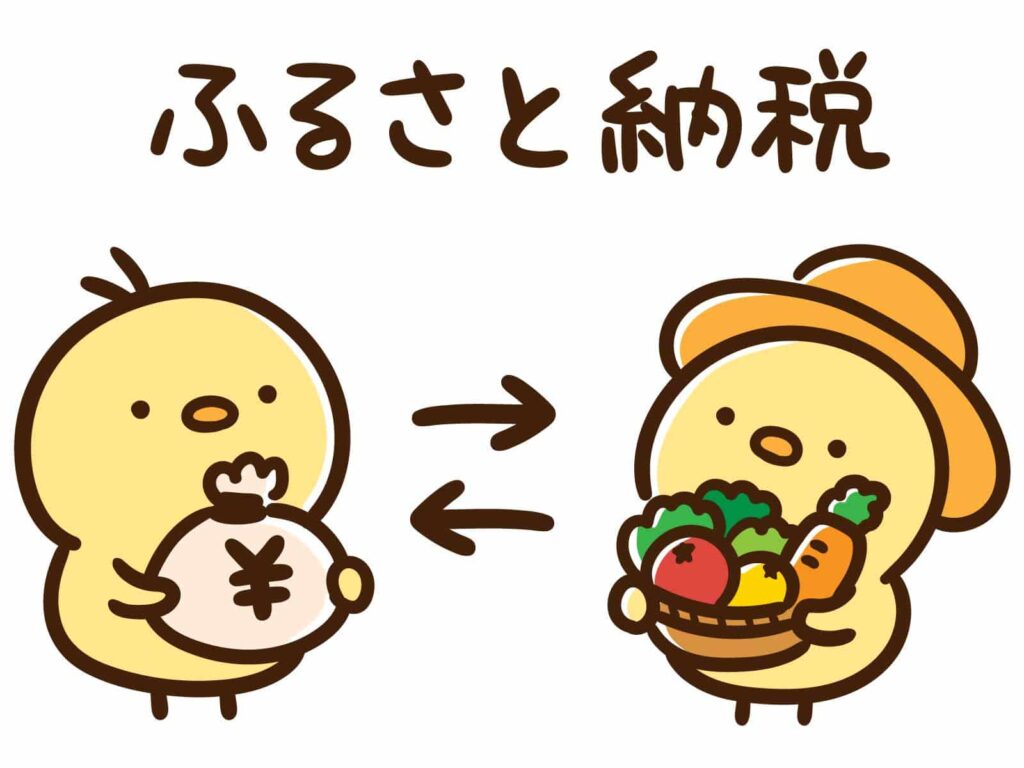
そもそも、ふるさと納税とは、住民税や所得税の一部を自分の選んだ自治体に寄付できる制度です。
返礼品という地域の特産品が魅力となり、利用者数は年々増加。楽天やYahoo!などの民間ポータルサイトがこの制度の広がりに大きく寄与してきました。
楽天ふるさと納税では、寄付者が商品を探しやすく、決済も簡単。加えてポイント還元があることで、「ふるさとを応援しながらポイントも貯まる」という一石二鳥のサービスでした。
しかし、こうした“お得感”が一部で過剰競争を生み、制度本来の趣旨から外れているのではないか、という声もあります。
今回の訴訟は、単なるポイントの話にとどまらず、国と企業、地方との協力体制の在り方そのものを問う重要なテーマといえます。
1.ポイント付与禁止の経緯と総務省の告示内容
総務省のふるさと納税指定基準見直し(2024年6月)
ふるさと納税をめぐっては、年々その規模と影響力が大きくなる中で、制度の透明性や公平性が課題として取り上げられてきました。
2024年6月、総務省はその見直しに踏み切り、ふるさと納税の運用ルールの厳格化を発表しました。
この見直しの大きな柱が、「寄付に応じたポイント付与の全面禁止」です。
背景には、返礼品競争に加えて、ポータルサイトによるポイント還元合戦が激化し、制度の趣旨から逸脱しているという批判がありました。
特に楽天やYahoo!など大手企業が自社ポイントを還元することで、寄付行動が「地域貢献」ではなく「買い物感覚」になっているとの懸念も指摘されていました。
2025年10月からの全面禁止方針とは?
総務省は、2025年10月以降、ふるさと納税に関連してポイントを付与する仕組みを用いた寄付募集を一律で禁止すると明言しました。
これには、「楽天ふるさと納税」や「さとふる」など、ポイントを活用して利用者を呼び込んでいたポータルサイトが該当します。
たとえば、ある自治体に寄付すると、3万ポイント近くの楽天ポイントが還元されるといったケースも存在し、実質的に「割引付き通販」と変わらないような感覚を与える側面もありました。
このような「過度なインセンティブ」が、寄付の本来の目的である「地域支援」から逸れてしまうというのが、総務省側の立場です。
告示による規制の根拠と総務大臣の裁量権
今回のポイント付与禁止は、法改正を経たものではなく、「総務省告示」という形で定められています。
つまり、法律そのものが変わったのではなく、行政の裁量によって運用ルールが変えられたということです。
この点について楽天は、「地方税法に基づく制度運用の範囲を逸脱している」と強く反発しています。
特に問題視されているのが、国会での議論や法的手続きを経ずに、行政の一方的な判断で広範な民間活動を制限しようとしていることです。
楽天は「これは総務大臣の裁量権の乱用であり、告示そのものが無効である」と主張し、訴訟に踏み切りました。
今回の見直しが単なる制度調整なのか、それとも憲法に保障された「営業の自由」への過剰な介入なのか――その判断は、今後の司法の判断に委ねられることになります。
2.楽天グループの主張と訴訟の論点

「ポイント付与は制度の普及に貢献」とする楽天の見解
楽天グループは、ポイント付与の仕組みこそがふるさと納税の認知と普及に大きく貢献してきたと主張しています。
たとえば、初めてふるさと納税を利用する人にとって、楽天ポイントの付与は「使ってみよう」と思う後押しになったという声も多く見られます。
楽天によれば、寄付件数や寄付金額の大幅な増加には、この「利便性」や「お得感」が重要な役割を果たしており、単なるマーケティング手法以上の意味を持っていたというのです。
また、楽天はポータルサイトを通じて、寄付先の自治体の情報をわかりやすく届ける役割も果たしており、これにより全国の過疎地や小規模自治体にも寄付が広がるなど、地域経済の活性化にも貢献してきたとしています。
つまり、楽天は単なる“儲けの手段”ではなく、“制度の定着と発展の担い手”であるという立場なのです。
地方税法の委任範囲を逸脱しているという主張
楽天が最も強く訴えているのが、総務省による今回のポイント付与禁止が「法律に基づいていない」という点です。
ふるさと納税の制度は、地方税法に基づき運用されており、ポイントの付与を明確に禁止する条文は存在しません。
それにもかかわらず、国会での議論や法改正を経ずに、総務省が告示という形で禁止措置を決定したことについて、楽天は「行政の暴走」ともいえる対応だと批判。
特に、「制度のルールを変えるなら、きちんと法的手続きを踏むべきだ」と訴えており、この点が訴訟の大きな争点となっています。
実際、過去にも政府による告示や通達が問題視され、裁判で「違法」とされた例は少なくありません。
今回のケースでも、地方税法の委任の範囲を超えていると判断されれば、告示そのものの有効性が問われることになります。
営業の自由への過剰規制という訴え
楽天はさらに、今回の全面禁止が「企業の営業の自由を不当に侵害している」とも主張しています。
たとえば、飲食店が「ドリンク1杯無料」といったサービスを提供するように、楽天のポイント付与も一種の販促活動に過ぎないという考えです。
これを一律に禁止することは、企業が自らの裁量で行ってきた営業戦略を否定するものであり、過度な行政介入であるというわけです。
また、これまで総務省がある程度黙認してきたにもかかわらず、突然全面禁止に踏み切ったことについても、「事業者との信頼関係を壊す行為」として強い不満を表明しています。
今後、他のポータルサイトや自治体からも同様の訴えが出る可能性があり、この問題はさらに広がる可能性をはらんでいます。
3.ふるさと納税の今後と地方創生への影響
ポイント制度廃止による寄付者減の懸念
ポイント付与の禁止によって、寄付者のモチベーションが低下するのではないかという懸念が高まっています。
これまで、楽天ふるさと納税では、寄付金に対して楽天ポイントが還元されることで、実質的に「返礼品+ポイント」という二重のメリットがありました。
たとえば、1万円の寄付で地方の美味しいお米がもらえ、さらに100ポイント以上の楽天ポイントも付いてくる。こうした“お得感”がリピーターの獲得に大きく貢献していたのです。
しかし今後、このポイント還元がなくなれば、寄付者側にとっての直接的なインセンティブは減少します。
「どうせ同じ返礼品ならポイントがつくサイトから寄付したい」という心理が働いていた層が離れてしまう可能性は否定できません。
結果として、自治体への寄付額の減少や、特に知名度の低い小規模自治体への支援が減ることが懸念されます。
地方創生2.0と関係人口創出への影響
政府が掲げる「地方創生2.0」では、単なる人口移転ではなく、関係人口──すなわち、地域とゆるやかにつながる人々──の創出が重視されています。
ふるさと納税はこの理念と非常に相性がよく、寄付者が自治体からの手紙や特産品を通じて「ふるさと」との絆を感じ、観光や移住といった次のステップにつながる可能性も生まれていました。
楽天などのポータルサイトは、地域ごとのストーリーや特産品の背景を紹介するなど、自治体と寄付者の距離を縮める努力を重ねてきました。
ポイント制度がその第一歩を後押ししていた面もあるだけに、それが失われることで、関係人口の創出が鈍化するのではないかという懸念が広がっています。
寄付額の将来予測と制度の持続可能性
楽天グループは、現在のふるさと納税の寄付額が今後ピークアウトすると予測しています。
実際、制度が始まってから十数年が経過し、多くの自治体では「寄付者の取り合い」ともいえる状態が続いています。
今後、人口減少や高齢化の影響で、寄付者そのものが減っていく可能性は高く、いま以上の成長は見込めないとする見方も現実味を帯びてきました。
そんな中、制度を維持・発展させるためには、「いかにして寄付者を呼び込み、継続してもらうか」がカギとなります。
ポイント制度は、その答えの一つでした。
もちろん制度の健全性も重要ですが、寄付者の心理や動機づけを無視しては成り立ちません。今回の全面禁止は、そのバランスを大きく崩すおそれがあり、制度そのものの持続性を揺るがしかねない決断といえるでしょう。
まとめ
楽天グループによる行政訴訟は、単なるビジネス上の争いにとどまらず、「ふるさと納税」という制度の根幹に関わる議論を社会に投げかけるものとなりました。
ポイント制度の廃止がもたらす影響は、寄付者の行動にとどまらず、自治体の財源確保や地域活性化、さらには「地方創生2.0」の実現にまで及びます。
制度を健全に保つためのルール作りと、寄付者や事業者の創意工夫が共存できる仕組みはないのか。
今回の訴訟を通して、国と企業、地方自治体、そして私たち一人ひとりが、ふるさと納税の「これから」を考えるタイミングが来ているのかもしれません。

コメント