モバイルオーダー上で「ありがとう」の気持ちをチップとして送れる——そんな新機能を、飲食店向けサービス「ダイニー」が導入したことをご存じですか?
「えっ、日本でもチップ文化が始まるの?」と驚いた方もいるかもしれません。実は今、外食業界は深刻な人手不足とコスト高に悩まされ、これまでの常識が少しずつ揺らぎ始めているのです。
一方で、チップ制度には「賃金を補うものとして依存されるのでは?」「日本の慣習に合わない」といった懸念の声も少なくありません。
この記事では、一般市民である筆者の視点から、ダイニーのチップ機能が誕生した背景や意義、そしてSNS上での賛否、制度としての課題までを、わかりやすく解説していきます。
「ありがとう」のカタチは、これからどう変わるのでしょうか?一緒に考えてみませんか。
はじめに
モバイルオーダーで“チップ”が送れる時代に
「ごちそうさま」の気持ちをスマホで伝える時代がやってきました。株式会社ダイニーが提供するモバイルオーダーサービス「ダイニー」では、2025年6月から会計時にチップを贈れる新機能が追加され、利用者の間で話題を呼んでいます。
レジで直接やり取りすることなく、スマホの画面上で「ありがとう」の気持ちを形にできるという、これまでにない仕組みです。
このチップ制度は、日本ではあまり馴染みのない文化である分、SNSでは「賃金を払うのは企業の責任では?」「チップという名の値上げでは?」など、否定的な声も少なくありません。
一方で、苦境に立たされている飲食業界を支える新しい選択肢として、静かに期待を寄せる声も広がり始めています。
飲食業界の苦境とチップ制度導入の背景
日本の外食産業は今、かつてない厳しさに直面しています。2025年上半期だけでも、負債1000万円以上の飲食関連倒産は458件と、前年を上回る勢い。
背景には、人件費や光熱費の高騰に加え、値上げによる客離れへの不安があり、利益率は年々下がり続けています。
その結果、サービス品質は維持しながらも、従業員の賃金アップには踏み切れないというジレンマを抱える店舗も多数。
そんな中で「チップ」という制度は、客側の自発的な応援として、従業員や店舗の支えになる可能性を秘めています。
飲食店のサービスは「無料」であることが常識とされてきた日本において、感謝を直接伝える手段として、今まさに新たな一歩を踏み出そうとしているのです。
1.なぜ今、チップ制度なのか?

外食業界を襲うコスト高と倒産増加の現実
2025年上半期、負債1000万円以上の法的整理による外食業界の倒産件数は458件にのぼり、前年同期を上回る結果となりました。
これは3年連続での増加であり、飲食店を取り巻く経済環境がいかに厳しいかを物語っています。
特にラーメン店、焼き肉店、居酒屋といった中小規模の飲食業態で倒産が相次ぎ、「大倒産時代」とさえ言われる状況です。
その背景にあるのが、原材料費や人件費、光熱費といったコストの高騰です。多くの店舗が売上は維持していても、支出の増加により経営が立ち行かなくなっているのが実情です。
値上げに踏み切れない飲食店のジレンマ
コスト上昇に対して本来取られるべき対策は「値上げ」ですが、現実にはそう簡単に実行できません。
物価上昇が続く中、消費者はますます価格に敏感になっており、少しの値上げでも客足が遠のくリスクを抱えています。
とくに、カジュアルな飲食店や日常的に利用されるお店では、値上げが売上減に直結する可能性が高いため、泣く泣く現状価格を維持しながら、薄利での営業を余儀なくされているケースも多いのです。
こうした状況下で、スタッフの給与を上げる余裕がないという声も多数聞かれます。
チップという“自主的支援”が持つ可能性
このような苦境を打開するための手段として、注目されているのが「チップ制度」です。
あくまで任意で、感謝の気持ちを込めて贈るというスタイルのチップは、価格設定を動かすことなく、サービス提供者のモチベーションや報酬アップに貢献できる仕組みです。
ダイニーのチップ機能は、モバイルオーダーの会計画面から簡単に送れる設計になっており、「ありがとう」の気持ちをさりげなく伝える新しい選択肢を提供しています。
強制ではなく、“気持ちを届けたい”という人だけが使える仕組みである点も、批判の声を和らげるポイントとなっています。
厳しい状況にある飲食業界のなかで、こうした自発的な応援スタイルが徐々に根付くことができれば、現場のスタッフや経営者にとって大きな力になるかもしれません。
2.ダイニーのチップ機能とは?

モバイルオーダー上で簡単に感謝を形に
ダイニーが導入したチップ機能は、会計時にワンタップで感謝の気持ちを伝えられる仕組みです。
モバイルオーダー上の「支払い画面」にチップ選択項目が表示され、100円、200円、任意の金額など、数パターンから自由に選べる形式になっています。
例えば、接客が気持ちよかった、料理が特に美味しかった、混雑の中でも丁寧に対応してくれた——そんなちょっとした感動を、現金ではなくスマホでさっと伝えられるのがこの機能の強みです。
店側も、このチップが従業員のインセンティブとなるよう工夫しており、支給ルールや活用方法は各店舗で自由に設定可能です。
実際に導入している飲食店からは、「モチベーションが上がった」「小さな気遣いが評価されてうれしい」といったスタッフの声があがっているといいます。
強制ではない“贈りたくなる設計”の工夫
チップ制度と聞くと、「結局払わされるのでは?」という不安を持つ人も少なくありません。
けれど、ダイニーのチップ機能はあくまで“任意”で、チップの案内は控えめ。目立つポップアップや派手なアラートは使わず、「贈っても贈らなくてもいい」という中立的な表示を徹底しています。
また、店ごとに「このチップは◯◯のために活用されます」といった簡単なメッセージが添えられており、寄付のように“誰かのためになる実感”を得やすいのも特徴のひとつです。
こうした丁寧な設計により、「見返りを求めない感謝」が気持ちよく循環する環境づくりがなされています。
サービスは“無料”であるべきなのか?
日本では、外食時のサービスは「料金に含まれているもの」「タダで当たり前」という感覚が根強くあります。
しかし実際には、笑顔の接客や、気配りのある配膳、お見送りまでの丁寧な応対など、多くの“目に見えない努力”が現場では積み重ねられています。
海外ではこうしたサービスに対してチップを渡す文化が定着していますが、日本ではその労力が「無償奉仕」として扱われがちです。
今回のチップ機能は、こうした状況に一石を投じる取り組みともいえるでしょう。
「ありがとう」をお金で表すのは気が引ける——そう思う人が多いかもしれませんが、実際に使ってみると、「想像以上に自然だった」との声もあり、価値観の変化を促す小さな一歩として注目されています。
3.SNSの反応と今後の展望
賛否両論ある中で浮かび上がる価値観のズレ
ダイニーのチップ機能が導入されて以降、SNSではさまざまな反応が飛び交っています。
「スタッフに直接感謝が伝えられて素敵」「少額でも応援できる仕組みはありがたい」といった前向きな声がある一方、「それは企業が払うべき給与では?」「日本にチップ文化を根付かせるのは違和感」といった批判的なコメントも多く見られました。
この意見の分かれ目にあるのが、“サービスは対価を払うものである”という価値観と、“気持ちの問題として感謝を伝える行為”としてのチップ観のズレです。
とくに「企業努力が足りないのにチップを求めるのは筋違い」とする声は根強く、背景には賃金の低さや物価高への不満も透けて見えます。
現場スタッフの努力と報われにくさ
日々笑顔を絶やさず、暑い日も寒い日も丁寧な接客をしている現場スタッフたち。
しかしその頑張りが、なかなか目に見える形で評価されづらいのが日本の飲食業界の実情です。サービス料が含まれていない場合、どれだけ丁寧に応対しても収入には反映されにくく、やりがいの維持が難しいという声もあがっています。
ある居酒屋の店員は、「常連さんに“今日もありがとう”って言われるのがうれしいけど、チップをもらえると“本当に役に立てたんだな”と感じられる」と話します。
こうしたエピソードからも、チップ制度が金銭以上の意味を持つことがうかがえます。
中小個店を守るチップ制度の役割と可能性
チップ機能は、大手チェーンよりも中小の個人店にこそ恩恵が大きい仕組みといえるでしょう。
資金力の乏しい個店では、値上げが客離れに直結するリスクが大きく、コスト上昇分を吸収する余裕がありません。そんな時、チップという任意の収入源は、店舗の経営だけでなくスタッフの待遇向上にもつながる可能性を持っています。
今後、チップ文化が日本にどのように根づいていくかは未知数です。ただ、サービスの価値を見直し、「ありがとう」を伝える手段が選べる社会へ向かうことは、多くの人にとってポジティブな変化となるはずです。
4.チップ制度に対する懸念と課題
チップが賃金抑制につながるという懸念も
ここまで読んで、「でもそれって本来、企業がきちんと給料を払うべきでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、チップ制度を導入することで、企業側が「どうせお客さんがチップをくれるだろう」と賃金を抑えるようになるのでは…という心配の声も多く聞かれます。
特に、すでに基本給が低く設定されている職場では、この傾向が強まるおそれもあるのではないでしょうか。
欧米でも見直しの動きが進むなかで
海外ではチップ文化が根付いているイメージがありますが、最近では「面倒」「不透明」といった理由から、あらかじめサービス料を料金に含める方式に見直す動きも出ています。
例えばレストランで「サービス料込み」と表示されていれば、いちいちチップを計算せずに済みますし、お客側も気が楽ですよね。
実際、日本を訪れた外国人観光客が「チップが要らないのが助かる!」と感動していたという話も聞いたことがあります。
日本の“全員接客”の現場での不公平さ
欧米では基本的に、テーブルごとに専属のスタッフがサービスを提供します。そのため、チップもその人個人に渡る仕組みです。
でも日本では、ホールのスタッフみんなで協力して接客することが多く、「この人が担当」という明確な線引きがありません。
だからこそ、チップを渡すとなると「誰に?どうやって?」と迷ってしまいますし、バックヤードで働いている人たちには届きにくいという不公平さも感じてしまいます。
さらに、チップをめぐってスタッフ同士で競争が生まれてしまったり、チップを多くもらうために無理に笑顔を作ったりと、ギスギスした職場になるのでは?という不安も…。
これはもう、接客というよりホストやキャバクラと同じ構図になってしまいそうです。「これだけチップを払ったのに何もなし?」といった常連客とのトラブルも起きかねません。
税制・申告の問題も無視できない
もうひとつ重要なのが、税金の問題です。海外ではチップをきちんと「所得」として申告する制度が整っていますが、日本ではまだまだ整備が追いついていません。
チップが雑所得扱いになるケースもあり、受け取った側が確定申告をしなければならないことも…。
こうした税務面のルールが曖昧なまま制度を広げてしまうと、思わぬトラブルに発展するかもしれません。
私自身の正直な気持ちとしては…
個人的には、チップのあるお店ってちょっと面倒に感じてしまいます。
「いくら渡せばいいんだろう?」「少なすぎたら失礼かな?」なんて考えてしまって、素直に食事を楽しめない気がして…。
だったら最初から「サービス料10%込みです」と明示してもらえた方が、よっぽどスッキリすると思います。
もちろん、感謝の気持ちは大切にしたいです。でも、その気持ちが“金額”になった瞬間に、なんだか変なプレッシャーを感じてしまうのも正直なところです。
まとめ
ダイニーが導入したモバイルオーダー上のチップ機能は、日本の飲食文化に新たな風を吹き込む試みです。
値上げが難しい現状の中で、客の「ありがとう」を形にする仕組みは、スタッフのやりがいを支え、中小個店の経営にも貢献し得る存在となっています。
もちろん、SNS上での賛否は今後も続くでしょう。
しかし、強制ではないチップの仕組みは、誰かの善意に支えられる持続可能な支援のかたちです。サービスに込められた努力に報いる手段を選べる社会は、多様性や個人の選択を尊重する社会でもあります。
苦境にある飲食業界にとって、チップ制度は“感謝の循環”を生む希望の一手となるかもしれません。
気持ちを伝える手段として、こうした選択肢が広がっていくことに、今後も注目していきたいところです。
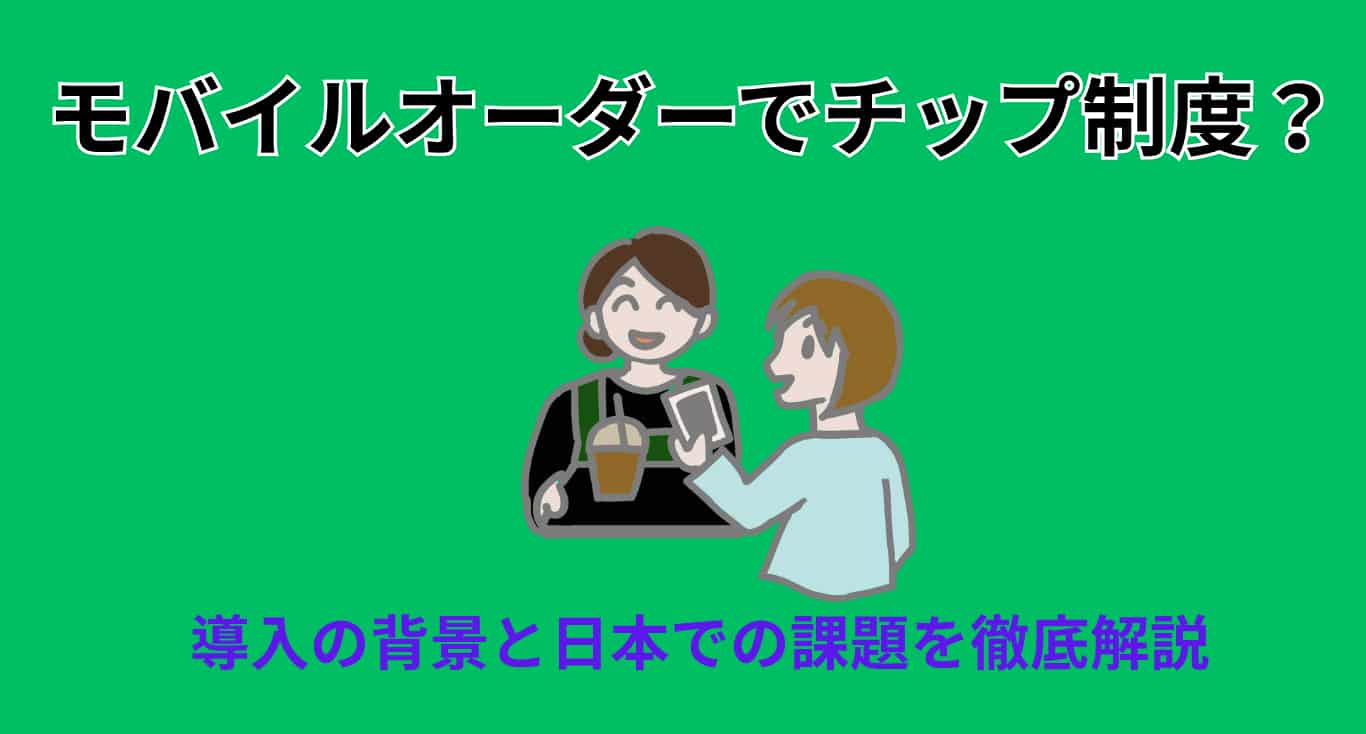
コメント