選挙期間中、「いつ襲われるか分からない」と本気で怯える候補者がいます。
その原因は、SNS上で繰り返し拡散される事実無根のデマや執拗な誹謗中傷。
ポスターは破られ、演説中に怒鳴られ、家族までも標的にされる――。
本来、有権者と候補者をつなぐはずのSNSが、いまや“攻撃の道具”として使われる現実に、私たちはどれだけ目を向けているでしょうか。
この記事では、ある女性候補者が直面したSNS被害の実態を通して、民主主義に潜む新たな危機を考えます。
はじめに
SNSが選挙にもたらす光と影
いまや選挙においてSNSは欠かせないツールとなっています。候補者が日々の活動を発信し、有権者と直接つながれる場として、街頭演説や新聞とは異なる新たなコミュニケーションの手段として定着しました。
たとえば、政策の詳細をSNSで補足説明したり、質問にその場で返答することで、候補者の考えや人柄が伝わりやすくなったという声もあります。
一方で、SNSには光の部分だけでなく「影」の側面もあります。情報が瞬時に拡散する仕組みは、誤情報や悪意ある投稿に対しても同様に働きます。誰でも自由に発言できる環境だからこそ、根拠のないデマが事実のように広まり、候補者を攻撃する手段として使われることもあります。
誹謗中傷とデマが候補者を追い詰める現実
今回の東京都議会議員選挙では、実際に「人身売買をしている」といった根拠のないデマがSNS上で広まり、候補者が街頭で怒鳴られるという深刻な被害が発生しました。
駒崎美紀さんはその標的となり、「いつ襲われるか分からない」という恐怖を抱えながら選挙活動を行いました。
彼女の夫が運営するNPO法人に対する誤解から始まったデマは、本人への直接的な攻撃へと発展し、家族や支援者にも不安を与えました。
このような状況は一部の候補者だけの問題ではありません。SNSでの誹謗中傷やなりすましアカウント、デマの拡散が常態化すれば、「立候補すると攻撃される」という印象が広がり、次世代の政治家を志す人が二の足を踏むようになるかもしれません。
SNSがもたらす利便性と危険性。私たちが直面しているのは、民主主義の土台そのものに関わる重大な課題です。
1.駒崎美紀さんを襲ったSNSデマの実態
夫の活動をめぐる誤情報の拡散
駒崎美紀さんが攻撃の対象となったきっかけは、夫の活動をめぐる根拠のないうわさでした。
彼女の夫は、特別養子縁組を支援する認定NPO法人の代表を務めています。本来、親のいない子どもたちに安定した家庭を提供するという社会的に意義のある取り組みを行っているはずの活動が、SNS上でねじ曲げられ、「海外に赤ちゃんを売って金儲けしている」といったデマが出回り始めたのです。
このデマには、事実確認や背景の理解が一切ありませんでした。
夫のNPO法人は海外への養子縁組の実績がないにもかかわらず、「外国人への売買」という根拠のない情報が繰り返し投稿され、画像付きで拡散されていきました。
「炎上狙い」や「センセーショナルな話題を求める」SNSの特性が、正しい情報よりも過激な嘘を拡大させてしまった典型例です。
街頭演説中の暴言と恐怖体験
やがてデマはネットの中だけにとどまらず、現実の選挙活動の場にも影響を及ぼしました。
昨年7月の都議補欠選挙では、駒崎さんが街頭演説をしている最中、通行人の男性から「お前の夫は人身売買してるだろ!」と怒鳴られる場面が何度も発生。
衆人環視の中で大声を浴びせられる状況は、言葉にできない恐怖と屈辱を伴うものだったといいます。
さらに、支援者の自宅には落書きされたチラシが投函されるなど、駒崎さんを支持する人たちにも悪影響が及びました。
日々の活動において、「今日は何が起きるだろう」と怯えながら選挙を続けなければならなかった駒崎さんの精神的負担は、想像を超えるものだったでしょう。
選挙妨害とSNSなりすましアカウントの被害
選挙本番を迎えても、SNS上の攻撃は止むことはありませんでした。
駒崎さんの写真や名前を無断で使い、「本人になりすました」偽アカウントが登場。そこから発信された内容は、彼女の立場や主張を貶める内容ばかりで、意図的に印象操作を狙ったものと見られます。
さらに、街頭に貼られた選挙ポスターが破られたり、消失していたりする事態も発生しました。
こうした物理的な妨害は公職選挙法にも抵触する違法行為ですが、犯人を特定するには多くの証拠と人手が必要で、すべてに対応するのは現実的に難しいのが実情です。
駒崎さんは選挙戦を勝ち抜き、最終的にトップ当選を果たしましたが、選挙を通じて受けた心の傷は深く、「本当に信じてほしいこと」がデマに埋もれてしまったという無力感を滲ませています。
はじめに
SNS上で拡散された「NPO法人フローレンスが人身売買に関与している」といった主張をご存じでしょうか?
この話題は、2024年〜2025年にかけてSNSや一部ブログ、動画などで大きく拡散され、特に東京都議会議員選挙に立候補した駒崎美紀さん(フローレンス代表・駒崎弘樹さんの妻)にも影響を及ぼしました。
しかし、この「人身売買」疑惑は完全なデマであり、すでに法的にも否定されている虚偽情報です。この記事では、なぜこのような誤解が生まれたのか、事実と背景を分かりやすくまとめます。
ベビーライフと日本こども縁組協会の関係
誤情報の多くは、「フローレンスが過去に人身売買的な活動をしていた」という誤解から始まっています。その発端となったのが、NPO法人ベビーライフとの関係です。
事実として、フローレンスは2016年、ベビーライフなど複数の団体と共に「日本こども縁組協会」を共同設立しました。この協会は、特別養子縁組制度を整え、子どもに安定した家庭を届けるために活動している団体です。
設立の記者会見には、駒崎弘樹さん(フローレンス)と篠塚康智さん(ベビーライフ)が並んで登壇していますが、それは同じ志を持った協力関係にあったからです。
海外への養子縁組や人身売買の事実は?
この協会やフローレンスの活動について、一部のSNSでは「海外に赤ちゃんを売って金儲けしている」といった誤解が拡散されました。しかし、フローレンスは公式に「海外養子縁組の実績はゼロ」であると明言しており、実際にも一件も行っていません。
駒崎弘樹さん自身もnoteやSNSで繰り返し説明し、事実無根であることを証明するために法的措置を取りました。実際、誤情報を流した弁護士はその後謝罪し、懲戒処分を受けています。
なぜここまで誤解が広まったのか
このようなデマが広がった背景には、SNSの特性があります。
「センセーショナルな情報」が好まれる傾向にあり、真偽を確かめずに拡散されることで、あたかも真実のように誤解されてしまうのです。
さらに、ベビーライフが以前に行政指導を受けたことなどが、まったく関係のないフローレンスにも影響を与えてしまいました。「関係があるから、同じ問題を抱えているはずだ」とする短絡的な連想が、今回のような誤解を生んだと考えられます。
まとめ:正しい情報を見極める目を
駒崎弘樹さん、そしてフローレンスは、法的にも社会的にも信頼された特別養子縁組支援の実績を重ねてきた団体です。
一方で、SNS上ではその信頼を根拠もなく揺るがすような言説が後を絶ちません。
私たち有権者や市民にできることは、「この情報は本当に正しいか?」と立ち止まることです。そして、信頼できる情報源から確認し、軽々しく拡散しないこと。それが、健全な民主主義と子どもたちの未来を守る第一歩になるはずです。
2.制度の限界と被害の深刻化
公職選挙法の規定と警察の対応
現在の公職選挙法では、候補者に対する虚偽の情報を広めることや、街頭演説を妨害することは明確に禁止されています。
ポスターを破る、貼るのを妨害する、あるいは演説の最中に暴言を浴びせるといった行為は、明らかな違法行為にあたります。
しかし現実には、それらの行為があっても、迅速な対応がなされないケースが少なくありません。
駒崎さんのケースでも、街頭演説中の妨害やSNSでの虚偽情報の拡散について警察に相談したものの、実際に被害届として受理されたのは「選挙ポスターが剥がされた件」だけでした。
他の行為については、証拠の不足や現行法の解釈の限界により、警察が動くには至らなかったのです。法はあっても、運用の壁がある――それが現状です。
被害届が出せない現実と証拠収集の困難さ
SNS上でのデマや誹謗中傷に関しては、「それが誰の発信であるか」が分からないケースも多く、証拠を集める作業が極めて困難です。
投稿が一時的に削除されていたり、匿名アカウントだったりすれば、法的措置に持ち込むためには専門的な知識と時間、そして労力が必要となります。
駒崎さんも、SNS事業者に削除要請を出しましたが、対応してもらえたのはごく一部のみ。
投稿のスクリーンショットやURLを保存していても、「それが本当にその人物からのものであるか」を立証するのは容易ではありません。また、選挙期間中は街頭活動やスケジュール調整で多忙を極め、証拠集めに手を割けないという現実もありました。
このような状況では、「被害があっても声を上げることが難しい」「泣き寝入りせざるを得ない」という構図が生まれてしまいます。SNSで攻撃を受けた候補者が、心身ともに追い詰められるのは避けられない状況です。
法整備の必要性と候補者の孤立
駒崎さんは、自身の経験から「候補者本人やその家族の人権を守るための法整備が急務だ」と語ります。
特に、選挙期間中に集中するSNS上の誹謗中傷やデマについては、削除要請への迅速な対応を義務づけるような仕組みや、悪質な投稿者への抑止となる制度が求められています。
さらに、攻撃を受けた候補者が孤立しないための支援体制も必要です。例えば、証拠保全を手伝う専門スタッフの配置や、選挙管理委員会によるモニタリング体制の強化など、行政が一体となった対応が求められます。
現状では「何か起きても自分で何とかするしかない」と候補者自身が背負う構図になっており、それが立候補への大きなハードルになっているのです。
こうした制度の穴を放置しておけば、将来的に政治の場から優れた人材が失われてしまう恐れもあります。誰もが安心して政治参加できる環境づくりは、民主主義を支える私たち一人ひとりにとっての課題でもあるのです。
3.デマと民主主義──問われるSNSリテラシー
有権者の判断に影を落とす偽情報
選挙での投票行動は、本来、有権者が情報を集め、自分の考えに合った候補者を選ぶという「自己判断」によって成り立っています。
しかしSNSが主な情報源になった今、その判断材料がゆがめられるケースが増えています。今回の駒崎美紀さんのように、事実とは異なる情報が繰り返し拡散され、それを信じた有権者が「間違った候補者像」を信じ込んでしまう現象が起きています。
たとえば、SNSで「人身売買をしている」と書かれた投稿を読んだ人が、それだけを信じて駒崎さんに投票しなかったとしたら――それは民主主義の根幹である「自由で公平な選択」が侵されたことになります。
誤情報に触れた一人ひとりが、真偽を確かめることなく判断してしまう社会では、まともな政策論争も育ちません。
「攻撃」がもたらす立候補の萎縮
デマや誹謗中傷の最大の被害者は候補者本人ですが、それは政治全体の損失にもつながります。
攻撃される恐怖や家族への被害を想像して、「立候補するのはやめよう」と考える人が増えてしまえば、多様な声が政治の場に届かなくなるからです。
とくに子育て中の女性や若手の市民活動家など、これまで政治と距離があった層が「自分も政治に関わりたい」と思っても、SNSでの攻撃やバッシングを目の当たりにすれば、二の足を踏んでしまうのは無理もありません。
駒崎さんも「この状況では誰も立候補しなくなるのでは」と懸念を示しており、実際に彼女自身も強い覚悟と恐怖の中で選挙を戦い抜いています。
SNSが候補者の思いや政策を広く伝えられる手段である一方、その場が「攻撃と中傷の舞台」と化すことで、有望な政治参加者を遠ざけてしまうという深刻な副作用が起きているのです。
SNS時代における選挙文化の再構築
こうした状況を打破するためには、制度面の整備だけでなく、私たち有権者の側の意識も変えていく必要があります。
SNSで見かけた情報をすぐに信じるのではなく、「これは本当か?」「発信元は誰か?」と立ち止まって考えるリテラシーが、民主主義の土台を支える鍵になります。
さらに、SNSに依存するだけでなく、実際に街頭演説を見に行く、候補者の公式サイトで政策を確認する、地域の対話会に参加するなど、自分の目と耳で判断材料を集める習慣も大切です。
拓殖大学の岡田陽介教授が指摘するように、SNSは候補者を知る「入り口」にはなり得ますが、それだけに頼っていては本質が見えません。私たちが情報の受け手として賢くなること――それこそが、デマに左右されない強い民主主義を築く第一歩なのです。
まとめ
駒崎美紀さんが選挙期間中に直面したSNS上のデマや誹謗中傷は、一候補者への攻撃という枠を超え、民主主義の根幹を揺るがす問題を私たちに突きつけました。
事実に基づかない情報が拡散され、それを信じた人々が直接候補者を非難する。その状況は、選挙の自由と公正さを大きく損なうものであり、誰もが安心して立候補できる環境を崩しかねません。
制度の未整備や警察対応の限界が被害の深刻化を招き、候補者が一人で対処せざるを得ない現実があります。
証拠集めや削除要請といった作業は、忙しい選挙期間中には大きな負担であり、法の保護が行き届かないままに被害が放置されるケースも少なくありません。
さらに、私たち有権者の側にも責任があります。SNSに流れる情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、「これは本当か?」と立ち止まって考える姿勢が求められています。
候補者の声を直接聞く機会を大切にし、自分の判断に責任を持つことが、民主主義を支える土台となるはずです。
選挙は、社会をより良くするための出発点です。そして、誰もが安心して立候補できる環境を守ることは、私たち自身の選択肢を守ることにもつながります。デマに惑わされず、真実に耳を傾けられる社会をつくるために――有権者一人ひとりの意識と行動が、これからますます問われていくでしょう。
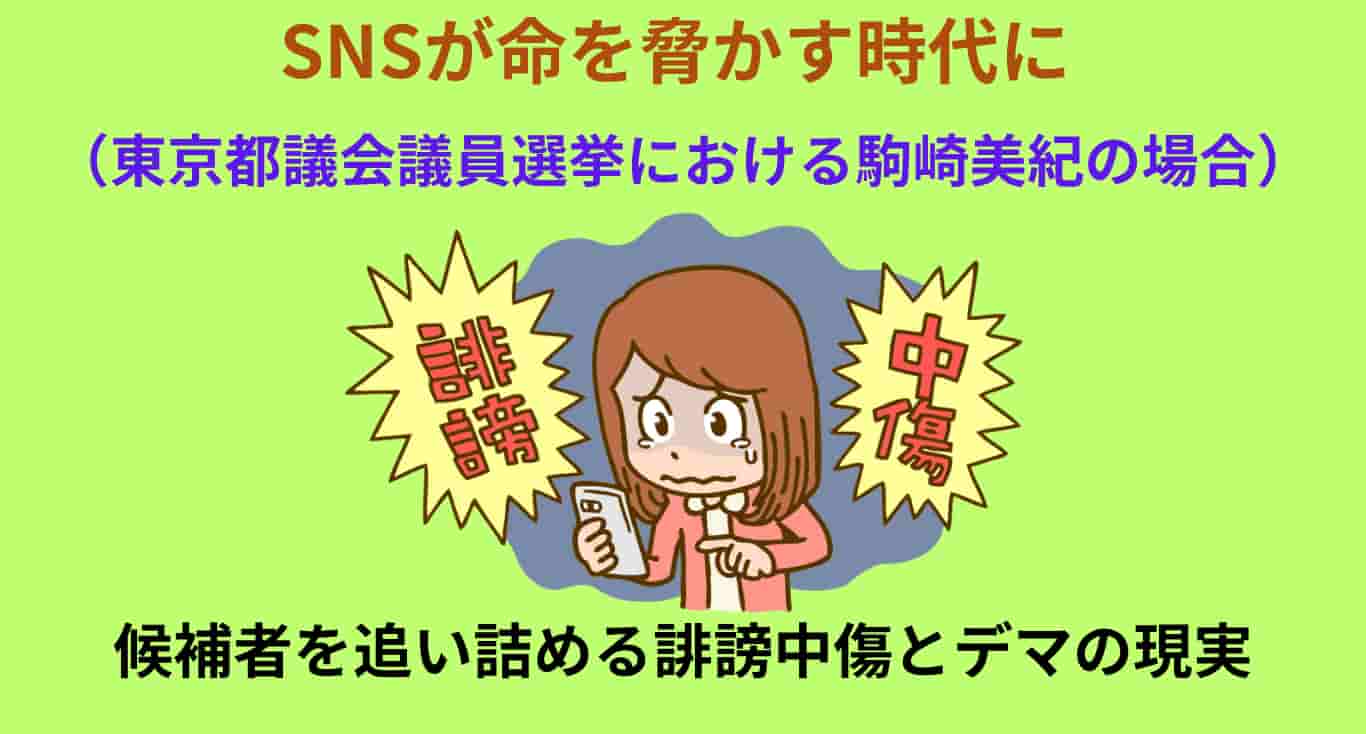
コメント