こんにちは、有権者のひとりとして、日々のニュースに耳を傾けながら「それって本当?」と感じることを調べています。
今回は、2025年7月に話題となった「外国人は日本の相続税を払わなくていい」という発言について、相続税制度の仕組みや国税庁の見解、そして徴収の実態について私なりにまとめてみました。
SNSでは「相続税の抜け穴だ!」「制度がおかしい!」といった声も上がりましたが、本当にそうなのでしょうか?この記事では、相続税の課税対象、不動産をめぐる不公平感、外国人の不動産取得に関する制度的な限界など、ニュースでは語りきれなかった背景をやさしい言葉で解説します。
はじめに

相続税制度に関する誤解と発言の波紋
さて、2025年7月、参政党の神谷宗幣代表がテレビ番組で発言した「外国人は日本の相続税を払わなくていい」「相続税は取りようがない」という内容が、大きな波紋を呼びました。この発言、ネットでも「よくぞ言ってくれた!」という声と「いや、それ違うでしょ…」という批判、両方が出ていました。
相続税って、簡単に言えば「人が亡くなって、その財産を受け継ぐときにかかる税金」です。日本では、外国人であっても、日本の土地や建物を相続すれば、原則として税金がかかる仕組みなんですね。
でも神谷さんは、「外国に住んでる人の場合、そもそも日本の税務当局が把握できないから“取りようがない”」って話していたんです。これに対して、国税庁は「いえいえ、ちゃんと課税してます!」と反論。番組を見ていた私も、「結局どっちの言い分が本当なの?」と正直戸惑いました…。
番組発言がもたらした課題提起の意図とは
ただ、神谷さんの発言は、単に「間違いだ!」と切り捨てるには惜しいところもあると思います。というのも、「制度上は課税できるけど、実際に取りきれているのか?」という問題提起だったからです。
たとえば、亡くなった人が中国やオーストラリアに住んでいて、相続する人もその国にいる場合。しかも、不動産の登記がそのままになっていたとしたら…。日本の役所が「相続が発生した」と気づくのも難しいですし、連絡して課税するのも簡単じゃないんです。こういったケースって、実際にあるんですよね。
もちろん、だからといって「相続税は意味がない!」という話にはなりません。でも、神谷さんが言いたかったのは、「今の制度には現実とのズレがあるんじゃないか」という問いかけだったのではないでしょうか。
番組の中では時間も限られていましたし、発言が断片的に切り取られてしまった面もあると思います。こういったテーマこそ、私たち一人ひとりが落ち着いて、きちんと事実を知って考えていくことが大切だと感じました。
1.神谷代表の発言内容と背景
相続税が「取りようがない」と語られた文脈
神谷宗幣代表の発言は、2025年7月6日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」の中で飛び出しました。与野党の党首たちが集まり、外国人による不動産購入規制について議論していた際、神谷氏は「外国人には日本の相続税が取りようがない」と明言しました。
その背景には、相続税の仕組みに加え、日本国外に居住する外国人が日本の不動産を相続した場合、課税や徴収が難しいのではという懸念があります。具体的には、「海外の人たちは日本に住所も資産もないため、相続が発生しても日本側からは実態が把握できず、課税しようにも届かない」という理屈でした。
こうした主張は、特にSNS上で「日本人ばかりが損をしている」と感じる層に響きやすく、「相続税を払わずに不動産を持てるなら、外国人の方が有利では?」という不満ともリンクしています。
不動産規制と外国人優遇論との接続
発言は相続税だけにとどまりませんでした。神谷氏は、「不動産購入に規制をかけないと、日本人が買い負ける」と主張し、外国人が資産を容易に取得できる現状を「不公平」と表現しました。
その根底にあるのは、「相続税のある日本」と「相続税のない外国」との制度格差に対する問題意識です。
たとえば、オーストラリアや中国など相続税が存在しない国では、資産の移転がスムーズに行える分、相続による負担が軽く、長期的な資産保有が可能とされます。
神谷氏は、そうした国の富裕層が日本に投資目的で不動産を取得し、日本人は相続税によって資産を手放す一方で、外国人は持ち続けられる――そんな「二重基準」のような状況に警鐘を鳴らしたのです。
このような主張は、国民感情に訴える効果がある一方で、制度の正確な理解を前提にしていないという点で、事実とずれた印象を与えてしまうリスクもはらんでいます。
発言の真意と後日の補足説明
放送後、批判や誤解が広がる中で、神谷氏は7月11日放送の「プライムニュース」に出演し、発言の真意を補足しました。
彼の説明によると、「制度上、課税可能なのは理解しているが、実務上、海外に住む外国人の相続について日本側がきちんと把握できない事例がある」とのことでした。
具体例としては、登記変更がなされず、死亡した所有者がそのまま名義人として残っているケース、相続人の居住地が不明で連絡が取れないケース、さらには相続人が複数国籍を持っている場合の対応の煩雑さなどが挙げられました。
つまり、神谷氏は「法律上の建付け」ではなく「現場での実効性」に焦点を当てた発言だったと説明したのです。
ただし、こうした主張には、裏付けとなるデータや件数の提示がなく、実態の把握や議論の深堀りが求められる状況です。
発言の真意は「制度の見直し」や「外国人による不動産取得の抑制」への提言であったとしても、放送時の説明不足が誤解を生んだことは否めません。
2.相続税制度の実態と国税庁の見解
日本の相続税は外国人にも課税される
神谷代表の発言を受けて、フジテレビが国税庁に確認したところ、相続税の対象について明確な回答がありました。
それは、「日本国内にある不動産を相続する場合、相続人が日本人か外国人か、または国内居住か国外居住かにかかわらず、すべて課税対象となる」ということです。
たとえば、中国在住の父親が、日本の不動産を持っていたとして、その不動産を中国在住の息子が相続する場合でも、日本の相続税がかかる仕組みになっています。
これは、「財産の所在地が日本にあること」が課税の根拠となるためです。さらに、課税されないケースというのは、財産の評価額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を下回るなど、金額的な条件に当てはまったときだけです。
つまり、相続税がかかるかどうかは「誰が相続するか」ではなく、「どこにある何を相続するか」によって決まるという、いたってシンプルな仕組みであると言えるでしょう。
実務上の課題と徴収可能性の現状
一方で、制度として課税できることと、実際に課税できるかどうかはまた別の問題です。ここで神谷氏が言及した「捕捉できない」「取りようがない」という点が登場します。
確かに、相続人が国外にいて連絡先が不明だったり、そもそも死亡の事実が日本の行政機関に届かなかった場合、課税のための処理が後手に回ることがあります。
特に、登記の変更が行われていない不動産については、名義が亡くなった人のまま長期間放置されるケースも少なくありません。
ただし、国税庁は「住所不明であっても、決定処分などの手続きを通じて課税を進める仕組みがある」としており、現場レベルでも相応の対応をしていると説明しています。
また、不動産登記を通じて所有権の移転を把握し、相続人に対して納税の通知を行う体制もあるため、「完全に取りようがない」とまでは言い切れないのが実情です。
「徴収困難」という主張の検証
とはいえ、「課税できるかどうか」と「実際に納税されるかどうか」の間には、やはりギャップが存在します。たとえば、相続人が納税義務を理解していなかったり、通知を受け取っても支払わなかったりするケースは、国内外問わず一定数あります。
さらに、相続財産が現金や預金ではなく不動産のみだった場合、納税のための資金を用意できずに滞納されるリスクもあるのです。
それでも、こうした「徴収困難」なケースは相続全体の中では例外的であり、制度全体が機能していないと断定するのは早計です。
国税庁が「テクニカルな手段をフル活用して課税・徴収している」と述べているように、課税の実効性を保つための工夫や運用も日々進められています。
このように、神谷氏の「取りようがない」という表現には、課税の実態をやや極端に単純化した印象があります。
制度の構造と現場の実情を切り離して語ることは、国民の誤解を招くおそれがあり、今後の議論にはより正確で丁寧な説明が求められます。
3.制度上の課題と政治的な論点
不動産購入をめぐる公平性と国際比較
日本の相続税制度は、国内に不動産がある限り外国人であっても課税される仕組みですが、神谷代表が指摘したように「現実的な不公平感」が生じていると感じる人が少なくないのも事実です。
特に、日本の相続税の最高税率が55%に達する一方で、中国やオーストラリア、シンガポールなどは相続税そのものが存在しません。
この差が何を意味するかというと、たとえば中国の富裕層が相続税の負担を気にせず日本に不動産を購入し、世代をまたいで保有できるのに対して、日本の資産家は相続税の支払いによって土地や建物を手放さざるを得ないという状況です。
結果として、「日本人が土地を守れず、外国人に奪われていくのでは」といった懸念が高まり、不動産をめぐる経済的・心理的な不公平感が醸成されているのです。
こうした問題は、単なる税率の問題だけでなく、資産形成のハードルや、家族経営の事業承継にも大きな影響を与えています。
シンガポールの加算印紙税との対比
神谷氏は国会質疑の中で、シンガポールの事例にも言及しました。シンガポールでは、永住権を持たない外国人が不動産を取得する際には、通常の購入印紙税に加えて特別な加算税(Additional Buyer’s Stamp Duty)が課されます。
これにより、シンガポール政府は国内不動産の投機的購入を抑制し、市民の住宅取得を保護する制度設計を行ってきました。
一方、日本では現時点でこのような差別的(区別的)課税制度は導入されていません。
理由としては、各国と締結している租税条約の中に「自国と相手国の国民を不当に差別してはならない」という条項が含まれており、外国人にのみ重い税を課すことが国際的に認められにくいためです。
そのため、日本でもシンガポール型の制度を導入するには、まず法的整備の見直しが必要であり、国際的な合意や二国間協定の調整が不可欠となります。
相続税見直し論と租税条約上の限界
神谷代表の発言をきっかけに、「相続税そのものを廃止すべきではないか」という議論も再燃しています。
実際、相続税は全体の税収に占める割合が4%程度とされており、「税収の柱」というには規模が小さく、むしろ資産の分断や企業の後継ぎ難化など、負の側面を指摘する声も多いのが現状です。
ただし、相続税は単に税収を得るためだけのものではなく、富の再分配という大きな役割を担っています。
社会全体の格差是正や、世代間でのバランス調整のための制度でもあるため、その廃止は慎重に議論されなければなりません。
また、外国人に対する特別課税や不動産取引規制を強化しようとする場合、租税条約やWTO協定などの国際法的な縛りが大きな壁になります。
国籍や居住地による差別を避け、あくまで「公平・中立な税制」として制度を運用し続ける必要があるのです。
このように、制度そのものの見直しを求める声は根強くありますが、現実の政治や外交の中で何をどこまで変えられるのか――そのバランス感覚が問われている局面と言えるでしょう。
まとめ
神谷代表の発言が注目を集めた背景には、日本の相続税制度に対する制度的な限界と国民感情の乖離があります。
国税庁の見解によれば、制度上は外国人であっても日本国内の不動産相続に対して相続税は課されるものの、実際には相続人が海外にいるケースや登記変更がなされない場合に、徴税の実効性が問われる局面が存在します。
また、日本の相続税は最高税率が55%と高く、世代を超えて資産を守ることが困難になりがちです。
一方、相続税のない国の外国人が日本で不動産を取得すれば、世代間での資産維持が比較的容易となるため、日本人との間に「制度による不公平感」が生じるのは自然な感情と言えるでしょう。
さらに、シンガポールのように外国人に対して追加の課税を課す国もある一方で、日本では租税条約や国際法の制約により、国籍による差別的な課税が難しいという現実もあります。
つまり、不公平に見える構造には、国際的な法的制約という裏付けがあるのです。
こうした課題にどう対応するかは、今後の政治的議論に委ねられています。
課税制度の見直しに踏み込むのか、それとも登記制度や国際的な情報連携の強化で実効性を高めるのか――今回の騒動をきっかけに、制度の現実と国民の感覚のギャップを埋める冷静な議論が求められています。
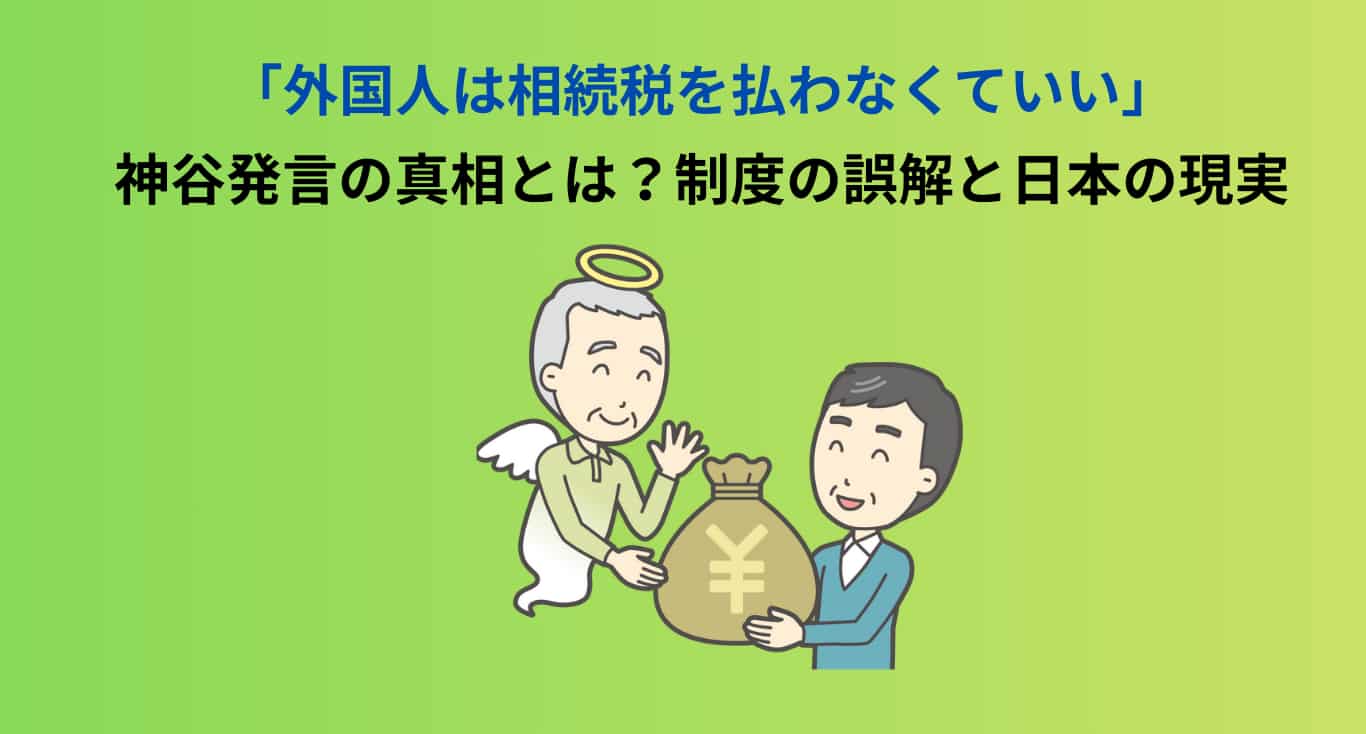
コメント