参議院選挙を前に、作家や表現者の立場から“民主主義の危機”を訴える声が上がりました。
日本ペンクラブは2025年7月15日、外国人に対する差別的な発言やSNSで拡散されるデマが選挙に影響を与えていることに強い懸念を示し、緊急声明を発出。
声明を主導した作家・中島京子氏は「デマが票になり、国の政策に反映されるのは恐ろしい」と語り、表現の自由とデマの違いについて改めて問題提起しました。
声明では、過去の歴史──関東大震災における朝鮮人虐殺の例──にも触れつつ、「私たちは民主主義の後退を許さない」と断言。SNS時代に生きる私たちが、いかに言葉と向き合い、一票を投じるかが問われています。
1. 日本ペンクラブが声明を発出──その背景と問題意識
東京都内で開かれた記者会見で、日本ペンクラブは差別的なデマや発言が票を集め、政治に影響を与える現実に強い危機感を示しました。
常務理事の中島京子氏は「デマによって票が伸びて、国の政策に反映されるのはこわいこと」と発言。声明では、関東大震災時の朝鮮人虐殺を引き合いに出し、過去の教訓を忘れてはならないと訴えました。
桐野夏生会長も「SNSには客観性のない軽い言葉があふれ、それが現実に影響している」と語り、創作に携わる者としての違和感を口にしました。
2. 具体的に広がるSNS上の“選挙デマ”とは
SNS上では、特に外国人や在日外国人に関する次のような事実に基づかない発言が拡散されています:
| 主張 | 実際の事実 |
|---|---|
| 「外国人は生活保護を優先的に受けられる」 | 制度上、日本人と同様に審査があり、外国人の受給割合はごくわずか(1~2%) |
| 「外国人は医療費が無料」 | 無保険の場合は自己負担。旅行者の踏み倒し問題と混同されている |
| 「外国人に選挙権がある」 | 外国人には国政選挙の投票権はない |
| 「外国人犯罪が急増」 | 統計では日本人の犯罪件数の方が圧倒的に多く、外国人の割合は横ばいか減少 |
このような誤情報は感情的に“バズりやすく”、事実よりも拡散されやすいという構造があります。
3. なぜ一部の政治家は誤情報をあえて使うのか
選挙では「敵を作り、それに怒ることで共感を得る」という手法が使われます。SNSやYouTubeを活用し、誤情報や差別的言説をあえて用いることで注目と票を集めようとするケースもあります。
例えば、以下の政党や政治家は過去にそのような発言で批判を受けてきました:
- 参政党(神谷宗幣氏):移民への過剰な不安を煽る発言
- 日本保守党(百田尚樹氏、有本香氏):在日特権や外国人排除を主張
- 日本第一党(桜井誠氏):ヘイトスピーチ的な街宣活動で知られる
これらの動きは短期的な「支持」を得る手段として機能していますが、長期的には民主主義の劣化を招く恐れがあります。
4. 民主主義の成熟と後退──私たちは何を選ぶのか
山田健太・専修大学教授は「ウソの方がネットでは面白く、信じる人も増える。ファクトチェックが追いつかない」と指摘しました。
ペンクラブ声明は、こうした状況に対して「一票の重み」を問い直すことを呼びかけます。
「私たちが少しずつ育んできた民主主義社会が、デマや差別的発言によって崩れていくことを決して許しません。」
5. 「善良な外国人は排除していない」という異論について考える
日本ペンクラブの声明に対し、SNSなどでは次のような意見がしばしば寄せられます。
- 「不法滞在や犯罪を犯した外国人を批判しているだけで、善良な外国人を排除しているわけではない」
- 「日本人ファーストと言っているだけで、なぜ“外国人排除”と非難されるのか分からない」
こうした主張には一定の共感を得る要素もありますが、私たちはそこに言葉のすり替えや印象操作が潜んでいないかを慎重に考える必要があります。
❶ 区別が曖昧になることで、全体が標的にされる
不法滞在者や犯罪者に法的対応を求めること自体は問題ではありません。しかしSNS上では、ごく一部の例が「すべての外国人は危険だ」という認識へと拡張されてしまう傾向があります。
たとえば「不法滞在の外国人が増えている」という投稿があっても、その投稿が統計的根拠に基づいていない場合、全体に対する不信と恐怖を煽る効果を持ちます。
❷ 「日本人ファースト」という言葉の文脈
「日本人ファースト」と言うだけで差別とは限りません。しかし、それが「外国人支援=税金の無駄」「外国人がいるから社会が崩壊する」といった論調とセットで語られると、外国人全体を否定する意図が含まれる可能性が出てきます。
“誰かを優先する”という言葉が、結果として“誰かを排除する”方向に働いていないか──この視点が重要です。
❸ 制度の問題は、デマではなくファクトで議論を
生活保護や医療制度における外国人対応について、制度上の課題がゼロだとは言いません。しかし、それらを議論するには正確なデータと冷静な議論が必要です。
ペンクラブが訴えたのは、そうした制度の是正を妨げる「感情に訴えるデマや差別的言葉」の蔓延です。問題の本質をぼかす言説が民主主義の後退を招くことに警鐘を鳴らしているのです。
異論があっても「正しい言葉」で対話を
「不法行為を問題視すること」と「属性で一括りにして排除すること」は、まったく異なる行為です。
現代は、誰もが発信者になれる時代。だからこそ、感情に流されず、言葉の背景と責任を見極める力が求められています。
私たちは事実に基づいて、正しい言葉と行動で社会をつくるべきときに来ています。
まとめ:言葉を扱う時代に生きる私たちへ
私たちは今、言葉が政治を動かす時代に生きています。SNSの一言が投票行動に直結し、それが現実の政策に反映される──そんな時代だからこそ、「何を信じ、何に耳を傾けるか」の責任は、ますます重くなっています。
あなたの一票が、共生か排除か、成熟か後退かを決める力を持っている。
だからこそ、立ち止まって考えてみてほしいのです。
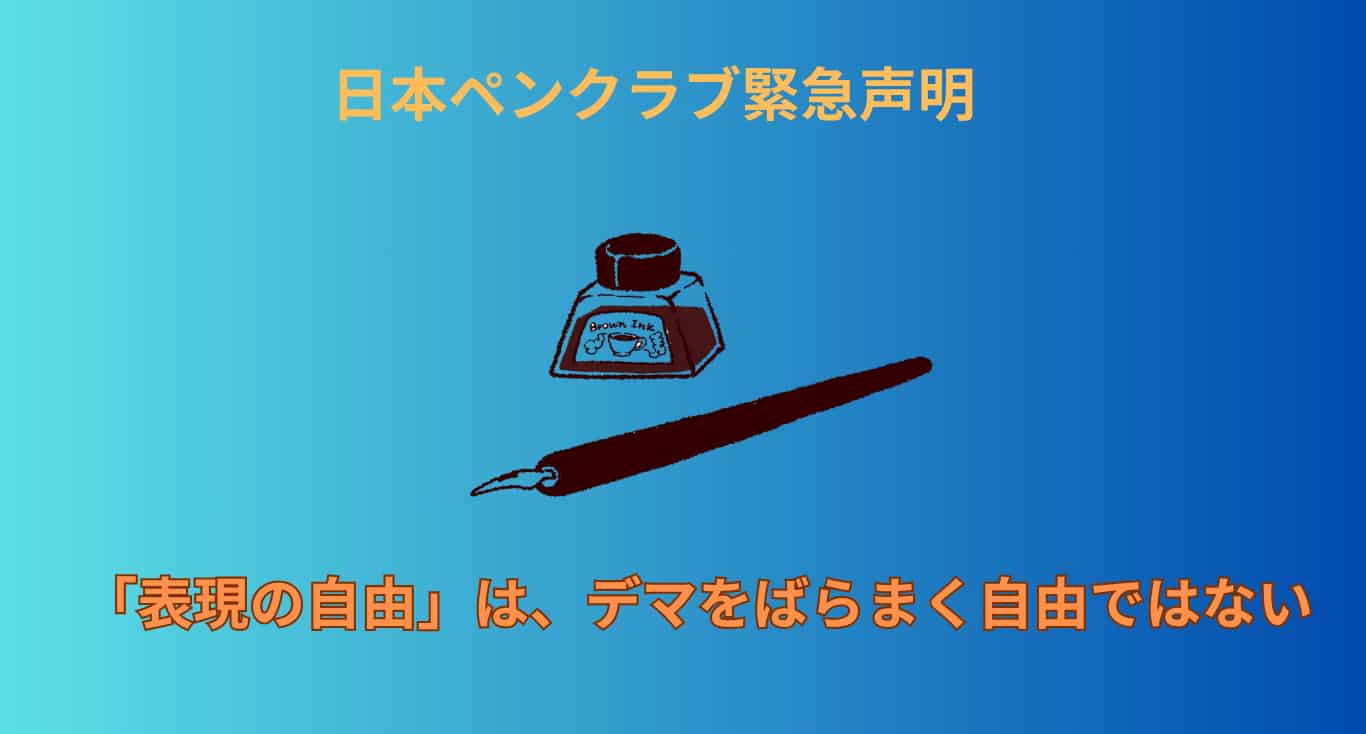
コメント