みなさんは、第7子に310万円が支給される町が日本にあると聞いたら、驚きませんか?
それが、岐阜県山県市の「赤ちゃんほほえみ応援金」。この制度は、第3子以降の赤ちゃんに現金を支給するもので、なんと第7子になると310万円ももらえるというから驚きです!
少子化や人口減少が進む中、全国の自治体が対策に悩むなか、山県市は本気で子育て世代を応援しています。このブログでは、山県市の具体的な支援内容や制度の背景、実際に支給を受けた家族の声まで、わかりやすくご紹介します。じめに
少子化が進む地方都市・山県市の挑戦
岐阜県山県市は、人口減少に歯止めをかけるため、子育て支援に本気で取り組んでいる自治体のひとつです。かつて3つの町村が合併して誕生したこの市は、都市部に近い立地ながらも、若者世代の流出に悩まされ続けてきました。その結果、現在の人口は約2万4500人と、合併時から約7,500人も減少。昨年にはついに「消滅可能性自治体」に指定され、地域の存続が現実的な課題となっています。
しかし、山県市はそこで立ち止まることなく、「今こそ攻めの姿勢で子育て支援を強化しよう」と決断。特に注目されているのが、2023年度からスタートした「赤ちゃんほほえみ応援金」です。この制度は第3子以降の新生児に対して現金を支給するもので、金額は子どもの人数に比例して増額。第7子の場合はなんと310万円が支給されるという、全国的にも前例のないレベルの支援策なのです。
高額な「赤ちゃんほほえみ応援金」が注目される理由
なぜ山県市がここまで思い切った支援を行うのか——その背景には、若年層の転入を促し、地域に子どもの笑い声を取り戻すという強い願いがあります。たとえば、今年度初めて応援金を受け取った宮川さん一家は7人の子どもを育てる大家族。制度開始後初の第7子ということで310万円の支給対象となり、市役所で行われた贈呈式では市長自らが祝福に立ち会いました。
この制度は、子どもをたくさん育てている家庭にとって大きな経済的支援になるだけでなく、「この町で家族を持つことには価値がある」と感じてもらうきっかけにもなります。さらに、保育料や給食費の無償化といった他の施策とも連携し、山県市全体が“子育てしやすいまち”としてのブランドを確立しようとしているのです。
1.山県市の現状と危機感
合併と人口減少の歴史
山県市は、2003年に高富町、美山町、伊自良村という3つの町村が合併して誕生しました。当初の人口は約3万2,000人。岐阜市に隣接する立地もあり、豊かな自然と利便性を兼ね備えた町としてスタートを切りました。しかし、少子高齢化の波には逆らえず、若年層の進学や就職による流出が進み、出生数の減少も相まって、人口は約2万4,500人にまで減少しています。
実際、近所のスーパーでも「子どもの声が聞こえなくなった」と話す高齢者の姿が増えてきました。空き家も目立ち、通学路の登校班は年々人数が減り、小学校の統廃合の話も出るようになっています。合併によって一時的に得たスケールメリットも、人口減により少しずつその効果を失っているのが現実です。
「消滅可能性自治体」への転落
こうした人口減少の現状が顕著になったのは、民間団体「人口戦略会議」が2023年に発表した報告書によってです。この中で、山県市は初めて「消滅可能性自治体」のリストに名前を連ねることとなりました。これは、若年女性(20~39歳)の人口が将来にわたり半減し、結果的に地域が維持困難になると予測される市町村のこと。山県市の50年後の人口は、2020年比で45%減の1万3,877人と推計されており、もはや“対岸の火事”ではないのです。
地元ではこの結果にショックを受けた声も多く、「まさかうちの町が」と感じた人も少なくありません。市の関係者も「思っていた以上に深刻だった」と語り、危機感を募らせるきっかけとなりました。
岐阜市・愛知県への人口流出
山県市のもうひとつの大きな課題は、若者や子育て世帯の近隣都市への流出です。市の南に隣接する岐阜市は人口約40万人の中核市で、大学や病院、ショッピングモールなどが充実しており、通勤・通学の利便性も高いため、若い世代の多くがそちらを選びます。さらに、名古屋圏へアクセスしやすい立地であることから、愛知県へ引っ越す人も後を絶ちません。
山県市で育った若者が進学で一度市外に出ると、そのまま戻ってこないというケースも多く、結果として出生数も減少していくという悪循環が続いています。「暮らしやすい町」としての魅力はあるものの、進学・就職・子育てのライフステージに応じて選ばれにくくなっている現状が、人口流出を加速させているのです。
2.赤ちゃんほほえみ応援金の概要
支給対象と金額の仕組み
山県市が2023年度から導入した「赤ちゃんほほえみ応援金」は、第3子以降に生まれた赤ちゃんが対象の現金支給制度です。特徴的なのは、子どもの数に応じて支給額が段階的に増えていくこと。具体的には、第3子で10万円、第4子で30万円、第5子で70万円、第6子で150万円、そして第7子以上には310万円が支給されます。これは全国の自治体の中でも突出した金額で、誕生祝い金としては破格です。
支給の条件も明快で、山県市に住民票があり、対象となる子どもが出生時から市内に在住していることなどが要件となっています。子育て支援に力を入れたい市の思いが強く反映されており、「頑張って子どもを育てている家庭を応援したい」というメッセージが制度に込められています。
第7子で310万円支給というインパクト
この制度が大きな注目を集めたきっかけは、令和6年度に初めて第7子の支給対象者が現れたことでした。対象となったのは、山県市でハウスクリーニング業を営む宮川慎治さん(54)・志乃さん(39)ご夫妻の三女。贈呈式は市役所で開かれ、林宏優市長から直接310万円が手渡されました。
贈呈式の様子は市民にも公開され、子どもたちが応接室を楽しそうに走り回る中、笑顔があふれる空間となりました。市長も「これだけ元気な子どもたちがいると、こちらまで元気になる」と語り、地域の明るい未来を象徴する出来事として報じられました。金額のインパクトはもちろんですが、それ以上に“子どもを町ぐるみで歓迎する姿勢”が、市内外の人々に強く印象づけられたのです。
実際の支給事例と家族の声
宮川さんご夫妻にとって、この制度はまさに「タイミングがぴったり」でした。というのも、6人目の子どもが生まれた直後に制度が開始され、今回が初めての受給。長男は高校2年生で受験を控え、他の子どもたちもスポーツや習い事を頑張っている最中で、出費は年々増加傾向だったといいます。
慎治さんは「上の子たちの進路や教育費の負担を考えると、本当にありがたい制度。こうした応援があると、子育てを前向きに続けていこうと思える」と語っています。志乃さんも「行政が自分たちの育児をちゃんと見てくれていると実感できる」と話し、経済的支援だけでなく精神的な安心にもつながっている様子でした。
実際、制度が始まってからこれまでに45人の子どもに応援金が支給されており、そのうちの約8割は第3子。つまり、「あと1人で支給対象になる」という家庭にも強く働きかけており、次の出産の後押しにもなっています。
3.子育て支援施策とその効果
保育料・給食費の無償化
山県市の子育て支援は、応援金だけではありません。市では、3歳未満児の保育料を完全無償化し、小中学校に通う児童生徒の給食費も無料にしています。これらの施策は、子どもが多ければ多いほど負担が増える家庭にとって、非常に大きな助けとなっています。
例えば、4人の子どもを育てている市内の家庭では、以前は月々3万円以上かかっていた保育料と給食費が全額免除に。家計に余裕が生まれたことで、子どもたちの学習塾やスポーツ活動に回すことができたといいます。「うちは共働きですが、こういう支援があると“育てられるか不安”という気持ちがずいぶん軽くなる」と、保護者からは好評です。
これらの制度は、子育て世代にとって「この町で子どもを育てる価値」が実感できるものとなっており、単なる一時的な支援ではなく、長期的な安心感を生み出しています。
若年層の転入促進と定住への期待
子育て支援策の充実は、実際に若年層の転入にも効果を発揮しはじめています。市によると、近年、就学前の子どもがいる家庭の転入件数が少しずつ増えてきており、「子どもが生まれるタイミングで山県市への移住を決めた」というケースもあるそうです。
例えば、岐阜市から引っ越してきた30代夫婦は「自然が多く、保育料も給食費もかからない。子どもを育てるには理想的」と話し、リモートワークの普及も相まって、都市部からの移住のハードルが下がっていることを実感しているといいます。こうした事例が少しずつ積み重なっていけば、地域全体の人口動態にも良い影響を与えることが期待されています。
また、地元の空き家を活用してリフォーム移住する若い夫婦も現れており、山県市の「暮らしやすさ」は確実に浸透しつつあります。
市長のビジョン「子どもを産むなら山県市」
林宏優市長は、こうした取り組みを“攻めの子育て支援”と位置づけ、「子どもが少ないからこそ大胆な施策ができる」と語っています。つまり、人口が少ない今だからこそ、一人ひとりの命を大切にできる環境が整っているという発想です。
市長の口癖は「子どもを産むなら山県市」。この言葉はキャッチコピーではなく、施策そのものに裏付けられた現実的な選択肢になりつつあります。実際に応援金を受け取った宮川さんのように、「制度があったからこそ決断できた」という家庭は今後さらに増えていくでしょう。
市は今後も、住宅支援や移住相談、保護者向けの育児サポートなどを組み合わせて、より包括的な子育て環境を構築していく方針です。この町が、全国の自治体の中でも“本気で子育てを支える町”として評価される日も、そう遠くはないかもしれません。
まとめ
岐阜県山県市の「赤ちゃんほほえみ応援金」は、単なるお祝い金の枠を超え、少子化や人口流出に本気で向き合おうとする自治体の強い意志の表れです。第3子から始まる段階的な支給制度は、子育て世帯の経済的不安を和らげ、特に第7子以上への310万円支給という全国でも突出した支援額は、多くの家庭にとって背中を押す存在になっています。
加えて、保育料や給食費の無償化など、日常の子育て負担を軽減する施策が市全体で進められていることも、山県市の魅力を大きく高めています。実際に、制度開始以降は就学前の子どもを持つ家庭の転入がじわじわと増えており、「子どもを産むなら山県市」という市長の言葉が現実味を帯びてきました。
全国の自治体が少子化対策に苦慮する中、山県市は「今いる子どもを大切に育てる環境づくり」と「これから生まれてくる命への大胆な支援」を同時に実現しようとしています。その姿勢は、他地域にとっても大きなヒントになるはずです。子どもを育てる場所として、この町が選ばれる理由は、これからますます増えていくことでしょう。
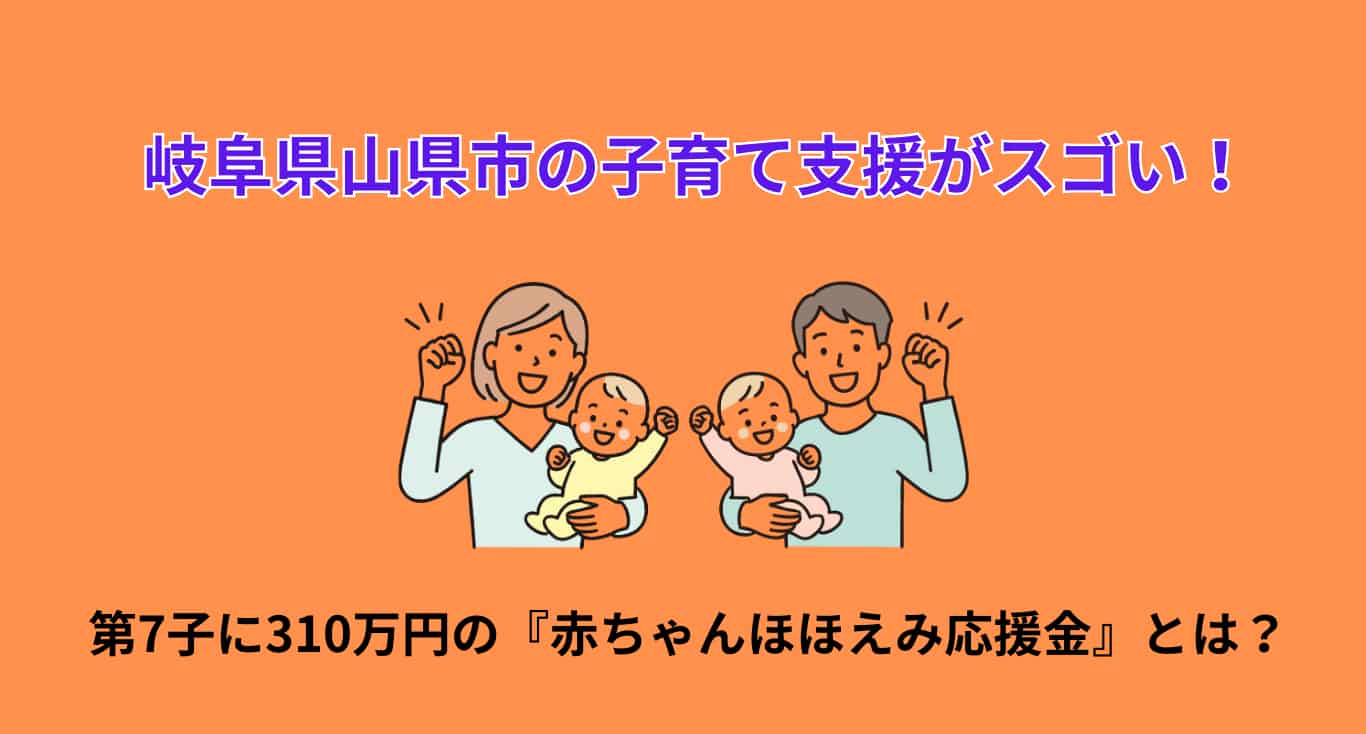
コメント