「米軍基地をなくそう」と主張する政党といえば、これまで多くの人が日本共産党を思い浮かべてきたかもしれません。しかし、近年では保守系の新興政党・参政党もまた、「在日米軍の段階的撤退」や「日米地位協定の見直し」を掲げ、注目を集めています。
このふたつの政党、米軍撤退を求めているという点では一致しているように見えますが、その理念や政策のゴールはまったく異なります。
この記事では、それぞれの立場を比較しながら、日本の安全保障をどう考えていくべきかを探ってみます。
共産党の主張:非武装中立と平和主義からの米軍撤退
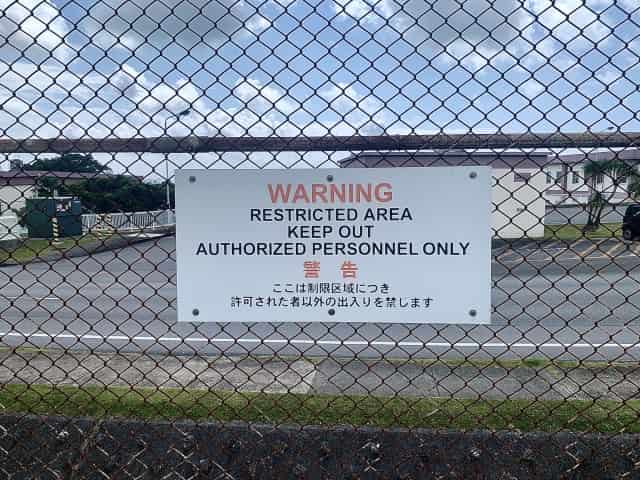
日本共産党は、戦後一貫して「日米安保条約の廃棄」と「在日米軍の全面撤退」を主張してきました。彼らの立場の根幹には、「日本は軍事力に依存せず、外交と国際的協調によって平和を守るべきだ」という非武装中立の理念があります。
共産党は、自衛隊についても「違憲であり、将来的には解消すべき」とのスタンスを取っています。米軍が駐留することによって、日本がアメリカの戦争に巻き込まれるリスクが高まることを問題視し、「米軍の存在こそが日本の安全を脅かしている」と訴えています。
代替案としては、国連を中心とした多国間協調の強化や、東アジアにおける非核・非軍事化の枠組みづくりを提唱しています。
参政党の主張:主権回復と自主防衛のための米軍撤退
一方、参政党が主張する米軍基地の撤退は、共産党とは全く異なる価値観に基づいています。
参政党は、「戦後レジームからの脱却」や「日本の主権回復」をキーワードに、在日米軍基地の段階的な返還・撤退を目指すとしています。その背景には、日米地位協定によって日本の主権が制限されていることへの強い問題意識があります。
ただし、共産党のように軍備そのものを否定しているわけではありません。むしろ参政党は、自衛隊を明確に肯定し、将来的には日本が独自の防衛力を確立することを主張しています。必要であれば憲法改正も辞さず、自国の防衛は自国で担うべきだという「保守ナショナリズム」に立脚した立場です。
さらに、党の一部には「核武装の是非も含めて議論すべき」という意見もあり、防衛に対する考え方は共産党とは真逆です。
共通点と相違点──方向は同じでも、たどり着く先は違う
以下は、共産党と参政党の「米軍撤退政策」における主な違いを比較した表です。
| 項目 | 日本共産党 | 参政党 |
|---|---|---|
| 政治的立場 | 左派・平和主義 | 右派・保守ナショナリズム |
| 撤退の目的 | 非武装中立・戦争回避 | 主権回復・自主防衛 |
| 日米安保への姿勢 | 完全否定・廃棄 | 見直し・再交渉の余地あり |
| 自衛隊の扱い | 違憲、解消すべき | 合憲、強化すべき |
| 外交戦略 | 多国間協調・国連中心 | 主権国家としての自立重視 |
一見すると同じ主張に見える「米軍撤退」ですが、その出発点も、到達点もまったく違います。共産党が理想とするのは「軍事に依存しない平和国家」、参政党が目指すのは「強く独立した国防国家」と言えるでしょう。
「撤退」のその先を、どう描くかが問われている
米軍が撤退した後、日本の安全保障をどのように維持するのか──これは両党ともに直面している難題です。
共産党は「戦争をしない」という前提で、国際協調の枠組みづくりによる平和を唱えていますが、現実にはウクライナや台湾をめぐる緊張の中、対話だけで平和が守れるのか疑問を持つ有権者も多いでしょう。
一方、参政党は自主防衛を掲げつつも、今の日本の軍事力や財政、外交力でそれが本当に可能なのかという現実的な壁もあります。米軍を退けたあと、日本だけで中国・ロシア・北朝鮮に対処できるのかという疑問は、具体的な戦略として未だ曖昧です。
安全保障のジレンマや地政学の現実
1. 🇺🇸 日米安保の「傘」の本質は双方向ではない
日米安保条約は「アメリカが日本を守る」枠組みとして語られてきました。しかし実際には、
- 日本が攻撃された場合、米国は自動的に参戦する義務を負っていない(「共同対処の義務」はあるが、発動は大統領や議会の判断に委ねられる)
- 米軍基地は日本が「前線」となることを前提に配置されており、沖縄などが極めて軍事的に危険な地域となっている
- つまり、日本はアメリカの戦略的な「盾」となりつつ、自らの攻撃力は制限されてきた
日本が「防波堤」になってきた現実は否定できません。
2. 軍備増強のジレンマ:「防衛」か「攻撃の口実」か
軍事力は本来「抑止」のためにあるとされます。しかし、
- 相手国(例:中国・北朝鮮)も防衛を名目に軍拡を進める
- 結果として「安全保障のジレンマ」が生まれ、軍拡競争が加速
- 軍事的緊張が高まることで、「偶発的衝突」や「武力誤算」のリスクも増大
この構図が、ウクライナやガザにおける悲劇にも通じています。
3. 軍産複合体の存在と経済的利益
アメリカを中心に、軍事産業は国家政策と深く結びついた巨大ビジネスです。
- 武器輸出は一大産業であり、「敵の存在」は継続的な需要を生む
- 紛争の長期化・泥沼化によって儲かる構造(例:湾岸戦争、アフガン戦争)
- 一部の専門家は「平和はビジネスにならない」とすら言います
日本でも「防衛装備移転三原則」の緩和などにより、防衛産業の育成が進められていますが、それが軍需依存型経済への転換を意味するならば、深刻な倫理的・経済的課題をはらみます。
結論:抑止力は必要、だが盲目的な軍拡は危険
- 日本が地政学的に厳しい立場にあるのは事実で、最低限の抑止力(防衛力)は必要です。
- しかし、軍拡をエスカレートさせても安全が保障されるわけではなく、むしろ戦争の引き金になる恐れもある。
- 外交・対話・信頼醸成こそが、軍事力に勝る「本質的な安全保障」ではないか――という考えも、十分に理にかなっています。
✍️ 補足的な視点として:
- 「日本が戦場になるリスクが高い」という点は、基地のある国の宿命です。これを正面から国民的議論とすべき時期に来ているとも言えます。
- 軍備の問題は「安全」と「倫理」と「経済」が絡む複雑なテーマです。単純に「持つべき」「持つべきでない」ではなく、国民的合意と透明な議論が不可欠です。
まとめ:スローガンではなく、中身を見る時代へ
米軍基地の撤退という主張は、国民にとってもインパクトが大きいテーマです。しかし、同じスローガンを掲げていても、その背景にある思想や将来像は政党によって大きく異なります。
「戦争を防ぐために基地をなくす」のか、「自分たちで国を守るために基地を返還させる」のか。いずれにしても、日本の安全保障をどう設計し直すかという問いは避けて通れません。
スローガンに飛びつくのではなく、その「中身」と「現実性」を冷静に見つめることが、いま私たち有権者に求められているのではないでしょうか。
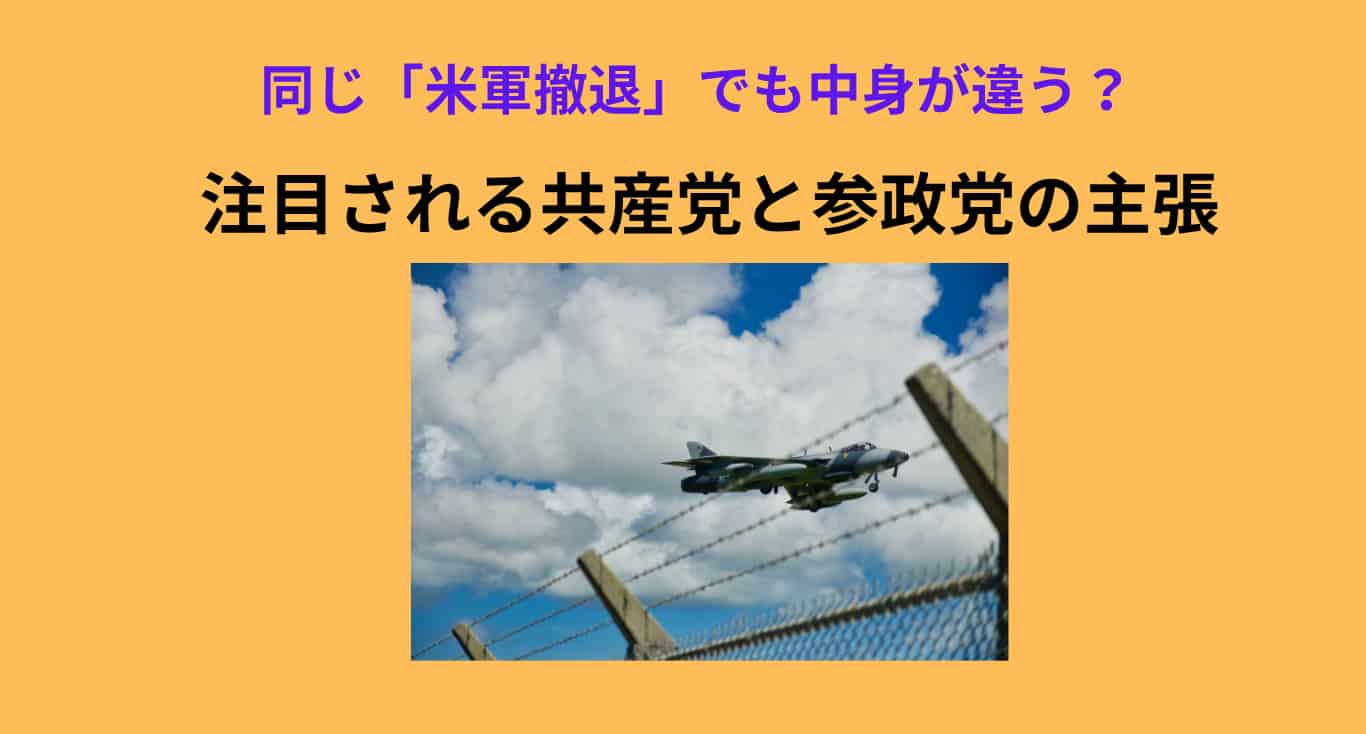
コメント