2025年に開催中の大阪・関西万博で、来場者が撮影・投稿した“ある画像”がSNS上で大きな波紋を広げています。
問題の写真は、会場内の「大屋根リング」や「オーストラリア館」で、女性が下着を露出する姿を撮影したもので、「不適切ではないか」「規約違反では?」との声がX(旧ツイッター)やインスタグラム上で相次ぎ、炎上状態に。
さらに、投稿者が有料の成人向けコンテンツへ誘導していた疑いもあり、問題はより深刻化しています。
この記事では、問題となった投稿の詳細、投稿者の意図、SNSを利用した手法、そして運営側の対応について、具体的に解説します。
1.問題の投稿とその内容
「大屋根リング」でのスカートめくり画像
問題となっている投稿は、ある女性が大阪・関西万博の会場内で撮影し、SNSに公開した露出画像です。女性は自称「OL」と名乗り、6月29日にX(旧ツイッター)のアカウントへ「大阪万博の大屋根リングの柱の影で…」とコメントを添えて写真を投稿しました。
この写真では、万博会場のシンボルである「大屋根リング」のエリアで、女性がミニスカートを左手でめくり上げて下着を露出しています。頭には万博公式キャラクター「ミャクミャク」のカチューシャを身につけ、投稿文には「実はスカートの中も、みゃくみゃくカラー」といった注目を引く一言も添えられていました。この大胆な投稿に対して、SNS上では「公共の場で不適切だ」「さすがにやりすぎでは」といった批判の声が相次ぎ、中には「通報した」というコメントをする利用者もおり、大きな物議を醸すことになりました。
オーストラリア館前での下着露出写真
この女性は問題の投稿以外にも、万博会場内で同様の露出行為を撮影した写真を公開しています。例えば、7月1日には大阪・関西万博のオーストラリア館エリアで撮影した画像を投稿しました。会場内のオーストラリア館入り口近くにはオレンジ色のカンガルーのモニュメントがありますが、その前で女性が足を開き気味のポーズをとり、再び下着を露出している写真です。万博という大勢の来場者が訪れる国際的な場で、各国パビリオンのシンボルと一緒にこのような行為をすることに対し、「万博の場でなんてことを」「海外のゲストにも失礼ではないか」と驚きや批判の声が寄せられました。
子どもが映り込むなどの二次的懸念
さらに深刻なのは、投稿された写真に周囲の無関係な人々――特に子どもが写り込んでいた点です。インスタグラムに投稿された同じ「大屋根リング」での写真の一つには、偶然通りかかった小さな子どもの姿が背景に映り込んでいました。そのため、「子どもの目に触れる場所で何をしているのか」「他の来場者に迷惑をかけている」といった指摘も出ています。公共の場で露出行為を行えば、その場に居合わせた家族連れや子どもたちに不快な思いをさせてしまう可能性が高く、周囲の人々のプライバシーにも関わる問題です。このように、今回の投稿は露出そのものの是非だけでなく、周囲への影響という二次的な懸念も引き起こしているのです。
2.投稿者の目的とSNSの構造
有料成人コンテンツへの誘導手法
問題の投稿を行った女性のアカウントには、X(旧ツイッター)やインスタグラムを通じて、多くの人の関心を集める工夫が散りばめられていました。いわゆる「過激投稿」のあとに、プロフィール欄やリンクをたどると、有料の成人向けコンテンツを案内する外部サイトへと誘導される仕組みが整えられていたのです。
こうした手法は「クリック数」を稼ぎ、ファンを有料サービスに登録させることが目的とされており、露出度の高い写真や大胆な行為によってSNS上で“話題になれば勝ち”という構図を利用しています。しかも、XやInstagramといったプラットフォームは、投稿が拡散しやすい仕組みになっており、ハッシュタグや画像付き投稿を使えば、アルゴリズムによってより多くの人に表示される可能性が高まります。この仕組みを逆手にとって、炎上覚悟の投稿から収益化に結びつけている点が、今回の問題の根深さを物語っています。
「ミャクミャク」など万博のモチーフ利用
女性はただ派手な服装で撮影していたわけではありません。彼女が着用していたのは、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のカチューシャや、マスコットカラーを模した下着とされており、「スカートの中も、みゃくみゃくカラー」といったキャッチーな文言が添えられていました。
こうした“公式モチーフの利用”は、あたかも万博との親和性があるかのように見せ、興味を引く狙いがあると考えられます。現地で販売されているグッズを使うことで、来場者にも馴染みやすく、投稿を見た人が「現地ならではの記念投稿か」と錯覚しやすくなるのです。しかしそれが、内容として不適切な露出や演出と結びつくことで、結果的には万博のブランドイメージを傷つける行為となりかねません。
注目を集める手段としての“炎上マーケティング”
SNS上では、「炎上すれば注目される」「注目されれば儲かる」という考え方が一部で蔓延しています。今回のケースも、まさに“炎上マーケティング”と呼ばれる戦略の典型です。わざと過激な投稿をして賛否を呼び、拡散によって注目を集め、その注目を利用して外部サイトへ誘導するという流れです。
特にXは拡散性が高く、批判コメントすらも“アルゴリズム上の評価”としてポジティブに作用するケースがあります。そのため、炎上はむしろ狙い通りとも言え、今回のように倫理やマナーを無視した行為が続く要因にもなっています。これにより、SNSを利用する善良な一般利用者や万博会場で真摯に過ごしている来場者までもが、巻き込まれる事態となっているのです。
3.協会の対応と今後の課題
公序良俗違反としての規約対応
大阪・関西万博の運営を担う「日本国際博覧会協会」は、今回の投稿について把握しており、事態を重く見た対応を進めています。協会は来場者向けの規約において、「公序良俗に反する服装」「平穏を乱す行為」「わいせつ目的の撮影」などを明確に禁止しています。問題となった画像の一部は、SNS上で拡散されたのち削除されましたが、協会側の関与による削除要請があったものと見られています。
また、協会は報道各社の取材に対し、「営利目的での撮影や公表行為は原則禁止」と明言。とくに万博の場を使っての商業的利用、ましてやわいせつ性を帯びた内容については、固く対処する構えを見せています。こうした対応は、万博の健全な運営と国際的な信頼を守るために不可欠であり、今後も同様の事案が発生した際の前例となるでしょう。
撮影・配信のルールとグレーゾーン
とはいえ、SNS時代において「撮影=即違反」とはならず、協会のルールにもグレーな部分が残っているのも事実です。例えば、YouTubeなどでの万博の紹介や個人による配信自体は許可されており、来場者が体験を記録することは基本的に認められています。しかし、そこに“収益化”が絡んだり、“公序良俗に反する可能性のある演出”が加わった場合、どこからが違反なのかは判断が難しくなります。
今回のように、投稿の一部がミャクミャクのグッズや万博施設を利用した「一見無害に見える」内容であると、チェックが追いつかないこともあります。つまり、撮影の自由と規制のバランスをどう取るかが、今後の大きな課題となるのです。
万博運営側が求められる情報発信と再発防止策
今回の件は、単に「不適切な投稿があった」という事実だけでは済まされません。万博という国際的なイベントの場で、こうした行為が発生したこと自体が、会場の管理体制や情報発信のあり方に課題を突きつけています。
例えば、撮影や服装のマナーについては、チケット購入時や入場ゲートでの案内表示だけでなく、SNSや公式アプリを活用して、より分かりやすく事前に共有すべきです。また、ボランティアや警備員による巡回体制の強化、違反行為の通報窓口の設置など、来場者が安心して参加できる環境づくりも求められます。
世界中から注目されている大阪・関西万博だからこそ、その場でのふるまいは、ひとりひとりの行動だけでなく、運営側の啓発と対応力が問われているのです。
まとめ
大阪・関西万博という国際的なイベントの場で発生した今回の“スカートめくり投稿”問題は、単なるマナー違反にとどまらず、SNSの拡散力と収益構造を利用した「炎上商法」の一環とも言える深刻なケースでした。
投稿者が着用していた「ミャクミャク」のカチューシャや、オーストラリア館などの施設を背景にした露出行為は、多くの来場者がいる公共空間で行われたという点でも強い批判を受けており、特に子どもが写り込んでいたことは大きな懸念材料となりました。
SNS上では注目を集めるために過激な手段をとるユーザーも少なくありませんが、それが公共イベントの場で行われた場合、多くの人々の信頼や安全に関わる問題に発展します。今回の件は、万博協会側の規約対応や削除要請によって一定の対処がなされたとはいえ、今後同様の事案を未然に防ぐためには、より明確なルールの提示と周知、そして会場内の監視体制の強化が求められるでしょう。
大阪・関西万博は、未来と調和をテーマに世界中の人々が集う舞台です。一人ひとりがルールとモラルを意識し、主催側もその環境づくりを怠らないことで、誰もが安心して楽しめる場が実現するはずです。今後の対応と改善に注目が集まります。
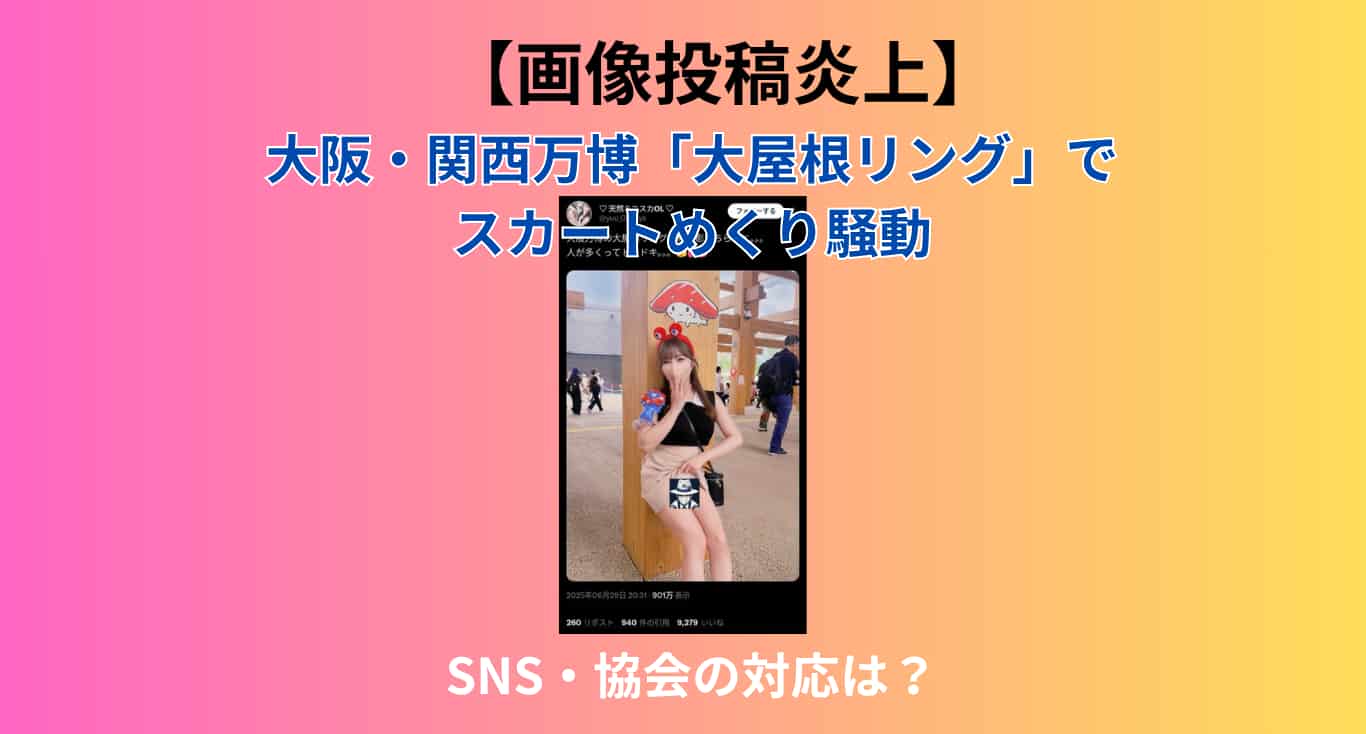
コメント