2046年のFIFAワールドカップ(W杯)に向けて、日本を含む東アジアとASEAN諸国が共催を目指す動きが本格化してきました!
実現すれば2002年の日韓大会以来、実に44年ぶりにW杯が日本に帰ってくることになります。
世界最大のスポーツイベントを再びアジアの地に──。この記事では、共催計画の背景や期待、そして乗り越えるべき課題について、サッカーファンの視点からわかりやすく解説します!
はじめに

アジア全体で再びW杯を──共催の新たな動き
世界最大のサッカーイベント、FIFAワールドカップ。その舞台を再びアジアに呼び戻そうという動きが、いま着実に進んでいます。日本サッカー協会(JFA)が属する東アジア連盟(EAFF)と、ASEANサッカー連盟(AFF)が連携し、2046年のW杯招致に向けた構想が明らかになりました。
この共催計画は、2023年3月に東京で行われた両連盟の合同会議をきっかけに具体化。正式な合意文書こそ交わされていませんが、「一緒にやれたらいいね」という関係者の言葉には、東アジアと東南アジアの連携強化という大きな意味が込められています。すでにインドネシアやオーストラリアといった有力国も招致に前向きとされ、共催実現に向けた土壌は整いつつあります。
日韓大会から44年、日本の再招致への挑戦
もしこの計画が実現すれば、日本にとっては2002年の日韓大会以来、実に44年ぶりのW杯開催となります。あの年、日本代表が決勝トーナメント進出を果たし、ロシア戦での歴史的勝利に全国が熱狂したのは記憶に新しい人も多いでしょう。
しかし現在のFIFA基準では、決勝戦には収容8万人以上のスタジアムが求められるなど、単独開催のハードルは年々上がっています。日本国内にはこの基準を満たすスタジアムはまだなく、今後のインフラ整備や国民的な機運の醸成が大きなカギとなります。
JFAは女子W杯の招致も視野に入れつつ、「2050年までに日本代表がW杯で優勝する」という長期目標を掲げています。その実現に向けて、今回の共催計画はまさに未来を切り拓く第一歩といえるでしょう。
1.W杯招致の新潮流と東アジア・ASEANの連携
EAFFとAFFの合同会議で生まれた共催構想
今回の共催案が最初に持ち上がったのは、2023年3月に東京で開かれた東アジア連盟(EAFF)とASEANサッカー連盟(AFF)の合同会議です。この会議は、E-1選手権を終えたばかりのJFA宮本恒靖会長が韓国から帰国後に出席したもので、関係者のあいだでは「一緒にW杯を開催できれば」といった前向きな意見が交わされました。
この動きの背景には、FIFAが複数国共催の方針を積極的に推進していることがあります。たとえば2026年大会はアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国での共催、2030年大会では南米・欧州・アフリカの6カ国による分散開催が予定されており、国際的にも“共催ありき”の時代に突入しつつあるのです。アジアでもこの流れを受け、地域同士が手を組むことで招致の現実味が増してきました。
招致戦略における日本サッカー協会の役割
この共催構想の中心にいるのが、日本サッカー協会(JFA)です。宮本会長は、EAFFの副会長にも選出されており、アジア全体のサッカー界において発言力を持つ立場です。彼のように国際的なネットワークと現場感覚のある人物が主導することは、招致にとって大きなプラスになります。
さらにJFAはこれまでにもW杯招致の経験を積んでおり、2002年大会や2022年大会の招致活動でも中心的な役割を担ってきました。こうした実績は、FIFAに対して「日本には世界大会を運営する能力がある」という確かな印象を与える材料になります。加えて、近年では女子W杯やクラブワールドカップの招致にも積極的で、2039年以降の女子W杯誘致も見据えた動きが同時進行中です。
東アジア×東南アジアの共闘が意味するもの
日本や韓国といった東アジアの国々は、これまで単独あるいは2国間での国際大会開催を経験してきました。一方で、インドネシア、タイ、マレーシアなどの東南アジア諸国は、急速に経済発展を遂げながらも、世界的イベントの招致実績は限られていました。今回、こうした地域がタッグを組むことで、アジア全体の結束力と可能性を世界に示すチャンスが生まれています。
たとえば、インドネシアはもともと2034年大会の招致に意欲を示していた国ですが、サウジアラビアの決定によってその夢は一時的に閉ざされました。今回の共催案では、こうした国々に新たな道が開かれ、経済力と経験を持つ日本と組むことで、実現性の高い招致チームが形成されようとしています。
この連携は、単にW杯を開催するというだけでなく、地域間のスポーツ交流、経済的つながり、そして観光や文化の相互理解を深める大きなきっかけにもなるのです。
2.過去のW杯招致と開催の教訓

2002年日韓大会の成功と視聴率の記録
2002年、アジアで初めてのFIFAワールドカップが日本と韓国の共催で開催されました。この大会は、サッカーの枠を超えて社会現象となり、日本国内では“ワールドカップ元年”とも言える盛り上がりを見せました。とくに、日本がロシア戦でW杯初勝利を挙げた際には、視聴率66.1%という驚異的な数字を記録。全国のスポーツバーや自宅のテレビの前で人々が歓喜に沸いたのを覚えている方も多いでしょう。
また、この大会ではインフラ整備や交通網の改善など、大会開催が地域に与える波及効果も大きな注目を集めました。空港や新幹線、スタジアム周辺のまちづくりが進み、その後の観光産業にも好影響を与えたといわれています。この経験は、2026年や2046年に向けての重要な財産であり、再招致に向けての説得材料にもなるでしょう。
2022年カタール大会招致での敗因
一方で、日本が単独で招致に挑んだ2022年大会は、残念ながらFIFAの投票でカタールに敗れました。日本側は、太陽光発電や冷却技術など最新テクノロジーを駆使した“未来型W杯”を提案しましたが、票数では及ばず。水面下で激しいロビー活動を展開していたカタールの前に、結果はついてきませんでした。
このときに浮かび上がった課題のひとつが、“アピール力”の弱さです。日本はクリーンで誠実なスタイルを貫いたものの、国際的な票集めの場ではその誠実さだけでは勝てない現実を痛感することになりました。FIFA理事会では複数の不正疑惑も報じられ、日本の“正攻法”が相対的に影を潜めた形となりました。
この経験から学べるのは、ただ良い企画を出せば選ばれるわけではないという現実です。技術や設備の充実だけでなく、世界中のサッカー関係者に「この国で開催したい」と思わせるような、魅力的なメッセージと発信力が求められているのです。
招致競争で求められる“ロビー力”とは
近年のW杯招致では、“どれだけ世界中に支持者を増やせるか”が大きな鍵を握ります。いわゆる「ロビー活動」とは、選挙のように各国のサッカー協会関係者やFIFA理事に対して、開催国としての魅力やビジョンを伝え、支持を取り付ける動きのことです。
たとえばカタールは、各国理事に接触するための外交戦略を緻密に組み立て、時には大型の投資プロジェクトや共同開発案などを提示することで信頼を得てきました。これに対して、日本は情報発信や戦略的な対話の面でやや後手に回った印象が否めません。
今後の招致においては、国としての誠実さを大切にしつつも、世界中のサッカーファンや関係者の心を掴む“語りかける力”が必要です。単なる技術力ではなく、共催する国々との文化的魅力や地域の未来像を、わかりやすく情熱的に伝えていく姿勢が、成功への道を切り拓くことになるでしょう。
3.開催実現に向けた課題と可能性
FIFA基準を満たすスタジアムの確保と建設
W杯を開催するためには、FIFAが定める厳しい基準を満たしたスタジアムが必要です。たとえば、決勝戦を行うスタジアムは収容人数8万人以上、準決勝は6万人超、グループステージやベスト16を含むその他の試合でも4万人以上の収容が求められます。
現在、日本には収容人数8万人を超えるスタジアムは存在しません。国立競技場でさえ、収容人数は約6万人にとどまります。つまり、W杯開催のためには既存施設の改修や、新設スタジアムの建設が必須なのです。これは多額の費用を伴う大事業ですが、経済効果や地域活性化の視点からは投資価値のあるテーマといえるでしょう。
また、共催を想定している他の国々──インドネシア、マレーシア、シンガポールなども同様に基準を満たす施設の整備が必要です。それぞれの国がどの試合を担当するのかを含めた綿密な計画が求められます。
候補国の利害と地域間調整の難しさ
共催での開催には、単独開催では見えにくい“難しさ”もあります。とくに問題となるのが、参加国間での調整です。W杯のような巨大イベントでは、どの国がどの試合を担当するのか、どの国の空港やホテルを使うのか、スポンサー収益をどう分配するのかといった実務レベルの課題が山積しています。
例えば2002年の日韓大会でも、開会式と決勝戦をどちらが担当するかをめぐり、両国の間で長時間にわたる議論がありました。最終的には日本が開会式、韓国が決勝戦を開催するという形で落ち着きましたが、このような交渉は国のプライドや政治的思惑も絡むため、慎重かつ冷静な対応が不可欠です。
東アジアと東南アジアの国々は、文化や宗教、経済レベル、政治体制も多様です。だからこそ、地域間で信頼関係を築き、柔軟に協力できる仕組みづくりが招致成功のカギとなります。
「2050年優勝」構想に向けた長期ビジョン
日本サッカー協会は2005年に「2050年までに日本代表がW杯で優勝する」という目標を掲げました。このビジョンは単なる夢ではなく、育成年代からの強化、女子サッカーの拡充、国内リーグの成長といった一連の戦略に基づいています。
W杯開催は、そのビジョンを国内外にアピールする絶好のチャンスでもあります。なぜなら、自国開催は国民の関心を高め、若い世代にサッカーの魅力を伝える絶好の機会だからです。2002年のW杯をきっかけにサッカーを始めた子どもたちが、いま日本代表として活躍しているように、2046年大会もまた「次のヒーロー」を育てる土壌となるはずです。
ASEAN諸国との共催は、この長期ビジョンをアジア全体に広げる試みにもつながります。アジア全域でサッカーを盛り上げることで、日本代表のレベルアップ、そして「世界一」への道が少しずつ現実のものとなっていくのです。
まとめ
2046年のFIFAワールドカップを日本で──そんな夢のような構想が、現実に向かって動き出しています!
日本サッカー協会(JFA)は、東アジアと東南アジア諸国と手を取り合い、共催という形でのW杯招致を目指しています。
過去には2002年の日韓大会という成功例があり、その一方で2022年のカタール大会招致では敗れた経験もありました。だからこそ、今回はこれまでの教訓を活かし、「地域連携」と「世界への発信力」を強化していく必要があります。
もちろん、FIFAの厳しい開催基準やスタジアムの整備、国際的な調整など、乗り越えるべき課題もたくさんあります。でも、それを超えた先にあるのは、日本中がサッカーでひとつになる感動の瞬間です!
筆者もいちサッカーファンとして、「またW杯を日本で見たい!」という気持ちでいっぱいです。
今後の動きに注目しつつ、サッカーの未来を一緒に応援していきましょう!
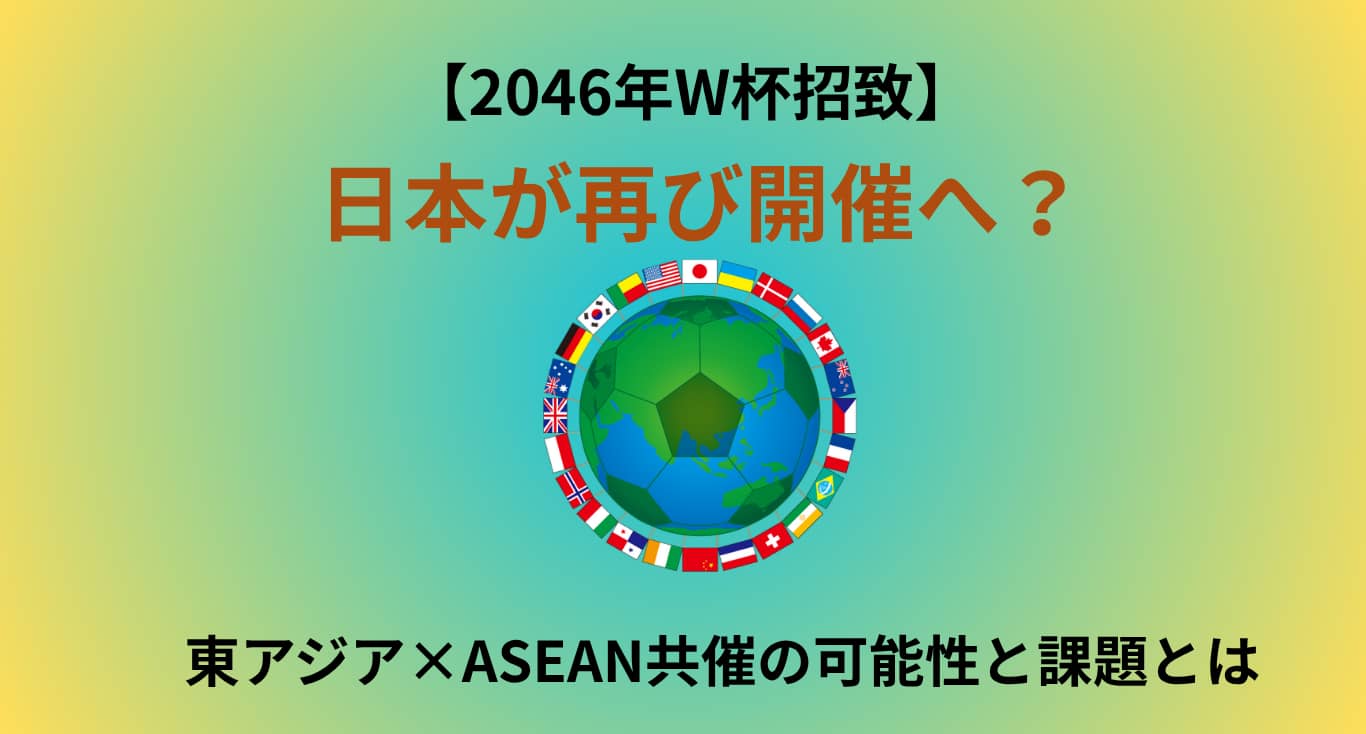
コメント