全国で300カ所以上の保育所を運営する大手企業「キッズコーポレーション」が、保育士の採用において男性や妊娠中の女性を排除するルールを内部で運用していたことが、元社員の証言と資料で明らかになりました。
このような差別的な採用基準は、男女雇用機会均等法に違反する可能性もあり、社会的な注目を集めています。本記事では、保育士の採用差別の実態、背景、法的な問題点や保育現場への影響について、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
保育士を目指す方や子育て中の保護者の皆さんにも、ぜひ知っておいてほしい内容です。
はじめに
保育の現場で何が起きているのか
保育士不足が深刻化する中、保育現場における採用のあり方が改めて問われています。
そんな中、保育所を全国で約300カ所展開する「キッズコーポレーション」が、採用時に男性や妊娠中の女性をあらかじめ排除する方針を内部で定めていたことが、元社員の証言や社内資料によって明らかになりました。
企業の都合によって一部の応募者を最初から不採用にするという姿勢は、保育の現場だけでなく、社会全体に大きな疑問を投げかけています。
このような差別的な方針がどのように運用されていたのか、また、それが何をきっかけに生まれたのか──本記事ではその背景に迫ります。
差別的な採用ルールとその背景
きっかけは、同社が運営する東京都内の保育所で起きた元園長による児童へのわいせつ事件でした。
逮捕を受け、同社は「男性は採用しない」というルールを密かに設けたとされています。
内部資料には、「断れるポイントを探す」といった文言があり、面接段階であらかじめ“落とすための理由”を見つけようとする動きが見られました。
問題なのは、そのルールが“あくまで指針”として運用されていたという会社側の主張に対し、現場では実質的に差別的な扱いが常態化していた可能性が高いということです。
さらに、妊娠中の女性にも同様の姿勢が取られていたとの指摘もあり、雇用の公平性が著しく損なわれていたことが伺えます。
1.差別的ルールの実態

「断るポイントを探す」内部資料の内容
キッズコーポレーションの採用現場では、「断れるポイントを探す」という言葉が記された内部資料が存在していました。
この言葉は、表向きには「適性を見るための工夫」とも受け取れますが、実態は明らかに異なっていました。
たとえば、面接で妊娠中であることを申告した応募者に対し、「現場が忙しい時期なので、またの機会に」と曖昧な理由で断ったり、男性応募者には「女性保育士を希望している保護者が多い」として不採用にするなど、事前に“断る理由”を設定しておくような対応が取られていたといいます。
ある元採用担当者は、「マニュアル的に“どうやって断るか”を考える研修もあった」と証言しており、採用判断において公平性を欠く“隠れたルール”が組織的に存在していたことがうかがえます。
妊娠中の女性・男性を対象にした排除
同社では、妊娠中の女性応募者に対しても採用を見送るケースが複数確認されています。
これは体調面や業務への支障を懸念しての判断とされますが、法的には妊娠を理由とした不採用は明確な差別にあたります。
元社員の話によれば、「妊婦と聞いたら、内定は出さないという空気が上層部にあった」という証言もあり、個々の体調や意欲を無視した一括排除が行われていた可能性が高いと考えられます。
また、男性についても同様に、保育士としての資質を個別に評価する前に、「男性であること」自体をリスクと見なす風潮が社内にあったとされます。
これは、過去に起きた元男性園長の不祥事を受けた対応とされており、「男性は保護者の印象が悪くなる」「事件が再発したら会社の信用にかかわる」といった理由で、男性全体を遠ざける判断につながっていたようです。
内部告発と元社員の証言
このような状況を明るみに出したのは、複数の元社員による内部告発でした。
彼らは、「現場ではやむを得ないという空気があったが、明らかに不当な差別だと思っていた」と語ります。
中には、面接のやり取りを記録し、「この対応はおかしいのではないか」と上司に訴えたものの、「会社方針だ」と押し切られたケースもありました。
告発者の一人は、「このままでは良心が許さない」として資料を持ち出し、メディアに提供。
そこには、「男性=事件リスク」「妊娠=長期休職リスク」といったステレオタイプに基づく分類が記されており、採用の公平性が企業の一方的な都合でねじ曲げられていた現実が浮かび上がりました。
2.不採用ルールの背景と口実
元園長のわいせつ事件が与えた影響
差別的な採用ルールが生まれた背景には、2019年に起きた同社の東京都内の認可保育所での事件がありました。
元園長の男性保育士が、小学生の女児に対するわいせつ容疑で逮捕されたというものです。
この事件を受け、会社側は再発防止の名のもと、「男性を採用しない」という暗黙のルールを定めたとされています。
確かに子どもを預かる保育の現場では、安全性が最も重視されるべきです。
しかし、その安全を守るために、性別だけを理由にすべての男性保育士を排除するという考え方は、あまりにも極端でした。
実際、この元園長の不祥事は一個人の問題であり、すべての男性に責任を押しつけることはできません。
元社員の一人は「事件のあとから急に、男性の応募が通らなくなった」と証言しており、ルールが事実上、男性全体を排除する目的で運用されていたことがうかがえます。
「会社として公にしていない」理由
この事件について、キッズコーポレーションは「会社として公表はしていない」と内部資料に記しています。
つまり、一般には伏せたまま、内部でのみ対応策として採用方針を変更していたことになります。
これは、企業イメージの悪化や保護者の不安を避けたいという思惑があったと見られます。
しかし、問題はここからです。事件の詳細が共有されないまま、「男性=リスク」といった決めつけが先行し、採用現場では形式的に不採用が続くという状況が生まれていました。
実際、ある面接担当者は「なぜダメなのか説明できないまま、採用を見送るように指示された」と話しています。
情報を伏せることで混乱を防ごうとした判断が、逆に差別的なルールを強化し、結果として不透明な採用運用を招いていたのです。
園児や保護者への説明対応の矛盾
会社側は「保護者や自治体には説明した」と述べていますが、元職員によると、その説明内容はかなり限定的で、事件の詳細は語られていなかったといいます。
保護者の中には「急に園長がいなくなって理由もわからなかった」という声もあり、不信感を募らせた家庭も少なくなかったようです。
一方で、採用現場ではこの事件が強く意識されており、「これ以上問題が起きると困るから男性は避けて」といった内向きの指示が徹底されていました。
このズレこそが、情報の出し方と向き合い方の不誠実さを物語っています。
企業がリスク管理として行った判断が、結果として差別的な制度につながり、さらにそのルールを外に明かさないことで内部矛盾を拡大させた──そんな構図がここにはあります。
- 事件の発生
東京都内でキッズコーポレーションが運営する認可保育所に勤めていた男性元園長が、小学生女児に対するわいせつ容疑で逮捕された事件が発端です。
逮捕は複数回(旅行先での行為を含む)行われ、判決の結果、2020年に実刑が確定しました。 - 事件の時系列
最初のわいせつ行為は園長を辞めた後、約20日後に発覚しましたが、当時はまだ同社に在籍しており、その後「職業不詳」として報じられました。 - 社内対応の実態
この事件を受け、会社は男性の採用を避ける社内ルール(いわゆる“キッズルール”)を策定。内部資料には「男性や妊娠中の女性、精神疾患のある人などを対象に“採用しない”と記載」され、さらに「逮捕を会社として公にしない」と明記されていました。 - 社会的影響と法的側面
この一連の措置は、性別や妊娠などを理由とした差別的な採用判断とみなされ、厚生労働省から男女雇用機会均等法違反の可能性を指摘されています。
この事件は、一個人の犯罪とはいえ、それが引き金となって性別や妊娠を理由に応募者を一律に不採用とする制度が導入された点が問題とされています。
3.法的問題と社会的影響
男女雇用機会均等法との関係
キッズコーポレーションの採用方針は、法律の観点からも大きな問題を抱えています。
とくに指摘されているのが、「男女雇用機会均等法」に抵触する可能性です。この法律は、性別を理由にした不当な差別的取り扱いを禁止しており、妊娠や出産を理由にした不採用も当然含まれます。
例えば、ある妊娠中の応募者は、面接時に「今後の出産予定があるなら、現場では難しい」と言われて不採用になったと証言しています。
これは個人の体調や能力ではなく、妊娠という事実だけを理由に排除されたケースです。
また、男性応募者に対しても、「うちは女性保育士しか取らない」と明言された例が複数あり、性別を前提とした不採用方針が明確に存在していたことがわかります。
このような採用基準は、法律上明らかに問題であり、厚労省の見解でも「指針であっても運用が差別的であれば法に違反する可能性がある」とされています。
厚労省の見解と企業の対応
厚生労働省は、今回の事案について「個別の事情によって運用されたとしても、結果として特定の属性の人を排除しているならば、均等法違反となりうる」と述べています。
つまり、表向きに「指針」であっても、実態が差別的であれば違法とみなされるということです。
これに対し、キッズコーポレーションは「誤解を与えないよう、指針の見直しを進めている」と説明していますが、現場の運用実態との乖離は大きく、内部からの告発によってしか明らかにならなかったことも信頼性を損ねています。
法令に沿った是正措置を講じるだけでなく、透明性のある運用方針や再発防止の仕組みが不可欠です。社員への研修や、外部による監査といった具体策も求められています。
差別が招く保育現場への不信感
こうした一連の差別的な対応は、保護者や地域社会に対して大きな不信感を与える結果となっています。
保育所は子どもの命を預かる場所であり、安心・安全が何よりも大切です。そのためには、職員の質はもちろん、採用や運営においても公正さと誠実さが求められます。
しかし今回のように、過去の事件を理由に特定の属性の応募者を排除するという判断が続けば、「この園は本当に信頼できるのか」と疑問を持たれても仕方がありません。
保育士の採用における透明性、公平性は、保育の質にも直結します。
差別的なルールが温存されたままでは、有能な人材が去り、現場の疲弊も進みかねません。
社会全体でこの問題を見つめ直すとともに、保育の現場が安心と信頼を取り戻すには何が必要か──その議論がいま、強く求められています。
教育現場での教師や保育士によるわいせつ事件の社会問題化と採用差別
教育現場での教師や保育士によるわいせつ事件が社会問題化している今、キッズコーポレーションの採用差別問題は、単なる一企業の不祥事にとどまらず、教育・保育の現場全体に大きな波紋を広げています。以下に、その影響をわかりやすくまとめます。
1.「安心・安全な環境」を求める声と採用差別の矛盾
保護者にとって、子どもを預ける施設には“安全性”が最優先されます。そのため、過去に性犯罪を起こした人物が教育・保育現場にいたと聞けば、不安や不信感を抱くのは当然です。
しかし、キッズコーポレーションが行ったように「男性はリスクがあるから不採用」「妊婦は現場に出られないから排除」というルールは、安全確保とは全く異なる“安易なラベリング”です。これは本質的な解決にはならず、むしろ現場の多様性や専門性を損ねるだけです。
2.「性別=リスク」という偏見を社会に広げかねない
一部の事件をきっかけに、「男性=危険」「妊婦=使えない」といったレッテル貼りを制度化してしまうと、社会全体にその偏見が広がり、男性保育士や若い妊婦の働き手がますます職場から遠ざけられることになります。
すでに教育現場では、「男性教師だから疑われるのが怖い」と子どもとの接触を避ける先生も増えているという声もあります。過剰な排除は、逆に子どもたちの成長にとってもマイナスです。
3.“安心”と“差別”の線引きを社会全体で考えるべき時
「子どもを守りたい」という思いは、どの立場の人にも共通しているはずです。でも、そのために性別や妊娠といった個人の属性を理由に門前払いするような制度が許されていいのでしょうか?
このキッズコーポレーションの採用差別問題は、「加害防止」と「差別防止」という2つの課題をどう両立させるかという難しい問いを私たちに投げかけています。
4.採用の公平性と現場の信頼回復が急務
教育や保育の現場にこそ、「性別・年齢・ライフステージに関係なく、誠実に子どもと向き合える人材をきちんと評価する」仕組みが求められています。
キッズコーポレーションのような大手企業が率先してそのモデルを示せば、教育業界全体の採用体制にもよい影響を与えたはずです。今回の件をきっかけに、保育・教育業界全体が「本当に子どもにとって必要な安心とは何か?」を見直す必要があります。
最後に
教師や保育士による性加害の防止は重要です。けれど、「属性」で線を引くのではなく、「行動」や「適性」をきちんと見極める視点を持つことが、本当の“子どもの安心”につながるのではないでしょうか。私たち一人ひとりがこの問題を、自分ごととして考えることが大切だと思います。
まとめ
今回明らかになったキッズコーポレーションの採用方針は、性別や妊娠といった個人の属性を理由に不採用とする、明らかに差別的なものでした。
たとえ「指針」として運用されていたとしても、実際には選考の段階で対象者を絞り、排除する動きがあったことは、元社員の証言や内部資料によって裏付けられています。
背景には、元園長による重大事件や、保護者の不安を過剰に意識した経営判断がありましたが、そうした出来事を理由に一部の属性の応募者を一律に不採用とすることは、法的にも社会的にも許されるものではありません。
保育の現場に求められるのは、「誰が働いているか」ではなく、「どんな姿勢で子どもたちと向き合っているか」です。
公平な採用と透明な説明責任があってこそ、保護者の信頼が生まれ、保育の質も向上していくはずです。
この問題は、一企業の姿勢にとどまらず、日本全体の雇用と人権のあり方を問い直す機会でもあります。採用の「当たり前」を、私たちは今、もう一度見直す時に来ているのかもしれません。
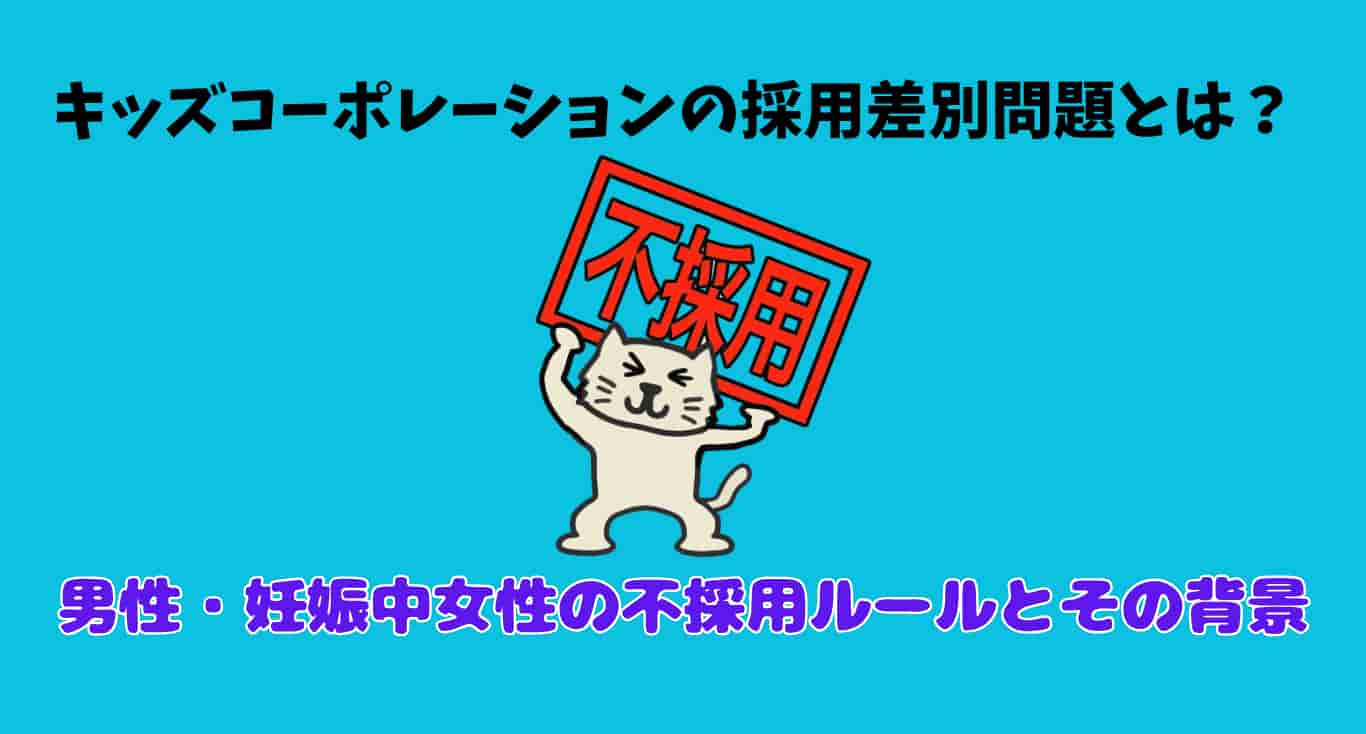
コメント