「年収1200万円もあるのに苦しいなんて贅沢では?」——そんな声とは裏腹に、子育て世代の間では深い不満と不安が広がっています。
収入が少しずつ増えても、それ以上に上がる物価や光熱費。さらに、社会保険料や住民税といった“見えにくい固定負担”が家計を圧迫します。そして何より厳しいのが、補助制度の“所得制限”。高所得者と見なされることで、保育料の軽減も児童手当も対象外——そんな“制度の谷間”で、3人目の妊娠をためらう家庭が増えています。
この記事では、こうした「見えない貧困」に苦しむ子育て世代の実情と、今の社会制度の矛盾について、一般市民の視点からリアルにお伝えします。どうか一緒に考えてみませんか。
「3人目」妊娠で揺れた心──年収1200万円でも不安な現実
「3人目ができたかもしれない」。そう打ち明けた友人は、世帯年収が1200万円を超える共働き家庭の母親でした。誰が聞いても「裕福」と思われる数字。
それでも彼女は「このまま産んでいいのか」と不安で涙ぐんでいました。
保育園の空きはない、長男の中学受験が控える、住宅ローンはあと20年。共働きとはいえ、外食や旅行を抑え、子ども服はフリマアプリ頼み。
彼女だけが特別ではありません。今、多くの家庭が“見えない苦しさ”を抱えているのです。
子育ての理想と経済的プレッシャーの狭間で
「子どもは3人欲しい」「きょうだいがいる方がいいよね」——そんな理想を胸に抱いていたはずなのに、現実はあまりにも厳しい。
3人目を考えたとき、「本当に育てられるのか」と経済的な壁が立ちはだかります。
学習塾にかかる費用、将来の大学進学、家計の中で存在感を増す“教育費”の圧力。さらには、物価の上昇や電気代の高騰も家計を直撃し、理想を語る余裕さえ奪っていきます。
子育てには、時間もお金も気力も必要です。そのどれもがギリギリの中、「産む」という選択肢をためらう夫婦が、今も静かに悩んでいます。
1.子育て世代を襲う“見えない貧困”

「十分な収入」のはずが、実際はカツカツ
「年収1200万円もあれば余裕でしょ?」。そんな声を受けるたびに、ある母親は言葉に詰まります。
実際には、夫婦共働きで得た収入の多くが住宅ローンや保育園、習い事の月謝に消えていくのが現実。
ボーナスはほぼ学資保険と車検代で終了。残るのは「もうちょっと節約しようか」と言い合う日常です。
数字だけを見れば“高所得”に分類されるこの層が、なぜここまで余裕がないのか。
それは、生活にかかる「基礎費用」が年々膨らんでいるからです。
教育費・住宅ローン・物価高…三重苦の家計
中学受験を視野に入れた家庭では、小学3年生から塾通いを始めるケースも多く、年間で数十万円が飛んでいきます。
兄弟がいればその倍以上。
加えて、郊外に建てた一戸建ての住宅ローンは月15万円以上。
さらに、物価上昇に伴い食費・光熱費もじわじわと上がり、「気づけば先月より2万円多く出ていた」なんてことも珍しくありません。
家計簿アプリを何度見直しても、赤字ぎりぎり。貯金に回せるお金はわずかで、将来への備えどころではないという声も多く聞かれます。
SNSに潜む“普通の家庭”という幻想
インスタグラムでは、整ったリビング、手の込んだ手作り弁当、笑顔あふれる家族写真が日々投稿され、「これが普通の家庭か」と感じてしまうことも。
しかし、その“普通”を保つために、実際には多くの犠牲や無理があることは表に出てきません。
見えないプレッシャーの中で、「うちは全然できていない」と自己嫌悪に陥る親たち。
3人目どころか、今いる子どもに十分向き合えているのかすら不安になる。それが、今の“見えない貧困”の正体です。
2.第3子を躊躇する理由

保育料や進学費用への具体的な不安
第3子を考えたとき、最初に頭に浮かぶのは「お金」の問題。たとえば保育園の保育料。
所得に応じた負担になるとはいえ、年収1200万円の家庭では軽減措置の対象外になることも多く、毎月の保育料が5万~7万円に達することもあります。
そこに兄弟の習い事や塾代も加われば、1か月の教育関連支出だけで10万円を超えるケースも珍しくありません。
また、私立中学や大学進学を想定すれば、教育資金として最低でも数百万円単位の貯蓄が必要。
「産む」ことはできても、「育て続ける」自信が持てない——それが、3人目をためらう大きな理由になっています。
キャリアとの両立に限界を感じる母親たち
経済的な不安に加え、女性のキャリア継続も大きな壁となります。
たとえば、都内でフルタイム勤務する母親の場合、朝7時に家を出て、子どもを保育園に預け、夜19時に迎えに行くのが日常。
それでも3人目が生まれれば、育休後の復職が難しくなるだけでなく、上の子の送り迎えや病気の対応にも追われ、職場に迷惑をかけているという自責の念に苦しむ人もいます。
「もうこれ以上、両立できない」「昇進も断った」という声も少なくありません。
3人目を産むことで、自分の人生が完全に後回しになる——そう感じている女性は決して少数派ではないのです。
心のゆとりが持てない──精神的負担の実態
「お金が足りない」「時間がない」「自分の居場所がない」——この三重苦は、親の心に大きなストレスを与えます。
実際に、3人育てている知人は「末っ子の夜泣きで寝不足なのに、長女の進学相談や次男の習い事の送迎が重なって、自分を見失いそうだった」と語っていました。
ふと「なんでこんなに疲れてるんだろう」と思うことも多いといいます。子どもはかけがえのない存在である一方で、親もまた一人の人間。心の余裕がなければ、優しく接することも難しくなります。
「産みたい気持ち」はあっても、「育てる気力」が残っていない。そう感じる親が増えている現状があります。
3.どう支える? 社会と政策の役割
十分に機能していない子育て支援制度
子育て支援制度は存在していても、「本当に必要な家庭」に届いていないという声が少なくありません。
たとえば、認可保育園の入所基準では、共働きでも勤務時間が短かったり、在宅勤務だったりすると不利になることもあります。
また、児童手当は所得制限によって段階的に減額され、年収1200万円の家庭ではほとんど支給されないケースも。「支援を受けたくても、“高所得”だからと外される」。
こうした“線引き”が、実情にそぐわない制度設計になっていることに、多くの子育て世代が疑問を抱いています。
“高所得”世帯が支援対象外になる問題
世帯年収1000万円を超えると、「余裕がある家庭」と見なされ、自治体の補助制度から外れることが増えます。
たとえば、医療費助成や学童保育の料金免除なども対象外になることがあり、実際には家計にゆとりがないのに「がまんするしかない」と感じている家庭は少なくありません。
ある父親は「年収の数字だけで判断され、生活の実態は無視される。3人目の出産をためらうのは当然」と話していました。
“中間層”とも呼ばれるこの層が、制度の谷間で孤立している現状は、少子化対策にとっても深刻な課題です。
少子化対策に本当に必要な視点とは
今、求められているのは「どの家庭が苦しんでいるか」を丁寧に見極める制度設計です。
所得ではなく、支出や子どもの人数、地域差なども加味した柔軟な支援策が必要です。
たとえば、3人以上の子どもを育てる家庭には、所得に関係なく保育料を一定額軽減するといった“横断的”な支援も考えられます。
また、労働環境の整備も不可欠です。育児と仕事を両立できる仕組みを企業にも求め、社会全体で「子どもを育てやすい環境」を整えることが、未来の少子化を止める第一歩ではないでしょうか。
まとめ
「3人目が欲しい」と願う気持ちと、「本当に育てられるのか」という不安。
その間で揺れる子育て世代の現実は、年収や外から見える生活水準だけでは決して測れません。
年収1200万円でも、自転車操業のような暮らしに陥ることがある。その原因は、教育費や住宅ローン、保育料などの固定費の重さに加え、社会制度の“穴”がカバーしきれていない現状にあります。
今後、少子化を真剣に食い止めたいなら、「高所得」とされる家庭も含めた“全体を見渡す”支援のあり方が必要です。
数字に惑わされず、声にならない家庭の葛藤や苦しみに耳を傾けること。その先に、すべての子育て世代が安心して「産みたい」「育てたい」と思える社会があるはずです。
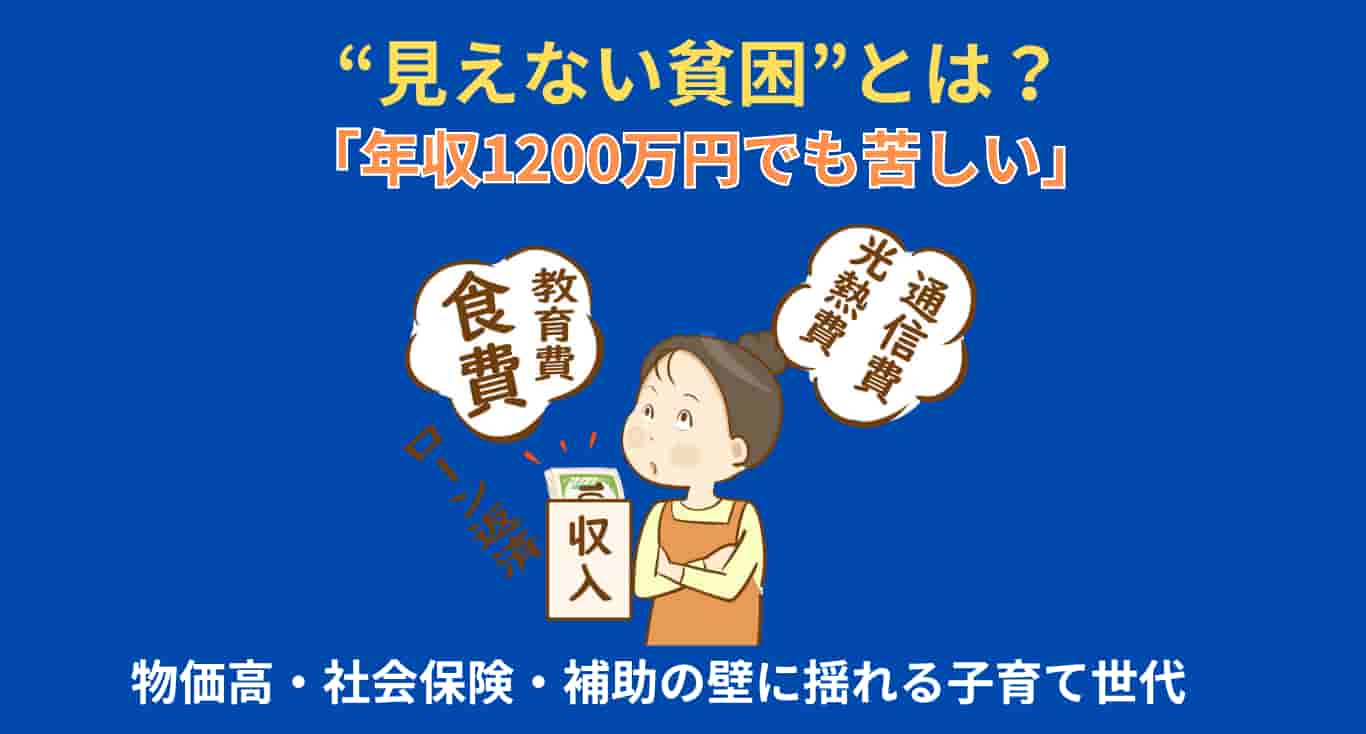
コメント