2024年の日本の出生数が、ついに68万人台にまで落ち込みました。これは明治時代以降でもっとも少ない数字で、いよいよ「少子化の現実」が私たちの目の前に突きつけられた形です。
中でも驚くべきは、40代前半の出産数が20代前半を初めて上回ったという“逆転現象”です。「晩産化が進んでいるだけでしょ?」と片づけるのは早計かもしれません。
このブログでは、一般市民である私の視点から、なぜこんなことが起きたのか、そしてそこに潜む日本社会の深刻な課題について、わかりやすくお伝えしていきたいと思います。
はじめに
出生数最少更新というニュースの衝撃
2024年、日本の年間出生数が68万6061人となり、1899年以降で最も少ない数字を記録しました。
かつて150万人を超えていた時代から見ると、およそ半分以下。
これは単なる統計の数字にとどまらず、家族のあり方や地域社会の未来を考えるうえで、私たち一人ひとりが無関心ではいられない問題です。
子どもが少ないということは、将来の働き手が減り、年金制度や医療、教育など多くの社会基盤が揺らぐことを意味します。
SNS上でも「いよいよヤバい」「これが現実か…」といった声が飛び交い、若者から高齢者まで広く話題にのぼりました。
年齢別で初の逆転現象──40代前半が20代前半を上回る
さらに注目を集めたのは、出生数の年齢別データにおける“異変”です。
なんと、これまで出産の中心世代とされてきた20代前半(20~24歳)の出生数を、40代前半(40~44歳)が初めて上回ったのです。数字で見ても、20~24歳の4万2754人に対し、40~44歳は4万3463人。まさに歴史的な“逆転”です。
この出来事を「晩産化が進んだ証拠」と一言で片づけるのは早計です。
専門家によれば、実は40代前半の出産数が増えたというよりも、20代前半の出産が大きく減ってしまったことが主因とのこと。
結婚・出産のタイミングが大きく変わってきた今、私たちは何を考え、どう向き合うべきなのでしょうか──その答えを探るため、次章から詳しく見ていきます。
1.2024年の出生動向と統計の事実
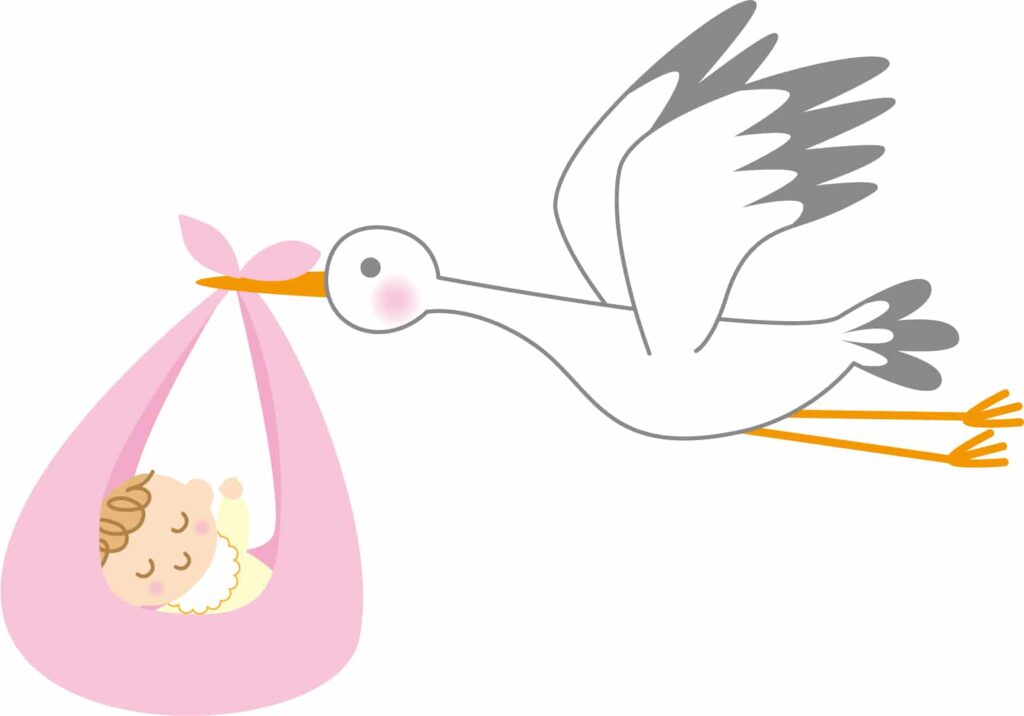
総出生数68万6061人──過去最少を更新
2024年の日本における出生数は、68万6061人。これは明治32年(1899年)に人口動態統計が始まって以来、最も少ない数字です。
かつて高度経済成長期や団塊ジュニア世代が出産期に入った頃には、年間100万人を超えていた時代もありました。その頃と比べると、現代の出生数は7割近く減少しています。
たとえば、1990年の出生数は約123万人。そこから30年余りで半分近くにまで落ち込んでいるのです。
こうした減少は一朝一夕に起こったものではなく、非正規雇用の増加や晩婚化、都市部での子育て負担の重さなど、さまざまな社会背景と結びついています。
40-44歳が20-24歳を上回る初の現象
さらに大きな注目を集めたのが、年齢別の出生数です。
2024年、20~24歳の出生数が4万2754人だったのに対し、40~44歳では4万3463人。
つまり、出産数において40代前半が20代前半を上回るという、これまでにない逆転現象が初めて起きました。
もちろん、これだけを見て「40代の出産が増えた」と考えるのは早とちりです。
実際には、40代前半の出産数は近年横ばいか微増程度。一方で、20代前半の出産数が急激に減っており、ここ数年で約24%もの減少が確認されています。
たとえば2021年には約5万6000人だったものが、3年で4万2000人台まで落ち込んだ計算になります。
この“逆転”は、40代の出産が特別に増えたのではなく、20代の出産が著しく減ったことで起きた結果なのです。
出生率で見ると依然20代前半が高い
数字だけを見ると40代が“勝った”ようにも見えますが、実際にはそう単純ではありません。
出生「率」──つまり、同年代の女性人口に対してどれくらいの子どもが生まれたかを見れば、話は逆になります。
たとえば、2024年の20~24歳女性人口は約277万人。一方、40~44歳は約362万人。
この「分母」の大きさの違いが大きなカギになります。出生率で計算すると、20~24歳は約0.0764、40~44歳はわずか0.0021。つまり、若い世代の方が、出産に至っている割合としては圧倒的に高いのです。
このことからも、「40代の出産増」というより、「若年層の結婚・出産の減少」が真の問題であることがわかります。見かけの数字に惑わされず、その背景を正しく読み解くことが今こそ求められています。
2.背景にある人口構造と婚姻動向

人口の世代差が逆転の背景にある
今回の出生数逆転には、単なる個人のライフスタイル変化だけでなく、人口構造の違いが大きく影響しています。
具体的には、40~44歳の女性人口が20~24歳のそれよりも圧倒的に多いという事実です。
2024年の総務省の推計によれば、20~24歳の日本人女性人口は約277万人。一方、40~44歳は約362万人。
単純に人数だけ見ても、40代前半は20代前半より85万人も多いのです。
これは1980年代に生まれた世代がまだ多かったことが背景にあります。当時は年間の出生数が150万人を超えていた時代で、いわゆる「第二次ベビーブーム」の影響が残っていた層です。
つまり、「40代の出産が多い」のではなく、「40代の女性がそもそも多い」ために、その中から出産する人も相対的に多くなっている、というのが実情です。
反対に、2000年代以降に生まれた20代前半の人口は大きく減少しており、その人数の差が、年齢別出生数の逆転という現象に大きく関わっています。
1980年代生まれの層が多い40代
もう少し背景を掘り下げてみましょう。1980年代前半に生まれた人たちは、いわゆる「団塊ジュニア世代」の一部にあたります。
この世代は、かつての“人数の多い世代”の最後の波といってもよく、人数的にも多いだけでなく、経済的にも比較的豊かな家庭環境で育った人が多いのが特徴です。
そのため、高学歴化・晩婚化の傾向が強く、30代後半〜40代前半での出産を選択する人が他の世代よりも多くなっています。
さらに、不妊治療の技術向上や、高齢出産に対する理解の広がりなども後押しし、この年代での出産が一定数保たれてきた側面もあります。
たとえば、「40代でようやく子どもを授かった」という声は、SNSやメディアでも多く見かけるようになりました。「40代の妊娠はレアケース」ではなくなりつつあるのです。
20代前半の婚姻・第一子出生の大幅減少
一方、20代前半の層では、結婚そのものが大きく減少しており、それに伴って第一子の出生も激減しています。
2021年から2024年までの3年間で、20~24歳の出生数は約24%も減少しました。この数字は単なる傾向ではなく、結婚・出産が人生設計から大きく外れつつあることを示しています。
背景には、経済的不安定さや、将来への見通しの立てにくさがあり、「子どもを育てる余裕がない」「結婚したいと思える相手に出会えない」といった声もよく聞かれます。
また、SNSやマッチングアプリが普及したことで、人とつながる手段は増えたものの、それが結婚や家庭につながりにくくなっている現状も無視できません。
さらに、非正規雇用や長時間労働、住居費の高騰といった社会的課題が若年層を直撃しています。
たとえば、都内で一人暮らしをしながら生活する20代女性が、結婚・妊娠・出産を考える余裕がないと語る声も珍しくありません。
こうしたさまざまな要因が重なり、20代前半での結婚や出産は、かつての“当たり前”ではなくなりつつあるのです。
3.国際比較と少子化の本質的要因

韓国は20代出生率壊滅で将来展望なし
少子化が進むのは日本だけではありません。とくに深刻なのが韓国です。
韓国の2023年の合計特殊出生率(ひとりの女性が一生に産むとされる子どもの数)は0.72と、世界で最も低い水準を記録しました。その背景にあるのは、20代女性の出生率がほぼ“壊滅的”なまでに下がっているという現実です。
たとえば、ソウルでは20代女性の出生率が0.1を切る地域もあるとされており、20代での出産が「選ばれない選択」になっていることがうかがえます。
その影響で、30代や40代の出生率が少し上がっても、全体の出生数を補うには到底追いつかない状態に陥っています。
韓国では住宅価格の高騰や教育費の過熱、就職競争の激化などが若者の結婚・出産への意欲を削いでおり、日本と似た構造問題を抱えながらも、より極端な形で進行しているのです。
出生率1.5超の国は20代出生が鍵
一方、出生率1.5を超える比較的“健闘している”国々を見ると、ある共通点があります。それは「20代での出産がそれなりに維持されている」という点です。
たとえば、フランスやスウェーデンでは、20代後半の女性を中心に出産が多く見られ、社会全体が若い世代の子育てを支える仕組みになっています。
手厚い育児休暇制度、無料または安価な保育、育児とキャリアの両立をサポートする職場環境などが整っており、「若いうちに産んでも生活が成り立つ」という安心感があります。
日本の場合、制度は存在していても利用しづらい、職場の理解が薄い、非正規雇用では恩恵が受けにくい、といった“実行面の壁”が根強く残っており、これが20代出産を妨げている要因の一つです。
「晩産化」では説明できない本質とは
今回の出生数逆転を「晩産化が進んでいるだけ」と片づけるのは、問題の本質を見誤ります。
確かに40代の出産は増えましたが、それ以上に20代の出産が減っており、それが少子化を決定づける最大の要因になっているのです。
出生数を支えるには、ある程度の人口規模を持つ若い世代が、安定した生活基盤を得て、子どもを持つことを“希望できる”環境が必要です。
つまり、出産年齢が何歳であるかよりも、「出産したくてもできない」若年層の不安や困難にこそ、真正面から向き合う必要があります。
晩婚・晩産を選ぶ人が増えたのは事実ですが、それはあくまで選択肢の一つ。若いうちに子どもを持つことが“贅沢”ではなく“普通”である社会に戻せるかどうか──それが、少子化対策の核心と言えるでしょう。
まとめ
2024年、日本の年間出生数は68万6061人と、統計開始以来もっとも少ない記録となりました。
さらに注目すべきは、年齢別で40代前半の出生数が20代前半を初めて上回ったという「逆転現象」です。しかし、これは単に晩産化が進んだというより、20代前半の結婚・第一子出産の激減がもたらした“結果”にすぎません。
その背景には、人口構造の変化──つまり40代前半の女性人口が多いという単純な数の差もありますし、経済的な不安やキャリアとの両立の難しさといった、若い世代を取り巻く厳しい現実も横たわっています。
国際的に見ても、出生率1.5を維持する国々は20代での出産がある程度支えられており、逆に韓国のように20代出産が極端に減った国では、少子化に歯止めがかかっていません。日本もいま、同じ道を歩みつつあります。
「若いうちに産め」と圧力をかけるのではなく、20代の人々が自然に結婚や出産を“選べる”ような社会環境を整えること。
そのためには、雇用や住まい、育児支援の制度を、机上の理屈ではなく実生活にフィットさせることが求められています。
少子化の解決は遠い課題に思えるかもしれませんが、今、目の前にいる20代の声に耳を傾けることこそが、長い目で見て持続可能な社会の第一歩となるのです。
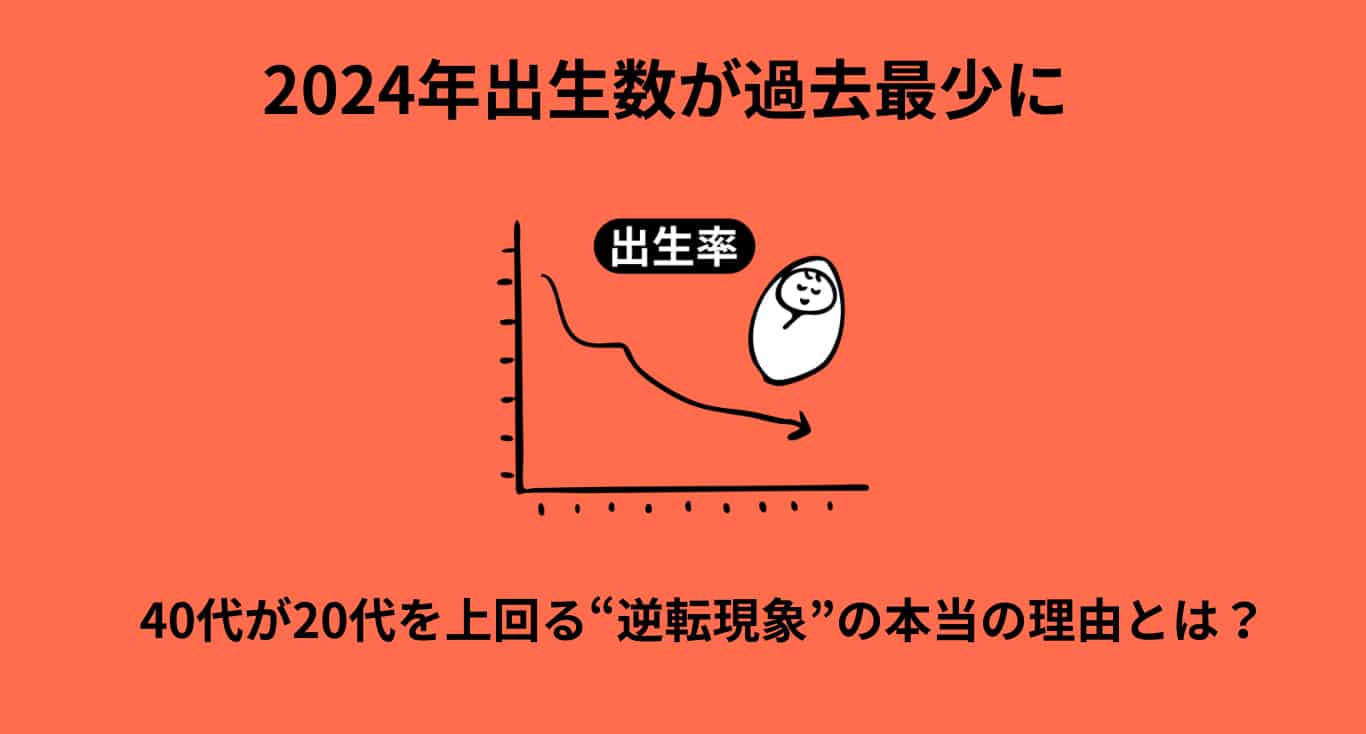
コメント