2025年8月30日・31日に放送される日本テレビ系『24時間テレビ48 愛は地球を救う』では、恒例のチャリティーマラソンに横山裕さん(SUPER EIGHT)が挑戦します。
昨年はお笑い芸人のやす子さんが走り、5億円以上の寄付を集めました。
今回の新たな目的別募金「マラソン子ども支援募金」にも注目が集まっています。
一方で、猛暑下での開催や出演者のギャラ問題など、賛否の声も少なくありません。
本記事では、横山裕さんが走る意味や番組の社会的影響、そして視聴者の反応をわかりやすく解説します。
はじめに
24時間テレビ48とチャリティーマラソンの概要
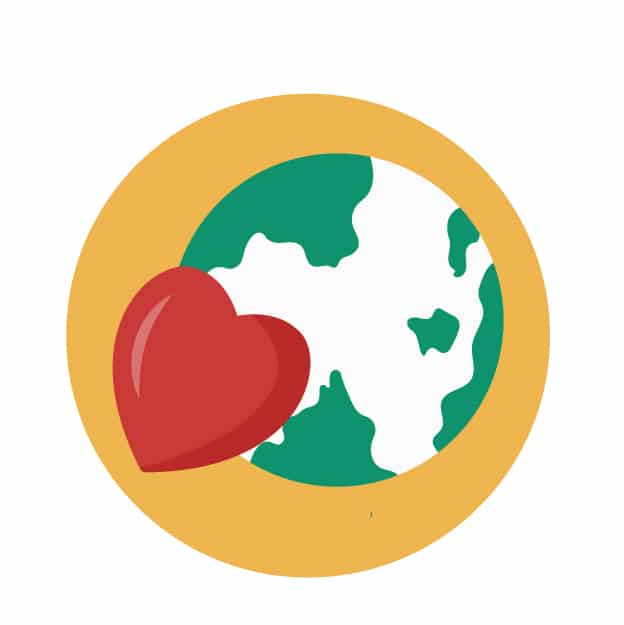
日本テレビ系で毎年夏に放送される『24時間テレビ 愛は地球を救う』は、チャリティーをテーマとした特別番組です。
その中でも恒例となっているのが、著名人が長距離を走る「チャリティーマラソン」です。
2025年の第48回大会では、アイドルグループSUPER EIGHTの横山裕さんがランナーを務めることが発表されました。
昨年はお笑い芸人のやす子さんが児童養護施設を支援するための「マラソン児童養護施設募金」の旗を掲げて走り、結果として5億円以上もの寄付を集める成果を上げています。
このチャリティーマラソンは、ただ走るだけではなく、ランナー自身が社会問題に関心を持ち、その思いを視聴者に届けることに大きな意味があります。
横山さんも「困難を抱える子どもたちの存在を知ってほしい」とコメントしており、2025年は「マラソン子ども支援募金」という新しい目的別募金が開設されました。
番組への期待と批判の両面
一方で、このマラソン企画には賛否の声がついて回ります。
「チャリティー番組として素晴らしい」とする声がある一方で、「猛暑の中で芸能人を走らせる必要があるのか」「感動を演出するために過酷な状況を作っているのではないか」といった批判も少なくありません。
さらに「出演者にギャラが支払われているのは矛盾ではないか」という指摘もあります。
番組側は今年、炎天下を想定して徹底した暑さ対策や安全面での“厳戒態勢”を敷くことを発表しましたが、その慎重さ自体に違和感を抱く視聴者もいるようです。
長年続いてきたこの企画が社会にどのような影響を与えているのか、そして今後も続けるべきなのか。期待と批判の両面が入り混じる中で、第48回のマラソン企画は大きな注目を集めています。
1.横山裕が挑むチャリティーマラソン

横山裕ランナー決定の背景
横山裕さんがランナーに選ばれた背景には、彼の人柄と影響力があります。
SUPER EIGHTのメンバーとして音楽活動やバラエティ番組への出演を続けてきた横山さんは、明るいキャラクターと誠実な発言で多くのファンに支持されています。
番組関係者は「困難を抱える子どもたちに寄り添う姿勢が、今回のテーマに合致した」と話しており、彼自身も「自分にできる形で誰かを応援できるなら」とコメントしています。
また、横山さんは過去にも災害復興支援や募金活動に参加してきた経験があり、社会貢献に関心を持っていることでも知られています。そのため、今回の起用は視聴者にとっても納得感のある選択だったといえます。
マラソン子ども支援募金の新設
2025年は、新たに「マラソン子ども支援募金」が開設されました。
この募金は、生活困窮や虐待などで困難な状況に置かれた子どもたちへの支援を目的としています。横山さんが走ることで集まる寄付金は、教育支援や生活環境の改善に活用される予定です。
昨年の「マラソン児童養護施設募金」では、やす子さんの走りが視聴者の心を動かし、5億円以上の寄付が集まりました。
今回も同様に、横山さんの真摯な挑戦が社会に与える影響が期待されています。
番組関係者は「寄付金額だけでなく、子どもたちの存在を知ってもらうきっかけになることが重要」と強調しています。
過去のやす子ランナー事例と寄付実績
2024年にランナーを務めたやす子さんは、もともと自衛官として社会奉仕に携わってきた経験を持ち、その姿勢が視聴者の共感を呼びました。
炎天下での厳しいコースを走り切った姿に、多くの人が心を動かされ、寄付総額は5億493万6310円に到達しました。
この結果は単に金額として大きいだけでなく、「誰かのために走る」という姿勢が持つ力を証明するものでした。
横山さんの挑戦は、この実績を引き継ぐ形で行われることになり、番組としてもより大きな社会的意義を目指しています。
特に今年は猛暑対策として給水ポイントを増やすなど安全面が強化されており、安心して見守れる環境づくりにも注力しています。
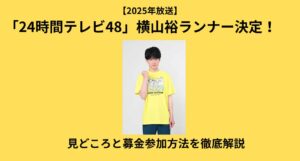
2.番組の社会的影響と評価
チャリティー番組としての意義
『24時間テレビ』は、チャリティーをテーマに掲げることで、普段は関心が薄くなりがちな社会問題に光を当てる役割を担っています。
障がい者スポーツの普及や災害被災地支援、児童福祉施設への寄付など、過去の放送で取り上げられたテーマは多岐にわたります。
特に、チャリティーマラソンは「誰かのために走る」というメッセージを体現し、視聴者に“助け合う気持ち”を思い起こさせるきっかけとなっています。
実際に番組がきっかけで募金活動に参加する人や、地域でのボランティアに興味を持つ人も少なくありません。たとえば、昨年の放送では、やす子さんの走る姿に心を動かされた視聴者が「寄付は初めてだけど参加した」とSNSで投稿するなど、行動変容につながる例もありました。
映像制作・企画構成の完成度
『24時間テレビ』は、マラソンだけでなくドラマやドキュメンタリー企画も高く評価されています。
特に、視聴者の心に訴えかける編集技術や構成力には定評があります。
過去には実話をもとにした感動的なドラマが話題になり、SNSでトレンド入りするなど、番組全体の完成度が注目を集めました。
また、映像制作の現場では、現役のテレビマンだけでなく映像演出の専門家も参加しており、長時間放送であっても飽きさせない工夫が随所に見られます。
今回の第48回放送も、マラソンと並行してドラマ・バラエティ・音楽企画を組み合わせ、チャリティーをエンターテインメントとして届ける点で期待されています。
視聴者・社会の反応と批判的視点
一方で、番組への批判も根強く存在します。「感動の押し付け」や「出演者にギャラが支払われているのは矛盾ではないか」といった指摘は、毎年のようにSNSやメディアで取り上げられます。
また、猛暑の中でのマラソン企画に対しては「出演者の体調リスクを伴うやり方は時代に合わないのでは」という声も増えています。
特に今年は、横山裕さんが走ることに注目が集まる一方で、「炎天下で走らせる意味はあるのか」「本当に子どもたちの支援につながっているのか」という疑問も呈されました。
しかし、寄付金総額が年々高水準を維持していることや、子ども支援や福祉への関心を呼び起こしている実績は否定できません。
番組は社会的な影響を与え続けており、期待と批判の間で揺れながらも存在意義を保っています。
3.マラソン企画への疑問と課題
厳戒態勢の暑さ対策と安全面
2025年のチャリティーマラソンは、真夏の終わりに行われるため、酷暑との戦いが避けられません。
番組側はランナーの体調を最優先に考え、給水ポイントの増設、走行ルート周辺のミスト設置、救護スタッフの増員など、例年以上の暑さ対策を実施すると発表しています。
しかし、この「厳戒態勢」という表現に違和感を覚える声もあります。
「そこまでリスクを負ってまでマラソンを続ける必要があるのか」という疑問です。
特に視聴者の中には、「感動よりも安全性を重視すべき」「別の方法で寄付を呼びかければいいのでは」という意見も多く見られます。
酷暑が常態化する中で、このマラソン形式が今後も適切なのか、考え直す時期に来ているといえるでしょう。
芸能人ギャラ問題とボランティア精神
毎年議論になるのが、出演者にギャラが支払われている点です。
「チャリティー番組なのに、なぜ出演料が出るのか」という批判は根強く、SNSでも「ノーギャラで出演するタレントを起用すべき」という意見が相次いでいます。
実際、一部の芸能人は「この番組だけは無償で出演する」と公言しており、その姿勢が好意的に受け止められることもあります。
ギャラを払うこと自体は制作上の慣習ともいえますが、視聴者からすれば「善意の象徴である番組と金銭のやり取り」という構図が矛盾して見えてしまうのです。
今後は、出演条件の見直しや、ボランティア精神を前面に出した番組作りが求められていくでしょう。
異常気象時代における新たなチャリティーのあり方
異常気象が日常化しつつある現在、屋外での過酷な企画に依存したチャリティーの形は見直されるべきです。
オンラインで参加できるチャリティーランや、SNSを活用した寄付キャンペーンなど、時代に合った新しい取り組みはすでに広がりつつあります。
例えば、2024年に別局が行ったオンラインウォーキングイベントでは、参加者がスマホアプリを使って歩数を寄付金に変える仕組みが採用され、全国から幅広い世代が参加しました。
このような企画なら気候や地域を問わず参加でき、より多くの人の関心を集める可能性があります。『24時間テレビ』も、この流れを取り入れることで、チャリティーとしての意義を一層高められるかもしれません。
まとめ
『24時間テレビ48』は、横山裕さんの挑戦を通じて子ども支援の重要性を伝え、多くの人に寄付やボランティアへの関心を呼びかけています。
番組は長年、チャリティーをエンターテインメントとして届ける独自のスタイルで、社会に一定の影響を与えてきました。
一方で、酷暑でのマラソン実施や芸能人へのギャラ支払いといった点は、時代の変化に伴い見直しが求められています。
特に異常気象や社会の価値観の多様化を踏まえれば、より安全で持続可能な新しいチャリティーの形を模索することが大切です。
視聴者の心を動かしながらも、批判に向き合い、進化する番組であることが求められているのではないでしょうか。
横山さんの走りと、その思いが未来のチャリティーのあり方を考えるきっかけとなることに期待が集まっています。
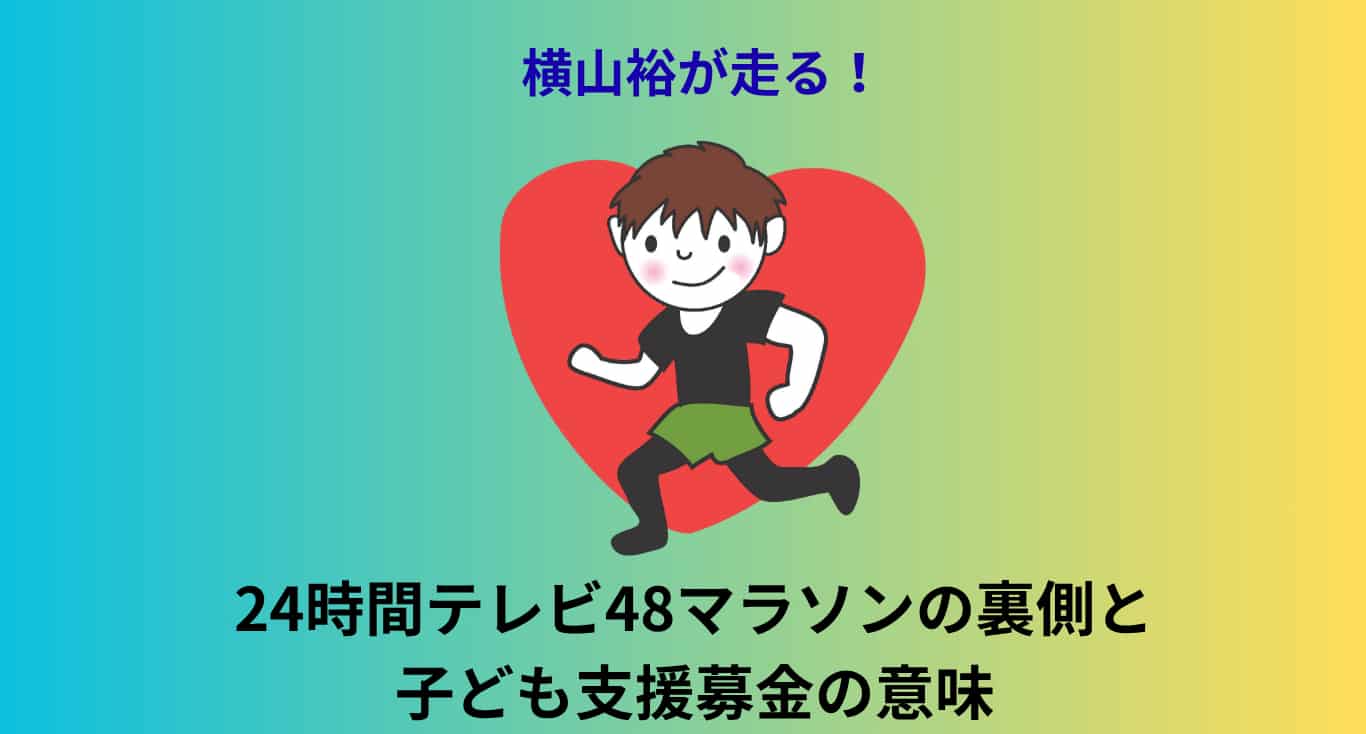
コメント