見出しの一語が想像以上の波紋を呼び、同日中に記事は削除。
SNSで拡散した指摘、編集段階で止められたチェックポイント、そして発信者が今日から使える“誤読に強い言い換え”まで、実例ベースでまとめました。
はじめに
TBSニュースの表現が物議を醸した背景
2025年10月7日、ニュースサイト「TBS NEWS DIG Powered by JNN」が掲載したある記事が、思わぬ形で炎上する事態となりました。
取り上げられたのは、タレントの辻希美さんの長女・希空さんが、自身の妹である生後2か月の夢空ちゃんを抱く微笑ましい写真。
しかし、記事タイトルに使われた「安らかに眠る妹・夢空ちゃん」という表現が、「まるで訃報のようだ」と多くの読者を驚かせたのです。
「安らかに眠る」という言葉は、一般的に故人を悼む際に使われる表現として定着しています。
そのため、赤ちゃんが寝ているだけの写真に対してこの言葉を使うのは不適切ではないかという声が相次ぎ、SNS上では「ぎょっとした」「タイトルだけで一瞬ヒヤッとした」といった反応が広がりました。
この出来事は単なる「言葉の選び方」の問題にとどまらず、報道機関が扱う表現の感覚や倫理、そして読者の受け取り方の多様化を浮き彫りにしています。
辻希美さんの家族写真が思わぬ方向で注目を集めた理由
辻希美さんといえば、SNSを通じて家族の日常を積極的に発信し、「理想のママ像」として支持される一方、常に賛否の声がつきまとう存在でもあります。
今回の写真も、本来であれば「姉妹の微笑ましい一枚」として話題になるはずでした。実際、希空さんの投稿文には「18歳差姉妹です」とあり、家族の温かさを伝える内容でした。
ところが、「安らかに眠る」という言葉の選択が“炎上の火種”となり、写真自体にも別の角度から注目が集まることに。
赤ちゃんの首の角度や抱き方をめぐって、「映えを意識しすぎ」「危なっかしく見える」といった指摘が飛び交い、まるで本来の意図とは異なる方向で議論が拡大していきました。
言葉の一つ、写真の一枚が、SNS社会では想像以上に大きな波紋を呼ぶ——。この一件は、現代の報道やインフルエンサー文化が抱える“表現のリスク”を改めて考えさせる出来事となりました。
1.「安らかに眠る」表現への批判
訃報連想を招いたタイトルの問題点
TBS NEWS DIGが使用した「安らかに眠る」という表現は、一見すると柔らかく優しい言葉のように見えます。
しかし、多くの日本人にとってこの言葉は“死を連想させる慣用句”として定着しており、報道や訃報の文脈以外で使われることは極めて稀です。
そのため、「安らかに眠る妹・夢空ちゃん」というタイトルを目にした読者の多くが、「亡くなったのかと思った」「まさか赤ちゃんに何かあったのかと焦った」と感じたのも無理はありません。
実際、ニュースタイトルはSNSのサムネイルや検索結果で単独表示されることが多く、本文を読む前の“第一印象”が非常に重要です。
報道機関が伝えるニュースタイトルにおいて、文脈を誤解させる表現を選ぶことは、それだけで読者の信頼を損なうリスクを伴います。
結果的に、今回のTBSの記事は「タイトルの不適切さ」だけでなく、「メディアの表現感覚そのもの」に対して批判が集中する形となりました。
ネット上の反応と「ぎょっとした」との声
SNS上では、記事公開直後から「安らかに眠る」という言葉選びに対する驚きや違和感の投稿が相次ぎました。
「赤ちゃんの寝顔なのに“安らかに眠る”って…言葉のチョイスが怖い」
「こういうの、チェックする人いないの?報道としてセンスなさすぎ」
といった声がX(旧Twitter)やコメント欄に多数寄せられました。
また、一部のユーザーは、過去に報道各社が同様の表現ミスをした事例を挙げながら、「TBSだけの問題ではない」「ニュース業界全体の言葉の感覚が鈍っている」と指摘する投稿も見られました。
一方で、「単なる言葉のあやに過剰反応では?」といった擁護意見もあり、ネット上では「言葉の適切さ」をめぐる議論が二極化する結果となりました。
「安らかに眠る」は報道用語として適切か?
本来、「安らかに眠る」という言葉は“永眠”を婉曲に表現するために使われてきた日本語です。
宗教や文化的背景を問わず、訃報の際に「どうか安らかにお眠りください」と使われることが一般的であり、日常的な「お昼寝」や「睡眠」とは明確に意味が異なります。
報道機関がこの言葉を「眠っている赤ちゃん」に対して使用すれば、読者が死を連想するのは当然とも言えるでしょう。
今回のケースは、ニュースメディアにおける「言葉の慎重さ」や「文脈の読み取り力」の欠如を象徴する出来事です。
特に、AIによる自動生成タイトルや外注記事が増える昨今では、こうした“誤用リスク”がさらに高まっています。
ニュースを発信する立場にあるメディアこそ、読者の感情に寄り添う丁寧な言葉選びが求められているのではないでしょうか。
2.「無言の帰宅」騒動との比較
言葉の選び方がもたらす誤解と炎上
今回の「安らかに眠る」という表現に対して、「まるで『無言の帰宅』と同じレベルだ」という声がSNS上で相次ぎました。
この「無言の帰宅」とは、2025年9月末ごろに話題となった別の騒動を指します。あるSNSユーザーが、外出先で亡くなった配偶者の遺体が自宅に戻ってきた際、「無事、無言の帰宅となりました」と投稿したのです。
この投稿には「よかったですね」「安心しました」といった誤解した祝福コメントが寄せられ、瞬く間にネットで炎上しました。
どちらのケースにも共通しているのは、「表現の選択がもたらす誤解の連鎖」です。
日本語は文脈によって意味が変わりやすく、普段使われる言い回しでも場面を間違えれば大きな誤解を招きます。特に、死を連想させる言葉や婉曲表現は、読み手の感情に大きな影響を与えるため注意が必要です。
TBSの記事タイトルも、意図としては「すやすや眠る」や「幸せそうに眠る」といった優しい描写だったのかもしれません。
しかし、ニュースサイトという公共性の高い場では、その微妙なニュアンスのずれが「炎上」として跳ね返ってしまったのです。
「無言の帰宅」と「安らかに眠る」に共通する問題
「無言の帰宅」も「安らかに眠る」も、もともと葬送や訃報の場で使われる言葉です。それを「日常の出来事」や「家族の写真」に使ってしまったことが、共通する誤用ポイントと言えます。
つまり、どちらも「使う場面を誤った結果、悲しみを連想させてしまった」ケースなのです。
SNSでは、「無言の帰宅=故人が家に戻ること」「安らかに眠る=永眠を意味すること」という認識が一般的に共有されています。
にもかかわらず、報道機関があえてこのような表現を採用したことで、「感覚がズレている」「人の気持ちを考えていない」との批判が集中しました。
特にTBSのケースでは、命に関わる報道ではなく、あくまで「芸能ニュース」。その中で“死のメタファー”を連想させる表現が使われたことに、多くの人が違和感を抱いたのです。
メディアの日本語表現に求められる配慮とは
ニュースタイトルは限られた文字数の中で印象的に伝える必要があります。しかし、「印象的=刺激的」と短絡的に捉えると、今回のように“誤解を招く表現”になりやすいのも事実です。
メディアには、視聴者の興味を引くだけでなく、「読者がどんな背景や感情で読むか」を想定した言葉選びが求められます。
また、SNS時代では見出しだけが拡散されるケースも多く、本文を読まないまま誤った印象が広がるリスクも高まっています。
その意味で、タイトルにおける一言一句の責任は、以前よりも格段に重くなっていると言えるでしょう。
「無言の帰宅」や「安らかに眠る」という言葉の炎上は、単なる“言葉狩り”ではありません。言葉が持つ文化的背景や読者の感情を軽視した結果起きた「伝達ミス」であり、報道や表現を扱うすべての人にとっての警鐘なのです。
3.報道倫理とSNS時代の影響
TBS NEWS DIGの記事削除までの経緯
今回の件では、問題のタイトルが公開されたのち、短時間で批判が集まり、同日中に記事が削除されました。
時系列で見ると、①希空さんがインスタに「18歳差姉妹です」と投稿 → ②ニュースサイトが「安らかに眠る」を含むタイトルで記事化 → ③SNSで「訃報連想」の指摘が急拡散 → ④当該記事が削除、という流れです。
本来、炎上が起きたときの基本対応は「誤りの認定」「修正・再掲」「経緯の説明」の三点です。
今回は削除までは実施されましたが、タイトル選定の経緯やチェック体制についての説明が見えづらかったため、「なぜこの言葉が通ったのか」「同様のミスを防ぐ仕組みはあるのか」という不信が残りました。
見出しは読者の第一印象を決める“看板”。公開前のダブルチェック(担当→デスク→校閲)や、死や事故を連想させる語のNGリスト化など、仕組みでリスクを下げる発想が不可欠です。
SNSでの言葉狩り・過剰反応の現状
SNSでは、ことば一つが単独で拡散され、文脈から切り離されやすくなっています。
今回も「安らかに眠る」というフレーズだけが画像キャプチャで回り、本文の意図や写真の雰囲気が伝わらないまま評価が確定していきました。
一方で、「過剰反応」と見える指摘にも理由があります。死に関わる言い回しは、受け取り手の体験(喪失の記憶など)と強く結びつくため、少数の違和感が一気に共感を呼びやすいのです。
重要なのは、①配慮に欠けた表現は改める、②指摘の口調が攻撃的になり過ぎないよう互いに自制する、という両立です。
言葉の選択に敏感な時代だからこそ、「誤用の指摘」と「個人攻撃」を切り分け、建設的に修正へつなぐ文化を育てたいところです。
家族写真や赤ちゃん写真を巡る“映え文化”の課題
議論は「言葉」から「写真」へも広がりました。
赤ちゃんの首の傾きや抱き方に対し、「安全面が不安」「映え優先では」といった声が集まったのは、SNSにおける“演出”が安全配慮を上回るのでは、という社会的な懸念の表れです。
育児写真を発信する際に意識したいポイントはシンプルです。
- 安全最優先:首すわり前は必ず首を支える、無理な角度・姿勢を避ける。
- 誤解を招かない画角:一瞬の切り取りで危険に見えないよう、支えの手やクッションなどもフレームに入れる。
- 説明のひと言:撮影状況や月齢など、見る人が安心できる補足をキャプションで添える。
“かわいい”や“おしゃれ”はSNSの楽しさですが、家族の記録ほど長く残るものはありません。赤ちゃんの心身への配慮が第一、演出はその次。
今回の一件は、メディアだけでなく、私たち一人ひとりの「見せ方」と「受け取り方」を見直す機会にもなったと言えるでしょう。
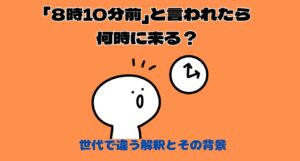
まとめ
今回の騒動は、「安らかに眠る」や「無言の帰宅」といった“訃報を想起させる定型句”を、日常シーンに流用したことで生じたミスコミュニケーションでした。
見出しは単体で拡散され、文脈が切り離される——このSNS時代の前提において、メディアと発信者は従来以上に言葉へ慎重である必要があります。
実務的には、①死・事故・災害を連想させる語のNGリスト化、②公開前チェック(担当→デスク→校閲)の多段化、③誤用発生時の「修正・注記・再掲」フローの明文化、の三点が有効です。表現の強さよりも誤読耐性を優先する姿勢が、結果的に信頼を守ります。
同時に、受け手側も“言葉狩り”と“正当な指摘”を分けて考える視点が求められます。
攻撃的な糾弾は議論を狭め、適切な改善を遠ざけます。建設的な指摘と丁寧な修正が往復することで、表現の質は上がっていきます。
家族写真、とりわけ乳児の写真は安全配慮が第一です。首すわり前は必ず支える、危険に見えない画角を選ぶ、月齢や撮影状況を一言添える——小さな工夫が誤解を防ぎます。
“伝わる言葉”と“安心して見られる写真”。この二つを意識し続けることが、炎上を避けるだけでなく、ニュースや日常の発信を気持ちよく届ける最短ルートです。

コメント