2025年7月20日の参議院選挙開票特番「選挙ステーション」(テレビ朝日系)にて、有働由美子キャスターと参政党代表・神谷宗幣氏とのやり取りが大きな波紋を呼んでいます。
そのやりとりをめぐっては、SNS上で「偏向報道では?」「言論封殺だ」「有働氏の質問がしつこすぎる」といった声と、「神谷氏の回答が曖昧すぎる」「質問にまともに答えていない」といった反応が二極化。
この記事では、番組中のやり取りとSNS上の論争を詳しくまとめました。
緊迫したスタジオ 核兵器をめぐる攻防
番組中、有働氏は神谷氏に対し「日本も核を持つということですか?」と繰り返し問いかけました。
神谷氏は「抑止力として何かを持つことも考える」としながらも、最終的には「今すぐ核武装を目指すわけではないが、将来的には核シェアリングなどを検討する可能性がある」と回答。
しかし、有働氏は「それは結果的に“核保有に前向き”とも受け取れる」とさらに踏み込み、広島や長崎への原爆投下に言及しながら重ねて質問。
神谷氏は「バリアや電磁波のような核以外の抑止力を探るべき」とも述べましたが、その回答は「現実味に欠ける」としてネットでも議論を呼びました。
SNS上の声①:偏向報道だ!有働由美子への批判

この一連のやりとりに対し、参政党支持層や保守系ユーザーを中心に、X(旧Twitter)では以下のような声があがりました。
- 「なぜ神谷氏だけ“さん付け”?他の党首は“代表”や“党首”で呼ばれていたのに」
- 「偏向報道すぎる。テレビ朝日は参政党潰しをしているのか?」
- 「有働さん好きだったのに…これじゃあ“有働ステーション”だよ」
- 「電磁波やバリア発言をバカにして笑い者にするのは印象操作」
一部では「報道ステーションに抗議の電話をしよう」とスポンサー一覧を拡散する投稿もあり、テレビ朝日への不信感が強まっています。
SNS上の声②:神谷氏の回答が弱すぎる?
その一方で、こうした偏向批判とは逆に、「神谷氏が答えられないのが悪い」「揚げ足取りではなく当然の質問だ」とする声も。
- 「そもそも参政党は“核保有・徴兵制”を掲げてるんだから聞かれて当然」
- 「電磁波で国防って…ギャグですか?」
- 「言論の自由を主張する政党が、自分に都合の悪い質問は封じたがるのは矛盾」
神谷氏が持論をうまく伝えきれなかったことへの批判もありました。
「言論の自由」をめぐるねじれた構図
参政党は過去にもTBS報道番組への抗議声明を発表するなど、メディア対応に敏感な姿勢をとってきました。
その背景には「メディアが我々の言論を封じようとしている」という不信感があります。
ただし、一部の視聴者は「言論の自由を守れ」と訴える参政党が、独自の憲法草案で“国が報道を管理すべき”と提言している点を指摘。
「本当に自由を守ろうとしているのか?」という疑念も湧き起こっています。
また、番組中のやり取りとは別に、7月中旬にはX(旧Twitter)上で参政党支持者の大手アカウントが一斉凍結される事案も発生。
これがさらに「ネットとテレビで言論封殺が行われている」との見方を強め、今回の騒動にも影響を及ぼしました。
むしろ“神谷上げ”になった?逆転の印象効果
興味深いのは、SNS上に「有働さんのおかげで神谷さんの良さがわかった」「逆に支持したくなった」といった声も見られたこと。
過剰な追及が視聴者に「いじめ」に見えたことで、神谷氏に対する“同情票”が集まった可能性もあります。
こうした「メディア vs 政党」の構図は、視聴者の立場によって真逆の印象を生み出すリスクもあることを示しています。

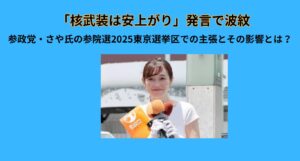
メディアの逆風が追い風に?──参政党躍進に見る「偏向報道」と大衆のねじれ現象
2025年7月20日、参院選の開票特番でテレビ朝日の報道番組に出演した参政党・神谷宗幣氏と、有働由美子キャスターのやり取りがSNSを中心に大きな物議を醸しました。
一部メディアからは明らかに批判的なトーンで扱われた参政党。しかし、選挙結果はその「逆風」ともいえる状況を吹き飛ばすような大幅な議席増という“躍進”でした。
この“ねじれ現象”──すなわち「メディアの懸念」と「民意の評価」のズレは、一体なぜ起こったのでしょうか?
ここからは、兵庫県知事選での斎藤元彦氏再選劇とも共通する構造から、現代における情報の信頼性・共感・選択の変化を読み解きます。
「偏向報道」がもたらす“逆転効果”
番組内で有働氏が神谷氏に対して繰り返し「日本も核を持つのか」と詰め寄る場面があり、「言葉狩りのようだ」「いじめに見える」といった批判がSNS上で拡散されました。
一方で、メディア側の主張は「国防に関する政策を問いただすのは当然の責務」としており、まさに「どちらが常識か」という感覚の衝突でした。
その結果として生じたのが、メディアに懐疑的な層からの“逆張りの支持”です。
「叩かれてるってことは、むしろ正しいことを言ってるんじゃないか?」
「大手メディアが怖れてるってことは、本質を突いてる証拠だ」
といった投稿がX(旧Twitter)上で数多く見られ、参政党に対する“感情的共感”が一気に広がりました。
SNSで変わる「真実」の見え方
参政党の選挙戦は、オールドメディアが支配してきた政治報道に対するネット市民の“反旗”という側面も持っています。
候補者や支持者がYouTube、X、Instagramなどを活用して直接発信し、テレビや新聞を介さずに支持層を形成できる時代。情報の流通経路が変わったことで、“真実”の定義すら変わりつつあるのです。
今回の選挙では、テレビではネガティブに扱われた候補が、SNS上では「現場に立つリアリスト」として支持された例がいくつも見られました。
ファクトチェックの限界と“誰が言うか”の時代
選挙期間中、「ファクトチェック」が多くのメディアで導入され、各政党や候補者の発言が検証されました。
しかし、参政党支持者からはこの動きに対し、以下のような疑念の声が上がりました。
- 「結局、都合の悪い主張を“誤情報”として切って捨ててるだけでは?」
- 「“正しいかどうか”より、“誰が正しいと言うか”の方が問われている」
つまり、ファクトよりも“解釈”が主導権を持つ時代に突入しているとも言えるのです。
正解は一つではなく、信じたいものを選ぶという構造に、有権者の判断が左右されるようになっています。
斎藤兵庫知事と参政党に見る“ねじれ現象”の共通点
2024年秋の兵庫県知事選でも、斎藤元彦氏に対し一部大手紙やテレビが批判的な論調を強める中、SNSでは「オールドメディアに屈しない姿勢」に共感が集まり、再選を果たすという展開がありました。
この構造は今回の参政党にも共通しています。
- メディアが「危険」「過激」と評する
- SNSでは「メディアが叩いてる=信じられる」という逆転のロジックが発動
- メディア不信層が団結し、投票行動に結びつく
このような「反メディア的共感の結晶化」が、参政党の得票を押し上げたと考えられます。
選挙は“政策”より“共感”で動く時代へ
政策の正確性や論理性はもちろん重要です。
しかし今の選挙は、より「誰に共感できるか」「誰が既得権益に挑んでいるか」が評価の基準になっています。
大手メディアからは厳しく扱われても、ネット上で“等身大のリーダー像”や“既得権に抗う姿勢”がシェアされれば、それが支持につながる──それが今の選挙の現実です。
メディア批判は終わらない──そして続く“民意”との乖離
参政党の躍進、有働氏へのバッシング、ファクトチェック不信、そしてSNSでの“炎上と拡散”──
これらの事象は、単なる一選挙の出来事ではなく、「誰が情報を支配し、誰が“正しさ”を語るのか」という現代民主主義の根幹を揺さぶる問いを私たちに投げかけています。
次の選挙でも、また別の構図が浮かび上がるかもしれません。
しかし一つ確かなのは、メディアと民意のねじれは今後ますます顕在化するということです。
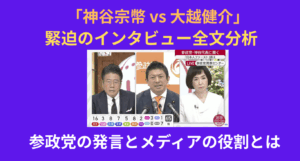
まとめ:報道とは誰のものか、誰のためのものか
今回の「有働 vs 神谷」論争は、ただの言葉の応酬では終わりません。
それは、メディアと政治、報道と主張、言論の自由と国防のジレンマ、そして視聴者の分断を浮き彫りにしました。
報道とは、権力を監視する“第四の権力”である一方、時に新たな声や勢力に対して“壁”として立ちはだかることもある。
その時、視聴者はメディアの問いに耳を傾けるのか、それとも報道の枠を超えた「新しい声」に期待を寄せるのか。
次の選挙、次の議論、次のニュースで、またその選択が試されます。

コメント