「男の子も性被害に遭っている」という、これまであまり語られてこなかった現実です。
この記事では、文藝春秋のルポ『沈黙を破る 「男子の性被害」の告発者たち』に登場する塚原たえさんの証言をもとに、彼女と弟・和寛さんに起きた出来事をご紹介します。
「なぜ誰も助けてくれなかったのか」「どうして弟は命を絶つことになったのか」──これは決して過去の話ではありません。
もしあなたが親なら、先生なら、あるいは地域の一員として、この記事を読んで何を感じるでしょうか?
一緒に考えてみませんか、「子どもを守る」ということの本当の意味を。
はじめに
男児性被害という「見えない苦しみ」
性被害という言葉を聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは、女性や少女に対するものかもしれません。
でも実は、同じように苦しんでいる男の子たちもいるのです。それなのに、その存在はなかなか表に出てきません。なぜなら、「男なのに情けない」とか「男は強くあるべき」という偏見が、彼らの声を押しつぶしてしまうからです。
この「見えない苦しみ」に光を当ててくれたのが、ジャーナリスト・秋山千佳さんによるルポ『沈黙を破る 「男子の性被害」の告発者たち』でした。
中でも、実名で声を上げた塚原たえさんの話は、私にとって本当に衝撃的でした。たえさんの弟・和寛さんは、実のお父さんから長い間性虐待を受け、最終的には命を絶ってしまいました。
そして、その苦しみはお姉さんのたえさんにも及んでいたのです。このブログでは、彼女の声を通じて、男児性被害の現実を一緒に見つめていきたいと思います。
沈黙を破った女性の勇気と社会への問い
「父親にとって、私たちは性の道具だった」。たえさんが語ったこの一言に、すべてが詰まっているような気がします。
20年以上も沈黙を守ってきた彼女が、今こうして名前を出してまで語ろうと決めたのは、ただの告発のためではありません。「これ以上、被害者を出したくない」「弟の人生が無意味だったと思われたくない」──そんな強い思いが、彼女を突き動かしたのです。
そしてその声は、私たち一人ひとりへの問いかけでもあると思います。子どもたちが「助けて」と言えなかった背景には、見て見ぬふりをしてしまった大人たちの無関心や、社会の冷たさがありました。
通報しても「しつけ」として片づけられてしまった警察の対応。養子にしたいと申し出た先生を、父親が追い返しても何もできなかった現実……どれも、子どもたちの声をさらに封じ込めてしまうものでした。
このブログでは、たえさんと和寛さんの歩んできた道をたどりながら、私たちが見過ごしてきたものについて、一緒に考えていけたらと思っています。
1.実名告発に至るまで

SNSから始まった匿名の声「T.T」
塚原たえさんがはじめに過去のことを語り始めたのは、「T.T」という名前のSNSアカウントを通じてでした。
本名ではなく、顔も出していなかったけれど、投稿された内容からは「父親から性的虐待を受けていた女性」であることが伝わってきました。
その言葉はとても静かで控えめなのに、読む人の胸に深く刺さるものばかりで、「生き延びた人の記録」として心を打つものでした。
アカウント名の「T.T」は、まるで泣いている顔のように見えて、多くの人が「心の叫びのようだ」と話題にしていたそうです。そうやって、次第に彼女の発信はメディア関係者の目にも留まるようになっていきました。
記者の秋山千佳さんが初めてたえさんに接触したのも、このSNSがきっかけだったそうです。
取材のとき、たえさんは最初こそマスクを外さなかったものの、2人きりになるとそれまで押し殺してきた過去を、とめどなく語ったといいます。その語りが、やがて匿名の「T.T」から、実名で語る「塚原たえさん」への変化につながっていくのです。
父親からの突然の手紙と動揺
「中村」という知らない名前から届いた一通の手紙。それを開けてみると、なんと20年以上も連絡を取っていなかった実の父親からのものでした。
「終活」と称して、相続について書かれていたその便箋には、過去の虐待への反省も謝罪もありません。ただ、「よく生きていてくれたと思います」といった、まるで自分が被害者かのような言葉が並んでいたのです。
その文面を読んだときのたえさんの動揺は、想像を絶するものだったと思います。
ずっと閉ざしてきた心の扉を、突然こじ開けられたような気持ちだったのではないでしょうか。
無視することもできたけれど、彼女は電話をかけるという決断をします。それは、自分の過去としっかり向き合うための第一歩でもありました。
弟の死と「実名で語る」決断の瞬間
2022年初め、たえさんは父親の残した電話番号に自ら連絡をしました。相続を放棄する意思を伝えると同時に、弟の和寛さんがすでに亡くなっていることを伝えるためです。
でも、返ってきた父親の言葉は、あまりにも冷たすぎました。
「和寛は死んでも構わないけど、たえちゃんが死ぬのは嫌だよ」
こんな言葉、信じられますか? この一言で、たえさんの中で何かが崩れ落ちたそうです。自分たちを「性の道具」としか見ていなかった父親の本性が、ここにはっきり表れていました。
だからこそ、たえさんは実名で語ることを決意します。「このまま父親を普通のおじいちゃんとして見送っていいのか?」「弟の人生をこのまま忘れ去らせていいのか?」──その答えは、たえさんの中ではっきりしていました。
彼女の行動は、「男の子の性被害は語られない」という社会の沈黙に、静かに、でも確実に一石を投じたのです。
2.父親による性虐待の実態

塚原たえさんと弟・和寛さんに起きた出来事は、言葉にするのも苦しいほどの連続した家庭内での被害でした。しかもそれは、ただの暴力ではなく、心身ともに子どもたちを追い詰める深刻なものでした。
たえさんが最初に父親から異常な行為を受けたのは、小学3年生の頃でした。
それ以来、父親の支配は日常のあらゆる場面に及び、弟の和寛さんもまた、似たような状況に置かれていったのです。生活の中にあるはずの安心や遊び、家族の絆はそこにはなく、ただ恐怖と孤独が広がっていました。
当時、通報があっても、警察が「しつけ」として片付けてしまう現実がありました。近所の人が異変に気づいていたにもかかわらず、何も変わらなかったというのも、たえさんが今でも悔しさを感じる部分です。
教師や親族が一時的に手を差し伸べようとしてくれたこともありましたが、それも叶わず、結果的に子どもたちは誰にも助けられないまま、家庭という閉ざされた空間に取り残されてしまったのです。
特に印象的だったのは、姉弟が言葉を使わずに「目」で気持ちを通わせていたことです。誰にも言えない苦しみのなかで、唯一理解し合える存在が互いだった──その絆は深く、切実で、だからこそ、弟の死はたえさんにとって耐え難いものでした。
このような体験は、家庭のなかにある“見えない暴力”の存在を私たちに突きつけています。暴力は殴ることや怒鳴ることだけではなく、心を奪い、尊厳を奪い、生きる力すら奪ってしまうのです。
3.「弟は父の性虐待で死んだ」の意味
姉弟間の深い絆とアイコンタクト
たえさんと和寛さんにとって、言葉を超えたコミュニケーション手段が「アイコンタクト」でした。
辛く苦しい日々の中で、2人は目と目で気持ちを伝え合っていました。笑い合うことさえ許されなかった家庭のなかで、テレビを見て一瞬でも顔を見合わせて笑う——そんなささやかなやりとりが、2人の心の支えだったのです。
子どもだけでは逃げ場のない現実のなかで、2人の絆は深くなる一方でした。
父親の不在時、近所の空き地でキャッチボールをした思い出や、怖くて家に戻れず段ボールを持って墓地に身を潜めた出来事など、数少ない「普通の兄妹らしい記憶」は、互いの存在があったからこそ成り立っていたのです。
性虐待の現場を目撃するという二重の苦しみ
たえさんは、弟の和寛さんがつらい目に遭っている場面を、時には近くで目にしてしまうことがありました。
それは、ただの“見てしまった”というレベルではありません。彼女自身が被害者でありながら、弟の苦しみをも目の当たりにしてしまうという、言葉にできないほど重い現実でした。
和寛さんが不自然な命令を父親から受けているのを、たえさんは目の端で捉えてしまう。その視線の先にあるのは、声を出せないまま、ただ助けを求めるような「無の目」をした弟の姿だったのです。
その“目”が、今でも忘れられない——たえさんはそう語ります。悲しい、辛いといった感情を超えてしまった、感情のない「無表情のまなざし」。
それは、耐え続けた結果、人間らしさを失ってしまったかのような、言葉を超えた哀しみだったのかもしれません。
和寛が残した「無の目」が語るもの
和寛さんが人生の終わりを選んだ背景には、たえさんと同じように、声をあげても届かない現実がありました。誰にも助けを求められず、大人も制度も何も守ってくれないまま、ただ時間だけが過ぎていく。その中で、弟の心は少しずつ「無」に近づいていったのです。
たえさんは語ります。「和寛は、生きることを諦めたわけじゃない。必死に生きようとしていた。でも、どこにも道がなかった」。弟が見せた「無の目」は、私たち大人が見て見ぬふりをし続けてきたことへの、最も静かで、けれど最も重い問いかけなのかもしれません。
彼が命を絶ったあと、たえさんは「このままではいけない」と強く感じました。実名で語ることに決めたのは、「弟の人生を、なかったことにしたくない」という思いからでした。弟を奪ったのは父親だけでなく、黙認してきた社会そのものでもある——そう、たえさんははっきりと言います。
「弟は父の性虐待で死んだ」。その言葉の裏には、深い絶望と、それでも声を上げようとする姉の強さが込められています。そしてその声は、今、私たちひとり一人に届いているのです。
まとめ
塚原たえさんが語った「弟は父の加害によって命を落とした」という言葉には、長年胸の奥に閉じ込めていた思いが凝縮されています。加害の実態、助けを求めても届かなかった声、そして周囲の無関心──これらが積み重なって、取り返しのつかない結果を招いてしまいました。
私たちは今、こうした事実から目を背けるべきではないと思います。「子どもの異変に気づいたとき、あなたならどうしますか?」という問いを胸に刻み、社会全体で子どもを守る仕組みや意識を育てていくことが求められています。
誰にも言えず、誰も気づかず、ただ耐え続けている子どもが、今もどこかにいるかもしれません。このブログを読んでくださったあなたにも、どうか「見て見ぬふりをしない勇気」を持ってほしいと思います。声をあげたたえさんのように、誰かの「助けて」に応えられる大人でありたいと、心から願っています。
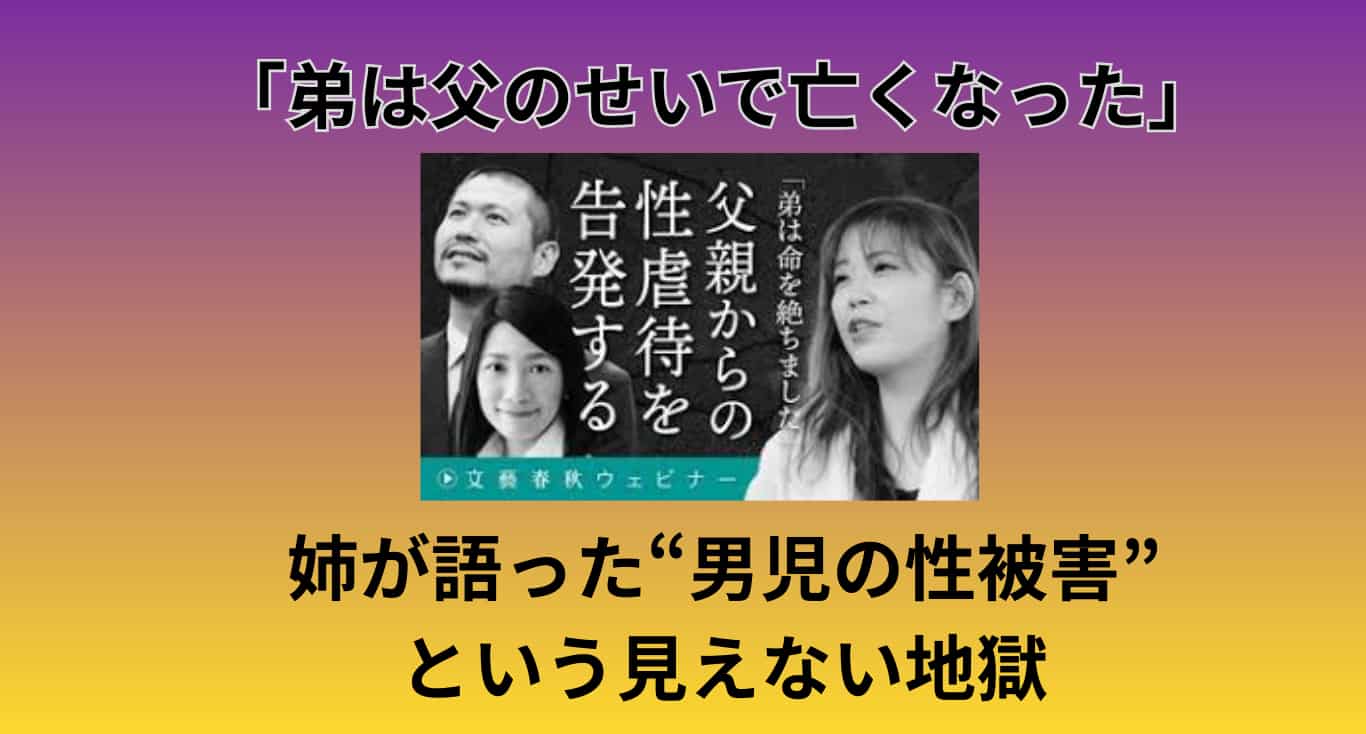
コメント