最近、TBSの報道番組「報道特集」が取り上げた「日本人ファースト」の報道内容をめぐって、参政党が反発し、BPO(放送倫理・番組向上機構)に申し立てるというニュースが注目を集めました。
政治的公平性や放送法第4条のあり方、そしてメディアの信頼性について、多くの視聴者が疑問を感じたのではないでしょうか?
この記事では、テレビ報道の「公平性」「偏向報道」「報道の自由」といったキーワードをもとに、いち視聴者の立場から、今回の問題をわかりやすく解説していきます。
はじめに
TBS「報道特集」と参政党の対立がBPOへ
2024年7月12日に放送されたTBS「報道特集」が、政治団体・参政党の掲げる「日本人ファースト」というスローガンについて、排外主義的な視点から報じたことを受けて、参政党がTBSに対して「可及的速やかな検証と訂正」を求める申し入れを行いました。
この報道の構成や表現に対し、参政党は「取材姿勢に偏りがある」と主張し、最終的にはBPO(放送倫理・番組向上機構)放送人権委員会への申立てを行う意向を示しています。
メディアと政治勢力との間の緊張が、制度的な監視機関へ持ち込まれるという事態は、報道の役割や限界を改めて考えさせる出来事となっています。
放送法第4条と公平報道の現実的限界
今回の問題の背景には、放送法第4条の存在があります。この条文は「政治的に公平であること」などを放送事業者に求めていますが、実際には倫理規定に近く、違反がただちに罰則につながるわけではありません。
特に選挙期間中の報道においては、有権者の判断に影響を及ぼす可能性が高いため、公平性が強く問われます。
しかし、現場の放送では「どこまでが公平か」という線引きが曖昧で、編集や演出の仕方によっては「誘導的」と受け止められるリスクもあります。
TBS側は「客観的な問題提起だった」と主張していますが、報道の受け取り方は視聴者によって分かれ、結果として大きな波紋を呼ぶことになりました。
1.報道の公平性と「日本人ファースト」
参政党の主張とTBS側の回答の食い違い
参政党が問題視したのは、TBS「報道特集」での報道構成です。
同番組では、「日本人ファースト」というスローガンが外国人排斥と結びついて紹介されました。これに対し参政党は、「本来の趣旨は国民の生活を第一に考えること。排外主義とは無関係だ」と反論しています。
実際、参政党の公式サイトや街頭演説でも「外国人を排除する」といった直接的な発言は確認されておらず、むしろ少子高齢化や経済安全保障などの文脈で国民優先の姿勢が語られることが多いようです。
こうした背景を十分に示さないまま、一部の映像やナレーションだけで「排外的」と断じた点に、参政党は「構成の公平性を欠いている」と反発したのです。
一方のTBSは、「あくまで客観的な問題提起であり、放送法の範囲内」とする立場を崩していません。こうした見解の食い違いが、放送倫理の是非をめぐるBPO申立てという事態に発展しました。
「日本人ファースト」の理念と誤解
「日本人ファースト」という言葉は、元々アメリカの「アメリカ・ファースト」政策になぞらえたもので、他国の利益より自国民の安全や経済を優先するという意味合いをもっています。
実際、国政において国民の福祉を第一に考えることは、どの国の政治でも当然とされる考え方です。
しかし、言葉の選び方や強調の仕方によって、誤解を招くこともあります。「○○人ファースト」という表現は、その対立軸として「○○人以外は後回し」と聞こえてしまう恐れがあるからです。
特に、移民や外国人労働者の増加が社会課題となっている日本においては、言葉の響きが敏感に受け止められやすい背景もあります。
報道機関がそうした表現に焦点を当てる際には、文脈や背景の説明が不可欠です。「何を言ったか」だけでなく、「なぜそう言ったのか」「本来どういう意図か」にも丁寧に目を向ける必要があります。
排外主義と報道演出の線引き
問題は、「日本人ファースト」という表現が、排外的な意図に基づくものか、それとも単なる政策スローガンなのかをどう捉えるかという点です。
視聴者の受け取り方に大きく影響するのは、報道の演出や編集方法です。
たとえば、映像編集で一部の極端な発言を繰り返し流したり、不穏なBGMを重ねることで、視聴者に特定のイメージを植え付けることは可能です。
意図的でなくても、演出の積み重ねによって「この政党は危ない」という印象が強まることがあります。
こうした中で、参政党がTBSに「構成の偏り」を指摘したのは、単なる言葉尻の問題ではなく、「どう描かれたか」という印象形成の問題にあります。
公平報道の観点からは、肯定的な側面と否定的な意見の両方を適切に扱うことが重要です。
報道は社会に対する窓口であり、そこに映る像が偏っていれば、現実がゆがんで伝わってしまいます。
まさに今回の対立は、報道が「何を映し、何を映さないか」という編集権と、その社会的責任のバランスをどう取るかが問われる事例と言えるでしょう。
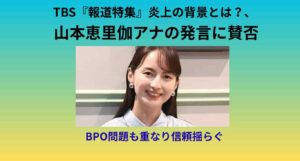
2.オールドメディアの信頼と経営リスク
偏向報道が招くブランド価値の毀損
報道機関が一方的な立場から番組を構成すると、単に「中立性に欠ける」と批判されるだけではありません。
長期的には、視聴者からの信頼を失い、メディアそのもののブランド価値を損なうことにもつながります。
たとえば、今回の「報道特集」での扱いに対してSNSでは「またTBSか」「政権批判ばかりでウンザリ」といった投稿が散見され、TBSという報道機関そのものへの信頼が揺らいでいる様子が見て取れました。
ブランド価値というと製品や広告の話に思われがちですが、メディアにとってのブランドとは「この報道は信頼できる」という認識そのものです。
過去に朝日新聞が「吉田調書」報道を訂正した際にも、信頼回復には長い時間を要しました。このように、いったん報道機関が誤りや偏りを抱えた報道を行えば、再建には膨大な労力とコストが伴うのです。
信頼喪失と視聴者の分散化現象
近年、テレビを「オールドメディア」と呼ぶ声が強まっています。その背景には、若い世代を中心にテレビ離れが進み、代わりにYouTubeやX(旧Twitter)、TikTokといった分散型メディアに情報源を求める動きがあります。
この傾向は、単なる媒体の変化にとどまらず、「テレビは偏っている」という感覚の広がりと深く関係しています。
とくに政治報道に関しては、「どうせマスコミはあの政党を叩きたいんでしょ?」という先入観をもつ視聴者が増えており、報道の中身以前に「信用できない」という前提で接している人も少なくありません。
今回のTBS報道をめぐる反応も、そうした信頼の喪失を象徴しているといえるでしょう。
SNS上では、報道に対するファクトチェックが即座に行われ、映像の切り取りや発言の文脈が検証されます。
その結果、テレビよりもSNSの方が「リアルだ」と感じる人が増えているのです。
信頼という資産を失えば、視聴者も広告主も離れ、結果的に経営にも影響を及ぼす――このサイクルが今、現実のものとして起きています。
経営資産としての「報道の信頼性」
企業が持続的に成長していくためには、金銭的な資産だけでなく「信頼」という無形資産をいかに築くかが重要です。テレビ局において、この信頼はまさに「報道の質」によって支えられています。
たとえば、災害時にNHKが求められる理由は、迅速かつ冷静な情報提供において長年積み重ねてきた信頼があるからです。
逆に、一部の民放が過剰な演出や誇張的な表現を繰り返せば、「また煽っているだけだ」と視聴者の反感を買ってしまいます。
TBSを含む各局が今後生き残っていくためには、報道を単なるコンテンツの一部と見なすのではなく、企業としての信用そのものを形成する中核資産と捉える必要があります。
つまり、視聴率のためのセンセーショナルな構成ではなく、「どれだけ公正かつ誠実に伝えるか」が、経営戦略としても問われる時代に入っているのです。
3.再興に必要な倫理と報道設計力
問いを提示する報道の重要性
報道の使命は、正解を押しつけることではなく、社会にとって重要な「問い」を提示することにあります。視聴者が自ら考える材料を与えることこそ、報道の本質的な価値です。
たとえば、選挙期間中にある政党の主張が議論を呼ぶものであったとしても、それを排斥的・危険と断定するのではなく、「なぜこうした言葉が支持されるのか」「背景には何があるのか」といった疑問を掘り下げてこそ、視聴者の理解は深まります。
今回の「日本人ファースト」をめぐる報道も、本来であれば「国民優先」の政策理念が、なぜここまで警戒されるのか、過去の類似例や諸外国との比較を交えて紹介することで、多角的な見方が可能だったはずです。
その機会を演出や構成で狭めてしまうことが、報道機関自身の首を絞める結果につながるのです。
思考の余白と多角的な視点の価値
「思考の余白」とは、視聴者が情報を受け取ったあと、自分の頭で考えられるスペースのことです。これは一方的な断定や誘導的ナレーションでは得られません。
むしろ、異なる立場の意見や複数の解釈を並べることで、視聴者は「自分ならどう考えるか」という主体的な判断に向かうことができます。
たとえば、ある街頭インタビューで賛成意見だけを流せば、それが「多数派」のように映りますが、反対意見も同じ比率で紹介すれば、「議論が分かれている」と感じられるでしょう。
そうした丁寧な編集が、視聴者の判断力を高め、メディアへの信頼を支える土台になるのです。
とくに社会の分断が深まる現代においては、視点の偏りが新たな対立を生むことも少なくありません。だからこそ、報道機関は「情報を絞り込む」のではなく「広げる」役割を担う必要があります。
倫理的リーダーシップとリスク対応力
報道機関がその信頼を守るためには、現場の記者やディレクターのモラルだけでなく、組織としての姿勢=倫理的リーダーシップが欠かせません。
これは単に「不祥事を起こさないように」といったルール遵守にとどまらず、社会に対してどのような価値を提供するのかという理念を明確にし、それを組織全体で共有する力のことです。
また、現代のメディアは「炎上」や誤報への即時対応も求められます。SNS上で一部の表現が批判された場合、そのまま放置すれば企業の評判が急速に悪化するリスクがあります。
こうした場面で問われるのが「リスク対応力」です。問題の本質を見極めたうえで、速やかに説明責任を果たす姿勢があれば、逆に信頼を深めることも可能です。
たとえばBBCやNHKでは、重大な編集ミスが判明した際、特設ページを設けて経緯を説明し、今後の対策を明示する例があります。こうした対応は、視聴者に対して「自浄能力がある」と感じさせる重要な要素です。
報道の質とは、情報の正確さだけでなく、その背景にある哲学と対応力にまで及ぶものです。信頼される報道を再び築くためには、構成や演出の見直しだけでなく、報道機関自身が何のために存在しているのかを問い直す必要があるでしょう。

「報道する責任」と「報道が生む影響」のジレンマ
今回の「日本人ファースト」に関する報道を見て、私自身とても複雑な気持ちになりました。というのも、「外国人排斥だ」と番組内で直接語られたわけではないにせよ、編集の仕方によってはそう受け取られかねない構成だったと思うんです。
しかも、そうした報道がかえって、外国人への差別や誤解を強めてしまう…そんな逆効果を生んでしまってはいないか?と感じました。
とはいえ、「差別が実際に起きている」「社会の中で特定の言葉がどう使われているか」ということを伝えるのも、メディアの大切な役割の一つ。報道が現実を可視化しなければ、問題はますます見えにくくなってしまいますよね。
一方で、過去にはメディアと政権との“距離の近さ”が問題になったこともありました。たとえば安倍政権時代、当時のNHK会長が「政府が黒と言ったら白でも黒になる」といった趣旨の発言をして物議をかもしたこと、覚えている方も多いのではないでしょうか。
このような歴史をふまえると、メディアは常に「権力から距離を取る」こと、そして「批判的な視点をもつ」ことがとても重要だと改めて思います。
でも同時に、批判が先行しすぎて“公平性”が置き去りになってしまうと、それはまた別の問題を引き起こしてしまいますよね。
だからこそ、いまのメディアには「ただ批判する」「ただ賛美する」という極端な方向ではなく、「事実を丁寧に積み上げ、視聴者に考える材料を提供する」――そんな姿勢が求められているのではないかと感じています。
まとめ
TBS「報道特集」をめぐる参政党との対立は、単なる一つの報道内容へのクレームではなく、日本のメディアが抱える根本的な課題をあぶり出しました。
それは、放送の「公平性」や「中立性」といった理念と、現実の編集判断や演出とのあいだにあるギャップです。
「日本人ファースト」という言葉をどう捉えるかは、人によって異なります。
しかし報道の役割は、その多様な捉え方に光を当て、視聴者自身が考えるための土台を築くことにあります。ところが今回のように、文脈を省略し、ある方向性に印象を誘導する構成がとられれば、それはもはや「問題提起」ではなく「答えの押し付け」と受け止められても仕方がありません。
さらに、視聴者の信頼を失えば、それは番組だけでなくメディア企業全体の経営に響く問題でもあります。信頼とは、数字で測れない無形資産であり、広告収入やブランド力を支える基盤でもあるのです。
いま求められているのは、報道を「どう伝えるか」の技術だけでなく、「なぜ伝えるのか」という倫理的な設計思想です。問いを立て、視点を広げ、誠実な姿勢でリスクと向き合う報道こそが、オールドメディアが再び社会に必要とされるための第一歩となるでしょう。

コメント