2025年の参議院選挙では、投票率が近年にないほど上昇し、若者を中心にSNS経由で選挙に参加する動きが目立ちました。
そんな中、テレビ番組での玉川徹さんの「政治の知識がない人が投票すると危険」といった趣旨の発言がSNS上で大きな議論を呼んでいます。
このブログでは、SNSで拡散されたその言葉の意味や、それに反論する著名人たちの声、そして実際に行動を起こした若者たちの視点を紹介しながら、「誰が政治を語るべきか?」というテーマについて、私自身も一般視聴者として感じたことを書いてみました。
選挙や民主主義について、身近に考えるきっかけになればうれしいです。
はじめに

SNS時代の選挙──投票率急上昇の背景とは?
2025年の参議院選挙では、これまで選挙から遠ざかっていた層の投票参加が大きく増え、投票率が急上昇しました。
その背景には、テレビや新聞よりもSNSを通じて情報を得る人たちの動きがあるとみられています。
特にX(旧ツイッター)やInstagram、YouTubeといった媒体では、短い動画や投稿が繰り返し共有され、「今すぐ投票へ行こう」という呼びかけが多く見られました。
こうした流れに乗って、これまで政治に関心を持っていなかった若者や無党派層が「自分の一票が変化につながるかもしれない」と感じて行動を起こした例が数多く報告されています。
発言が波紋──玉川徹氏のコメントとその反響
このような投票行動の変化に対し、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演した元局員の玉川徹氏が、「政治や選挙の知識を持たない人が投票したことで、結果が大きく変わった可能性がある」といった趣旨の発言をしたことで、大きな議論を呼びました。
SNSでは、漫画家の倉田真由美氏やタレントのフィフィ氏、実業家の三崎優太氏などが次々に反応。
「民主主義を否定するような発言だ」「知識がなければ投票する資格がないのか」といった批判の声が相次ぎ、Xでは「愚民扱い」「若者軽視」といったキーワードがトレンド入りしました。
投票とは何か、誰が参加すべきなのか。SNS世代が問い直す、選挙と民主主義のあり方が、いま注目されています。
1.「知識のない投票は危険」?──玉川徹氏の問題提起
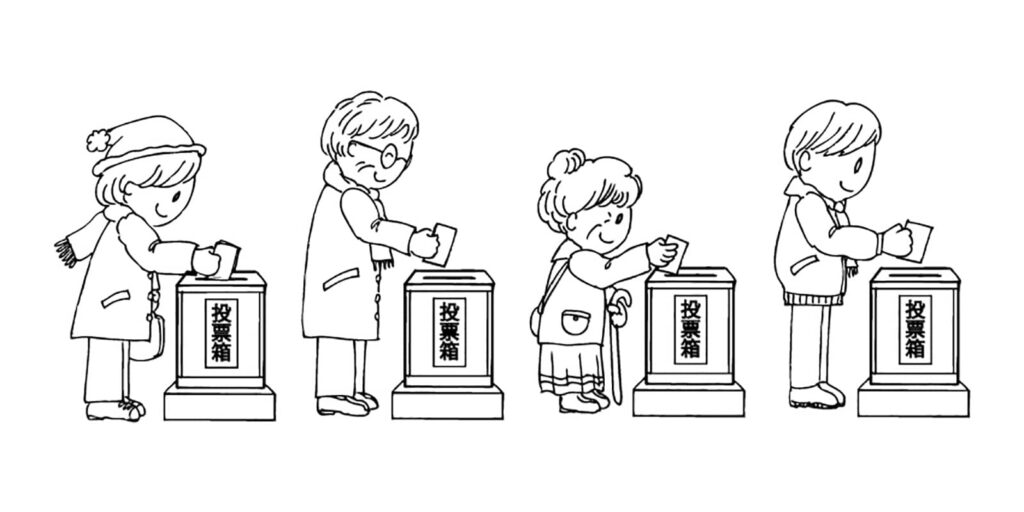
SNSきっかけの投票行動に警鐘を鳴らす発言
投票率の急上昇に関して、玉川徹氏が問題視したのは「知識のないまま投票した人が多かったのではないか」という点でした。
彼は、「これまで選挙に行っていたのは政治や社会の仕組みをある程度理解している人たちだったが、今回はまったく予備知識がない人たちがSNSを通じて投票に動いた」と述べ、やや懐疑的な姿勢を見せました。
たとえば、X(旧ツイッター)やTikTokでは「この政党を推してる芸能人が好きだから」といった単純な理由で投票先を決める投稿が拡散されていました。
玉川氏の見解は、こうした行動が民主主義の健全性に影響を及ぼす可能性を示唆したものとも言えます。
「エリートが愚民を導く」的思考と民主主義への疑念
こうした発言はすぐにSNS上で反発を招き、「政治の知識がなければ選挙に参加すべきでない」という、いわば「知識階層による民主主義の制御」という思想に近いのではないかと問題視されました。
漫画家・倉田真由美氏は、玉川氏の発言に対して「左派の『エリートが愚民を導く』的な思想が凝縮された発想」と指摘。
これは、選挙権を持つすべての人が等しく価値ある存在であるという民主主義の原則に真っ向から反するものだとし、「民主主義が死んでいる」とまで断じました。
SNSとアルゴリズムがもたらした新たな選挙参加層
一方で、今回の投票行動はまさにSNS時代ならではの現象でした。
たとえば、ある20代女性は「今まで選挙は自分に関係ないと思っていたけど、Xで“黙ってたら変わらない”という投稿を見て、思い切って投票に行った」と発言。
また、YouTubeでは若者向けに政策をかみ砕いて紹介する動画が再生回数を伸ばし、選挙前には「初心者向け政党比較」動画が急上昇ランキングに入りました。
アルゴリズムによって届けられた情報が、これまで政治から距離を置いていた層に届き、実際に行動を変えた。こうした変化をどう評価すべきか、社会全体で考える必要があるのかもしれません。
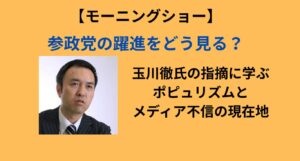
2.反論する声──倉田真由美とフィフィの批判
倉田真由美氏「民主主義が死んでいる発想」と断罪
玉川氏の発言に対して、真っ先に強い言葉で反応したのが漫画家の倉田真由美氏でした。
彼女はX(旧ツイッター)で、「政治の知識がない人は選挙に行ったらいかんのか」と疑問を呈し、「左派の『エリートが愚民を導く』的な思想が凝縮された発想」と痛烈に批判。
さらに「投票率が上がることは必ずしも良いことではない、という発想になること自体、民主主義が死んでいる証拠」と断じました。
この発言には、多くの一般ユーザーから共感の声が寄せられました。
「知識のあるなしで選挙の価値を分けるのはおかしい」「自分も政治のことは詳しくないけど、だからこそ一票を大切にしている」といった投稿がX上にあふれ、倉田氏の主張が広く共有されるきっかけとなりました。
フィフィ氏「偏向報道こそ悪質」とマスコミ批判
続いてエジプト出身のタレント・フィフィ氏もXで私見を述べました。
玉川氏の発言を報じた記事の画像を添え、「ポピュリズムは悪なのか?マスメディア(テレビ)が敵だと言われるのが相当お嫌いのようで…」と皮肉を交えながら指摘。
「公共の電波で偏向報道を垂れ流してるあなたの方がSNSよりよっぽど悪質」と強い言葉でテレビメディアそのものを批判しました。
このコメントにも、「SNSよりもテレビの方が情報操作が巧妙で怖い」「情報源が偏っていることに気づかず見てる層のほうが問題」といった声が寄せられ、メディアに対する不信感が浮き彫りになりました。
ポピュリズムへの過剰な警戒に潜む差別意識?
玉川氏は番組内で「参政党のようなポピュリズム政党が支持を集めるようになった」と語り、その要因として「大衆の不満をうまく言語化して訴えたこと」を挙げました。
しかし、「ポピュリズム=悪」とするような文脈に違和感を抱いた人も少なくありません。
実際、SNS上では「政治に不満があるのは当然。それを拾い上げたら悪なの?」「“ポピュリズム”って言葉で支持層を見下してない?」といった声が相次ぎました。
ここには、エリート層から見た“正しい政治参加”という無意識の線引きが見え隠れしています。
つまり、「わかっている人たち」だけが選挙を語るべきという考え方が、知らず知らずのうちに「知らない人たち」を排除してしまっているという指摘です。
こうした反論の数々は、今回の選挙で表面化した「情報の格差」や「メディア不信」、さらには「誰が発言権を持つべきか」という根本的な民主主義の問いにつながっています。
3.若者の声と世代間の摩擦──三崎優太氏の視点
「若者にツケを払わせ黙れは理不尽」と憤る三崎氏
SNS上で玉川氏の発言に対し、強い疑問を投げかけたのが実業家・三崎優太氏、通称「青汁王子」でした。
彼は「テレビで『政治をよく知らない若者が投票するのはいかがなものか』って発言があったらしい」と引用し、「それ本気で言ってるの?」と真っ向から批判。
さらに、「借金まみれの国を作ったのは高齢者たち。そのツケを払わされる若者が、黙ってろって筋が通らない」と憤りをあらわにしました。
この投稿には多くの若者から共感の声が集まりました。
「自分たちは政治に無関心だったけど、将来の不安から初めて投票に行った」「年金や社会保障のしわ寄せを受けているのに、発言するなって言われたら不公平すぎる」といった声が相次ぎました。
ネット世代の投票をどう捉えるべきか
近年、若年層の多くがテレビではなくSNSを通じて情報を得ており、その情報源は必ずしも専門家の発言や報道だけではありません。
YouTuberやインフルエンサーの呼びかけ、TikTokでの選挙啓発動画、Instagramのストーリーズで流れる政治的メッセージなど、日常の延長線上で「選挙に行こう」という空気が醸成されています。
たとえば、人気インフルエンサーが「投票してきたよ!」と投稿しただけで、それがきっかけとなって「自分も行こう」と思ったというケースは少なくありません。
従来のような「討論番組を見て政策比較する」という参加スタイルではないものの、それでも投票に行くという行動に移った点は、民主主義の裾野が広がったことを示しています。
世代間の責任と選挙の意味を問う議論の広がり
今回の騒動は、単に玉川氏の発言への批判にとどまらず、「誰がこの国の未来を担い、誰がその責任を取るのか」という世代間の摩擦にも波及しました。
三崎氏が言うように、現在の日本が抱える財政問題や年金制度のひずみは、長年にわたる政治の積み重ねによるものです。
そのツケを背負わされる若者が、未来のために声をあげ始めた今、果たしてその声に「知識が足りないから静かにしろ」と言っていいのか——。
SNSでは、「若者の声を笑うな」「学びながら参加するのが民主主義」といった意見も目立ちました。
完璧な知識を持ってから投票する人は、むしろ少数派かもしれません。
それでも一人ひとりが、自分の思いや不安をもとに政治参加することができる社会であること。今回の選挙をめぐる議論は、そんな基本的な価値を改めて問い直す機会となりました。
まとめ
今回の参議院選挙で注目されたのは、投票率の急上昇と、それに対するさまざまな立場からの反応でした。
玉川徹氏が「政治の知識がない層の投票」に警鐘を鳴らしたことで、民主主義の本質や情報格差、さらには「誰が政治を語る資格があるのか」といった根源的な問いが浮き彫りになりました。
それに対し、倉田真由美氏やフィフィ氏のように「すべての人に選挙権は平等にあるべきだ」と訴える声や、三崎優太氏の「将来を担う若者こそ発言すべきだ」とする立場は、多くの人々の共感を呼びました。
知識の有無で線引きすることなく、誰もが“今の気持ち”や“生活実感”をもとに一票を投じる。それこそが民主主義の土台であり、SNSの普及によって広がった政治参加の可能性でもあります。
この選挙をきっかけに、「政治を語るのは偉い人だけ」「難しい話は専門家に任せる」といった旧来の常識を見直し、私たち一人ひとりが“未完成なままでも関わっていい”という空気が、社会全体に広がっていくことを願います。

コメント