高市首相の誕生で「BLは規制されるのか?」という声がSNSで広がっています。
本記事では、日本の現行ルールや自主規制の動き、中国で進むBL規制の実態を整理。
読者・創作者が今知っておくべきリスクと具体的な備えを、やさしく解説します。
はじめに
高市早苗首相誕生で広がるBL規制の懸念

2025年、自民党の新たな総裁として高市早苗氏が選出されたことで、日本国内では表現の自由をめぐる議論が再び活発になっています。
とくにSNS上では、「高市首相の就任によってBL(ボーイズラブ)作品が規制されるのではないか」という不安の声が急速に広がりました。
高市氏はこれまでに「放送法の遵守」や「児童ポルノ法改正」など、表現やメディアに関わる議論の中心にいた政治家です。そのため、「政治的公平性を欠いた放送局には電波停止を命じ得る」との発言をはじめ、メディア統制的な姿勢と受け止められる場面もありました。
こうした経歴から、一部のクリエイターや読者は「創作の自由が脅かされるかもしれない」と感じているのです。
BLはフィクションとしての創作表現であり、読者の間では「現実の性や恋愛とは切り離された文化」として発展してきました。その文化が“規制”の対象になるかもしれない──。そうした危機感が、SNSを中心に拡散しているのが現状です。

中国の現状との比較から見える表現の危機
一方で、隣国・中国ではすでにBL表現に対する厳しい規制が進行しています。
BL作家の摘発や作品の削除、さらには同人誌サイトの閉鎖などが相次ぎ、創作文化そのものが萎縮する事態となっています。
映像作品でも、恋愛描写を「友情」や「ブロマンス」と言い換える“検閲対応”が一般化。SNSでは「腐文化(ふぶんか)」という言葉が検索できなくなるなど、国家レベルでの表現統制が行われています。
日本のファンやクリエイターの間では、「高市政権で日本も同じ道をたどるのでは」との懸念が高まっています。
ただし、日本は憲法で表現の自由が保障されており、中国のような全面的な検閲制度を導入することは容易ではありません。それでも、政治や社会の風向き次第で“自主規制”という形で創作の場が狭まる可能性は否定できません。
本記事では、このような背景を踏まえつつ、「高市首相の就任が本当にBL規制につながるのか」、そして「中国ではなぜここまで厳しい取り締まりが行われているのか」を、順を追って考察していきます。
1.高市首相の就任で表現規制は進むのか?
過去の法案と発言に見る規制志向
高市早苗首相が「表現規制の象徴」として語られる理由のひとつは、過去の法案提出や発言にあります。
とくに注目されたのは、2013年の「児童ポルノ法改正案」。この改正案では、実在する児童だけでなく「漫画やアニメなどの創作物」を対象とする可能性が示唆され、同人業界から強い反発を受けました。
また、2016年には総務大臣として「放送局が政治的公平性を欠いた場合、電波停止を命じることもあり得る」と発言し、報道の自由を脅かすとして大きな波紋を呼びました。
これらの事例から、「高市氏は表現の自由よりも“秩序”や“公序良俗”を重んじる政治家だ」という印象を持つ人が増えたのです。
一方で、高市氏自身は「創作物そのものを規制する意図はない」との立場を明言しており、実際に法案の最終形では創作表現への直接的な規制文言は削除されています。
ただ、「青少年の健全育成」や「有害情報対策」といった名目で、今後も議論の俎上に上がる可能性は高いと見られています。
同人・出版業界が警戒する背景

BLをはじめとした創作文化の世界では、過去にたびたび“自主規制”という形で影響が及んできました。
たとえば、書店や電子配信サイトが年齢制限の強化を行ったり、イベント主催者が表現基準を厳格化したりするケースです。
こうした動きの背景には、「政治的に問題視される前に、自主的に対応しておこう」という業界側の防衛意識があります。
特に高市首相のように、道徳観や倫理観を重視する政治家が政権の中枢に立つことで、出版社やプラットフォームが“先回り”して規制を強める可能性も否定できません。
同人誌や電子BL作品を扱うクリエイターの間では、「直接法で禁止されなくても、実質的に発表の場が減るのでは」という不安の声が多く聞かれます。つまり、問題は“法規制”そのものよりも、それがもたらす社会的圧力なのです。
SNSで広がる「表現の自由」への不安
X(旧Twitter)やInstagramでは、「#BL規制」「#表現の自由を守れ」といったハッシュタグがトレンド入りするなど、ファンや作家の間で危機感が共有されています。
特に若い世代のBLファンは、創作や二次創作をSNSで発表することが当たり前になっているため、アカウント凍結や投稿削除といった“見えない規制”に敏感です。
高市政権が成立して以降、「アルゴリズムが性的表現をより厳しく検知するようになった」と感じる投稿も見られます。
一方で、「憲法で保障された自由がある限り、表現活動は守られる」という冷静な意見もあり、社会全体が揺れ動いている状況です。
つまり、現時点で法律的にBLが規制される兆候はありませんが、“空気としての圧力”が強まりつつあることが、多くの人の不安の根底にあるといえるでしょう。
2.現時点での政策動向とリスク
現在の法制度ではBLは直接規制対象ではない
いまの日本の法律では、「BL(同性愛の恋愛表現)だから」という理由だけで禁止されることはありません。行政が「BL=違法」と決めているわけでもありません。
実際、書店の一般棚にBL単行本が普通に並び、電子書店でもBLレーベルが多数配信されています。年齢制限が付く場合は、性描写の強さや露骨さが基準であって、同性愛か異性愛かは直接の判断材料になっていません。
たとえば、男女の過激描写も18禁になりますし、BLでも淡い恋愛表現なら一般区分で販売されています。
つまり“現行制度”の出発点は「描写の程度」であり、「同性恋愛であること」そのものではありません。
「青少年健全育成」名目で進む可能性のある自主規制
注意したいのは、法律が変わらなくても“自主規制”が強まるケースです。ここでは具体例を挙げます。
- 書店・電子書店のレーティング強化:各社の社内基準で「この表紙は刺激が強い」「あらすじに明確な性表現がある」と判断されると、年齢確認の導入やR区分への移動が行われます。
- イベント主催者のガイドライン厳格化:同人誌即売会で「成人向けは不透明袋」「表紙に性的暗示が強い表現は不可」などの基準が細かくなり、搬入時チェックが増えることがあります。
- プラットフォームの機械審査:画像・本文をAIが自動判定し、成人区分への振り分けや一時非表示が起きることがあります。BLに限らず、肌色面積や行為を連想させるワードがトリガーになりやすいのが実態です。
- 決済・流通の“横串リスク”:クレジットカード会社やアプリストアのポリシーが厳しくなると、プラットフォーム側が一斉に基準を引き上げ、結果として創作側に影響が出ることがあります。
これらは「青少年保護」「苦情への先回り対応」を名目に進みやすく、法改正がなくても現場の体感としては“狭くなった”と感じられます。
憲法上の自由と社会的圧力のバランス
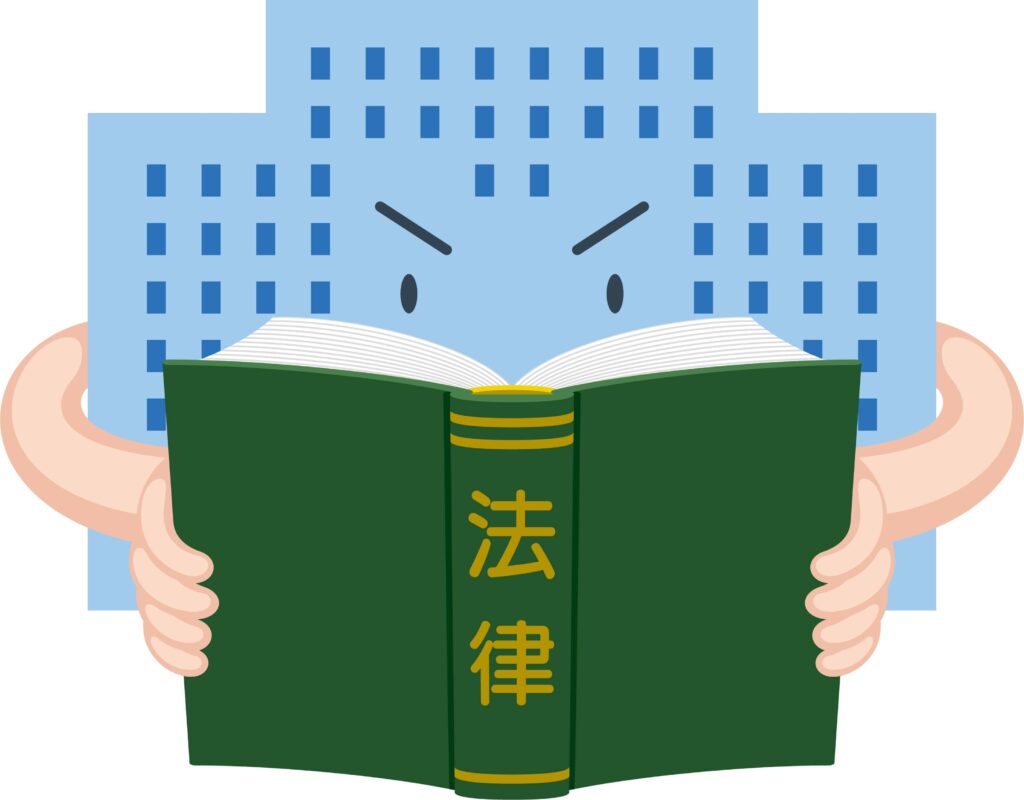
日本では表現の自由が強く守られており、いきなり中国のような全面検閲になる可能性は低いと見られます。ただし、次の“社会的圧力”が重なると、自由が目減りしたように感じられます。
- 苦情や通報の増加:SNSや問い合わせ窓口に意見が集中すると、企業は“安全側”に倒れて基準を厳しめに運用しがちです。
- 炎上回避の空気:「問題化する前に線を引く」方針が広がり、創作・広告・販促の表現が無難化します。
- 自治体・学校との連携配慮:図書館の選書や学校行事との関係で、公共空間に置く表現はより慎重になりやすい傾向があります。
対処のコツは、「法律に照らして適切か」を押さえつつ、年齢区分や表示方法を整えることです。
たとえば、通販ページでの年齢確認、成人向け表示の明確化、サンプル画像のトリミング、イベント用の頒布ルール遵守、ガイドラインを意識した表紙デザインなど。これらは“表現そのもの”を諦めるのではなく、“届くべき相手に適切に届ける”ための工夫です。
要するに、いまの日本は「法の大枠で自由は確保されているが、社会の空気次第で実務の基準が上下する」状態。だからこそ、創作者・読者・流通が同じ土台(年齢区分・表示・販売導線)を共有することが、自由を保ちながら続けるための現実的な鍵になります。
3.中国で実際に進行するBL規制の実態
作家摘発とコンテンツ削除の現状
中国ではここ数年、BL(現地では「耽美/danmei」などと呼ばれる)分野に対して、当局の監視と取り締まりが段階的に強まってきました。
具体的には、BL小説投稿サイトや同人プラットフォームが突然閉鎖・長期停止になったり、人気作家のアカウントが一斉に凍結される事例が繰り返されています。
作品の削除は「サイト側の自主対応」という形で告知されることが多いのですが、背景には行政指導や通報制度の存在があります。
投稿ページに“違反の疑い”が付くと、管理者が該当話数だけでなくシリーズ全体を非公開にすることも珍しくありません。電子書店でも、成人向け描写が強い巻から順に在庫が消え、検索してもヒットしなくなる“サイレント削除”が起きやすい状況です。
作家側の実感としては、「明確なルールが見えにくいまま、後から線引きが厳しくなる」という点が負担になっています。結果として、あらかじめ露骨な表現を避ける“自己検閲”が広がり、新規参入の作家が筆を折るケースも出ています。
「友情」表現への書き換えと検閲体制
映像・ドラマ化の段階では、原作に恋愛要素があっても、脚本の時点で「明示的な恋愛」を削ぎ落とし、深い友情や相棒関係として再解釈するのが一般的になりました。
台詞やカットの修正だけでなく、人物設定や関係性そのものを変更して“恋愛に読めない形”へと寄せる対応も行われます。
こうした変更は、制作会社の“自主基準”という建て付けになっていますが、実際には放送・配信の許認可や審査をにらんだ“通過可能性の最大化”が狙いです。
脚本審査・完成映像の審査・宣伝素材の審査と、複数のゲートでチェックが入りうるため、現場は最初から安全側に大きく振って制作を進めます。
結果、観客は「ブロマンス(友情)」として描かれた作品を受け取る一方、原作読者は“改変感”を強く覚えやすく、創作と受容のあいだでズレが生じやすくなっています。
国家主導の価値観統制がもたらす影響
この種の統制は、BL領域にとどまらず、女性作家の創作機会やLGBTQ+表現全体にも冷や水を浴びせます。
- 萎縮効果:どこまでが許容範囲か不明確なため、作家・編集・配信側が過剰に安全運用を選び、物語の厚みや多様性が失われやすくなります。
- 流通の分断:国内配信が難しくなると、作品は断片的なファン翻訳や海賊版に流れ、創作者に正当な対価が戻りにくくなります。
- 産業的損失:人気ジャンルの改変や供給縮小は、関連グッズ・イベント・二次創作の波及効果を小さくし、文化産業としての裾野を狭めます。
- 海外流出:作家や読者コミュニティが国外プラットフォームに移動し、国内市場の競争力が落ちる懸念があります。
要するに、中国のBL規制は「禁止の明文化」だけでなく、審査・許認可・プラットフォーム運用・通報文化が互いに影響し合うことで、見えない壁を高くしているのが実態です。
創作側の慎重運用が“新しい当たり前”になるほど、物語の表現幅は静かに縮小していきます。
まとめ
日本では、BLだからという理由だけで禁止されることはなく、判断の基準はあくまで「描写の程度」です。
書店での区分けや電子書店の年齢確認などは、同性愛か異性愛かではなく、どれだけ露骨かで決まります。現時点で「BLを直接規制する」法案や声明は出ていません。
一方で、社会の空気や企業のリスク回避で“自主規制”が強まる可能性はあります。
たとえば、通販サイトが表紙の肌色面積を理由にR区分へ移す、イベントが成人向けの包装や陳列をより厳格にする、プラットフォームの機械判定で一時非表示になる――こうした「法改正なしの圧縮」が起きやすいことは覚えておきたいポイントです。
中国の実態は、審査や許認可、プラットフォーム運用、通報制度が重なり合って“見えない壁”を高くする構図でした。
恋愛を「友情」に置き換える脚本改変、サイト全体の閉鎖、検索からの排除などが続くと、作り手も受け手も萎縮し、作品の幅が静かに狭まります。
日本が同じ仕組みをすぐ導入する可能性は低いものの、空気次第で似た圧力は生まれえます。
創作を守る実務的な工夫としては、(1)成人向け表示と年齢確認の徹底、(2)サンプル画像のトリミングやモザイクなどの配慮、(3)イベント・プラットフォーム規約の定期チェック、(4)表紙や紹介文の設計で「過度に性的に見える要素」を避ける――といった対応が有効です。
これらは“表現を諦める”ためではなく、“届くべき読者へ適切に届ける”ためのゲート整備です。
最終的に、自由を支えるのは読者・作家・流通の三者の合意形成です。過度な同調圧力に流されず、年齢区分や販売導線を共有し、問題が起きたときは「どの規約のどの条項に抵触したのか」を具体的に確認する。小さな透明性の積み重ねが、表現の幅を実務的に守る近道になります。

コメント