2025年7月5日、北九州で行われたラグビー・リポビタンDチャレンジカップで、日本代表が世界ランキング12位のウェールズを相手に24―19の逆転勝利を収めました!
これは12年ぶりの快挙であり、ラグビーファンのみならず、多くの人々に感動を与えた試合となりました。
本記事では、試合の詳細な流れはもちろん、活躍した注目選手や、今後の課題・可能性について、ラグビー初心者の私なりの目線でわかりやすくお届けします。
超速ラグビーの真価を見せた90分間、あなたもぜひ一緒に振り返ってみませんか?
はじめに
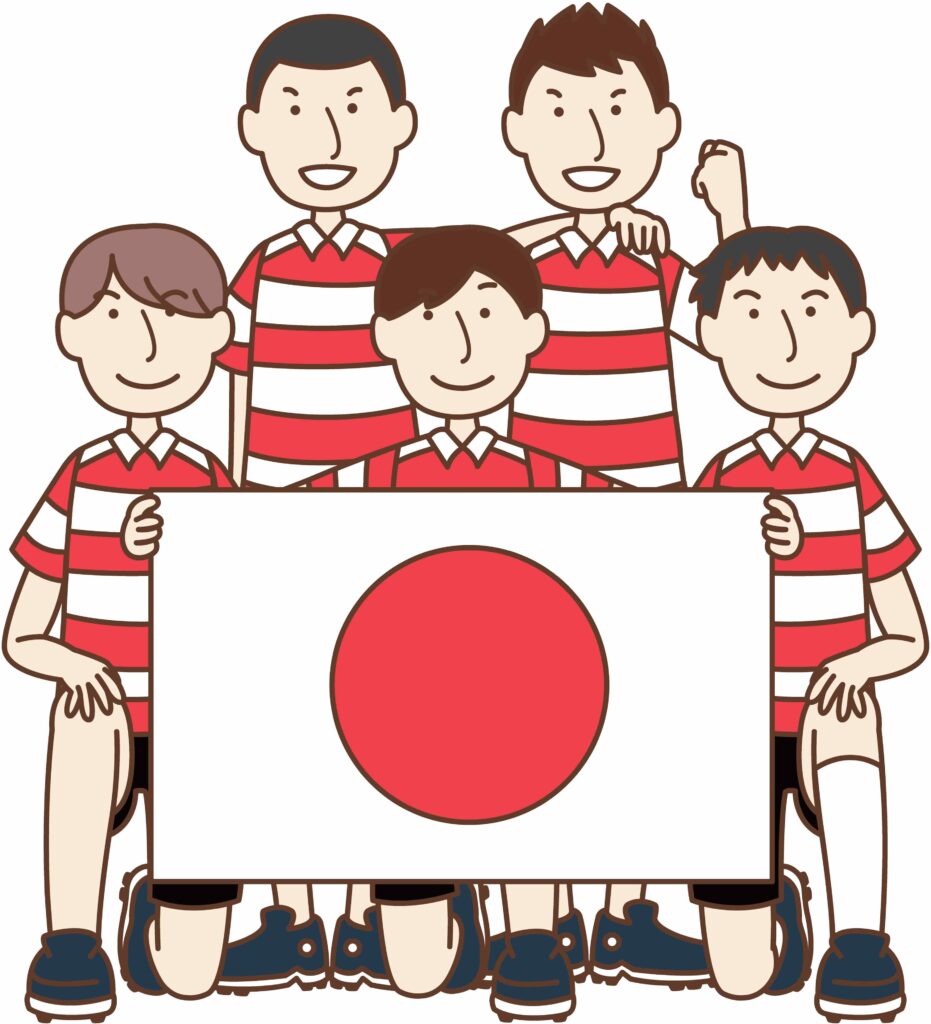
歴史的勝利となったリポビタンDチャレンジカップ2025
2025年7月5日、ミクニワールドスタジアム北九州で行われたラグビー・リポビタンDチャレンジカップ。
日本代表が世界ランキング12位のウェールズを相手に、24―19で劇的な逆転勝利を収めました。
これは実に12年ぶりのウェールズ撃破であり、テストマッチでの対戦成績もわずか2勝目という記念すべき快挙です。しかも、前半を7―19と大きくリードされながらの逆転という展開に、会場は大いに沸きました
。まさに“歴史的”と呼ぶにふさわしい一戦でした。
試合内容もさることながら、この勝利は数字以上の意味を持ちます。
ウェールズは前回W杯以降、公式戦で18連敗中という状況でしたが、それでもティア1の強豪国であることに変わりはありません。そんな相手に勝った日本代表の今後の可能性が、大きく広がったことは間違いありません。
新世代ジャパンの挑戦とその意義
この試合で日本が送り出した先発メンバーのうち、なんと8人が代表キャップ未経験という“フレッシュ”な布陣でした。
特にWTB石田吉平やPR紙森陽太といった若手選手の起用は、将来を見据えた重要な一歩と言えるでしょう。
これまでの実績ではなく、現在の実力と将来性を見て選ばれた選手たちが、実際に試合の中で躍動し、チームの勝利に貢献したことに、今のジャパンの新たな方向性が見えました。
また、キャプテン経験もあるSO李承信が試合終盤に冷静にPGを決め、勝利を引き寄せた場面は、単なる技術だけでなく“精神的支柱”としての存在感も感じさせました。
ティア1との戦いにおいて、日本がどう戦っていくべきか――そのヒントが詰まった90分間だったと言えます。
1.試合展開の詳細
前半:ウェールズの猛攻と日本の耐える展開
試合開始からわずか数分で、会場の空気は緊張感に包まれました。前半4分、ウェールズが右ラインアウトからの展開で日本ディフェンスの隙を突き、CTBのB・トーマスが右中間にトライ。
いきなり0―7と先制を許す厳しい立ち上がりとなりました。さらに悪いことに、前半19分にはFB松永拓朗が負傷交代。そのわずか1分後には、代わって入った中楠一期がトライゾーン内でのプレーでペナルティートライとイエローカードの判定を受け、7―14と点差を広げられてしまいます。
それでも日本は沈まず、16分には石田吉平が左サイドから鮮やかに切り込んで、松永が左中間にトライ。スピードと連携が光る一連の動きで、ウェールズに食らいつきました。
しかし22分、スクラムからの一発でWTBロジャースに走り切られ、7―19とさらに突き放され、前半を終えることとなりました。
後半:スクラムとモールで日本が主導権を奪取
後半に入ると、日本のプレーには明らかな変化が見られました。スクラムでは押し込む場面が増え、相手にペナルティを与えるなど、前半とは打って変わって主導権を握ります。
19分、右サイドのラインアウトから攻撃を重ね、中楠がリベンジとも言えるトライを左中間に決め、14―19と5点差に迫りました。
勢いに乗った日本は、24分にSO李承信が冷静にPGを成功させ、17―19とついに2点差に詰め寄ります。
相手にプレッシャーをかけ続けたことで、ペナルティも引き出せるようになり、ゲームの流れは完全に日本に傾いていきました。
決勝点:ヴァイレアの逆転トライが生んだ歓喜
そして試合を決定づけたのが、31分に生まれた逆転のトライでした。ゴール前のスクラムで反則を誘発し、日本はラインアウトからモールを形成。
着実に前進したのち、途中出場のWTBハラトア・ヴァイレアが左中間に突っ込み、24―19とスコアをひっくり返しました。観客席からは大きなどよめきと拍手が湧き起こり、選手たちも抱き合って喜びを分かち合いました。
その後も集中力を切らさず、スクラムやラインアウトでの優位性を活かしてリードを守り切った日本。
前半とは別のチームのような後半の戦いぶりが、この歴史的勝利をたぐり寄せたのです。
2.注目選手の活躍

李承信の冷静なゲームコントロールと決勝PG
逆転勝利を支えた立役者のひとりが、SO(スタンドオフ)の李承信です。
スコアが17―19と2点差になった場面では、緊張の中でPG(ペナルティゴール)をしっかりと沈め、流れを完全に日本に引き寄せました。彼は過去にも代表戦で大舞台を経験しており、その経験がこの試合でも光りました。
李は試合後、「前半は少し受けてしまったが、後半は自分たちの超速ラグビーに立ち返った」と語っています。冷静な判断力と、チームをまとめるリーダーシップで、若手中心の今回のメンバーをしっかりと導いた姿は、まさに“新しい日本の司令塔”としての貫禄を感じさせました。
フレッシュメンバー石田・松永・中楠の存在感
この試合で特に注目を集めたのが、ノンキャップ(代表初出場)の選手たちです。
まず印象的だったのがWTB石田吉平。スピードと切れ味のある走りで前半16分、ラインアウトからの展開でギャップを突き、見事なアシストにつなげました。若干20代前半ながら、その落ち着きは堂々たるものでした。
そしてFB松永拓朗も、開始早々にトライを決めるなど好調な滑り出しを見せました。
残念ながら前半途中で負傷交代となってしまいましたが、その後を継いだ中楠一期が素晴らしい働きを見せました。
中楠は、前半にペナルティトライとイエローカードという厳しい洗礼を受けながらも、後半にきっちりとトライを決めて汚名返上。プレッシャーの中で結果を出した姿に、多くのファンが胸を打たれたことでしょう。
ディアンズのラインアウト支配とスクラムの強さ
忘れてはならないのが、LO(ロック)ワーナー・ディアンズの存在です。後半、スクラムとラインアウトで日本が優位に立てたのは、彼の安定したプレーによるところが大きいです。
特にラインアウトでは、相手のクリーンキャッチを何度も妨害し、ポゼッション(ボール支配率)を高める貢献を果たしました。
また、体格とパワーを生かしてスクラムで相手を押し返す場面も多く、日本の“前に出るラグビー”を支えました。
試合終盤、リードを守りきる展開の中で見せた彼の一つひとつのプレーには、安心感と頼もしさがありました。ディアンズのような選手がいるからこそ、日本は世界と互角に戦えるのだと実感させられるパフォーマンスでした。
3.ウェールズの現状と日本の課題

連敗が止まらないウェールズの苦境
今回の試合で、ウェールズ代表はテストマッチ18連敗という深刻な状況に陥りました。
最後に勝利を挙げたのは、2023年10月のW杯フランス大会・ジョージア戦。以降、勝てない試合が続いており、チームの自信喪失がパフォーマンスにも表れています。
この日も前半こそ日本を突き放す展開でしたが、後半になるとスタミナ切れや連携ミスが目立ち、スクラムでも明らかに劣勢。
とくに猛暑の影響でハーフタイムを20分に延長するほどの環境下では、フィジカル面の差が浮き彫りになりました。
チームとしての立て直しが急務であり、戦術面とメンタル面の両方に課題を抱えていることは明らかです。
日本のミスと判定への対応力
一方の日本も、課題がなかったわけではありません。前半はパスの精度やノックオンなど、アタック時のミスが多く見られました。
中楠のペナルティトライ判定のように、試合を左右する判定への対応が十分ではなかった点も反省点です。
ただし、ここからの修正力は見事でした。
後半に入り、ボール保持とセットプレーでの精度が上がり、冷静な試合運びができたことは評価すべき点です。ミスの後にどう立て直すか――この“試合中の修正力”は、これからティア1と戦ううえでの大きな武器となるでしょう。
「超速ラグビー」の完成度と今後の伸びしろ
日本代表が掲げている「超速ラグビー」は、この試合の後半でその一端を見せてくれました。
スクラムでの押し込み、ラインアウトでの早い展開、そしてフェーズを重ねて崩す連携プレー。すべてにおいてスピードが意識されており、相手を走らせて疲弊させる戦術が機能していました。
しかし、まだ“完成”には遠く、プレー精度や意思統一の面では伸びしろがあると感じます。
特に若手主体の布陣だった今回は、試合の中で意思疎通がうまくいかない場面も散見されました。とはいえ、今回の勝利はチームにとって大きな自信となり、この先のテストマッチや国際大会での成長に繋がるはずです。
まとめ
リポビタンDチャレンジカップ2025で見せた日本代表の逆転劇は、ただの1勝ではありませんでした。
ティア1との対戦で長く勝利から遠ざかっていた中、新世代を中心に組まれたチームが、苦しみながらも結果をつかみ取ったことには大きな意味があります。
李承信の冷静な判断、中楠の汚名返上トライ、石田の突破力、ディアンズのセットプレー支配力──それぞれが役割を全うし、チームとして勝利を掴んだ姿は、これからの日本ラグビーの可能性を強く感じさせるものでした。
一方で、前半のミスや不運な判定、若手ゆえの連携不足といった課題も明らかになりました。
しかし、それらを試合中に修正し、最後に勝ちきったという事実こそが、このチームの進化の証でもあります。
今回の勝利は、通算成績2勝13敗のうちの“1勝”にすぎませんが、日本ラグビーにとっては未来への確かな一歩。超速ラグビーをさらに磨き上げ、次なる挑戦にどうつなげていくのか。
2025年の日本代表から、ますます目が離せません!

コメント