2025年8月6日に広島で行われた平和記念式典で、石破茂首相が行った挨拶全文を紹介します。
式典では、被爆者支援への姿勢や核兵器廃絶への誓いが語られ、歌人・正田篠枝の短歌も引用されました。
この記事では、その挨拶の要点と引用短歌の意味をわかりやすく解説します。
石破茂首相の平和記念式典での挨拶全文
日本被団協への敬意と「核兵器のない世界」への誓い
2025年8月6日に広島で行われた平和記念式典での石破茂首相の挨拶全文をご紹介します。平和を願う気持ちを、皆さんと共有できたら嬉しいです!
挨拶の全文(要約・引用)
首相は、まず八十年前に広島に投下された原子爆弾で亡くなった十数万の命への哀悼の意を示しました。また、被爆の後遺症に苦しむ方々へのお見舞いも述べています。
二年前に訪れた広島平和記念資料館での体験に触れ、原爆投下直後の惨状を振り返りながら「広島、長崎にもたらされた惨禍を決して繰り返してはならない」と強調しました。
さらに、日本が唯一の戦争被爆国として非核三原則を守り、「核兵器のない世界」に向けた国際社会の取り組みを主導していく決意を表明。「ヒロシマ・アクション・プラン」を通じ、核兵器保有国と非保有国双方の対話と協調を重視する姿勢も示しました。
特に印象的だったのは、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が昨年ノーベル平和賞を受賞したことに言及し、長年の核廃絶活動への敬意を表した点です。「被爆の実相を正確に理解することが大切であり、その記憶を決して風化させてはならない」と語っています。
政府として、国内外の指導者や若者に広島・長崎を訪問するよう呼びかけており、資料館の入館者数が200万人を超えたことにも触れました。
被爆者支援では「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の施行30年を迎えたことを踏まえ、医療や福祉の分野での総合的な援護施策を進めることを約束しました。
結びに、「核戦争のない世界」「核兵器のない世界」、そして恒久平和を実現する誓いを述べ、犠牲者の御霊とご遺族、参列者、広島市民の平安を祈念しました。
だからこそ、このようなメッセージをどう受け止め、どう次世代に伝えていくのかを考え続けたいですね。
平和記念式典で引用された短歌の背景
2025年8月6日、広島市で行われた平和記念式典において、石破茂首相は被爆歌人・正田篠枝の短歌を引用しました。その短歌は「太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり」というものです。
この歌は、原爆の炎に包まれた学校で、子どもたちを守り抜こうとした教師と、その教師を頼りに集まった子どもたちの無念さを伝えています。
式典の場で首相がこの短歌を2度繰り返し読み上げたことで、当時の悲劇と平和への願いが改めて注目を集めました。
正田篠枝という歌人の存在意義
正田篠枝(1910~1965年)は、被爆体験をもとにした短歌を多く残したことで知られ、「原爆歌人」と呼ばれています。爆心地から約1.7キロの自宅で被爆した彼女は、戦後、目の当たりにした惨状や人々の体験を短歌として記録しました。
特に1947年に私家版として発行された歌集「さんげ」は、占領下での厳しい情報統制をかいくぐり、原爆被害を伝える貴重な作品として歴史的価値が高く評価されています。その存在は、広島の記憶を次世代へつなぐ重要な役割を果たし続けています。
1.石破首相が引用した短歌とは
式典での引用シーンとその意図
平和記念式典の終盤、石破茂首相は会場全体に静かな声で短歌を詠みました。「太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり」。この一首は2度繰り返して読み上げられ、参列者の心に深く響きました。
首相は、原爆で命を落とした教師と子どもたちの無念を忘れず、未来へ平和をつなぐことの重要性を訴えようとしていたのです。引用を重ねることで、その思いの強さと、亡くなった人々への深い追悼の気持ちが表現されました。
短歌の内容と表現が示す意味
短歌に描かれているのは、必死に教え子を守ろうとした教師と、そのそばに集まった子どもたちの姿です。
「太き骨」という表現は教師の体格や存在の大きさを、「小さきあたまの骨」は幼い命の儚さを象徴しています。
この対比は、守る者と守られる者が共に犠牲となった悲劇を端的に示しています。言葉は短いですが、戦争がもたらした現実と、その場にいた人々の恐怖や悲しみを鮮烈に伝えています。
参列者・市民への反響
式典後、参列した市民や報道各社からは「胸が締め付けられた」「涙が出た」といった声が相次ぎました。
特に教育関係者や、平和学習で会場を訪れた小学生たちにとって、この短歌は強い印象を残しました。
また、SNSでも引用された短歌が拡散され、「言葉で平和を訴える力の大きさを感じた」という意見が目立ちました。今回の引用は、単なる追悼の場を超えて、戦争の記憶を改めて社会全体で考えるきっかけとなったといえます。
2.短歌が収録された歌集「さんげ」

戦後占領下での出版と検閲回避
歌集「さんげ」が出版されたのは1947年、終戦からわずか2年後のことでした。
当時、日本は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下にあり、原爆被害に関する情報は厳しい検閲の対象でした。新聞や雑誌では被爆の実態を自由に伝えることが難しく、市民の声が封じられる状況が続いていたのです。
こうした中で、正田篠枝は自らの目で見た惨状を歌に託し、あえて私家版として歌集を制作しました。印刷は広島刑務所で行われ、知人に手渡すという秘密裏の方法で配布されました。
検閲を避けるため、出版の経緯や発行部数(150部)すら明かせない中での挑戦であり、その行動は大きな勇気を伴っていました。
歌集誕生の経緯と残された逸話
歌集「さんげ」に収録された100首の短歌には、被爆直後の広島の街の惨状、失われた命への哀悼、そして生き残った者としての苦悩が込められています。
今回、首相が引用した「太き骨は先生ならむ…」の短歌もこの中に含まれています。
正田は後年、自身の著書で「死刑になってもよいという決心で歌を世に出した」と述べています。
これは、当時の発表がいかに命懸けであったかを物語る言葉です。また、知人たちが印刷や製本に協力し、完成した歌集をこっそり持ち帰ったというエピソードも伝わっています。
歴史的資料としての価値
現在、「さんげ」は原爆文学を語る上で欠かせない資料とされています。戦争直後に書かれた生々しい被爆体験の短歌は、後世に向けて当時の現実を伝える重要な役割を果たしてきました。
原爆資料館や平和祈念館などでは、正田篠枝の作品を通じて、戦争の悲惨さを知る教育プログラムも行われています。
こうした取り組みにより、「さんげ」は単なる文学作品を超え、広島の記憶と平和教育を支える文化遺産として受け継がれているのです。
3.「原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑」

建立の経緯とモニュメントの特徴
「原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑」は、1971年8月、広島市の平和記念公園南側に建立されました。
建立のきっかけは、原爆投下で犠牲となった教師や児童の存在を広く後世に伝えるためです。
モニュメントは、高さ2.4メートルのブロンズ像で、子どもを抱きしめて悲しむ教師の姿が表現されています。
台座の銘板には正田篠枝の短歌「太き骨は先生ならむ そのそばに 小さきあたまの骨 あつまれり」が刻まれており、訪れる人々に当時の悲劇を強く訴えかけます。
短歌と教師・児童の悲劇的な歴史
この碑が象徴するのは、原爆の炎に襲われた学校で教師と児童が共に命を落とした悲劇です。
爆心地付近の学校では、子どもたちが必死に教師を頼り、そのそばに集まりながらも、逃げ場を失って命を落としました。教師もまた、自らの命を顧みず子どもたちを守ろうとした結果、犠牲となったのです。
短歌はその光景をわずか31文字で描き切り、守る者と守られる者の絆と無念さを深く伝えています。碑を前に立つと、その短歌が語りかけてくるようで、多くの来訪者が立ち止まり、静かに手を合わせています。
毎年の慰霊祭と継承される記憶
毎年8月4日、この碑の前では広島市内の小学生や教職員による慰霊祭が行われます。
参加者は献花や黙祷を行い、教師や児童の冥福を祈るとともに、平和の大切さを心に刻みます。
学校教育の一環として訪れる児童も多く、碑は平和学習の重要な場として機能しています。
短歌を通じて当時の悲劇を知り、命の尊さや平和を守る意義を学ぶ機会となっており、この取り組みは世代を超えて続けられています。
まとめ
今回の平和記念式典で引用された正田篠枝の短歌は、原爆で犠牲になった教師と子どもたちの無念を凝縮した言葉でした。
その背景には、被爆体験を記録した歌集「さんげ」の存在があり、占領下という困難な時代にあえて声をあげた正田の決意があります。
そして、その短歌は「原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑」に刻まれ、今も多くの人々に語りかけています。
式典での引用は、単なる追悼を超えて、過去を忘れず未来に生かすためのメッセージでもありました。こうした記憶を語り継ぎ、平和を願う取り組みは、これからも続けていくべき大切な営みです。
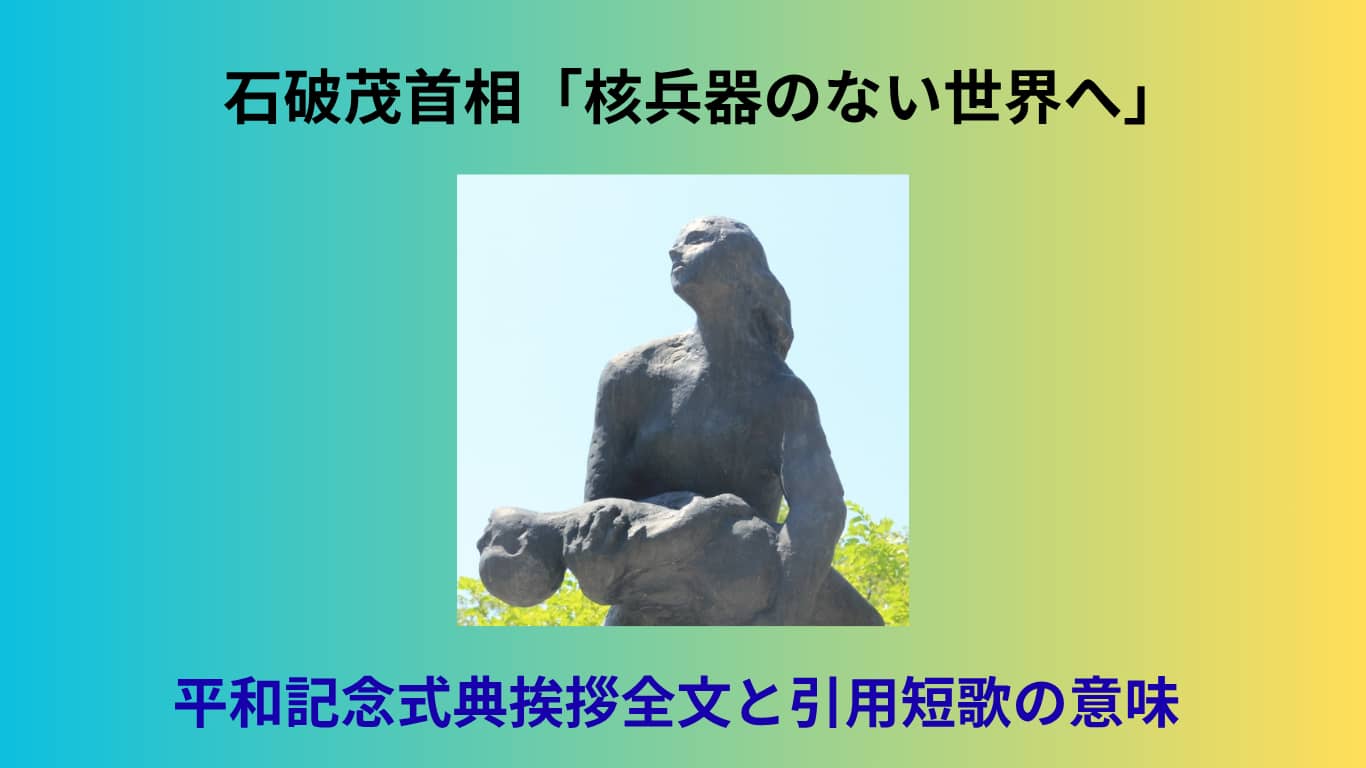
コメント