2025年9月からスタートするスマホ保険証。
マイナンバーカードをスマホに登録し、保険証として使える新しいシステムは、忙しい毎日を送る私たちにとって大きな助けになるでしょう。
スマホ一つで受診できる便利さや、高額療養費の自動適用など、数多くのメリットが期待されています。
しかし、便利さだけでなく、セキュリティ面での懸念もついて回ります。特に、高齢者にとっては、技術的なハードルや、スマホの紛失・盗難のリスクが心配ですよね。
本記事では、スマホ保険証を安心して使うためのセキュリティ対策と、実際にどのように利用するかについて解説していきます!
スマホ保険証とは?

利用開始時期
- 実証実験は関東圏の医療機関(15か所)・薬局を対象に、
2025年7月1日〜18日と 8月4日〜15日の2回に分けて実施されています 。 - 本格運用は、実証実験での問題点を整理したうえで、2025年9月ごろから環境が整った医療機関・薬局で順次開始される予定です 。
- 対応医療機関は任意となるため、すべての施設で同時に使えるわけではありません 。
利用方法
- マイナポータルなどで「マイナ保険証利用登録」を実施
- スマートフォンにマイナンバーカード機能を搭載(iPhone・Androidとも対応)
- 医療機関・薬局で、顔認証付きカードリーダー + 汎用スマホリーダーにスマホをかざす
- 資格確認画面上で本提供情報への同意(ボタン選択)を行えば受付完了
✅ メリット
- カード不要でスマホだけ持参で受診可能に → 財布を持ち歩く必要が減る
- 初診窓口負担が割安:マイナ保険証利用時は6円、紙カードでは12円(3割負担例)
- 就職・引越時なども保険証手続きを待たずに受診できる
- 高額療養費制度との自動連携:事前申請不要で窓口負担額を軽減
- 医療情報の共有により適切な診療・処方へ(患者の同意による履歴参照)
- 将来的には診察券の廃止やアプリ統一も可能性あり
❌ デメリット・注意点
- 対応していない医療機関では使えない
医療機関の導入は任意であり、全医療機関が即対応しているわけではありません。スマホだけでは不安定なため、従来の保険証や資格確認書も併せて持参することが推奨されています 。 - カードリーダー設置や機器操作の事務負担
医療機関は外部スマホリーダーの導入が必要で、高齢者など機器操作が負担になる可能性があります 。 - システムトラブルや誤登録
過去にはオンライン資格確認システムで別人データや自己負担割合の誤登録問題が報告されており、まだシステムは完璧ではありません 。 - 紛失時のリスク
スマホ・カードリーダー忘れや未回収による個人情報漏洩リスクが残ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実証実験期間 | 2025年7月1–18日、8月4–15日(関東の15医療機関等) |
| 本格運用開始 | 2025年9月ごろより、環境整った施設から順次開始 |
| 利用条件 | 利用登録+スマホへのマイナ搭載+対応施設での受付 |
| メリット | スマホのみで受診、費用削減、履歴共有、省力化など |
| 注意点・デメリット | 対応未整備、操作負担、誤登録リスク、情報漏洩など |
📱 利用者向け:登録手順(iPhone/Android別)
共通の事前準備
- マイナンバーカードを所有していること
- マイナポータルで「健康保険証利用登録(マイナ保険証)」を完了(スマホからも可能)
- スマートフォンにマイナンバーカード機能を登録済(iPhoneならWallet、Androidなら電子証明書)
iPhoneの手順
- Walletアプリでマイナンバーカードを登録(iPhone XS以降やiPhone SE 第2/3世代、iOS 18.5以上)
- 医療機関の受付でカードリーダー画面の「スマートフォンを利用」を選択し、iPhoneを選ぶ
- Walletでマイナンバーカードを表示 → Face ID または Touch ID で認証 → スマホリーダーに“タッチ”するだけでOK
Android の手順
- マイナポータルアプリから利用登録およびAndroid端末への証明書搭載(無料)
- 医療機関の受付で「スマートフォンを利用」を選び、Androidを選択
- 画面に表示されたキーパッドで “利用者証明用電子証明書”の4桁数字の暗証番号を入力
- Android端末をカードリーダーに載せる → 認証完了 → 同意選択で受付完了
スマホ乗り換え時に発生すること
- 電子証明書の再設定が必要
- スマホ保険証は、スマホ内にマイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用電子証明書など)を格納して動作します。
- 新しいスマホに機種変更した場合、古い端末からの自動移行は不可で、再度マイナポータルやWalletなどで設定し直す必要があります。
- 暗証番号の入力
- 再登録時には、マイナンバーカード利用時と同様に暗証番号(4桁と6〜16桁)を入力するプロセスがあります。
- 旧スマホの証明書無効化
- 機種変更の際は、古いスマホのマイナ機能を削除または初期化しておくことが推奨されています。
- これは不正利用防止のため。
実際の負担感
- 従来の物理カード→ 買い替え時の再設定は不要。
- スマホ保険証→ 新しいスマホに変えるたびに登録手順が必要。
メリットとデメリットの整理
- メリット
- 普段の通院時に財布・カードを持ち歩かなくてよい。
- スマホひとつで本人確認ができる。
- デメリット
- 機種変更のたびに登録作業(数分〜10分程度)が必要。
- 古いスマホを手元に残す場合は、不正利用防止処理(初期化)が推奨される。
今後の改善の可能性
総務省・デジタル庁もこの「機種変更時の煩雑さ」を課題として認識しており、
- クラウド連携やバックアップによる簡易移行
- ワンタップ移行機能
といった改善が検討されています。
スマホ保険証の利便性とセキュリティ上の懸念
2025年9月から、いよいよスマホ保険証(マイナンバーカードのデジタル化版)が本格的に運用される予定です。
この新しいシステムでは、マイナンバーカードをスマートフォンに登録し、保険証として利用できるようになります。
これにより、マイナンバーカードを常に持ち歩く必要がなく、スマホ一つで簡単に健康保険証の役割を果たすことができるようになります。
さらに、受診時のスムーズさや、高額療養費制度との自動連携などのメリットもあり、便利さと効率性を提供することが期待されています。
しかし、その一方で、個人情報の保護やセキュリティの問題も懸念されています。
特に、高齢者が利用する場合、スマホやマイナンバーカードを常に持ち歩くことが必須となり、その結果としてセキュリティ上のリスクが高まることが懸念されています。
このような新しいデジタルシステムに関しては、どのように安全性を確保するかが大きな課題となります。
高齢者を含む全ての利用者への影響

スマホ保険証の導入によって、特に高齢者やITに不慣れな人々に対して、セキュリティの問題や技術的なハードルが立ちはだかる可能性があります。
例えば、スマホ操作に不安を抱える高齢者にとって、スマホ保険証を正しく利用するためのサポートが重要です。
また、デバイスの紛失や不具合によって、保険証としての機能を十分に活用できない事態も考えられます。こうした問題に対する解決策や、安心して利用できるためのサポート体制の強化が不可欠です。
1.スマホ保険証のメリット
1. マイナンバーカードを持ち歩かなくてよい
スマホ保険証の最大のメリットは、マイナンバーカードを常に持ち歩く必要がなくなることです。
これにより、財布やカードケースを軽減でき、スマホ一つで健康保険証としての役割を果たすことができます。
たとえば、毎日の生活の中で、マイナンバーカードを忘れてしまうことや紛失するリスクを避けることができ、いつでもどこでもスマホを使って受診できるという利便性が大きなポイントです。
実際、財布やカードを減らすことで、外出時に持ち物を少なくしたい人々にとっても、非常に便利です。特に、高齢者や忙しい仕事を持つ人々にとって、スマホ保険証の導入は大きな助けになるでしょう。
2. 受診時のスムーズさ
従来、病院や診療所での受付時に保険証を提示する手間がありましたが、スマホ保険証なら、スマホをかざすだけで資格確認が完了します。
これにより、診察前の待機時間が短縮され、受付も迅速に行えるため、患者にとって非常に便利です。例えば、朝一番で診察を受ける際に、少しでも時間を短縮したいというニーズに応えることができます。
また、スマホ保険証はQRコードの読み取りでスムーズにデータを認証でき、保険証の情報を素早く正確に確認できるため、手書きの手間を省くことができ、効率的な医療環境が提供されます。
3. 高額療養費制度との自動連携
高額療養費制度は、病院での治療費が高額になった場合、一定額以上の費用を超えた分を補助する制度です。
スマホ保険証を利用することで、自動的に高額療養費制度が適用され、事前申請なしで窓口負担額が軽減されるメリットがあります。例えば、長期治療が必要な患者や、手術費用が高額なケースでは、負担を大幅に減らすことができ、患者の経済的負担を軽減する役立ちます。
この自動連携により、窓口での煩雑な手続きが不要になり、治療に集中できる環境が整うことになります。
4. 医療情報の管理と共有
スマホ保険証は、過去の医療情報やアレルギー情報など、健康に関する重要なデータを管理する機能も持っています。
これにより、複数の病院で受診した際にも、一貫した情報の管理が可能となります。たとえば、転院時や別の専門医にかかる場合でも、医療情報をスムーズに共有でき、診断がより早く、正確に行えるようになります。
また、アレルギー情報や過去の疾患履歴がスマホに保存されていれば、医師が迅速に適切な治療法を提案しやすくなり、誤診のリスクを減らすことにもつながります。
5. 環境への配慮
紙の保険証を廃止することで、環境への配慮も進みます。
スマホ保険証は、物理的な紙の代わりにデジタルデータを活用するため、資源の節約や廃棄物の削減にも貢献できます。例えば、毎年の保険証の更新時に発生する印刷や配送のコストを削減できるため、環境に優しい選択となります。
また、デジタル化が進むことで、無駄な印刷物を減らし、効率的に運用できるようになり、持続可能な社会に向けた一歩となります。
2.スマホ保険証とセキュリティ:高齢者にも安心な使い方
1. 紛失・盗難のリスク
スマホ保険証の大きな懸念事項の一つは、スマホの紛失や盗難によって、保険証情報が不正に利用されるリスクです。
特に、マイナンバーカードと同様に、スマホ保険証には個人情報や保険証の詳細なデータが保存されています。
もしスマホを紛失した場合、第三者がその情報を悪用する可能性もゼロではありません。このリスクを減らすためには、スマホにロック画面のパスワードや生体認証(指紋認証、顔認証)を設定することが重要です。
例えば、スマホが盗まれた場合に、簡単にアクセスされることがないようにするために、指紋認証や顔認証の設定を強化することが求められます。
もしスマホを使っている本人の顔が認識されない場合、他人がその情報を使うことが難しくなります。
2. スマホのセキュリティ設定
スマホ保険証を安全に使うためには、スマホのセキュリティ設定が非常に重要です。
万が一、スマホが盗まれた場合でも、パスコードや生体認証(指紋認証、顔認証)でデータが保護されるようにする必要があります。
特に、高齢者やITに不慣れな方々にとっては、これらの設定が少し難しく感じることもあるかもしれません。そのため、簡単に設定できるセキュリティ機能の導入が大切です。
高齢者向けには、スマホ操作が難しくないように、分かりやすく簡単に設定できるガイドを提供したり、スマホの購入時にセキュリティ設定をサポートしたりすることが有効です。
また、万が一スマホを紛失した際のために、遠隔操作で利用停止できる機能を活用することも重要です。
3.セキュリティ対策と改善点
1. セキュリティ強化
スマホ保険証を安全に利用するためには、セキュリティ強化が不可欠です。
デジタル化された保険証情報は、強力な暗号化で守られていますが、それだけでは完全なセキュリティとは言えません。
特にスマホのセキュリティ設定を強化することが求められます。スマホ自体が紛失や盗難に遭った場合でも、データの流出を防ぐための二重認証や、生体認証(指紋、顔認証)の設定は必須です。
例えば、スマホに強力なパスコードや指紋認証を設定し、不正アクセスを防止することで、万が一スマホが盗まれた場合でも情報が安全に保護されます。
また、端末を遠隔操作してデータを消去する機能を有効にすることも、紛失時のセキュリティを強化する一つの方法です。
2. サポートの充実
高齢者やITに不慣れな人々にとって、スマホ保険証の利用は少し難易度が高く感じられることがあります。
そのため、利用サポートの充実が非常に重要です。まず、スマホ保険証を正しく設定するためのガイドラインや操作マニュアルを提供することが求められます。
さらに、コールセンターやオンラインサポートの充実により、利用者が困ったときにすぐに質問できる環境を整えることが大切です。
例えば、高齢者向けには、簡単な操作ガイドやセキュリティ設定の手順を簡単に理解できるようにした冊子や動画を提供することが有効です。
加えて、スマホの利用に慣れていない方に対しては、操作サポートを電話で受けられる仕組みを用意することも有効です。
まとめ
スマホ保険証は、便利で効率的な健康管理の手段として多くの利点を提供しますが、その利用にはセキュリティ面での慎重な対策が必要です。
特に高齢者をはじめとする利用者が安全にスマホ保険証を活用できるように、セキュリティの強化やサポート体制の充実が不可欠です。
スマホ保険証のセキュリティ強化には、指紋認証や顔認証、パスコードなどの多層的なセキュリティ設定が必要です。また、スマホの紛失や盗難に備え、データの遠隔消去や利用停止機能の活用も重要です。
加えて、操作に不安がある高齢者に対しては、簡単に設定できるガイドやサポートを提供することで、安心して利用できる環境を整えることが求められます。
さらに、医療機関における対応体制の整備も大切です。スマホ保険証を利用する施設が増える中で、万が一のトラブルに備えたバックアップシステムや資格確認書の発行体制が整備されることが、利用者の安心感に繋がります。
これらの対策がしっかりと行われることで、スマホ保険証はより多くの人々にとって信頼できるツールとなり、日常の医療利用をスムーズに、そして安心して行えるものとなるでしょう。
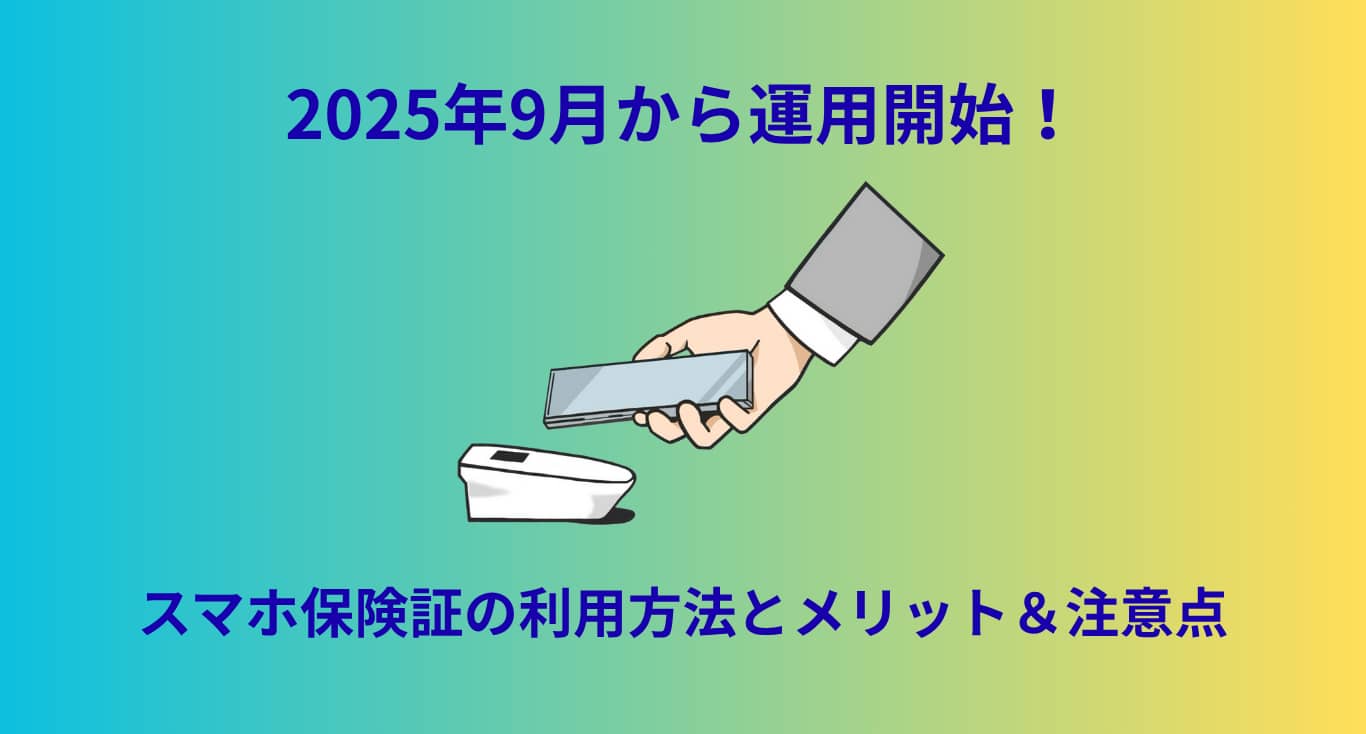
コメント