車を持つ人なら誰にとっても気になるのが「税金」ではないでしょうか。
今、ニュースやSNSで話題になっているのが 「走行距離課税(走行税)」 です。
これは「どれだけ道路を走ったか」に応じて税金を支払う仕組みで、電気自動車の普及によって減少するガソリン税に代わる新しい財源として検討されています。
本記事では、走行距離課税とは何か、日本での導入状況や海外の事例、そしてメリットとデメリットを一般利用者の視点からわかりやすく解説します。
「導入されたら私たちの生活にどんな影響があるの?」と気になる方に向けて、具体例を交えながら整理しました。
はじめに
走行距離課税とは何か
走行距離課税とは、車がどれだけ走ったかに応じて税金を支払う仕組みです。従来のように排気量やガソリンの使用量に基づくものではなく、「どれくらい道路を使ったか」という実際の走行距離に合わせて課税されます。
たとえば、普段ほとんど車を使わない高齢者や都市部で短距離しか運転しない人は、負担が軽くなります。
一方で、毎日長距離を走るトラック運送業者や、通勤・買い物で車を頻繁に使う家庭は、負担が大きくなる可能性があります。
この制度は「使った分だけ負担する」という考え方に基づいており、公平性の観点から注目を集めています。
なぜ今この制度が注目されているのか
現在、ガソリン税は自動車関連税収の大きな柱ですが、電気自動車やハイブリッド車の普及でガソリンの使用量は年々減っています。
そのため、ガソリン税に依存していると将来的に道路の維持費や交通インフラ整備の財源が不足する懸念があります。
例えば、地方では道路の補修費がかさみますが、EVの普及によってガソリン税が減れば資金不足は深刻化します。
こうした背景から、「ガソリンに依存しない新しい税の仕組み」として走行距離課税が議論されるようになりました。
また、海外でもオレゴン州やニュージーランドなどで試験的に導入が進んでおり、日本も同様の仕組みを検討する流れが強まっています。
1.日本での導入現状
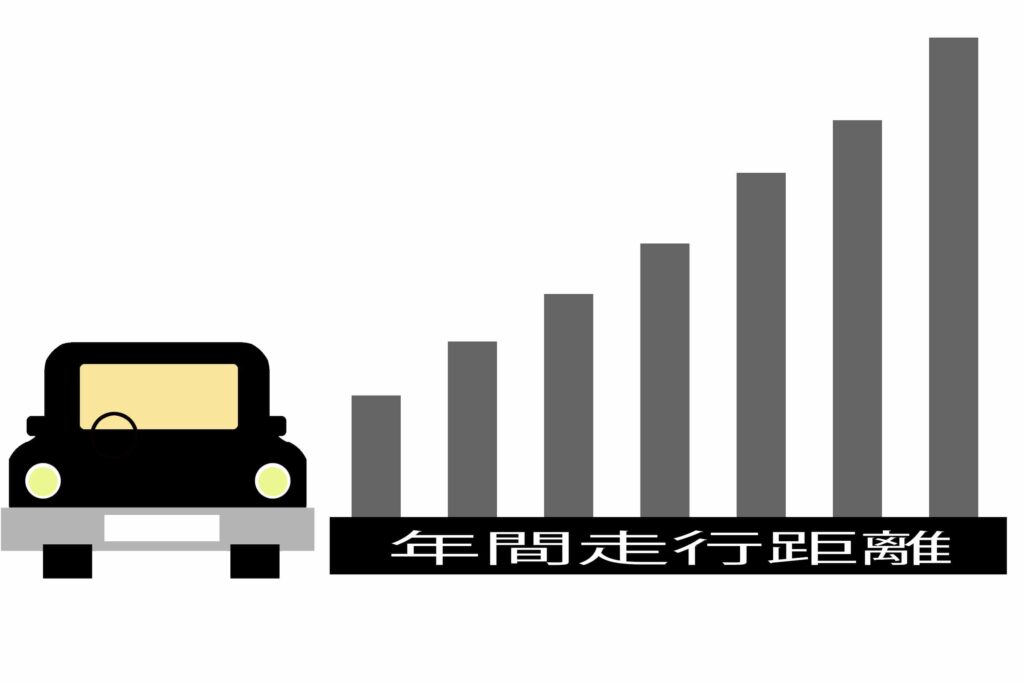
導入時期は未定で検討段階にある
日本では、走行距離課税の導入はまだ正式に決まっていません。
2025年の夏時点でも、国会や政府の税制調査会で議論は続いていますが、導入のタイミングや税率といった具体的な内容は未定のままです。
2022年頃から検討が始まり「2030年頃に導入の可能性もある」と言われていますが、技術面や社会的影響をめぐる課題が多く、現状は「検討中」という段階にとどまっています。
国交省・財務省による検討と課題
この制度を主に検討しているのは、国土交通省と財務省です。
国交省は道路の維持や交通インフラのための財源をどう確保するかに注目しており、財務省は税収の安定化を重視しています。
ただし、課題は少なくありません。例えば「どの税を置き換えるのか」「既存のガソリン税や自動車税と重複しないか」といった二重課税の懸念があります。
また、物流業界や地方の生活者が大きな負担を強いられる可能性も指摘されています。そのため、制度を設計する際には、地域や業界ごとの事情に合わせた配慮が欠かせません。
技術的アプローチ(GPS・オドメーター方式)
走行距離をどうやって測るかも大きな論点です。
代表的な方法は2つあります。ひとつはオドメーター(走行距離計)の数値を申告する方式です。車検や点検のときに走行距離を確認する形であればシンプルですが、改ざんの可能性が課題になります。
もうひとつはGPSを搭載した車載器を用いる方式で、走行した距離を自動で記録できます。ただし、位置情報が含まれるためプライバシーへの懸念もあります。
海外では、オドメーター方式とGPS方式を組み合わせたり、利用者が選べる仕組みにしたりと、複数のアプローチが検討されています。日本でも、現実的にはこうしたハイブリッド型の運用が検討されていくと考えられます。
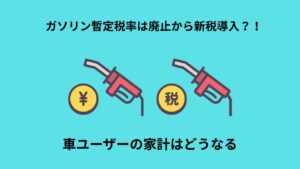
2.海外の導入事例
アメリカ(オレゴン州・ハワイ州)の先行モデル
アメリカでは、州ごとに走行距離課税の取り組みが進んでいます。
オレゴン州では2015年から「OReGO」という制度を始め、任意で参加したドライバーが1マイルごとに約1.9セントを支払う仕組みです。
ガソリン税の代わりに支払うイメージで、参加すると登録料が軽減されるなどのメリットがあります。例えば年間1万5000km走る場合、およそ200ドル弱の負担になる計算です。
また、ハワイ州では2025年7月から電気自動車を対象に走行距離課税を導入し、2028年以降はすべてのEVに義務化される予定です。
EVユーザーにとっては「年額50ドルの定額制」か「走行距離に応じた支払い」のどちらかを選べる仕組みが検討されています。
ニュージーランドのRUC制度
ニュージーランドでは「RUC(Road User Charges:道路利用者料)」と呼ばれる制度がすでに広く定着しています。
ディーゼル車や大型車を中心に、1000kmごとに利用者が前払いでチケットを購入する方式です。
例えば、軽車両の場合は1000kmあたり約5000円を支払う必要があります。もし購入した距離を超えて走れば追加で支払い、不足分があれば返金される仕組みです。
こうしたシステムは、観光バスや長距離トラックだけでなく、日常的にディーゼル車を使う一般家庭にも適用されており、道路整備の安定財源として機能しています。
ドイツのLkw-Mautと環境配慮型課税
ドイツでは2005年から「Lkw-Maut」と呼ばれる大型車向けの距離課税を導入しています。
対象はトラックで、料金は走行距離だけでなく、車両の重量や排出ガスのクラスによっても変わります。つまり、重い車や排出量の多い車は高く、環境性能の良い車は安くなる仕組みです。
2024年からは3.5トン以上の商用車にも対象が拡大され、さらに二酸化炭素排出量に応じた追加課金も始まっています。
例えば、最新の低排出トラックと旧型のディーゼルトラックでは、同じ距離を走っても大きな料金差が出ます。こうした仕組みは、運送会社に環境性能の良い車両への切り替えを促す狙いもあります。
3.導入によるメリットとデメリット
メリット:公平性・EVへの課税・環境負荷軽減
走行距離課税の大きなメリットは「公平性」にあります。
従来はガソリンを使う車だけが税金を多く負担していましたが、電気自動車の普及でガソリン税収が減り、負担のバランスが崩れていました。
走行距離に応じて課税することで、EVやハイブリッド車も「道路を使った分だけ負担する」仕組みになります。
たとえば都市部で年間5000kmしか走らない人は負担が軽くなり、年間2万km以上走る長距離利用者はその分を負担することになります。
さらに、距離に加えて時間帯や走る道路によって税率を変えれば、渋滞や排ガスの多い時間帯の利用を減らす効果も期待でき、環境負荷の軽減にもつながります。
デメリット:物流業・地方住民の負担増
一方で、走行距離課税にはデメリットも多く指摘されています。
特に影響が大きいのは物流業界です。長距離を走るトラックは年間10万kmを超えることも珍しくなく、その分コストが大きく増加する可能性があります。
運送会社が負担を吸収できなければ、結果的に商品価格に転嫁され、消費者の生活費に影響します。
また、地方に住む人々も負担増の対象です。公共交通が少ない地域では日常の買い物や通勤に車が欠かせず、走行距離が自然と長くなります。そのため都市部に比べて相対的に重い税負担を強いられる懸念があります。
プライバシー懸念と二重課税リスク
技術面での課題も無視できません。
GPSを使った方式では、走行距離だけでなく「いつ・どこを走ったか」という情報まで記録される可能性があり、プライバシーへの不安が強く指摘されています。
また、走行距離課税を導入する際にガソリン税や自動車税が残ったままだと「二重課税」になる恐れがあります。
例えばガソリンを使う車は燃料に課税され、さらに走行距離にも課税されれば、結果的に負担が二重にかかってしまいます。制度を導入するなら、既存の税制との調整が欠かせない点が大きな課題となっています。
現在の導入状況(日本)
- 導入時期は未定
2025年6〜7月時点でも、走行距離課税の「導入時期」は正式に決まっていません。制度の具体案や税率なども公表されておらず、国会などでの議論は続いているものの、意思決定には至っていません。 - 検討主体は国土交通省・財務省
近年になって検討が本格化していますが、導入に向けた具体的なタイムラインや制度設計(税率、測定方法など)は未設定です。 - 提案の背景
走行距離課税は、省エネ車・電気自動車(EV)の普及によって減少するガソリン税に代わる財源確保手段として、2022年10月の税制調査会でも言及されました。
ただし、2025年3月時点でも、政策としての実施は依然として「検討段階」にとどまっています。
検討されている技術的アプローチ
- 車載器+GPS方式
専用の車載器を用いて、走行距離を自動取得し通信。正確なデータ取得をねらう方法です。 - オドメーター申告方式
走行距離計(オドメーター)の数値を自己申告する方法。ただし、改ざんリスクがあるため、他方式との併用も検討されています。
これらの方式を組み合わせた運用が現実的に想定されていますが、プライバシー保護やシステム構築・維持のコストも課題です。
まとめ:日本での導入現状
| 項目 | 現状 |
|---|---|
| 導入時期 | 未定(2025年6〜7月時点) |
| 制度設計状況 | 国土交通省・財務省で検討中。具体案未決定 |
| 背景 | ガソリン税減収に対応する新たな税収手段として注目 |
| 測定方式の検討状況 | GPS付き車載器やオドメーター申告などを複合的に検討中 |
現状では、「検討段階」であり、具体的な導入へはまだ時間がかかりそうですが、着実に議論が進んでいることは確かです。
ガソリン税の減収やEV普及を背景に、「走行距離課税(走行税)」が議論されています。
とはいえ、いつ・どの税をどう置き換えるのか、計測方法やプライバシー、物流・地方の負担など、設計しだいで影響は大きく変わります。
制度設計の選択肢と影響のイメージを、表と試算でシンプルに整理しました。
① 賛否・論点早見表
| 論点 | 賛成側の主張 | 反対側の懸念 | 設計オプション(緩和策) | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| 公平性(使った分だけ) | 走行距離に比例し負担が妥当化 | 生活・仕事で走行が多い人ほど重く | 年間◯kmまで低率/非課税の「基礎枠」 | “最低移動”の守りを |
| 二重課税 | 既存税の整理で中立にできる | ガソリン税と重なる恐れ | 導入と同時に燃料税・重量税の縮減/置換 | セット設計が命 |
| 地方負担 | 都市部より道路維持が必要 | 公共交通が薄く走行距離が伸びる | 地域係数・年額控除・医療/通学低率 | 地域事情に寄せる |
| 物流業の影響 | 効率化・低炭素投資を促す | 運賃/物価への転嫁リスク | 中小上限(キャップ)・必需物流軽減・投資減税 | 初期は守って育てる |
| プライバシー | 総距離だけでも運用可 | 位置情報の取得・保存が不安 | 総距離のみを基本、位置は任意・短期保存 | “位置なし”をデフォ |
| 渋滞/環境 | 時間帯・場所で賦課差配可 | 複雑化・導入コスト | 希望者のみ可変料金(基本は単一率) | シンプル×選択制 |
| 法的安定性 | 国法ベースで整備可 | 権限争い・違憲リスク | 国の根拠法で一本化 | まず土台づくり |
② 数値シミュレーション(※仮定。日本の税率は未定)
A. レート別の年負担(単純モデル)
仮に 0.5 / 1.0 / 2.0 円/km とした場合の概算。
(家計・事業の感覚を掴むための目安です)
| ペルソナ | 走行距離/年 | 0.5円/km | 1.0円/km | 2.0円/km |
|---|---|---|---|---|
| 地方在住(通勤+買物) | 15,000 km | 7,500 円 | 15,000 円 | 30,000 円 |
| 都市部通勤(鉄道併用) | 5,000 km | 2,500 円 | 5,000 円 | 10,000 円 |
| 中小トラック | 80,000 km | 40,000 円 | 80,000 円 | 160,000 円 |
| 長距離大型 | 120,000 km | 60,000 円 | 120,000 円 | 240,000 円 |
| EVオーナー | 10,000 km | 5,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
B. 緩和策を入れた場合の例(ベース 1.0円/km)
- 設計例:年間3,000kmは非課税/地方係数0.8(地方在住のみ)/中小・長距離トラックは年上限10万円
- 概算結果(年額)
| ペルソナ | ルール適用後の年負担 | 月あたり目安 |
|---|---|---|
| 地方在住(15,000km) | 9,600 円 | 約 800 円/月 |
| 都市部通勤(5,000km) | 2,000 円 | 約 167 円/月 |
| 中小トラック(80,000km) | 77,000 円 | 約 6,417 円/月 |
| 長距離大型(120,000km) | 100,000 円(上限適用) | 約 8,333 円/月 |
| EVオーナー(10,000km) | 7,000 円 | 約 583 円/月 |
③ 設計チェックリスト(実務案)
- 対象はEV/超高燃費車から段階導入 → 既存税との収入中立で開始
- 基礎非課税km+地域係数+産業別上限で急激な負担増を回避
- 総距離のみを基本データ(位置情報は任意・短期保存)
- 用途別に使途の見える化(道路保全/安全/環境)を年次公表
まとめ
走行距離課税は、ガソリン税に依存しない新しい財源として注目されています。
実際に導入している国々では「使った分だけ負担する」という公平性や、電気自動車への課税、環境負荷軽減といったメリットが見られます。
一方で、日本に導入する場合には、物流業界のコスト増や地方在住者の負担増、さらにプライバシー保護や二重課税といった課題も避けて通れません。
オレゴン州やニュージーランド、ドイツなどの事例は参考になりますが、そのまま日本に当てはめることは難しく、地域性や交通環境を踏まえた制度設計が必要です。
今後の議論では「誰がどのくらい負担するのか」「どのように公平さを保つのか」が焦点となりそうです。
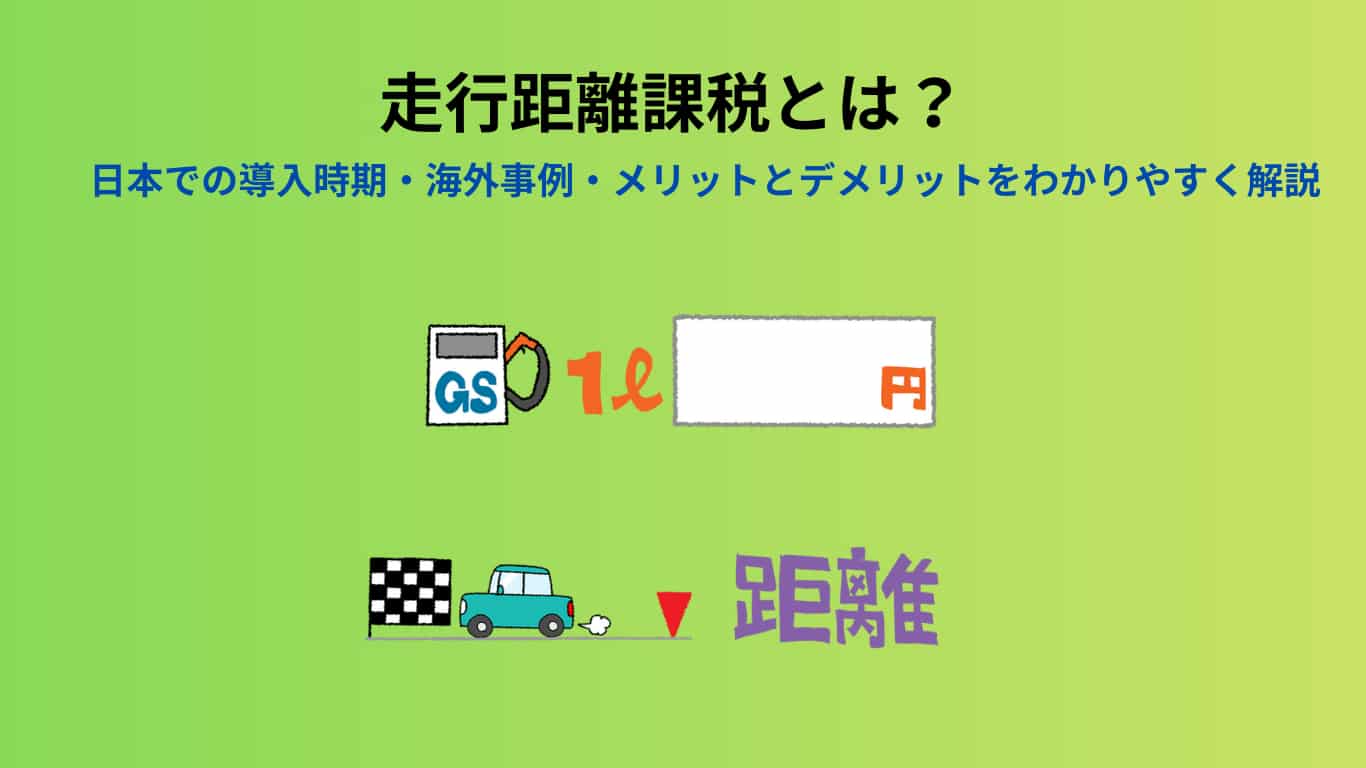
コメント