2025年7月20日投開票の参院選・東京選挙区で注目を集めているのが、参政党のさや氏(43)です。
芸能活動を経て政界へ転身した彼女は、YouTube番組での「核武装は安上がりで安全を強化する策のひとつ」という発言により、SNSを中心に大きな議論を呼んでいます。
唯一の被爆国・日本で、政治家の「核」に関する発言はどのように受け止められるのか──。
この記事では、さや氏の発言の背景や党のスタンス、被爆者団体の反応、そして有権者としての視点から問題を深掘りしていきます。
はじめに

注目集める東京選挙区──さや氏の存在感
2025年7月20日に投開票を迎える参院選・東京選挙区。
その中でも注目を集めているのが、参政党から立候補しているさや氏(43)です。
元音楽ユニット「saya」としての活動歴を持つ彼女は、芸能界から政界へと挑戦の場を移し、連日メディアでもその発言や姿勢が取り上げられています。
新聞各社の情勢調査では「当選圏内」とも言われ、知名度と発信力を背景に、若年層を中心とした支持を広げているようです。
彼女が出演した日本テレビ系のYouTube番組『投票誰にする会議~参院選2025東京選挙区~』では、社民党や日本保守党の候補者らとともに安全保障や外交の課題について語り、その中での“ある発言”が大きな話題となりました。
“核武装”発言が広げた波紋とその背景
さや氏が物議を醸したのは、安全保障に関する議論の中で「核武装は最も安上がりで、安全を強化する策のひとつ」と発言したことでした。
日本は世界で唯一の被爆国として、核兵器に対して強い拒絶感を持つ国でもあります。
そんな中での“コスト重視”ともとれる表現は、多くの有権者や被爆者団体に衝撃を与え、SNS上では「被爆国としてあり得ない」「軽率すぎる」といった批判の声が相次ぎました。
さらに、広島県被爆者団体協議会の佐久間理事長も「なぜ核武装したら安全だと思うのか」と疑問を呈し、核の恐ろしさや平和の尊さを訴えるコメントを発表しました。
このように、さや氏の発言は単なる政策論争にとどまらず、日本の歴史や倫理観にも深く関わる重要な論点として、広く議論を呼んでいるのです。
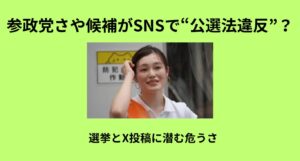
1.さや氏の核保有発言とは何か
「核武装は安上がりで安全強化」発言の全文と文脈
さや氏が“核武装”について語ったのは、日本テレビの報道局が配信するYouTube番組『日テレNEWS』のライブ配信「投票誰にする会議~参院選2025東京選挙区~」の中でした。
東京選挙区の候補者3名をスタジオに招いて、それぞれの政策や安全保障への考えを聞くという内容で、さや氏は「核保有」についての司会者の問いに対し、こう述べました。
「北朝鮮ですら核を持っていることでトランプ大統領と交渉できるようになった。それを見た時に、結局核武装が一番安上がりで、安全保障を強化する策の一つだと思います」。
この発言は一見すると軍事戦略の合理性を語っているようにも聞こえますが、「安上がり」「交渉の道具」という表現が、唯一の被爆国としての日本の立場と大きくかけ離れていたことで、多くの視聴者の心に強く引っかかる結果となりました。
さらに彼女は「これは私個人の考え」と断りつつも、発言の影響力は決して小さくありませんでした。
番組内での発言内容と他候補者との違い
同じ番組に出演していた社民党の西美友加氏や、日本保守党の小坂英二氏も安全保障について持論を展開していましたが、さや氏のように「核武装」という具体的かつセンシティブなワードを用いた候補はいませんでした。
西氏は「平和外交の強化」や「対話による信頼関係の構築」を重視し、小坂氏は「自衛隊の能力強化」や「防衛費の見直し」といった現実路線を打ち出しました。
それに対し、さや氏の発言は「核保有を視野に入れた自立防衛」にまで踏み込み、他の候補と比べて極端に聞こえたのは否めません。
また、発言の中に「“みかじめ料”」という言葉を使った点も、SNSなどで「例えが下品」「軽率すぎる」と批判される一因となりました。真剣な安全保障議論の中で使うには、言葉選びとして疑問が残る印象を持った人も少なくなかったようです。
「個人の見解」と「党としての姿勢」のギャップ
注目すべきは、さや氏がこの発言を「個人的な意見」と断ったうえで、「党としては核の議論を封じない立場」と表現したことです。
つまり、参政党全体として核武装を推進しているわけではなく、「今はその段階にないが、議論は必要だ」との立場をとっていると説明しました。
一方で、党の公式政策文書では《核廃絶を目指しつつ、核を使わせない抑止力を持つ》という一文があり、あくまで核兵器は“使わせないための手段”として捉えていることがわかります。
さや氏の「最も安上がり」という表現が、こうした党の公式見解とズレていることも、議論を複雑にしています。
発言の背景にある思考や意図を汲み取るにしても、「なぜこの表現だったのか」「党としてそれをどう受け止めているのか」は、今後の説明責任としても問われるポイントと言えるでしょう。
2.参政党の公式政策と核保有議論
参政党の「核を使わせない抑止力」政策の意図
さや氏の発言が注目を集める一方で、参政党の公式なスタンスはどうなっているのでしょうか。
党のホームページに掲載されている「参政党の政策2025」には、核保有に関して《核保有国に囲まれた日本を守るため、厳しい国際社会の現実を踏まえ、核廃絶を長期的な目標としつつ、今の日本を守るために、核保有国に核を使わせない抑止力を持つ》と記されています。
つまり、党としては「核を持つことで核を使わせない」という“抑止力”を重視していることが読み取れます。
これは、直接的な核保有を推進する立場ではなく、あくまで「議論は必要」という柔らかい表現にとどまっています。
外交や安全保障の厳しさを現実的に見つめながらも、核兵器そのものを積極的に持つというよりは「他国に対して牽制力を持つ」という考え方です。
ただ、その“抑止力”が何を意味し、具体的にどんな手段をとるのかは曖昧なままです。
たとえば、アメリカの「核の傘」への依存なのか、自国による核配備の議論を進めるのか、その点は明確には書かれていません。このあたりに、有権者が戸惑う要素が含まれているともいえるでしょう。
核廃絶と現実主義──矛盾する文言の読み解き
参政党は長期的な核廃絶を掲げつつ、現実としての核抑止を認めるという“二段構え”の政策を打ち出しています。
この構え自体は国際政治の場でもよく見られるスタンスではありますが、日本のような被爆国においては、そのバランスは非常にデリケートです。
核廃絶という理想と、現実的な防衛の必要性――。
この二つを両立させるには、高度な外交力や国際的な信頼構築が求められますが、現時点ではその実現性について十分な説明がなされているとは言いがたい状況です。
さや氏の「安上がりで安全を強化する策」という発言も、この“現実主義”の一部として受け取られる可能性がありますが、それが党の理想とどう整合するのかは今後の議論に委ねられています。
「核廃絶を訴えながら核保有を視野に入れる」という文言は、受け取り方によっては矛盾しているようにも感じられ、有権者にとっては判断を迷わせる要因となりかねません。
有権者にとっての「議論すべきか否か」の論点
今回の選挙で有権者にとって問われているのは、「核を持つかどうか」だけではなく、「その議論自体を開かれた場で行うべきかどうか」という点です。
さや氏の発言を契機に、「核をタブーにせず話し合うこと自体は必要では?」という声も一定数出てきています。
たとえば、SNS上では「現実的に中国や北朝鮮の脅威にどう対応するかを議論するのは当然」といった意見がある一方で、「被爆国である日本が“核を持つべき”という発言をすること自体が傷つく」という批判も根強くあります。
背景には、戦後の平和教育や原爆の記憶、そして世界に対して持ち続けてきた“被爆国としての誇り”があります。
このように、「議論のあり方」そのものが、有権者にとって一つの投票基準となっているのです。
核の議論は、武力だけでなく日本のアイデンティティや価値観をも問うテーマ。だからこそ、党としてのメッセージと候補者個人の発言の一貫性が、より厳しく見られているのかもしれません。
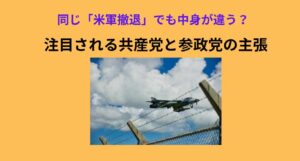
3.被爆者団体の反応と倫理的問い
広島被団協・佐久間理事長の見解
さや氏の「核武装は安上がりで安全強化になる」という発言を受け、広島県原爆被害者団体協議会(広島県被団協)の理事長・佐久間邦彦氏(80)は、強い違和感を表明しました。
佐久間氏自身は原爆投下時にまだ幼く、直接的な記憶こそないものの、多くの被爆者の体験を聞き取り、語り継いできた立場から、今回の発言に対して「なぜ核武装すれば安全になると考えるのか」と疑問を呈しました。
佐久間氏は「核兵器を持った国が、平和をもたらした実例があるだろうか」と問いかけます。
そして、さや氏のような“交渉力”としての核兵器という見方に対し、「それは人間の命を、駆け引きの道具にする考え方ではないか」と厳しく指摘します。
彼の発言には、「日本が核を持てば安全になる」という理屈が、いかに非人道的で、過去の惨劇を軽視しているかという強い懸念がにじみ出ていました。
「安上がり」「備える」発言への倫理的批判
特に多くの人が衝撃を受けたのは、さや氏の「核武装は安上がり」という言葉でした。
防衛コストの一環として核保有を検討するという視点そのものが、倫理的に疑問視されたのです。
戦争による犠牲者の記憶が今も生々しく語り継がれる中で、兵器を「コスト」で語る姿勢に、多くの被爆者やその家族が強い怒りを覚えました。
「“みかじめ料”という言葉もひどかった。まるで暴力団と対等にやり合うための“用心棒”のような発想だ」。これは、広島市で活動する別の被爆二世から聞かれた声です。
防衛論とは本来、命と平和の尊厳を守るために語られるべきものであり、価格やコスパの話として語ることは、日本が70年以上かけて築いてきた「非核・平和国家」としての信頼にも関わる重大な問題です。
被爆体験と日本の国際的立場から見た核兵器
唯一の被爆国として、国際社会に対して核兵器の非人道性を訴えてきた日本。佐久間氏は「右か左かではない。人間としてどう生きるかの問題だ」と強調します。
原爆を経験したからこそ語れる、核兵器の現実。それを武力バランスの一部として語ること自体が、日本のこれまでの姿勢と真っ向から衝突するのです。
国際的な条約や会議の場でも、日本の被爆者の声は特別な重みを持ってきました。
たとえば、2022年に行われた核兵器禁止条約締約国会議でも、日本から出席した被爆者が「核兵器が存在する限り、私たちは平和とは言えない」とスピーチし、多くの国の代表に深い感動を与えました。
このような背景があるからこそ、さや氏のような候補者が「核も選択肢のひとつ」と発言することは、単なる個人の思想では済まされません。被爆国としての責任、そして世界に対するメッセージの一貫性が問われているのです。
4.徴兵制や軍による教育──さや氏の発言を読み解く
徴兵制を全肯定する参政党のさや氏。教育的役割があって、学校では教えられないことが兵役の中で教えられる、だとさ。軍国教育かよ。参政党に投票すれば、あなたやあなたの子どもが、徴兵されるんですよ。#参政党#参政党に騙されるな#参政党はヤバくてキモいpic.twitter.com/0irqrB5EdK
— 芻狗 (@justastrawdog) July 16, 2025
「傭兵から国家の軍隊へ」──その意味するところは?
さや氏は番組内での発言において、「傭兵国家から国家の軍隊へ」と語り、徴兵制に言及しました。
これは一見すると、「他国に頼らず自らの国を守るための体制を構築するべきだ」という“自立防衛”の姿勢に聞こえるかもしれません。しかしその裏には、重大な制度的・倫理的転換が含まれています。
たとえば現在の自衛隊は志願制であり、職業選択の自由の下に成り立っています。一方「徴兵制」とは、国が強制的に国民を軍隊に動員する制度です。
戦後日本では憲法第18条(奴隷的拘束の禁止)や第13条(個人の尊重)との兼ね合いもあり、長らく忌避されてきた制度でもあります。
にもかかわらず、さや氏は「傭兵的な戦争ビジネス」から脱却し、国民が担う“国家の軍隊”への転換を主張しています。これは明確に「徴兵制導入」へと繋がる議論であり、有権者にとっては「国が戦争への道を開こうとしているのではないか」との懸念を抱かせる内容です。
「新自由主義からの脱却」とは何か
さらに、さや氏は「新自由主義からの脱却」という言葉も用いました。新自由主義とは、自己責任・民営化・小さな政府などを重視する経済思想です。軍事分野においては、民間軍事会社の活用や外注化がその例とされることがあります。
この文脈において、さや氏は「民間任せの戦争ではなく、国民自身が担うべき」という立場をとっているように見えます。つまり「戦争を他人任せにせず、自ら血を流せ」という、かなり過激で政治思想的なメッセージが含まれていると受け取る人も少なくありません。
ですが、有権者である私たちからすれば、「徴兵制によって“自己責任”から逃れるのではなく、逆に“国家責任”に巻き込まれるのでは?」という根本的な疑問が湧いてきます。
「軍は学校で教えないことを教えている」──教育の役割を誰が担うのか?
さや氏はさらに、軍隊には「学校では教えられない教育」があるとし、道徳や規律の学び場としての意義を語っています。一部の保守系論者が唱えるように、軍隊を「礼儀や公共精神の鍛錬の場」として捉える立場に近いと思われます。
しかしそれは、「国家の価値観に沿った教育を強制する場」に転化するリスクも孕んでいます。現に戦前の日本では、兵役を通じて国体思想や天皇への忠誠を“教え込む”場として軍が機能していました。
教育とは本来、自由と多様性を前提とした場であるべきですが、軍による教育は「国家に従わせる訓練」となる恐れがあります。
教育の名の下に、国への服従や集団規律が重視されすぎると、それは“育成”ではなく“統制”になってしまうのではないでしょうか。
現代日本における徴兵制のリアリティ
なお、日本では現在、徴兵制は法的にも制度的にも存在していません。憲法に明記された「個人の尊厳」や「職業選択の自由」などと大きく矛盾するため、導入には憲法改正が必要になります。
仮にそれが議論されるとしても、国会での長期的な審議や国民投票などのプロセスが必要です。
しかし、「議論するだけなら自由」という立場であっても、候補者が公に「徴兵」や「軍による教育」を肯定的に語るという事実は、国のあり方を大きく左右する可能性を秘めています。
選挙とは、未来の方向を選ぶこと。徴兵制や軍事教育というテーマが、どこかで既定路線として進められていないか──その一言一言に、有権者として敏感でありたいと思います。
このように、さや氏の徴兵制発言には「国の自立」「国民の覚悟」「教育の再建」といった、耳障りのよい言葉が並んでいます。しかし、その裏にあるのは、戦後日本が避けてきた“国家による人の支配”の再来なのではないか。
その問いを私たちが投げかけることこそ、民主主義の根幹ではないでしょうか。
まとめ
さや氏の「核武装は安上がりで安全を強化する策のひとつ」といった発言は、参院選の候補者としての安全保障観を示すものであると同時に、日本社会が戦後守ってきた「非核三原則」と「平和国家としての歩み」に強く反するものでした。
党としての公式スタンスと、候補者個人の見解とのギャップ、そして“コスト”や“交渉材料”として核を捉える発言の是非が、今改めて問われています。
被爆者団体や多くの市民からの声は、「核を持つかどうか」以前に、「核という存在にどれだけの重みと痛みがあるか」を理解しているかどうかにあります。
日本が世界に訴えるべきは、武力による抑止ではなく、悲劇の記憶を生かした非戦と対話の姿勢であるという信念です。
選挙の一票が、日本の未来をどのような方向へ導くのか――候補者の言葉一つひとつを通じて、有権者の私たち一人ひとりが深く考えるべきときが来ているのかもしれません。
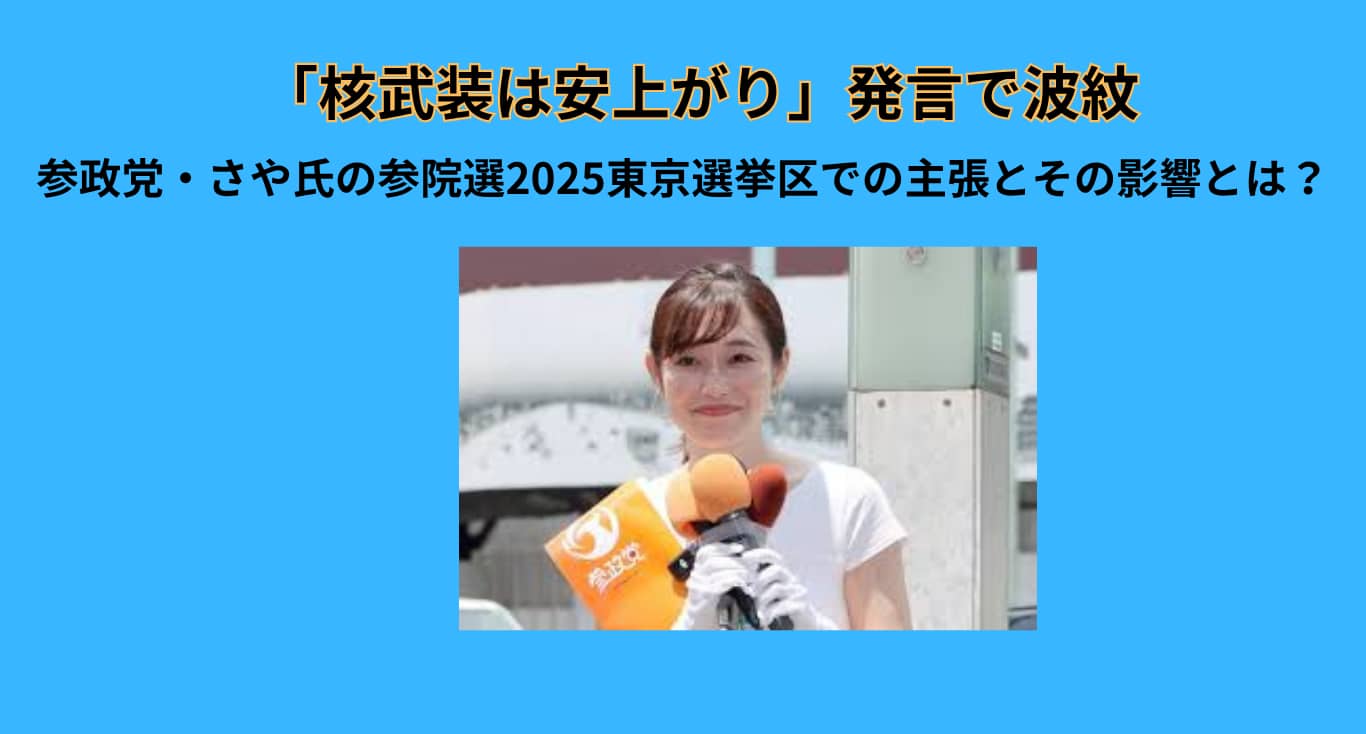
コメント