2025年の参院選を前に、参政党の候補者によるSNS上での投稿が「公職選挙法違反の可能性がある」として波紋を呼んでいます。
X(旧Twitter)での「感謝でいっぱいです」という返信──一見、何気ない応援コメントへのお礼のようにも見えますが、それが“飲食提供と投票を結びつけた投稿”に対するものだったことから、ネット上では批判と困惑の声が噴出しました。
「SNS時代の選挙のあり方」について深く考える必要があるようです。
本記事では、参政党の対応や公選法の基本、そしてSNSと選挙活動の課題について、できるだけ分かりやすくお伝えします。
はじめに
参政党候補者のSNS投稿が波紋を呼んだ背景
2025年7月12日、参政党の公式X(旧ツイッター)アカウントで、「不適切な内容が含まれていた」とする謝罪文が投稿され、大きな注目を集めました。
発端となったのは、東京選挙区から立候補しているさや氏によるSNSでの返信。あるユーザーが、飲食物と引き換えに投票を呼びかけるような内容を投稿したのに対し、さや氏は「感謝でいっぱいです」と反応したのです。
一見すると応援に対する普通の返信のようにも思えますが、「飲食の提供」と「投票の呼びかけ」が絡むと話は別。
SNSではすぐに「これは法律に触れるのでは?」という声が広がり、投稿は削除されたものの、騒動は瞬く間に拡散しました。
公職選挙法との関係が指摘される理由
今回の問題が大きく取り上げられた背景には、日本の選挙を規定する「公職選挙法(こうしょくせんきょほう)」の存在があります。
この法律では、有権者に対して飲食物を提供することを、買収など不正行為につながる恐れがあるとして原則禁止しています。たとえば「お弁当を配って投票してね」といった行為はNGとされます。
つまり、たとえ候補者本人が飲食物を提供していなくても、「そうした行為を賞賛・黙認している」と受け取られる投稿は、選挙の公正性に疑問を投げかける行為になりかねません。
今回は第三者の投稿への返信という形でしたが、「感謝の言葉」が法に触れる可能性を持つという、SNS時代ならではの複雑な問題が浮き彫りになったのです。

- 名前(候補名):さや(平仮名2文字で公表)
- 年齢:43歳(1982年7月7日生まれ)
- 肩書:シンガーソングキャスターとしても活動
🗳 選挙情報
- 選挙区:2025年参議院選挙/東京選挙区(投開票日:2025年7月20日)
- 政党:参政党公認候補
🎙 活動実績
- X(旧Twitter)では「@sayaohgi」として情報発信中
- YouTubeチャンネル「チャンネルさや」を運営
- 選挙ドットコムにブログ投稿多数(例:2025/7/7〜12にかけての活動記録あり)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 1982年7月7日 |
| 職業 | シンガーソングキャスター |
| 政策等活動 | SNS発信を積極的に活用し、街頭演説やイベント参加なども文で報告 |
ただいま選挙戦の最中で、7月7日から12日までの活動がブログでも公開中です。
「さや」は参政党から東京選挙区へ立候補した43歳のシンガーソングキャスター。
SNS(X・YouTube)を通じて、若者や市民にも響く発信を続けています。
学歴・経歴
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 出身高校 | 神奈川県立横浜日野高校(2003年に統合、現・横浜南陵高校)人と政治と名言と |
| 最終学歴 | 青山学院女子短期大学 英文学科 卒業(英語学習が後の音楽活動・国際活動に直結)人と政治と名言と |
| 職歴・実績 | 短大卒業後ジャズシンガーとして活動し 2008 年CDデビュー。FM 横浜のDJやテレビ神奈川CM出演などを経て、YouTube番組MC・コメンテーターとしても活躍。2025年参院選で政治の世界に挑戦。人と政治と名言と |
具体的な政策(公式サイト「清の会」より要約)
| 政策分野 | 主なポイント |
|---|---|
| 財政・金融 | – 財務省の任務を「安定的な経済成長」へ変更 – PB(プライマリーバランス)黒字化目標を破棄し「国民負担率35%以下」を掲げる – 消費税を当面5%に引き下げ、段階的に廃止 |
| 経済・賃金 | – 名目GDP5%・実質GDP3%成長を15年間続けて規模を倍増 – 医療・介護など公共分野の賃金を年10%ペースで7年で倍増 – 社会保険料を半減し手取りアップ |
| 防災・インフラ | – 南海トラフ・首都直下地震対策など総額約60兆円の「多年度強靭化」特別予算を確保 |
| 食料安全保障 | – 農協・漁協を守り株式会社化に反対 – 種子法復活・遺伝子組み換え表示義務の厳格化 – 外国産食品に世界最高水準の安全基準を適用 |
| エネルギー | – 原発は短期的に再稼働しつつ将来的な「原発ゼロ」を視野に技術開発を推進 |
| 外交・安全保障 | – 日米地位協定の「不平等」是正を目指す発展的改定 – 自主防衛力強化と、将来的な沖縄の米軍基地全面撤廃を掲げる – 外国人の土地取得を制限する法改正 |
- キーワードは「手取りアップ」と「食と国土の守り」。家計の可処分所得を増やしつつ、農業・防災・インフラへ大胆に投資する姿勢が特徴です。
- 学歴は短大卒ですが、音楽活動とキャスター経験で培った発信力・英語力を武器に「情報発信型」の選挙戦を展開中。
- 公式サイトでは更に細かい条文レベルの提案も公開されています。政策を深掘りしたい場合は「清の会 さやの政策」ページをチェックすると◎。
「社会保険料半減」「消費税廃止」「外国人土地規制」などインパクトの大きい主張が並ぶ一方、財源論・実現プロセスについては議論が分かれるところ。
投票前にメリット・デメリットを見比べながら、自分の暮らしや価値観に照らして判断してみてくださいね。
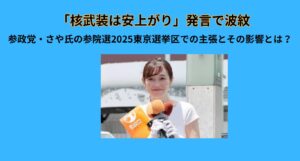
1.候補者の投稿とその問題点
「感謝でいっぱい」リプライが招いた誤解
さや氏がリプライした「感謝でいっぱいです」という一文は、一見すると支持者への感謝を表すだけのものであり、大きな問題には見えないかもしれません。
しかし、この返信の相手が投稿していた内容には、「飲食を提供するから、さや氏に投票しよう」と受け取れるような表現が含まれていました。その投稿に肯定的な返信をしたことで、「飲食と投票を引き換えにする行為を、候補者本人が黙認・応援している」と捉えられるリスクが生じたのです。
とくに選挙期間中は、候補者の言動が法的にも社会的にも厳しく監視されています。
たとえ悪意がなかったとしても、「見過ごせない発言」として批判の対象になることは避けられませんでした。SNSという即時性の高いツールでは、こうした誤解が一瞬で広がるため、なおさら注意が必要なのです。
第三者投稿との関係性と削除の経緯
問題の投稿は、さや氏自身が書いたものではなく、支持者と思われる第三者によるものでした。
この人物は、自分の店で飲食物を提供することと投票をセットで呼びかけるような内容を投稿し、それに対してさや氏が好意的に反応してしまった――という構図です。
その後、両者の投稿はすぐに削除されました。公式アカウントも「問題のある内容があった」として謝罪していますが、投稿がすでに拡散した後だったため、火消しは簡単ではありませんでした。
SNSでは削除されても「スクリーンショット」が拡散され、永続的に残ってしまうのが現代のリスクです。
飲食提供との関連で浮上した違法性の可能性
本件の焦点は、「飲食と投票を結びつける行為」が、公職選挙法で禁じられている“買収”に該当する可能性がある点です。
法律上は、有権者に対して食べ物や飲み物を提供して「投票してね」と働きかけることは原則として禁止されており、違反すれば候補者だけでなく関係者にも処罰が及ぶことがあります。
たとえば過去にも、地域の集会でお菓子やジュースを出してしまった候補者が「違反の可能性あり」として注意を受けたケースが報じられたことがありました。
今回は投稿者が候補者本人ではなかったとはいえ、それに同調する返信を行ったことで、結果的に「違法行為に加担した」と見られるおそれがあったのです。
SNSの活用が当たり前になった今、「どこまでがOKでどこからがNGか」というラインが非常にあいまいになっています。その曖昧さこそが、今回のようなトラブルの背景にあるといえるでしょう。
2.参政党の対応と釈明
公式アカウントによる謝罪声明の内容
騒動の拡大を受け、参政党の公式X(旧ツイッター)アカウントは、7月12日に謝罪文を投稿しました。
声明では、「候補者の認識不足により、公職選挙法に抵触する可能性のある投稿へ、投票への感謝のコメントを行ってしまいました」と説明し、「不適切な内容が含まれていたことを深くお詫び申し上げます」と陳謝しています。
この対応は迅速だったものの、SNS上では「対応が遅すぎた」「なぜあのような投稿を許したのか」といった批判も多く見られました。
公式アカウントからの謝罪には、選挙戦を続ける上での信頼回復という意味もあったのでしょうが、すでに拡散された印象は簡単には拭えません。
また、政党として候補者の投稿をどこまで管理していたのか、チェック体制への疑問も残りました。これまでにも他党を含めて、SNS発言が問題となるケースは多数あったことから、今回も「またか」と冷ややかな目で見られる一因となったのです。
候補者本人の謝罪投稿とその影響
候補者であるさや氏も、自身のアカウントで謝罪の意を示す投稿を行いました。「私の軽率な対応により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしました」といった趣旨のコメントを発信し、投稿に対する責任を一部認める姿勢を見せました。
しかし、その謝罪文に対しても反応は賛否両論。支持者からは「素直に謝っていて立派」「次から気をつければいい」と擁護の声があがった一方で、「謝れば済む問題ではない」「法律を理解していない証拠」とする批判も少なくありませんでした。
とくに公職に立候補する人物として、法令遵守の姿勢が求められるなかで、「知らなかった」では済まされないという意識が広がっています。
候補者自身がSNSでの発言に慎重であるべきという認識が、今回の件で改めて浮き彫りになったとも言えます。
「認識不足」によるミスとして処理された背景
政党および候補者の双方が今回の問題を「認識不足」「意図的ではない」と表現している点も注目されます。
つまり、「違反の意思はなかった」「知らなかったために起きた失敗である」として、法的責任を回避しようとする説明がなされているのです。
このような対応は、選挙戦を継続するうえで必要な“火消し”策だったとも取れますが、有権者の中には「言い訳に聞こえる」「準備不足では」と受け止めた人も多く、信頼回復には時間がかかるかもしれません。
さらに、政治活動において「知らなかった」は通用しないという社会の空気感も強まっています。
今回の処理が形式的な“謝って済ませる対応”にとどまらず、今後の運営や候補者教育にどう反映されるのかも問われることになるでしょう。
3.選挙とSNS時代の課題
公選法におけるSNS投稿のグレーゾーン
今回のような事例が物議を醸すのは、SNS上の発言が公職選挙法にどこまで抵触するか、その線引きが非常に曖昧だからです。たとえば、演説や街頭活動では当然とされる「応援ありがとう」といった言葉も、SNSでは文脈が切り取られ、誤解を招きやすい構造になっています。
実際、「飲食物と投票を結びつける行為はNG」という明確な規定がある一方で、SNS上のリプライがそれを黙認したと見なされるかどうかは、法的にも解釈が分かれる部分です。
今回のように「候補者本人が飲食を提供したわけではない」場合、違反にあたるかどうかは微妙なラインと言わざるを得ません。
とはいえ、SNSは多くの有権者に直接メッセージを届ける手段として欠かせないものとなっており、選挙の現場でも当然のように活用されています。
それだけに、発言ひとつで法的・倫理的な問題に発展するリスクも高まっているのが実情です。
候補者のネットリテラシーとその限界
この問題を通じて、候補者本人のネットリテラシー(ネット上の発言や行動に関する知識や配慮)の重要性も改めて浮き彫りになりました。
SNSでの言動が瞬時に注目を集める現代において、たとえ1つのリプライでも、その影響は計り知れません。
さや氏のケースでも、「応援に対する素直な気持ちだった」との弁明は理解できるものの、候補者という立場においては“発言の先読み”が求められます。
仮に第三者の投稿であっても、それが法令に触れる可能性のある文脈ならば、無視するか、慎重に対応する必要がありました。
とくに、地方選挙や新人候補のように、ボランティアや個人で運営する場面が多い選挙では、スタッフ含めてネットリテラシーが不足していることが少なくありません。
今後、候補者になる人には、SNS研修や法令に関する基本的な教育が強く求められる時代になるでしょう。
今後の選挙活動に求められるルールと配慮
SNSが選挙活動の主戦場となっている今、これまでの選挙運動ルールだけでは対応しきれない場面が増えています。
たとえば、動画投稿に登場した食べ物や、他人の発言へのリアクションひとつで問題視されるケースも出てくるでしょう。
今後は、SNS上での候補者・支持者の発言に関しても、明確なガイドラインが必要とされる場面が増えるはずです。
現在でも総務省や一部自治体が「SNS選挙ガイドライン」のような資料を出していますが、一般候補者まで浸透しているとは言いがたいのが現実です。
また、SNSは有権者の目が非常に近いため、候補者の「人柄」がダイレクトに伝わる分、軽率な一言が命取りになることもあります。
ルール整備と並行して、候補者自身が“発信者”であるという強い自覚を持ち、慎重かつ誠実な情報発信を心がけることが不可欠です。
まとめ
今回の一連の騒動は、SNSと選挙活動が密接に結びつく時代における、新たなリスクと責任を浮き彫りにしました。
候補者さや氏の「感謝」のリプライは、たった一言であっても選挙の公正さに疑問を生じさせる結果となり、公職選挙法との関係性が問われました。参政党の対応は迅速だったものの、「知らなかった」では済まされないという社会の目も厳しく、候補者自身のネットリテラシーや政党の教育体制にも課題が残るかたちとなりました。
SNSが選挙の主戦場になった今、候補者は一人の発信者として、法令を正しく理解し、発言の影響を見極める力が求められます。
選挙制度そのものも、時代の変化に即したルール整備と候補者教育が急務です。今回の事例は、すべての政党・候補者にとって、「ネット時代の選挙」とどう向き合うかを考える重要な教訓となるでしょう。
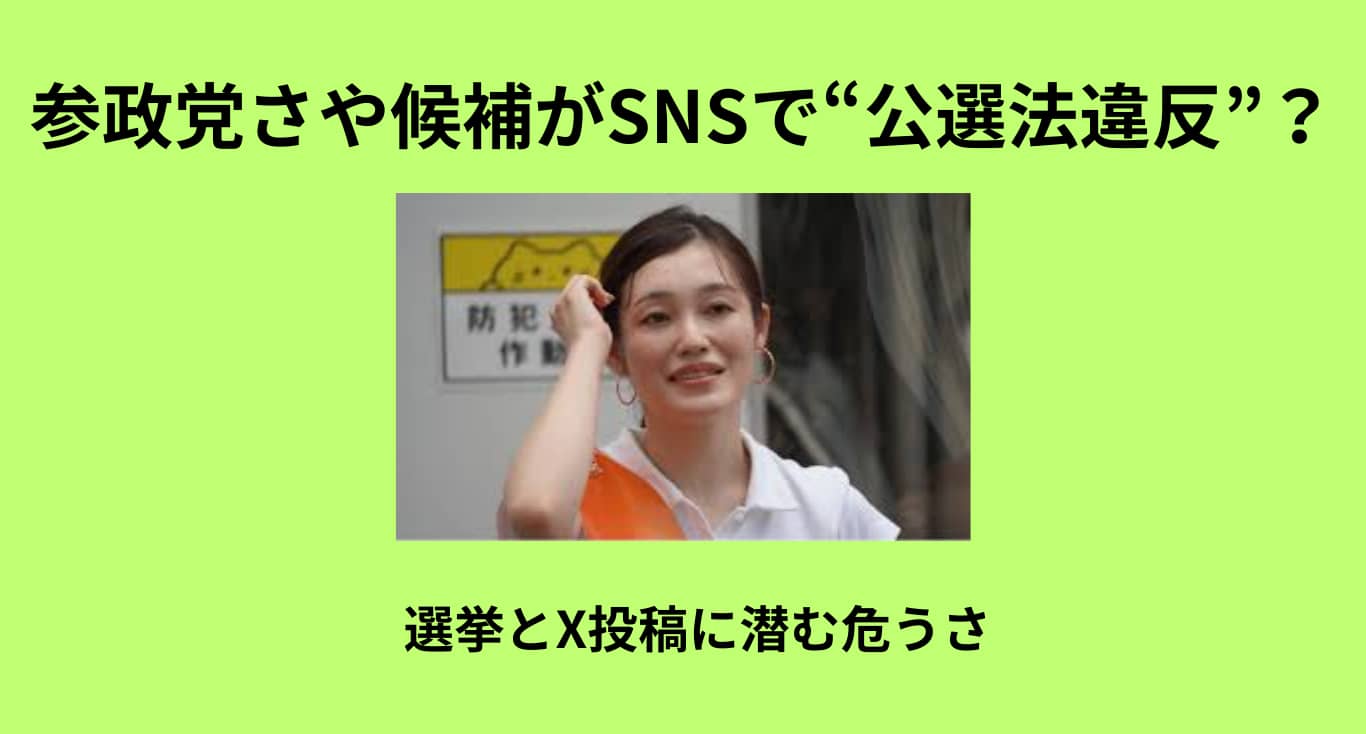
コメント