2025年の参院選で大きく議席を伸ばした「参政党」。その支持の背景には、一体何があるのでしょうか?
元テレビ朝日社員・玉川徹氏は、『羽鳥慎一のモーニングショー』で「ポピュリズム政党の典型」と評し、SNS時代における政治とメディアの関係についても言及しました。
この記事では、視聴者の立場から、参政党の主張やその広がり、既存メディアへの不信、そして「日本人ファースト」という言葉の意味について、わかりやすく掘り下げてみたいと思います。
政治に詳しくない方でも読みやすく、今の社会の空気感を知るきっかけになれば嬉しいです。
はじめに

ポピュリズムとは何か──玉川徹氏の指摘をもとに
最近よく耳にする「ポピュリズム」という言葉、なんとなく「極端な政治」や「過激な主張」といったイメージがあるかもしれません。でも実際には、もっと身近で感情に寄り添ったものなんです。
ポピュリズムとは、かんたんに言えば「今の政治はおかしい!」「このままじゃダメだ!」という多くの人の不満を、わかりやすい言葉で代弁してくれるスタイルのこと。
たとえば、「国民の声が無視されている」「エリートが得ばかりしている」といったメッセージを通じて、「私たちの味方」をアピールするんですね。
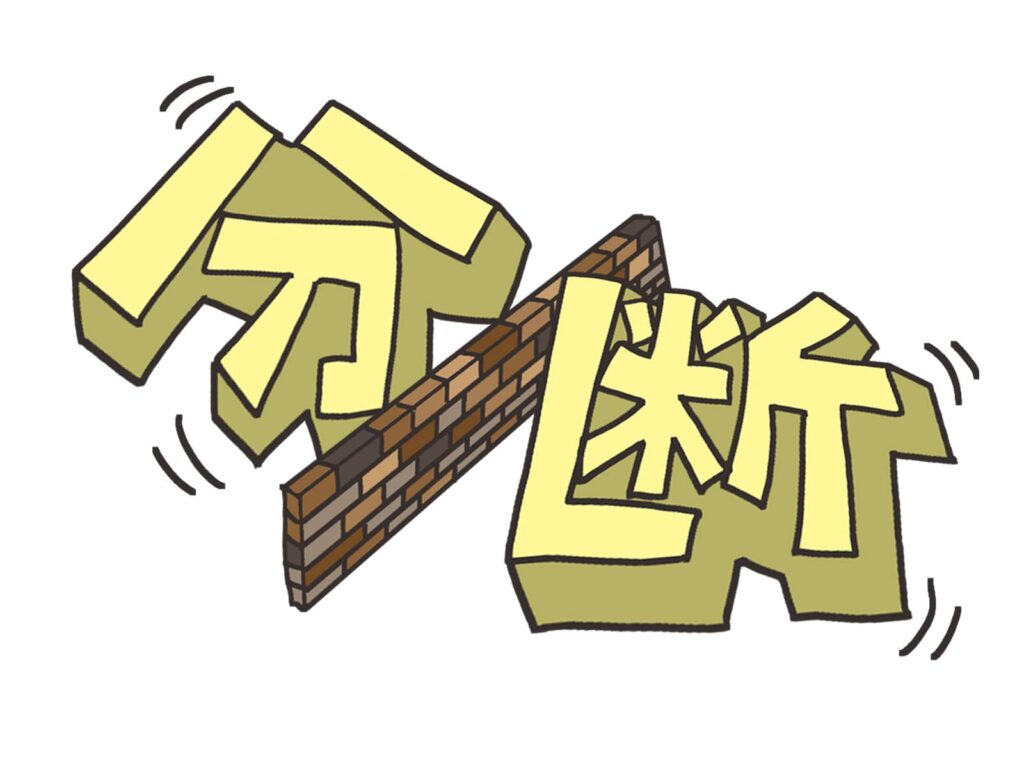
ただしそのぶん、敵や悪者をはっきり決めてしまう傾向もあり、「あれが悪い」「これのせいだ」と断言することで支持を集めることもあります。
だからこそ、力強い言葉に「そうそう!」と共感しやすい半面、分断を生みやすい面もあるんです。
政治の世界で近年よく聞かれるようになった「ポピュリズム」という言葉。
元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、モーニングショーの中で「ポピュリズムとは、大衆の不満をうまく言語化し、明確な“向け先”を提示することで支持を集める手法」だと語りました。
今回の参院選で参政党が躍進した背景には、まさにその「不満の向け先」の巧みな設定があったといいます。
たとえば、「財務省が日本をダメにした」「科学は信用できない」「日本が貧しくなったのは外国人のせいだ」といった、耳障りのよい断定的なメッセージ。
これらは一見乱暴に見えても、多くの人が感じている漠然とした不安や不満に、明快な答えを出してくれるように感じられるのです。
SNS時代の選挙戦とメディアの立ち位置
こうしたポピュリズムの流れに拍車をかけているのが、SNSの影響力です。
以前ならテレビや新聞といった大手メディアが世論を形成する中心でしたが、今やX(旧Twitter)やYouTubeのような個人発信の場が、政治家と有権者を直接つなげています。
参政党もまた、こうしたSNSを駆使し、「マスコミは報じない真実を伝える」と訴えることで支持を広げました。
一方で、既存メディアには「真実を報じていない」という批判も根強くあります。「嘘は言わないが、都合の悪いことは伝えない」といった不信感。
報道機関としての使命を果たしているのか──玉川氏の言葉を借りれば、「それは真実か?」と問い直す姿勢が、メディアにも今まさに求められているのです。
1.参政党の躍進とポピュリズムの構造
現状への不満と“向け先”の提示という戦略
参政党が今回の選挙で注目を集めた背景には、多くの有権者が感じている「今の日本はおかしい」という漠然とした不満があります。
生活は苦しくなる一方、政治家はどこか遠い存在で、何をやっているのかよく分からない。そのような空気の中で、参政党は「不満の向け先」を明確に示しました。
たとえば、「日本をダメにしたのはエリート官僚だ」「財務省が増税ばかりで庶民を苦しめている」「外国人ばかり優遇されている」といった、感情に訴えるメッセージを次々と打ち出しました。
こうした主張は、確固たる根拠があるわけではないかもしれませんが、日々の不満を抱える人々にとっては、「それ、分かる」と共感しやすいものでした。
SNS上では、街頭演説の切り抜き動画や、デモでのスピーチが拡散され、多くの人に「この政党は自分の言いたいことを代弁してくれている」と思わせる効果を生みました。
まさに、感情に働きかける“向け先”の設定が、支持の土台を築いたのです。
反エリート・反科学・反外国人といった語り口
ポピュリズム政党の特徴として、既存の権威に対する強い批判があります。参政党も例外ではなく、「エリート」や「専門家」への反発を前面に出しました。
「東大出の官僚が日本をダメにした」「マスクやワクチンは本当に必要なのか」「科学は万能じゃない」という訴えは、多くの不安を抱える人に響きました。
さらに、「外国人によって治安が悪化している」「移民政策の裏で日本人が損をしている」といった発信も一部で支持を得ました。
これらは事実と異なる場合も多くありますが、難しい言葉を並べず、感覚的に理解しやすいメッセージであることがポイントです。
こうした語り口は、学歴や情報リテラシーに関係なく、誰にでも届きやすいものです。
そして「私たち庶民」と「彼らエリート」という構図が、強い一体感を生み、対立軸として機能しました。
支持拡大の鍵は「感情」と「共感」のメニュー化
参政党の支持拡大は、政策の中身よりも、「共感できる言葉」をいかに用意できたかにあります。
「子どもを守ろう」「日本を取り戻そう」といった漠然としたスローガンも、政治に詳しくない人でも直感的に意味が分かります。
また、ワクチン慎重派や食の安全を重視する層、教育に不安を抱える親世代など、それぞれの不安や関心に合わせた「感情のメニュー」を提示できた点も大きいでしょう。
「オーガニック」「自然志向」「伝統回帰」など、一見すると政治とは無関係に思えるテーマすら、参政党のメッセージの中では“日本を良くする手段”として組み込まれています。
人は必ずしも理屈で動くわけではありません。「なんとなく安心できそう」「ちゃんと話を聞いてくれそう」という感情のつかみが、政治参加のきっかけとなり、今回の参政党の躍進につながったのではないでしょうか。
2.玉川徹氏の見解と既存メディアの課題

メディアは「真実かどうか」を検証・提示できているか
玉川徹氏が番組内で繰り返し強調したのは、「それは真実か?」という視点です。
つまり、どれほど強い言葉で主張されても、それが事実に基づいていないのであれば、メディアはきちんと検証し、反論しなければならないという立場です。
しかし実際のところ、既存メディアはこうした検証報道に消極的になっている印象を受けます。
たとえば、「外国人のせいで治安が悪化している」という主張に対して、具体的なデータを示して反論する報道はあまり見かけません。その結果として、「報道しない自由」を使っているように受け取られ、視聴者からの信頼を失っていくのです。
一方、SNSでは個人が調べた情報や意見がどんどん拡散されます。
中には誤情報や偏った意見もありますが、「既存メディアが扱わない真実がここにある」と信じる人々の目には、テレビよりもリアルな現実が映っているように感じられるのです。
ネットとテレビ──情報発信の主導権争い
情報をめぐる主導権は、もはやテレビだけのものではありません。かつては「テレビで報じられたら真実」と考える人が大多数でしたが、今や「テレビで報じないことこそ重要」という逆転現象すら起きています。
特に今回の参院選では、参政党のSNS活用が光りました。街頭演説のライブ配信、YouTubeでの政策解説、X(旧Twitter)での応援ポストなど、あらゆる手段で“自分たちの言葉”を届けていきました。
これに対してテレビは、そうした動きを「危険視する」あるいは「無視する」ような姿勢を取ることが多く、視聴者とのギャップがますます広がっています。
一例として、参政党が街頭で「子どもを守る」と訴えていた場面を、SNSでは熱烈に支持する声が相次いだ一方で、テレビではほとんど紹介されず、結果的に「なぜ無視するのか」という批判につながったケースがあります。
メディア不信と「報じない自由」への批判
こうした背景もあり、今の日本では「メディアへの不信感」が根強く広がっています。
とくに、ある問題が明らかになっても、それを扱うかどうかをメディア側が恣意的に決めているように見える点が、批判の的となっています。
たとえば、外国人による犯罪報道や政治家の失言など、SNSではすぐに拡散され議論になる話題でも、テレビでは扱われなかったり、ごく短く報じられたりすることがあります。
こうした「偏向報道」と受け取られる動きが、「既存メディアは信じられない」という印象を強めています。
玉川氏が言うように、メディアが果たすべき役割は、「これは事実か、真実か」という目線でしっかりと情報を確認し、必要であれば間違いを指摘することです。
その姿勢が欠けてしまえば、いくら正しい情報を発信しても、届く先は限られてしまいます。
今こそ、メディア自身が「自分たちの報道姿勢」を問い直す必要があるのではないでしょうか。
3.「日本人ファースト」と国民の危機意識
外国人排斥ではなく「不公平感」への怒り
参政党が掲げた「日本人ファースト」というメッセージは、一見すると外国人排斥のようにも受け取られがちです。
しかしその根底にあるのは、必ずしも排除の思想ではなく、「なぜ日本人が損をしているのか」という素朴な疑問と怒りです。
たとえば、保育所の待機児童問題や生活保護の制度運用について、「外国人の方が優先されているのでは?」という不満を持つ人は少なくありません。
ある地域では、外国人の家庭が多数保育園に入れているのに、自分の子どもは落ちたというケースもありました。事実関係はともかく、こうした“損をしている感覚”が、支持を後押しした側面があります。
この「自国民優先であるべき」という思いは、世界中の多くの国で見られる傾向でもあります。
日本でもその空気が強まり、「自分たちの暮らしが後回しにされているのでは?」という危機意識が投票行動につながったのです。
行政の無策・優遇への反発が票に表れた
選挙での結果には、国民の「今のままではいけない」という意思が色濃くにじみ出ています。
たとえば、技能実習生制度や留学生支援のあり方に対して、「外国人にはいろいろと制度があるのに、日本人には何もない」という不満がSNSでも広まりました。
実際、地元自治体による外国人向けの支援窓口や通訳サービスがある一方で、高齢者の日本人が申請方法も分からずに困っているという声は、決して少数派ではありません。
そうした実体験に基づく「行政の優遇」に対する疑問が、「選挙で意思表示するしかない」という形で表れたのです。
参政党は、こうした声を吸い上げる形で「現場で困っているのは国民のほうだ」と訴えました。それが政治に関心が薄かった層や、これまで投票に行かなかった層にまで響いたという点は、これまでの選挙とは異なる特徴です。
SNSユーザーを“扇動される側”と見なすリスク
既存メディアの中には、今回のような動きを「SNSの影響で民意が歪められている」と見る向きもあります。
しかしそれは、SNSを利用している人々を「騙されやすい」「冷静な判断ができない」と決めつけているようにも聞こえます。
実際には、SNS上では多様な意見が飛び交っており、そこから自分で情報を取捨選択している人も少なくありません。
むしろ、「テレビが報じない話題」や「現場の声」を直接拾える場として、SNSが信頼を得てきたともいえます。
「自分の意見を持つこと」や「メディアに依存しない情報収集」が当たり前になった今、SNS利用者を一括して“扇動される側”と見るのは時代錯誤です。
情報の質と量が爆発的に増えた今だからこそ、視聴者や有権者をリスペクトし、丁寧な対話を重ねていくことが、メディアにも政治にも求められているのではないでしょうか。
たしかに、「ポピュリズム=ナチスや極右政党」と結びつける議論もありますが、今の若い世代にとっては、その歴史的背景があまりピンとこないのかもしれません。それよりも、目の前の生活が苦しいという実感の方がリアルで深刻です。
たとえば、保育所や住居支援などの場面で「外国人が優先されている」と見える状況があると、それが事実かどうかに関係なく、「自分たちが後回しにされている」と感じてしまうのも無理はないと思います。
参政党自身は「外国人を排斥したい」と明言しているわけではありません。
しかし、発信されるメッセージが強い言葉であるぶん、受け取る側の解釈が過剰になりやすく、結果的に「外国人が悪い」といった単純な構図で語られてしまうこともあります。
このような感情の波をどうすれば健全な議論に変えられるのか──それは政治やメディアだけでなく、私たち一人ひとりにも問われていることかもしれません。
まとめ
参政党の躍進は、日本社会に横たわる不満や不信感が可視化された結果とも言えます。
玉川徹氏が語ったように、現代のポピュリズムは「不満の向け先を提示する技術」に長けた政治手法であり、今回の選挙ではそれが多くの有権者の心をつかみました。
また、SNSの普及によって、従来メディアとは異なる「もう一つの現実」が存在し、多くの人がそこから情報を得て判断する時代になっています。
こうした時代の変化を既存メディアが正確に捉え、真摯に向き合っていけるかどうかが、今後の民主主義にとっても大きな分かれ道となるでしょう。
「日本人ファースト」とは、本来であれば“排除”ではなく、“守られていない”という実感の裏返しです。
その声をどう受け止め、どう対話していくか。政治もメディアも、今まさに真価が問われているのではないでしょうか。
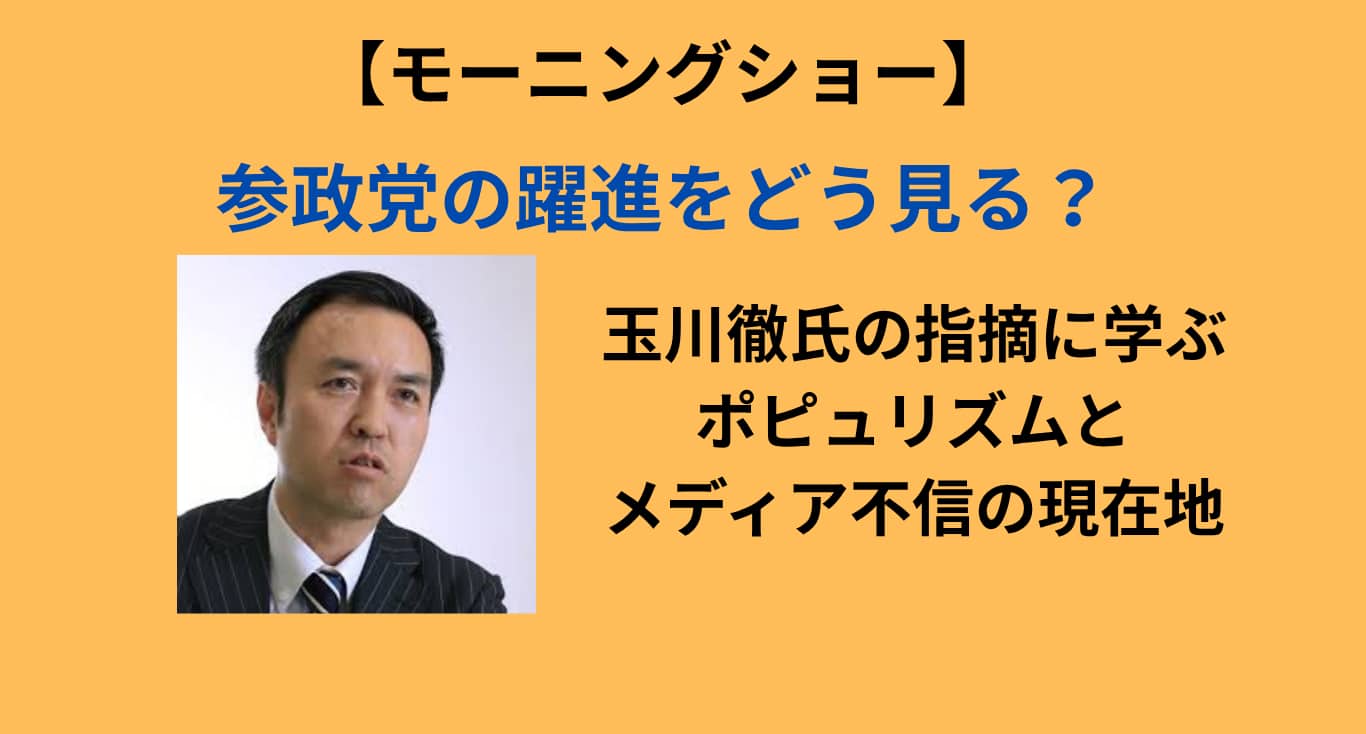
コメント