2025年7月21日に初開催された、お笑い賞レース『ダブルインパクト~漫才&コント二刀流No.1決定戦~』。
漫才とコントの両方で競う新しいスタイルは大きな注目を集めましたが、放送後にSNSを賑わせたのは意外にもカメラワーク。
「ネタの最中にMCや審査員の表情を映す“画面のよそ見”演出はアリなの?」という声が飛び交い、賛否が分かれています。
本記事では、その演出の狙いと視聴者の反応を深掘りし、今後の賞レース番組に求められる映像演出について考察します。
はじめに

『ダブルインパクト』初開催の背景
2025年7月21日、日本テレビと読売テレビが共同で制作した新たなお笑い賞レース『ダブルインパクト~漫才&コント二刀流No.1決定戦~』が初開催されました。
この番組は、漫才とコントの両方で勝負するという珍しい形式を採用し、全国から集まった芸人たちが二刀流の実力を競いました。
これまでのM-1グランプリやキングオブコントといった単独ジャンルの大会とは異なり、幅広い笑いのスタイルを一度に楽しめる新しい挑戦として注目を集めました。
また、番組は初回から大きな話題を呼び、SNSでは出演芸人やネタ内容、そして新鮮な番組構成について多くのコメントが飛び交いました。
特にファイナリストたちが披露したネタのクオリティと、それを盛り上げる演出面が視聴者の関心を集めています。
ネタ中の「画面のよそ見」が話題に
そんな中で目立ったのが、ネタの最中にカメラが頻繁にMCや審査員の表情へと切り替わる演出でした。
たとえば『セルライトスパ』の漫才では、オチの直前に審査員の塙さんが笑っているアップが映し出され、SNSでは「肝心なところで芸人を映してほしい」という声や「リアクションを見せてくれるから臨場感がある」という肯定的な意見が入り混じりました。
このような「画面のよそ見」は、お笑い賞レースでは珍しくない演出で、過去にもM-1やTHE Wといった大会で同様の議論が起きています。
今回の『ダブルインパクト』でも、番組制作側の狙いと視聴者の求める映像体験の間にズレが生じ、さまざまな意見が飛び交う結果となりました。
1.ネタ中に切り替わるカメラワークの実態
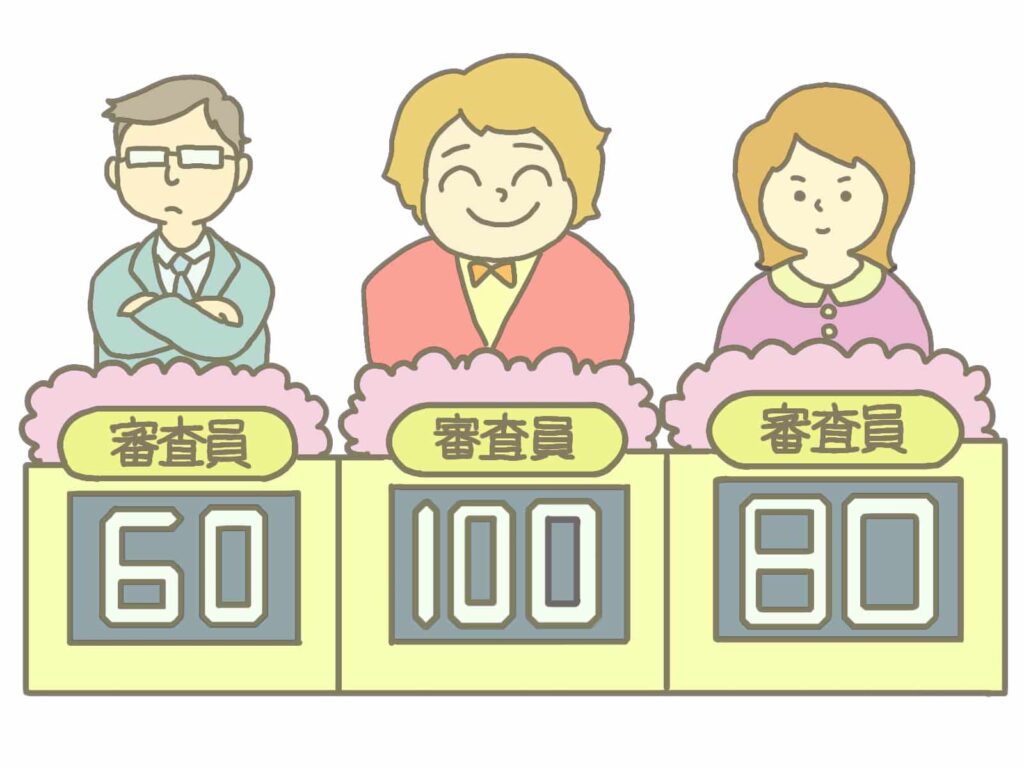
MCや審査員の表情を映す意図
『ダブルインパクト』の放送では、ネタの最中にMCや審査員の表情へとカメラが切り替わる場面が頻繁に見られました。
これは視聴者にとって、笑いが「共感されている」ことを伝えるための演出と考えられます。
芸人のネタに対して、MCが大笑いしている様子や審査員がうなずいている表情を映すことで、「今のポイントは面白いんだ」と視覚的に補足する効果があるのです。
映画やドラマでも、主要キャラクター以外の人物の反応を映すことで場面の感情を強調する手法がよく使われますが、その考え方に近いものだと言えます。
さらに、番組のスイッチング担当者はリアルタイムで状況を判断し、適切なタイミングで別のカメラに切り替えます。
特に『セルライトスパ』の漫才でオチ直前に塙さんの笑顔が映された場面は、その象徴的な例でしょう。
「このネタは評価されている」と伝えたい制作側の思いが込められている可能性があります。
SNSでの賛否両論と主な意見
しかし、こうしたカメラワークに対してSNSでは賛否が大きく分かれました。
否定的な声としては「肝心なオチの瞬間に芸人ではなく審査員を映すのはもったいない」「ネタに集中したいのに、演出で気が散る」というものが目立ちました。
一方で肯定的な意見もあり、「審査員やMCの笑顔が見えると、スタジオ全体の空気が伝わってくる」「現場にいるような臨場感があって楽しい」と評価する声も多く見られます。
特に初開催の『ダブルインパクト』は、番組自体が“お祭り感”を前面に押し出しており、その一体感を表現するための映像手法として「画面のよそ見」が選ばれたとも考えられます。
こうした演出が成功しているかどうかは視聴者の受け取り方次第で、番組の個性として今後も議論の的となりそうです。
他番組における類似の演出
お笑い賞レースにおけるカメラワークの議論は今回に限ったことではありません。
M-1グランプリやTHE Wといった他の大会でも、審査員の反応や観客の笑顔を映す演出はしばしば見られます。
過去には「漫才中はカメラを固定してほしい」という要望が視聴者から寄せられたこともあり、松本人志さんが「漫才は凝った撮り方、本当にしなくていい」とコメントしたことでも話題になりました。
つまり、この「画面のよそ見」は日本テレビ系だけの特徴ではなく、お笑い番組全体で繰り返し議論されてきた課題と言えます。
制作側としては臨場感やスタジオの空気感を届けたいという狙いがありますが、視聴者の多くが求める“ネタそのものに集中できる映像”との折り合いは、今も模索されているのです。
2.演出効果としての「画面のよそ見」

映像演出としての役割と狙い
「画面のよそ見」は、単にカメラの切り替えミスではなく、番組全体を盛り上げるための演出として意図的に行われている場合があります。
お笑いのネタは、現場で見ている観客の反応も含めて完成すると言われることがあります。
テレビでは観客の笑いや拍手、そして審査員やMCの反応が、その場の雰囲気を視聴者に伝える重要な要素です。
『ダブルインパクト』のような賞レース番組は一発勝負の緊張感が魅力であり、演出側はその「空気感」をどう家庭に届けるかを常に考えています。
MCが身を乗り出して笑っている表情や、審査員が驚いた顔を映すことで、視聴者は“今、会場が盛り上がっている”と感じることができるのです。
映画・ドラマとの共通点
こうした演出手法は映画やドラマでもよく用いられます。
たとえば感動的な場面で、主人公だけでなく周囲の人が涙を流すシーンを映すことで、感情が場面全体に広がっていることを表現します。
お笑い番組の場合も同じで、観客や審査員の笑い顔を差し込むことで「この笑いは会場全体に伝わっている」という印象を強調できるのです。
実際、『ダブルインパクト』ではネタの途中で一瞬カメラが審査員の笑顔に切り替わり、続いて会場全体の様子を映すシーンがありました。
これは観客だけでなく、自宅で見ている人にも「この笑いはみんなが共有している」という感覚を与える狙いがあると考えられます。
視聴者の没入感と臨場感への影響
しかし、この手法は必ずしもすべての視聴者に歓迎されるわけではありません。
ネタに集中したい人にとっては、突然のカメラ切り替えが流れを遮る要因になることもあります。
一方で、「会場の反応が見えるから盛り上がる」「現場にいるような臨場感がある」という意見もあります。
例えば、SNSでは「オチ直前で審査員を映すのは集中が切れる」という声がある一方で、「あの瞬間、会場が一体になったのが伝わって良かった」というポジティブな感想も見られました。
つまり、「画面のよそ見」は視聴者に臨場感を与える可能性を持ちながらも、ネタそのものを見たい人との間で好みが分かれる演出だといえます。
3.今後の賞レース番組に求められる映像演出
ネタ集中派と臨場感派のバランス
『ダブルインパクト』の放送後、SNSでは「ネタに集中したい派」と「臨場感を楽しみたい派」に分かれる声が目立ちました。
特にお笑いファンの中には「オチの直前でカメラが切り替わると集中力が途切れる」という意見が多く、一方で「MCや審査員の笑いを見られると会場の盛り上がりが伝わる」と評価する声もあります。
今後の賞レース番組では、この二つの視点をどう調和させるかが重要です。
たとえば、オチの直前は演者に固定し、リアクションはオチの後にまとめて差し込むなど、視聴者の体験を分断しない工夫が求められます。
また、オンライン視聴者向けには「ネタ映像のみ」と「リアクション入り」という2種類の映像配信を用意するなど、多様な楽しみ方に対応する方法も考えられるでしょう。
技術進化で可能になる新たな演出
最近では、AIを活用した映像解析やリアルタイム編集技術が進化しており、将来的には視聴者が自分の好みに合わせて映像を選択できるようになる可能性があります。
例えば、スマートテレビや配信アプリで「ネタ中心モード」や「臨場感モード」を選択できると、視聴体験はより自由になります。
さらに、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)の技術を応用すれば、自宅にいながら会場にいるような感覚でお笑いを楽しむことも可能です。
将来の賞レース番組は、従来のテレビ演出に加え、テクノロジーを活用した「体験型の笑い」を届ける方向に進化していくかもしれません。
賞レース番組の価値向上のために
映像演出は番組の印象を大きく左右します。
ネタだけに集中したい視聴者にとっても、臨場感を重視する視聴者にとっても満足度を高められる構成が、番組全体の価値を高めるカギです。
『ダブルインパクト』のような新しい形式の賞レースは、笑いの多様性を提示するだけでなく、視聴者参加型の新しい体験を提供できるチャンスでもあります。
視聴者の声に耳を傾けつつ、最新技術を取り入れた柔軟な演出を試みることが、これからの賞レース番組の進化につながるでしょう。
まとめ
『ダブルインパクト』は、漫才とコントの二刀流で競う新しい形式の賞レースとして注目を集めました。
しかし、ネタ中に頻繁に映し出されたMCや審査員の表情、いわゆる「画面のよそ見」は視聴者の間で賛否を呼びました。
番組の臨場感やお祭り感を高めたいという制作側の意図は理解できる一方で、ネタに集中したい視聴者にはストレスとなることもあり、このバランスは今後の課題といえます。
映像演出には番組の魅力を広げる力があり、最新技術を活用することで、ネタ中心で楽しむ人も臨場感を求める人も満足できる仕組みを提供できる可能性があります。
今回の議論は、お笑い番組の演出全体を見直すきっかけともなり、これからの賞レースの進化にとって貴重なヒントになるでしょう。
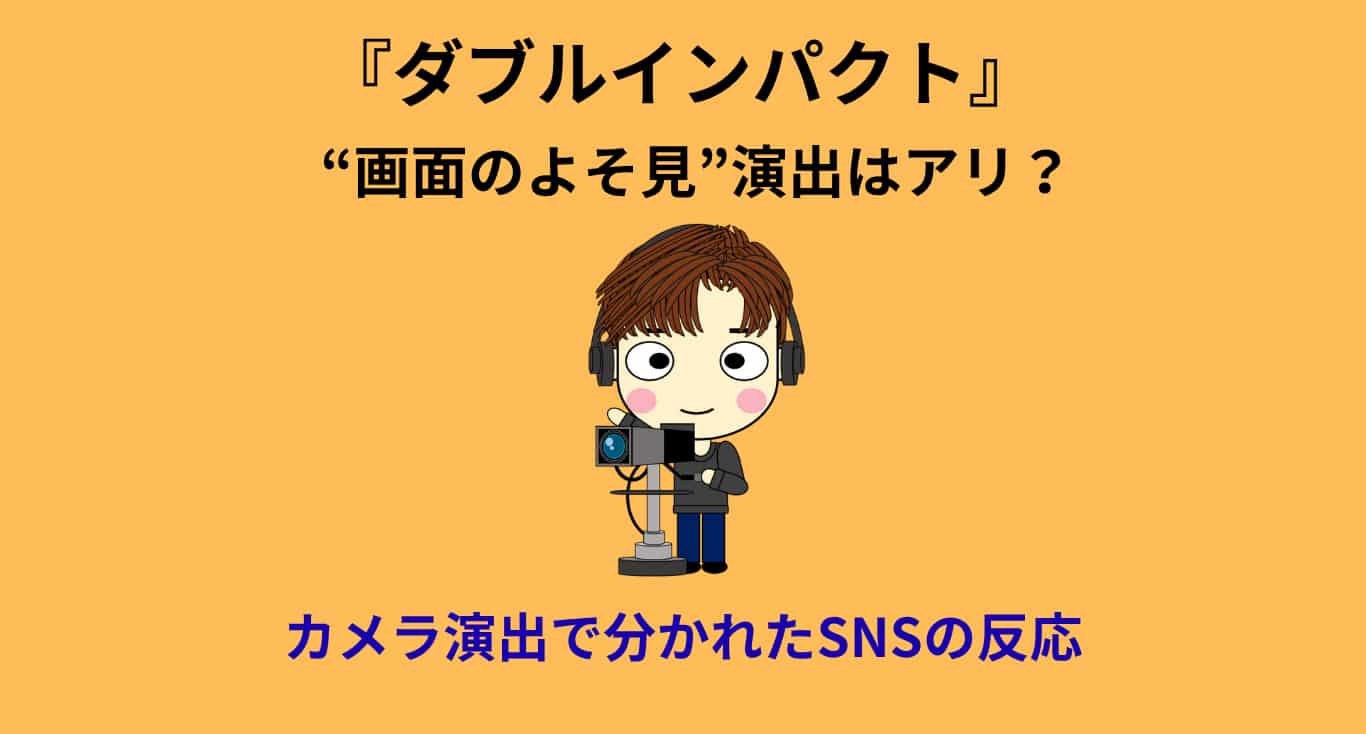
コメント