2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博の“その後”をわかりやすく解説します。
夢洲の跡地利用計画、象徴建築・大屋根リングの200メートル保存案、ミャクミャク像の移設・譲渡の動き、周遊・イベント活用の可能性までを整理しました。
はじめに

万博閉幕と次のステージへ
2025年10月13日、「大阪・関西万博」は6か月の会期を終えました。
会場だった夢洲(ゆめしま)では、空を切り取るように伸びた大屋根リングや、各国の個性が光るパビリオン、至る所で手を振るミャクミャクが来場者を迎え、家族連れが写真を撮ったり、学生が最新ロボットの実演に歓声を上げたりと、毎日が“お祭り”でした。
閉幕後は、そのにぎわいを一過性で終わらせないために、跡地をどう使い、どんな記憶を残すのかが次のテーマになります。
たとえば、イベントが開ける広場を残す、海風を感じながら散歩できる遊歩道にする、アクセスを良くして観光拠点と結ぶ――といった、暮らしに近いアイデアが具体化の段階に入っています。
跡地利用とミャクミャク像の行方に注目
注目は大きく2つ。ひとつは「どの施設を残し、どう活かすか」。
象徴だった大屋根リングを一部レガシーとして残す案や、仮設パビリオンの素材をベンチや日よけ(パーゴラ)に生まれ変わらせる再利用の動きなど、日常で使える形に“転用”する発想が出ています。
もうひとつは公式キャラ「ミャクミャク」像の行き先です。
ゲート前でおなじみだったモニュメントを、公園や施設に移して“会いに行ける存在”にする、府内各地を巡回展示して地域のイベントとコラボする、といった案が検討されています。
会場で撮った写真が、今度は近所の公園でも再現できる―そんな“続き”の体験が生まれれば、万博の思い出は街に根づき、観光のきっかけや子どもたちの学びの場にもつながります。
1.夢洲(ゆめしま)跡地の再構築構想
基本方針とゾーニング計画
閉幕後の夢洲では、「残すもの」と「生まれ変わるもの」をはっきり分ける方針が土台になります。
たとえば、会場の骨格だった歩行者導線は海沿いのプロムナードとして残し、ベンチや日よけを配置して“毎日使える散歩道”へ。イベントで使われた広場は、マルシェ・音楽ライブ・スポーツ大会などが開ける“まちなかの広場”として再整備します。
一方で、仮設パビリオンの多くは撤去し、その資材をベンチやパーゴラ(つる棚)に再利用して、記憶を日常の景色に溶け込ませます。
車両の搬入路と歩行者の散策路はゾーンを分け、子ども連れでも安心して歩ける設計に。海風が強い場所には植栽帯や風よけ壁を組み合わせ、夏はミスト、冬は日だまりができるポケット広場を点在させるなど、季節ごとの使い心地も考えます。
交通は「ゆっくり・じっくり・迷わない」が合言葉。
駅やバス停から広場・プロムナードまでを一直線のサインで結び、混雑時はシャトルバスや水上バスを連携。観光客は海沿いへ、物流はバックヤードへと動線を切り分けることで、にぎわいと効率を両立させます。

段階的整備(第1~第3期)とIR・観光・国際交流の核
整備は“段階戦略”で進みます。
第1期は解体・原状回復と同時に、プロムナードや広場など無料で使える公共空間を最優先で開放。たとえば、週末マルシェやアウトドア映画祭、朝のランニングイベントなど、小さく始めて手応えを測ります。
第2期は商業・宿泊・MICE(展示会・国際会議)に向けた施設を少しずつ足し、港辺の特性をいかした「海のアクティビティ」を育てます。
具体的には、地域の食を集めたフードホール、親子向けのサイエンス体験ラボ、夜はライトアップで散歩が楽しくなる“光の回廊”。修学旅行の校外学習コースとして、再生エネルギー体験や資材リユース工房の見学も組み込みます。
第3期は、IR(統合型リゾート)や大規模コンベンションとの相乗効果を最大化。
海外の見本市やスタートアップ見本市、eスポーツ国際大会、海を背景にした花火フェスなど、世界と大阪をつなぐ“定番イベント”を年間カレンダー化します。
来阪者はIRや都心部ホテルに滞在しつつ、日中は夢洲の水辺で過ごす――そんな周遊動線を、水上バスやBRTで結ぶイメージです。
ポイントは、観光だけに偏らず「暮らしの延長」に置くこと。朝はランニング、昼はピクニック、夜はライトアップ散歩――地元の人が毎日使い、週末は世界から人が集まる。その“二重の使われ方”が、跡地を長く元気に保つエンジンになります。
2.万博の象徴・大屋根リングの保存構想

約200メートルをレガシーとして残す案
会場のランドマークだった大屋根リングは、閉幕後に“全部なくす”のではなく、“一部を残して日常で使う”という方向が検討されています。
イメージは、北東側などの一画を約200メートル程度、歩ける・触れられるかたちで保存するプラン。床はフラットに整え、車いすやベビーカーでも回遊しやすいスロープを設けます。海側に向けてベンチを配し、朝はジョギング、昼はお弁当、夕方は夕日を眺めるスポットとして開放します。
具体例として、週末はキッチンカーが並ぶマルシェや、音楽・大道芸の小さなフェスを開催。夜はリングに沿ってライトアップを施し、水面に映る光の帯を楽しめる“夜の散歩道”に。
年間を通じて「春の花回廊」「夏のミストテラス」「冬のイルミネーション」など季節演出を切り替え、何度来ても新しい発見がある場所をめざします。
保存の意義と観光資源化の可能性

大屋根リングを残す最大の意義は、「万博という時間の記憶」を街の生活に接続できることです。
来場経験のある人にとっては“あの時ここで見上げた景色”がよみがえり、初めて訪れる人には“大阪の新名所”としてわかりやすい目印になります。
学校の校外学習では、万博のテーマだった「いのち・共生・循環」を、再生材のベンチや省エネ照明の見学を通じて学べます。
観光面でも、都心やIRエリアからの遊覧船・BRT(連節バス)と組み合わせて周遊ルートをつくれば、昼は海辺でピクニック、夜はライトアップを撮影、といった“滞在の伸び”が期待できます。
写真映えする撮影ポイントや、記念スタンプ・デジタルバッジを配置すれば、SNSを通じて自然に情報が広がり、リピーター育成にもつながります。
補強・維持管理などの課題と検討状況

一方で、保存には現実的な壁もあります。
まずは安全性。仮設要素を含む構造のため、恒久利用には耐久性の検証や補強が不可欠です。
たとえば、耐風・耐塩害対策として金物の防食処理や部材交換の計画を立て、定期点検を年に1~2回実施。通行量が多い区間は転倒・転落リスクに配慮し、手すりやノンスリップ舗装を標準化します。
コスト面では、照明のLED化や太陽光+蓄電池の併用で電力費を圧縮し、メンテナンスは「スポンサー花壇」「企業協賛のベンチ」など参加型で一部を賄う工夫が考えられます。
運営は、地元事業者・大学・NPOが関わるコンソーシアム形式にし、清掃やイベント運営、ガイドツアーを地域雇用に結びつけると、単なる“保存費”ではなく“まちの投資”として説明しやすくなります。
これらを段階導入(まずは安全対策と最低限の設備→来場状況を見て演出を追加)で進めれば、負担を抑えつつ、育てるようにレガシーを定着させられます。
3.ミャクミャク像の移設と譲渡の動き
吹田市・万博記念公園への移設構想

ゲート前で人気だったミャクミャク像は、「会場だけの思い出」で終わらせず、身近な場所で再会できるように――という考えから、万博記念公園(吹田市)への移設案が取り沙汰されています。
実現すれば、太陽の塔と並ぶ“撮影の定番”がもう一つ誕生。
具体的には、自然文化園の芝生広場など、人が集まりやすく、子どもが走り回っても安全な場所へ。足元はクッション性のある舗装にし、ベビーカーでも近づけるスロープを設けます。
季節イベントとの連動もわかりやすい効果があります。
たとえば、春は桜並木とのコラボ撮影、夏は夜間のライトアップ、秋は紅葉スタンプラリー、冬はイルミネーションと合わせた“再会ウィーク”。
公園の売店ではコラボ菓子や記念缶バッジを販売し、来園者の回遊を促します。
公募譲渡・巡回展示など多様な展開案

すべての像を一箇所に集めるのではなく、公共施設や商業施設、大学、子ども向け科学館などへ“分散配置”するアイデアも有力です。
たとえば、市役所のロビーに「いらっしゃいませミャクミャク」、駅前広場には子ども向けの小型像、海辺の遊歩道にはベンチ一体型のモニュメント――といった具合に、それぞれの場所に“似合う”設置を考えます。
巡回展示の形なら、府内各地のイベントに1~2か月単位で登場。地域の祭りや商店街フェア、学校行事と組み合わせて、来場者が自然に写真を撮りたくなる導線を作ります。
移設や譲渡にあたっては、専門の運搬・設置チームが付く「出前キット(輸送箱・固定金具・注意書き一式)」を標準化し、受け入れ先の負担を軽くします。
展示期間中は、子ども向けの安全ルール(よじ登らない・金具に触れない)をイラスト掲示で伝え、誰もが安心して楽しめる環境を整えます。
公共性・保存意義・地域ブランディングへの期待

ミャクミャク像の価値は、かわいさだけではありません。街に“語りかける目印”ができることで、地域の一体感や誇りが育ちます。
たとえば、学校の総合学習で「私たちのまちのミャクミャクをデザインしよう」と題したポスターづくり、図書館で「ミャクミャク読書月間」を開催、商店街ではレシート応募でオリジナルステッカーが当たるといった、参加型の企画が広がります。
観光の面では、像を巡る“デジタル御朱印”のスタンプラリーが効果的。スマホでQRを読み取ると限定バッジがたまり、3か所集めると記念壁紙、5か所で限定ポストカードを進呈――といった仕立てにすれば、家族連れの週末のお出かけが自然と増えます。
医療施設や福祉施設に小型像を寄贈し、院内のキッズスペースに設置する取り組みも、やさしさの循環を生みます。
大切なのは、“いつでも誰でも会える場所にいること”。
会場での思い出を、毎日の散歩や買い物の道すがらにふとよみがえらせる――そんな距離感でミャクミャクが街に根づけば、万博の記憶はイベントの外へと広がり、地域のブランドそのものになっていきます。
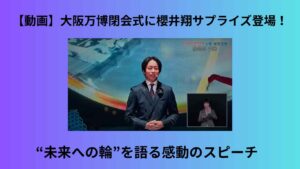

まとめ
万博の幕が下りても、夢洲の物語は続きます。
海沿いの散歩道や“まちなかの広場”として日常に開く計画、季節ごとに表情を変える大屋根リングのライトアップ、再生材のベンチや日よけに生まれ変わる資材――どれも「イベントの記憶を暮らしへつなぐ」ための具体的な一歩です。
週末マルシェや野外映画、学校の校外学習、夜のランニングコース……誰もが“用がなくても行きたくなる場所”に近づけるほど、跡地は息の長いにぎわいを育てます。
ミャクミャク像も、会場のシンボルから“街の案内役”へ。
万博記念公園への移設や巡回展示が実現すれば、太陽の塔や駅前広場、海辺の遊歩道など、身近な場所で再会できます。
QRスタンプや限定バッジのラリー、商店街や図書館とのコラボは、家族のお出かけや地域イベントのきっかけに。医療・福祉施設への小型像の設置は、やさしさを循環させる合図になります。
大屋根リングは約200メートルの保存を軸に、“歩けるレガシー”へ。
安全対策と段階導入で無理なく育て、スポンサー花壇や企業協賛ベンチなど参加型の仕組みで維持費を賄えば、「守るコスト」は「関わる楽しさ」に変わります。
アクセスはBRTや水上バスで都心・IRと結び、昼はピクニック、夜は光の回廊――そんな周遊の流れをデザインすれば、観光と日常の二重の使われ方が定着します。
合言葉は「特別を、ふだんへ」。思い出の景色を毎日の散歩道に、万博のワクワクを地域の行事に。小さな手入れと小さなイベントを積み重ねるほど、EXPOの“その後”は強く、しなやかに根づいていきます。

コメント