南海トラフ巨大地震に備えた国の最新調査で、「巨大地震警戒」が発表された場合に事前避難の対象となる住民が全国で約52万人にのぼることが分かりました。
特に高齢者や避難に時間がかかる方が半数近くを占め、静岡・高知・宮崎などの沿岸部では数万人規模が対象とされています。
この記事では、南海トラフ地震臨時情報「巨大地震警戒」とは何か、対象となる住民の内訳、自治体の課題、そして私たちができる備えについて分かりやすく解説します。
日頃からの準備や意識の持ち方が、命を守る大切な一歩になります。
はじめに
南海トラフ巨大地震と「巨大地震警戒」情報とは
南海トラフ巨大地震は、日本列島に大きな被害をもたらすとされる地震の一つです。
特に太平洋沿岸の広い範囲で強い揺れや津波が発生する可能性があり、過去からも繰り返し警鐘が鳴らされてきました。
こうしたリスクに対応するために設けられたのが「南海トラフ地震臨時情報」であり、その中でも「巨大地震警戒」が発表されると、次の地震で大きな津波が発生する危険が高まっていることを意味します。
この情報が出されると、平時に比べてさらに注意を要し、津波避難が間に合わないおそれのある地域では1週間程度の事前避難が求められる仕組みになっています。
単なる「注意喚起」ではなく、命を守るための具体的な行動指針としての意味合いが強いのが特徴です。
調査で明らかになった52万人の事前避難対象者
2025年8月、日本テレビの報道で明らかになったのは、この「巨大地震警戒」が発表された場合に事前避難の対象となる人が、全国でおよそ52万人に達するという事実です。
そのうち半数近くは、高齢者や障がいを持つ方など、避難に時間がかかる住民です。
たとえば、静岡県だけで約7万人、高知県では9万人を超える住民が対象とされています。沿岸部の地域だけでなく、東京都や千葉県といった首都圏の一部住民も含まれていることは、多くの人にとって意外かもしれません。
こうした数字は、「自分の地域は大丈夫」と思っている人にも改めて現実を突きつけるものです。
さらに、国の調査に答えた707市町村のうち、200を超える自治体が「事前避難の対象指定を検討していない」と回答しており、その理由の多くが人手不足でした。つまり、数字以上に課題は深刻で、住民一人ひとりの意識と準備が欠かせない状況にあるのです。
1.南海トラフ巨大地震のリスク

なぜ「巨大地震警戒」が発表されるのか
「巨大地震警戒」は、普段から警戒されている南海トラフ地震のリスクが、特に高まっていると判断されたときに出されます。
たとえば、地震活動が活発化したり、専門家が異常なデータを検知した場合などです。
単に「地震が来るかもしれない」という漠然とした注意ではなく、実際に津波被害の危険性が一段と増していることを国民に伝えるサインなのです。
この情報が出れば、対象地域に住む人たちは「もしかしたら数日以内に大地震が起きるかもしれない」という前提で生活を考え直す必要があります。
津波からの避難が間に合わない地域の特徴
津波被害のリスクが特に高いのは、海岸線に近い低地や、避難先までの距離が長い地域です。
例えば、港町や川の河口に位置する住宅地では、地震発生から津波到達までの時間がわずか数分というケースもあります。
そのため、地震直後に避難行動をとっても間に合わないおそれがあるのです。特に高齢者が多く暮らす集落や、道幅が狭く車のすれ違いが難しい地域では、混雑や渋滞によって避難時間が大幅にかかることも予想されます。
こうした現実的なリスクが、「事前に避難しておく必要性」を強調する理由になっています。
事前避難の必要性と想定シナリオ
もし南海トラフ巨大地震が発生すれば、東海から九州にかけて広範囲で津波が押し寄せ、過去の東日本大震災を上回る規模の被害が想定されています。
避難が間に合わない可能性が高い地域では、あらかじめ安全な場所へ移動しておくことで命を守る確率が大きく高まります。
たとえば、高知県の一部地域では、住民が津波から逃れるのに必要な時間が「到達予測時間よりも長い」と報告されており、事前避難なしでは救えない命が多数出ると想定されています。
このような背景から、国や自治体は「巨大地震警戒」が出た時点での1週間の事前避難を呼びかけているのです。
2.事前避難対象者の内訳
高齢者など避難に時間がかかる住民の割合
事前避難の対象者52万人のうち、約27万5000人は高齢者や障がいを持つ方など、避難に時間がかかる住民です。実際に地震が起きてからでは、すぐに避難ができず命の危険にさらされる可能性が高いため、事前避難の重要性が強調されています。
例えば、介護施設に入所している人や、歩行に時間がかかる方が多い地域では、移動手段の確保や避難場所までの移送が課題となっています。
このため、自治体では福祉施設と連携した避難計画づくりが欠かせない状況です。
都道府県別の対象人数(静岡・高知・宮崎など)
調査によると、都道府県ごとに避難対象者の規模は大きく異なります。
静岡県では約7万200人、高知県では約9万2100人、宮崎県では約7万9900人と、太平洋沿岸部を中心に非常に多くの住民が対象となっています。
特に高知県は全国最多であり、県の人口に対する割合を考えても深刻な数字です。また、愛知県で約6万人、三重県で約6万6600人と、東海地方も同様に高いリスクを抱えています。
こうした地域は過去の歴史的な津波被害の記録も多く、再び甚大な被害が予想されているため、避難計画の実効性が問われています。
東京や関東圏の対象者規模
一方で、首都圏でも事前避難対象者が存在します。東京都では約2500人、千葉県では約1万7400人と、太平洋沿岸の地域に比べると少ない数ですが、決して無視できません。
特に東京湾沿岸や房総半島の一部地域では、津波の到達時間が短く、避難が難しいケースが想定されています。
普段から「自分の地域は安全」と思われがちな都市部でも、実際にはリスクが潜んでいることが数字からも明らかです。
こうした結果は、全国的に防災意識を共有し、都市部でも備えを強化する必要があることを示しています。
3.自治体の課題と現場の声
アンケートで浮かび上がった人手不足の実態
国が行ったアンケートでは、事前避難の体制づくりにおいて「人手不足」が大きな壁となっていることが明らかになりました。
特に高齢化が進む地域では、住民を支える側の担い手も減少しており、避難誘導や移送のための職員・ボランティアが不足しています。
ある自治体の担当者は「避難計画を作っても、それを実行できる人がいない」と危機感を口にしています。
災害時に最も弱い立場にある人を守るためには、平時からの人的支援体制の強化が欠かせません。
事前避難指定を検討中・未検討の市町村
今回の調査対象となった707市町村のうち、204の自治体が「事前避難対象地域の指定を検討していない」と回答しています。
その理由の半数は「人員や予算が足りない」ことでした。
例えば、四国の一部自治体では「避難先の確保はできても、住民を安全に運ぶ車両やスタッフが足りない」との声が上がっています。
また、都市部では「地域の特性上、どの範囲を指定すべきか判断が難しい」という現場の葛藤もあり、地域ごとに異なる課題が浮き彫りになっています。
今後の防災対策と国・自治体への期待
こうした現場の声を受け、今後は国や自治体の連携による支援が一層求められます。
具体的には、ボランティアや民間事業者との協力体制づくり、避難所のバリアフリー化、災害時にすぐ使える移送用バスの整備などが必要です。
さらに、地域住民自身が防災訓練に積極的に参加し、隣近所で助け合う体制を築くことも重要です。
実際、和歌山県の一部地域では、住民が自主的に避難支援チームを組織し、高齢者の避難ルートを事前に確認する取り組みが始まっています。このような地域発の動きが広がれば、大規模災害への備えは確実に強化されるでしょう。
まとめ
南海トラフ巨大地震は、日本の広い範囲に甚大な被害を及ぼすと想定されている大規模災害です。
今回の調査で明らかになった「52万人もの事前避難対象者」という数字は、決して他人事ではなく、私たち一人ひとりに備えの必要性を突きつけています。特に高齢者や障がいを持つ方の避難には時間と人手がかかり、地域社会全体でのサポートが欠かせません。
また、静岡や高知、宮崎といった沿岸部だけでなく、東京都や千葉県など都市部にも対象者がいることから、全国どこに住んでいても「自分の地域は安全」とは言い切れない現実があります。自治体の多くが人手不足や予算不足で課題を抱える中、地域住民や民間の力を合わせた取り組みが今後ますます重要となるでしょう。
「巨大地震警戒」という情報は、恐怖を煽るためのものではなく、命を守るための行動指針です。自宅の避難経路を確認する、防災用品を準備する、近所と声を掛け合う――その一つひとつの行動が、大規模災害から生き延びる力につながります。今回の調査結果をきっかけに、私たち自身も日常から防災意識を高め、備えを見直していくことが求められています。
私も一人の市民として、日頃から「備え」を忘れずに、家族や地域と一緒に安全を守っていきたいと思います。
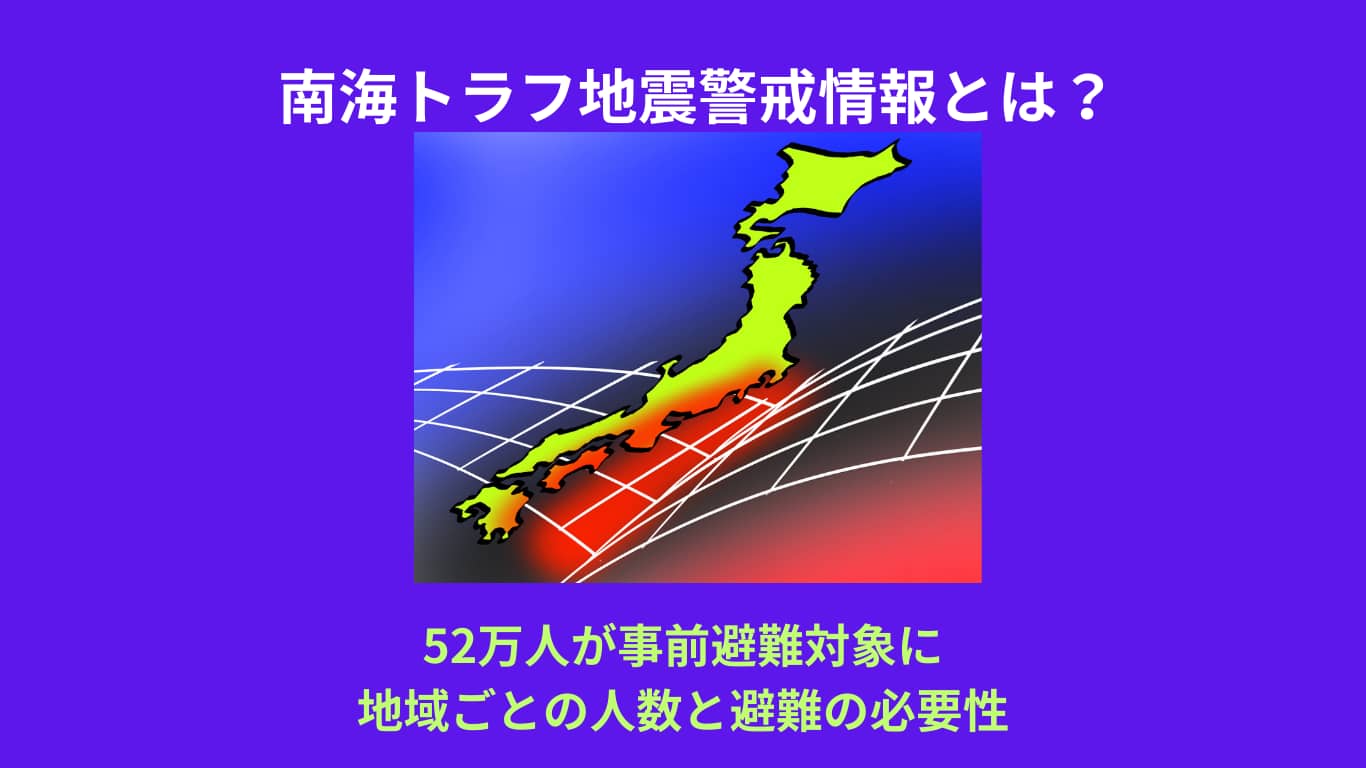
コメント