退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロス(東京都品川区)が、弁護士法違反(非弁行為)容疑で警視庁による家宅捜索を受けました。
報道によれば、退職代行の案件を違法に弁護士へあっせんし、紹介料を得ていた疑いが持たれています。利用者数4万人規模とされるサービスで、業界全体への影響も避けられません。
はじめに
速報の位置づけと注意点(容疑段階/無罪推定)
本件は、2025年10月22日に実施された「家宅捜索」という捜査の初期段階の出来事です。逮捕・起訴・有罪判決とは異なり、この時点では事実関係が完全に確定していません。
報道で扱われる言葉(「疑い」「関係先」など)は、あくまで捜査当局が疑っている論点の説明にすぎず、結論ではない点にご注意ください。
たとえば、退職代行サービスが「本人の退職意思を会社に伝えるだけ(通知)」であれば合法と理解される場合がありますが、「未払い残業代を請求する」「退職日を交渉して折り合いをつける」などに踏み込むと、法律の専門業務に当たる可能性が出てきます。
今回のニュースは、こうした線引きが守られていたか、弁護士への紹介のやり方に問題がなかったか――を捜査で確かめている段階だ、と受け止めてください。
読者が得られること(捜査の要点・法的整理・実務対策)
本記事では、①「いつ・どこが捜索されたか」「何が疑われているか」という要点を、具体的な出来事の流れと合わせて整理します。
次に、②通知と交渉の違いを、身近な例でわかりやすく解説します(例:会社へ「退職します」と伝えるのは通知/「未払い分を払ってください」と条件を詰めるのは交渉)。
最後に、③これから利用を検討する人や、すでに申し込んでいる人のために、契約書で確認すべきポイントをチェックリスト化します。
たとえば申込み前に、「やってくれることが通知までなのか」「交渉が必要な場合は弁護士が直接対応するのか」「料金の内訳に“紹介料”のような項目がないか」を、紙の契約書やサイト表記で確認できます。
進行中の方は、「自分の依頼内容が通知にとどまっているか」「返金規定や窓口が明記されているか」を見直すだけでも、トラブルの早期回避につながります。
捜査の概要
- 実施日:2025年10月22日(水)
- 対象:アルバトロス本社(東京都品川区)および都内の法律事務所など複数拠点。[1]
- 容疑:退職代行の案件を弁護士に違法あっせんし、紹介料を受領した疑い(弁護士法違反)[1]
- 補足:残業代請求など法律交渉に該当し得る実態も捜査過程で把握と報道。[1]
- 現段階:家宅捜索(任意/捜査段階)であり、逮捕・起訴等は未確認(無罪推定)。
「モームリ」とは
- 運営:株式会社アルバトロス(代表:谷本慎二)[2]
- 開始:2022年[2]
- 方式:本人の代わって退職意思を会社へ通知する「代行通知型」サービス[2]
- 規模:累計利用者 約4万人超と報じられる。[2]
- 派生事業:2024年12月〜「退職理由データ」を活用した離職防止アドバイスを提供。[1]
問題とされた疑点(報道ベース)
- 弁護士への違法あっせん:退職代行案件を弁護士に周旋し、紹介料(キックバック)を受領した疑い。[1]
- 非弁行為の可能性:「退職通知」以外に、残業代請求や有給取得等の交渉まで踏み込んだ実態が報道されている。[1]
- 資金フローの透明性:手数料・成果報酬・紹介料の表示/説明の適切性。複数報道で指摘。[3]
(筆者より)こんにちは。一般市民としてニュースを日々追いかけている筆者です。専門家ではありませんが、家族や友人にも伝わる言葉で「結局どういうこと?」をやさしく整理するのが好きです。今回も、私自身が気になった点をかみくだいてまとめました。いっしょに確認していきましょう!
1.家宅捜索の概要と経緯
いつ・どこを捜索したか(本社/関係法律事務所)
警視庁が家宅捜索に入ったのは、2025年10月22日(水)の朝でした。捜索対象となったのは、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの本社(東京都品川区)と、都内にある複数の関係法律事務所です。
報道によれば、捜査員が段ボール箱を運び出す様子も目撃され、内部資料や契約書、電子データなどの押収が進められたとみられます。[1]
今回の家宅捜索は「任意捜査」にあたるため、会社や関係先が捜査に協力している段階とされています。現時点では逮捕者は出ておらず、関係者の聴取や押収資料の解析が中心です。警察としては、弁護士へのあっせんや報酬のやり取りに不透明な部分がないかを丁寧に調べているとみられます。
何が疑われているか(弁護士法違反:違法あっせん・紹介料)
警視庁が問題視しているのは、「モームリ」が扱った退職代行案件の一部で、弁護士への“違法なあっせん”が行われた疑いです。つまり、利用者からの相談を受けた後、その案件を弁護士に紹介し、その見返りとして「紹介料」や「キックバック」を受け取っていたのではないかという点が焦点になっています。[1]
弁護士法では、弁護士以外の人が報酬目的で法律事務をあっせんすること(非弁行為)を禁止しています。たとえば、弁護士を探している人に単に「紹介する」だけなら無料で可能ですが、「1件あたりいくら」という形で報酬を受け取れば違法になるおそれがあります。
今回のケースでは、退職代行というサービスの一環として、どこまでが“紹介”でどこからが“あっせん”にあたるのか、その線引きが問われています。
さらに、関係者によると、一部の案件では「退職の通知」だけでなく、「残業代の請求」や「有給の取得交渉」など、法律交渉に近い対応が行われていた可能性も浮上しています。
これらが事実であれば、弁護士の独占業務を侵していたことになり、非弁行為の疑いがより強まることになります。
これまでの報道と時系列(週刊誌報道→一斉捜索)
「モームリ」に関する疑念が初めて報じられたのは、2025年4月に掲載された週刊誌の記事でした。記事では、「弁護士への紹介料を受け取っている」とする内部関係者の証言が紹介され、SNSでも「非弁行為では?」と話題になりました。
その後、法曹関係者や退職代行業界内でも関心が高まり、弁護士会の一部が注意喚起を行う動きも見られました。[3]
半年後の2025年10月、警視庁が実際に本社や関係事務所への一斉捜索を実施。このスピード感からも、警察が早い段階で内部資料や資金の流れを把握していた可能性がうかがえます。
今後は押収された資料をもとに、報酬の流れや契約の実態を分析し、立件の可否を慎重に判断していくとみられます。
なお、現時点で「モームリ」公式サイトや代表者からの正式コメントは出ておらず、関係各所の見解が待たれます。報道ベースでは「容疑段階」にすぎず、断定的な判断は避けるべき状況です。
弁護士法違反(非弁行為)とは
弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を扱ったり、これを周旋(あっせん)したりすることは、弁護士法第72条以下で禁止されています。[4][5]
「通知代行(意思表示を会社に伝えるのみ)」の範囲は合法とされる可能性がありますが、請求・交渉・示談・和解などに踏み込むと、非弁行為に該当する可能性が高いとされています。[3][4][5]
| 項目 | 通知代行(許容される範囲) | 交渉・請求(非弁行為に該当し得る) |
|---|---|---|
| 退職意思の伝達 | ◯ 本人の意思を会社へ伝えるのみ。 | — |
| 有給取得や日程調整 | △ 事務的連絡にとどまる範囲。 | × 権利主張・合意形成の交渉は非弁リスク。 |
| 未払い賃金・残業代 | — | × 請求や示談交渉は弁護士しか行えない可能性が高い。[4][5] |
| 弁護士への周旋 | — | × 報酬目的のあっせん・紹介料は違法の可能性。[4] |
利用者のチェックリスト(申込前に確認)
- 契約書の範囲:業務は「通知」までか?「交渉」「請求」「和解」に踏み込んでいないか?
- 法的対応の担当:交渉が必要な場合は弁護士本人が直接対応しているか?監修だけでは不十分。[4][5]
- 手数料・成果報酬:料金や紹介料の有無・資金フローに不透明さがないか?
- トラブル時の窓口:弁護士会・労働相談窓口(労基署/自治体)へ案内できるか?
- 口コミの見方:スピード評価だけでなく、実際の合意形成・返金対応の事例も確認。[2][3]
報道タイムライン(要点)
| 日時 | 出来事 | 要点 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 離職防止アドバイス事業を開始 | 退職理由データ活用。BtoB領域にも展開。[2] |
| 2025年4月 | 週刊誌が紹介料(キックバック)疑惑を報道 | 弁護士へのあっせんと報酬の有無が論点に。[3] |
| 2025年10月22日 | 警視庁が家宅捜索 | 本社・法律事務所など複数拠点を捜索。非弁行為の有無も捜査。[1] |
2.退職代行「モームリ」の実像
サービスの方式(通知代行)と規模(利用者数・開始年)
「モームリ」は、利用者に代わって会社へ“退職します”という意思を伝えることに特化したサービスとして、2022年に始まりました。
基本の流れはシンプルで、(1)利用者がフォームやチャットで状況を伝える →(2)担当者が会社へ電話やメールで退職の意思を通知 →(3)会社からの連絡は利用者ではなくサービス側が受け、必要事項だけを橋渡し、という形です。
たとえば、上司に直接会うのがつらいケースでは、会社への連絡役をすべて任せられます。会社から貸与物(社員証・PCなど)の返却方法を聞かれたら、その手順を“事務連絡”として利用者へ共有する、といった運びです。
逆に、「未払い残業代の支払いを求める」「退職日を会社と交渉で動かす」といったやり取りは、原則として“交渉”にあたる可能性があるため、通知代行の範囲からは外れます。
規模感としては、累計利用者は4万人規模と報じられており、短期間で広く知られるサービスに成長しました。背景には、「対面や電話が苦手」「会社と距離を置きたい」というニーズの強さがあります。
なお、2024年末からは、退職理由のデータをもとに企業へ“離職防止のアドバイス”を行う取り組みも発表されています。これは、これまで消費者向けだった活動を、企業側の課題解決にも広げた形です。
争点となる運用(通知と交渉の線引き・資金フローの透明性)
今回のニュースで焦点になっているのは、“どこまでが通知で、どこからが交渉か”という運用上の線引きです。たとえば、会社から「退職日は1か月後にしてほしい」と返ってきたとします。
サービス側が「本人はこの日付で退職します」と伝えるのは“意思の伝達”ですが、「それなら退職金を上乗せしてください」など条件の駆け引きに踏み込むと“交渉”に近づきます。
読者の方が見極めるコツは、「条件を変えるためのやり取りをしているかどうか」。ここが通知と交渉の分かれ目です。
もうひとつの論点は、資金の流れの透明性です。利用者から見える料金(基本料やオプション)は明確か、そして第三者(たとえば弁護士や別の団体)へ案件をつなぐ場合に“紹介料”のような名目が発生していないか――この2点がチェックポイントになります。
具体的には、申込み前に「業務範囲」「料金内訳」「返金条件」「第三者への委託や紹介の有無」を、Webの表示や申込書・利用規約で確認しましょう。
もし、サイトにない項目が見積書や請求書に突然あらわれるようなら、いったん質問して書面で説明をもらうのがおすすめです。
現時点では、家宅捜索という“調べている段階”であり、事実関係はこれから整理されていきます。利用者としては、通知代行にとどめたいのか、交渉が必要なのかをまず自分のケースで切り分け、そのうえで契約書の文言や料金の見え方に不安がないかを落ち着いてチェックしていくのが実務的です。
3.弁護士法違反(非弁行為)の基礎知識
非弁行為とは何か(周旋・報酬目的の法律事務)
ここでいう「非弁行為」とは、弁護士ではない人や企業が、報酬を得ることを目的に“法律の仕事”をすること、またはその仕事を弁護士にあっせん(紹介して対価を得ること)を指します。ポイントは次の2つです。
- お金がからむか:無料の世間話レベルなら問題になりにくいですが、「1件○円」のように報酬が発生すると違法の可能性が高まります。
- 法律の仕事かどうか:単なる伝言や連絡ではなく、相手と条件をやり取りして結果を動かす行為(示談、請求、支払いスケジュールの調整など)は“法律の仕事”にあたることがあります。
たとえば、退職をめぐって会社に「未払い分を払ってください」「この日に辞めるので了承してください」と条件のやり取りをするのは、交渉=法律の専門業務に近づきます。
また、「弁護士を紹介してあげます。その代わり紹介料をいただきます」という有償のあっせんも非弁行為とみなされるおそれがあります。
合法となり得る範囲と違法リスクが高い行為(通知/交渉の線引きと具体例)
実務で迷いやすいのは、「ここまでならOK」「ここからはNG」という線引きです。次の表のように考えると整理しやすくなります。
- 通知(OKとなり得る)=本人の意思を“そのまま”伝える
- 交渉(NGになり得る)=条件を変えるためにやり取りする
OKとなり得る例(通知にとどまる)
- 「本人は◯月◯日に退職します」と日付を伝えるだけ
- 社用PCや社員証の返却方法を受け取り、本人へ連絡する
- 会社から届いた連絡内容をそのまま橋渡しする
違法リスクが高い例(交渉・請求に踏み込む)
- 「未払い残業代を支払ってください」「いくらなら和解できますか」と条件を詰める
- 「退職日を短縮してほしい代わりに、退職金を上乗せしてください」と交換条件を持ちかける
- 弁護士へ案件を有償であっせんし、紹介料を受け取る
境目で迷ったら、次の3つを自問してください。
1) 言い換えず、事実だけを伝えているか?(編集や主張を足していないか)
2) 相手の条件を動かそうとしていないか?(合意形成や妥結を狙っていないか)
3) 金銭が第三者に流れていないか?(紹介料・キックバックなど)
この3つで「NO」が混じるなら、弁護士の出番です。通知で済むケースでも、不安があれば契約書の“業務範囲”と“料金の内訳”を確認し、交渉が必要になりそうな場合は弁護士が直接対応する体制になっているかを事前にチェックしましょう。
今後の見通し
- 押収資料の解析:紹介料スキームの実在性・規模、非弁行為の立証可否。
- 会社・関係士業の見解:公式コメント、再発防止策、利用者への案内の発表。
- 利用者影響:進行中案件の継続可否、返金・代替支援の有無。
- 業界的波及:ガイドライン見直し、広告表示や「監修」表現の厳格化。
まとめ
家宅捜索は容疑段階であり、いまの時点で違法性が確定したわけではありません。ただし、通知と交渉の線引き、並びに紹介料スキームの有無は、退職代行サービスの適法性を左右する中核論点です。申込前に契約範囲と担当者(弁護士の直接関与)を必ず確認しましょう。
FAQ(よくある質問)
Q. 退職代行の利用は違法ですか?
いいえ。退職意思の通知にとどまる限り、一般には違法とはされません。問題となるのは、未払い賃金の請求・示談交渉・和解など法律事務に踏み込む場合であり、そこは弁護士の業務領域です。[4][5]
Q. 「弁護士監修」なら交渉もOK?
「監修」はマニュアル整備や助言であることが多く、弁護士本人が実務を担当することとは異なります。交渉が必要なら受任(委任契約)と弁護士本人の関与が明記されているか確認しましょう。[3][4][5]
Q. 既に依頼中。どうすれば?
契約書・請求書の記載(業務範囲/料金/返金規定)を再確認し、不安があれば弁護士会の法律相談や労働相談窓口に相談を。進行中案件の中止・返金の可否も書面で確認を。[2][3]
注意:本記事は報道ベースの速報整理です。容疑段階のため、関係者の名誉に配慮しつつ、確定情報が出次第更新します。
[1] TBS NEWS DIG 「【速報】退職代行「モームリ」を運営する「アルバトロス」に警視庁が家宅捜索 弁護士法違反の疑い 法律事務所など関係先も一斉捜索」2025年10月22日配信。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2241924
[2] Biz-Journal「弁護士『モームリは非弁行為で違法では』→社長が反論し話題…退職代行への誤解」2025-03-06。
https://biz-journal.jp/company/post_386843.html
[3] 東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」解説。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/column/post_3.html
[4] 契約ウォッチ「非弁行為とは?弁護士法で禁止されている理由・報酬の有無・具体 …」2025-04。
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/hibenkoi/
[5] 千葉の弁護士【よつば総合法律事務所】コラム「退職代行は非弁行為(弁護士法違反)?適法サービスの選び方と判例」2024-07。
https://yotsubalegal.com/newsletter/vol182-2024-07/
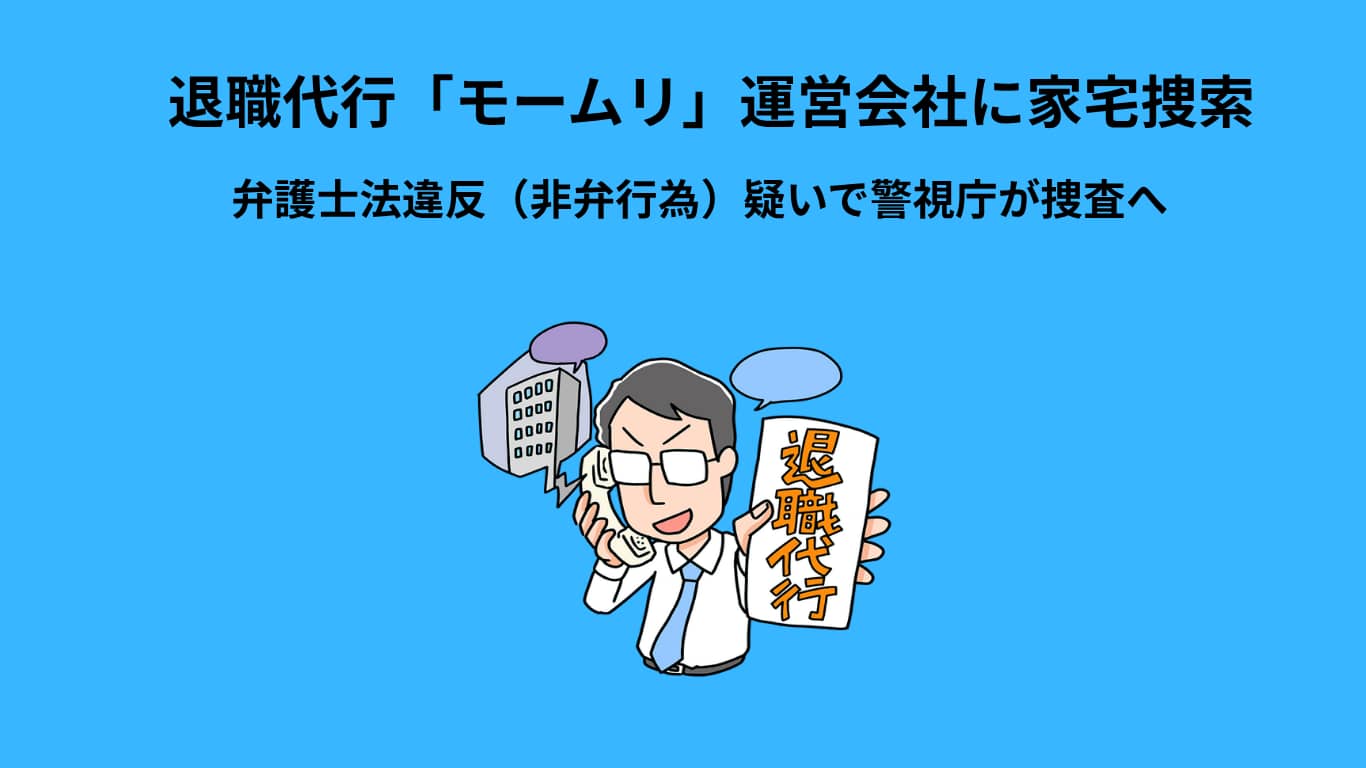
コメント