世界陸上2025東京大会(9月15日)の男子3000m障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司選手(SUBARU)が大歓声の中で力走しました。
レース終盤、最終障害でケニアの有力選手エドマンド・セレムと接触するハプニングがあり、会場からは悲鳴が上がる場面も…。それでも最後まで粘り抜き、見事8位入賞を果たしました。
この記事では、接触の瞬間の詳細、審判の裁定、観客やメディアの反応、そして今後の課題と期待についてわかりやすく解説します。
はじめに
世界陸上2025東京大会の概要
世界陸上2025は東京・国立競技場を主会場に開催され、9月15日(大会3日目)は夜間セッションで多くの決勝種目が組まれました。
スタジアム周辺は国旗や応援グッズを手にした観客でにぎわい、都心でも大型ビジョンでのパブリックビューイングが行われるなど“お祭りムード”。気温や湿度への配慮から競技は涼しい時間帯に集中し、テレビ中継やネット配信でも視聴しやすいタイムテーブルでした。
日本勢は短距離から中長距離、跳躍・投てきまで幅広く出場し、特に地元開催ならではの大歓声が選手の背中を押す一日となりました。
男子3000m障害決勝に注目が集まった理由
男子3000m障害は、日本記録保持者の三浦龍司選手(SUBARU)が出場する注目の決勝。
水濠とハードル越えが続くタフな種目で、駆け引きやリズムの良し悪しが順位を大きく左右します。
レース終盤、最終障害付近でケニアの有力選手と接触があり、観客席から思わず悲鳴が上がる場面も。三浦選手はバランスを崩しながらも最後まで粘り、結果は8位入賞。
もし接触がなければ──と感じたファンが多かった一方で、公式には失格や順位変更はなく、激戦の末の堂々たる入賞として受け止められました。
地元開催、緊迫のラスト1周、そしてドラマのあるフィニッシュ。このレースには“現地の空気感まで伝えたくなる”だけの物語が詰まっていました。
1.三浦龍司選手の挑戦
日本記録保持者としての期待
地元・東京の大歓声を背に立つ三浦龍司選手(SUBARU)は、日本記録保持者として「表彰台争いに絡むか」が最大の見どころでした。
3000m障害は、平地のスピードだけでなく、ハードルと水濠をいかに“減速せずに越えるか”が勝負の分かれ目。
三浦選手は、助走の歩数を一定に保ち、踏み切り足を崩さないフォームで知られ、特に水濠では着水後にすぐ前傾をつくって再加速する技術が武器です。
地元開催でコンディション面のアドバンテージも期待され、「序盤は無理をせず、終盤に上げる」得意の展開に持ち込めるかが注目されました。
予選から決勝までの流れ
予選では、中盤以降に前へ位置を上げる“いつものリズム”で安定感を見せ、危なげなく決勝進出。
決勝では、序盤は隊列の中で力を温存しつつ、水濠後の立ち上がりと障害越えのリカバリーで少しずつポジションを回復していきました。
ラスト2周に入る頃には先頭集団の背中を射程に入れ、最終盤のスパートに備える形。地元の拍手と手拍子が会場全体に広がり、フィニッシュへ向けて緊張感が高まっていきました。
2.接触の瞬間
最終障害でのケニア選手セレムとの接触と、そこまでの流れ
ラスト1周、三浦選手は先頭争いの背中を追いながらホームストレートへ。スピードが最も上がる局面で、最終障害(最後のハードルと水濠の直後のハードル)に差しかかりました。
ここで外側から並びかけたのがケニアのエドマンド・セレム選手。両者がほぼ同じタイミングで踏み切りに入ったため、着地の足運びが重なり、肩—腕まわりが触れる形で接近。
三浦選手は一瞬バランスを取り直す動きとなり、着地直後の“再加速の一歩目”がわずかに遅れました。
3000m障害では、この「着地から1〜2歩の立ち上がり」が伸びの差に直結します。スピードゾーンでの小さなロスが、直後のフィニッシュスプリント全体に影響しました。
観客の悲鳴、失速、そしてメダルの可能性が揺れた瞬間
接触の直後、スタンドからは「わっ!」と声が上がり、会場の空気が一気に張りつめました。三浦選手は倒れずに踏みとどまったものの、体勢を戻す間に前を行く選手との距離が数歩分ひらきます。
残りは直線のみ。トップ争いはさらにスピードを上げ、三浦選手も最後まで腕を振り切って粘走しましたが、勢いの差を詰め切るには距離が足りない——結果は8位入賞。
仮に接触がなく、あの最終障害を“ノーミスで抜けられていれば”、表彰台ラインの攻防に食い込めた可能性は十分にありました。
わずかな接触、ほんの一拍の乱れが勝負を左右する——その厳しさとドラマが、地元・東京の夜に刻まれた瞬間でした。
世界陸上
— 猫になりたい😽 (@mura45708) September 15, 2025
男子3000m障害決勝
の
三浦龍司選手のラスト
これはイケる!
彼は攻めました!
ナイスラン!👏
メダル級の攻めでした👍
激闘直後のインタビュー全編
彼は間違いなく世界のトップ選手です👍#世界陸上2025#男子3000m障害決勝 pic.twitter.com/K1FIY7fLUa
3.公式裁定と反応
審判による反則判定の有無
最終障害で接触があったものの、競技運営からは失格・順位変更などの裁定は出されませんでした。
男子3000m障害は選手同士が密集した状態でハードルを越えるため、身体が触れる場面自体は珍しくありません。明確な進路妨害や押し倒しと判断されない限り、レースはそのまま成立します。
今回も公式結果は三浦選手の8位入賞で確定し、タイム・順位に関する修正アナウンスはありませんでした。
選手本人・チーム・メディアの受け止め
レース直後の報道や現地レポでは「最終障害の接触で失速」という描写が中心で、観客席から悲鳴が上がった臨場感も伝えられました。
SNS上では「よく倒れず踏みとどまった」「表彰台に届きそうだっただけに悔しい」といった声が相次ぎ、接触の有無よりも“粘りの走り”を評価する反応が目立ちました。
チームとしては、地元開催の重圧下で入賞を確保した事実を前向きに捉えつつ、ラスト局面の位置取りやリズムの微調整を次戦の課題として共有——そんな空気感でした。
今後の課題と期待される成長
課題は大きく三つです。
①位置取り:最終障害へ入るライン取りを半歩早く確定し、「踏み切りの被り」を避ける。
②可変リズム:接触回避で一瞬ストライドが乱れても、1〜2歩で元のピッチに戻す再起動力を高める。
③加速余力:着地後の“再加速の一歩目”をより強く、短く踏み出せる筋力と反発感(中足部の使い方)を磨くこと。
これらが噛み合えば、ラスト100mの総合スピードは確実に底上げできます。三浦選手は水濠後の立ち上がりとフォームの安定感に強みがあり、経験の積み増しで表彰台ラインの攻防に戻ってくる素地は十分。地元で得た歓声と悔しさは、次の国際大会での“あと一段”を押し上げる糧になるはずです。

まとめ
東京開催の世界陸上で、男子3000m障害は最後の最後まで手に汗握る展開でした。
日本記録保持者・三浦龍司選手は、地元の大歓声を背に予選を突破し、決勝でも終盤まで食らいつく力走。
最終障害付近でケニアのセレム選手との接触があり、着地後の“再加速の一歩目”が遅れたことでスプリント勝負に響き、結果は8位入賞となりました。
失格や順位変更はなく、公式結果はそのまま確定。わずかな体勢の乱れが順位を左右する、この種目の厳しさが浮き彫りになりました。
それでも、三浦選手の持ち味である水濠後の立ち上がりやフォームの安定感、そして最後まで粘り抜く姿勢は観客の心を掴みました。
今後に向けては、①最終障害へ入る位置取りの先取り、②接触やリズムの乱れからの立て直しを1〜2歩で完了させる可変リズム、③着地直後にもう一段上げられる加速余力の強化——この三点が鍵。地元で得た歓声と悔しさは、次の国際舞台で“あと一段”を押し上げる糧になるはずです。
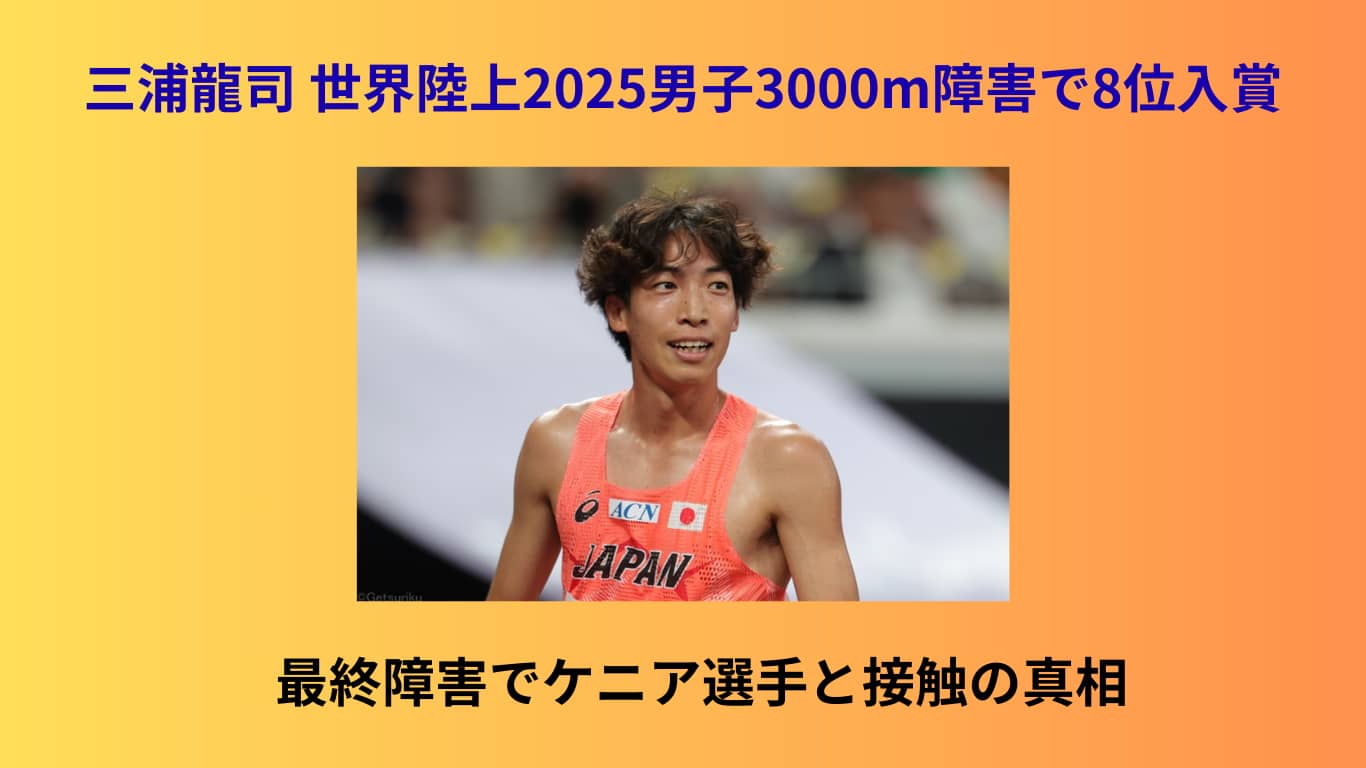
コメント