「ラオスで、日本人が現地の子どもを搾取している」
そんな投稿がSNSで拡散され、社会に衝撃を与えました。発信したのは、実業家の三崎優太氏。「信頼される職業に就く人々が関与している」との言葉に、多くの人が耳を疑いました。
本記事では、この問題の背景にある法制度、SNSの影響力、そして社会全体に求められる意識の変化について、「一市民」の視点から丁寧に解説していきます。センシティブなテーマですが、子どもたちの権利を守るために、私たち一人ひとりが知っておくべき内容です。
1.ラオスにおける子どもへの搾取的行為と法的対応

ラオスの法律で禁止されている未成年者への加害行為
ラオスでは、18歳未満の子どもを対象とした性的な関係や搾取行為は厳しく法律で禁止されています。
たとえ子どもの「同意」があるように見えても、それは認められません。とくに、金銭が関わるような行為は重い犯罪とされ、長期の懲役刑が科されることもあります。
また、現地では経済的な事情から、弱い立場にある子どもが不適切な扱いを受けるケースが問題視されています。
ラオス当局は、そうした加害行為を防ぐために、国内外からの観光客に対しても注意を促しながら、捜査や摘発を強化しています。
海外でも日本の法律は適用されるという現実
日本では「児童の保護に関する法律」により、海外であっても日本国籍を持つ人が未成年者に不適切な行為をした場合、日本国内でも処罰の対象となります。
これは、いわゆる「国外犯処罰制度」と呼ばれるしくみで、日本国内と同様の倫理観が求められています。
実際、過去には海外での行動をきっかけに、日本へ帰国後に摘発される事例も起きています。
SNS上に投稿された画像や情報が手がかりとなり、捜査に発展したケースもあることから、「現地では見逃されるだろう」といった安易な考えは非常に危険です。
日本大使館からの注意喚起とその背景
2025年6月、在ラオス日本国大使館は、公式ウェブサイトにて「現地で日本人に関わる不適切な行動がSNS上で指摘されている」とし、現地と日本の双方の法律に違反するおそれがある行為について、強く警告を発しました。
この警告には、ラオス当局と日本の警察が連携し、違法行為に対しては厳正な対応を取ることも明記されています。
国や地域が異なっても、日本人としての責任あるふるまいが求められていることを、私たちは忘れてはいけません。
2.SNSでの告発と社会的反響
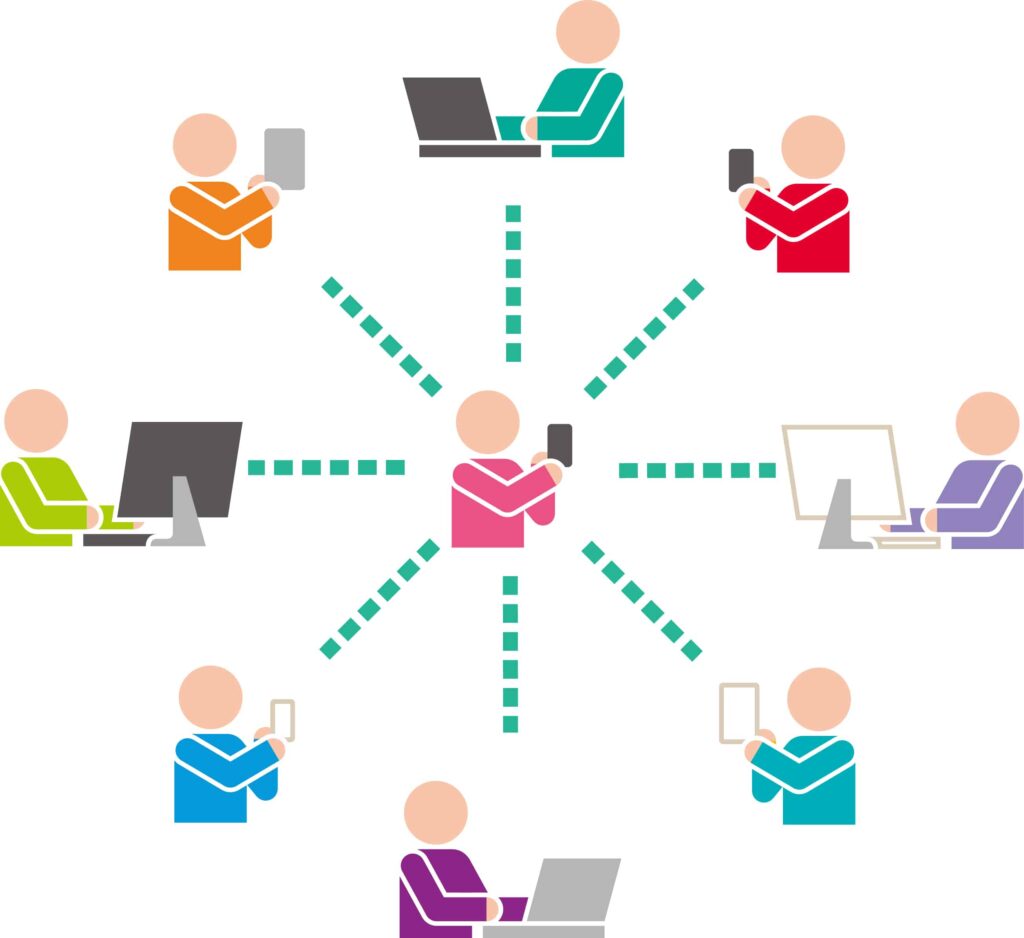
三崎優太氏の問題提起と反響の広がり
実業家の三崎優太さんが、自身のSNSであるX(旧Twitter)に投稿した内容が、大きな注目を集めました。
投稿では、海外において子どもが不適切に扱われている可能性がある状況を取り上げ、その加害行為に関与しているのが日本人だとする指摘がなされました。
さらに、「本来、社会から信頼される職業の人たちが関与している」とも述べられ、教育や医療など公共性の高い分野で働く人々の行動にも言及されました。
この発言は、瞬く間に拡散され、共感や驚き、そして深い問題意識を呼び起こすこととなりました。
発信者の影響力と責任
三崎氏のように影響力のある人物が社会問題に触れると、それは大きな波紋を呼びます。
今回も「有名人の発言だからこそ、事実ではないか」と受け取った人も多く、SNS上では実際に多くの議論が巻き起こりました。
ただし、影響力のある立場だからこそ、発言には慎重さが求められるのも事実です。
情報の出所が不明確なまま広まると、誤解や偏見を生むおそれがあります。
とくに特定の職業や人々を断定的に非難するような表現は、社会的にデリケートな問題をさらに複雑化させてしまう可能性があります。
ネット上で交差する声と私たちの受け止め方
今回の件について、SNS上ではさまざまな声が飛び交いました。
「なぜ報道されないのか」「恥ずかしい行為は絶対に許されない」という強い怒りや悲しみの声が多く見られた一方で、「事実確認ができていない段階で断定するのは危険ではないか」といった冷静な意見も寄せられました。
さらに、「個人や職業を名指しすることよりも、制度や教育の見直しが必要ではないか」といった建設的な意見も多く見られました。
このように、ネット社会では多様な立場からの考え方が交差し、それぞれに意味のある視点が含まれています。
大切なのは、感情的になりすぎず、問題の本質を見つめること。SNSは「気づき」の場でもあり、私たち一人ひとりが情報の受け手としても、発信者としても、責任ある態度が求められるのだと感じました。
3.問題の根深さと背景にある構造

社会的信頼のある立場にある人が加害者となる現実
三崎氏の投稿が特に強く注目された理由の一つは、「社会的に信頼されているはずの職業に就く人々が加害行為に関与している」と指摘されたことでした。
教育や医療、行政といった分野は、人々の暮らしや子どもたちの未来を支える重要な役割を担っています。
だからこそ、そうした立場にある人が不適切な行動に及んだ可能性を示唆されることは、私たちに大きな衝撃と失望を与えます。
実際に、日本国内でも、立場や肩書きに関係なく不祥事が明るみに出ることがあります。
学校や医療現場、公共機関での不適切行為が報道されるたびに、信頼が傷つき、子どもや弱い立場の人々が安心して過ごせるはずの場所が脅かされていると感じます。
このような現実を目の当たりにすると、「職業や肩書きで人を信用する」だけでは不十分であり、その人の行動や倫理観こそが問われるべきだと、強く思わされます。
海外での行為に至る背景と無自覚な加害
「なぜわざわざ海外で?」と思う方も多いのではないでしょうか。
そこにはいくつかの背景があると考えられます。たとえば、国内での監視や取り締まりが厳しくなってきた中で、「海外なら見つからない」といった安易な発想で行動に出るケースがあるようです。
また、訪問先の国について十分な知識がないまま、「現地では黙認されている」「文化が違う」といった誤った先入観を持ってしまうこともあります。
しかし、どの国でも子どもを搾取する行為は決して許されるものではありません。
問題の本質は、そうした行動を「悪いこと」と認識せずに、自分の立場や都合を優先してしまう意識にあります。無知と無関心、そして自己正当化が重なることで、加害行為は生まれてしまうのです。
モラルの再構築と、社会全体での防止の取り組み
このような問題に対して、「一部の人の問題だから」と他人事にするのではなく、社会全体でモラルや価値観を問い直す必要があります。
「性加害は誰が行っても絶対に許されない」「どこにいても人権は守られるべき」という共通の意識が、すべての世代に求められています。
そのためには、家庭や学校、職場など、あらゆる場面で人権や倫理について考える機会を持つことが大切です。子どもたちには、「人として大切にされる権利がある」ということを、私たち大人が行動で示さなくてはなりません。
そして、SNSやメディアの力を使って「見えなかった問題」を見える形にしていくことも重要です。被害者の声を丁寧にすくいあげ、仕組みとして守れる社会を目指すこと。それが、私たちが未来の子どもたちにできる最も誠実な行動なのではないかと感じています。
4.なぜメディアは報じないのか?SNS告発と報道の「壁」
三崎優太さんがSNSで告発した内容には、「社会的に信頼されている職業に就く人たちが、子どもを搾取するような行為に関わっている」といった非常に深刻な指摘が含まれていました。
それにもかかわらず、テレビや新聞などの大手メディアではこの件について大きく報道されていないことに、違和感や疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
私もそのひとりです。けれど調べていくと、そこにはいくつかの理由があることがわかりました。
事実確認が不十分な段階では報道できない
まず、報道機関には「裏付け」が不可欠です。たとえSNSで多くの人が話題にしていても、加害の証拠や公的な捜査情報が出ていない段階では、報道は難しいというのが原則です。
事実であっても、誤報や名誉毀損になるリスクを避けるため、報道はあくまで慎重に行われます。
被害者保護と公益性のバランス
加害行為の対象が未成年者である場合は、報道によって二次被害が発生するおそれもあります。
実名報道や職業の明示が社会的利益よりも個人の損害を上回ると判断されれば、報道は控えられることもあるのです。
社会的影響の大きさから、報道が慎重になるケースも
残念ながら、加害が疑われる人物が社会的に影響力のある職業(医師、教師、官僚など)の場合、メディア側が慎重にならざるを得ない場合もあります。
報道によって信用不安が広がることを避けようとする“忖度”が、ある種の「沈黙」を生むことも否定できません。
海外での出来事ゆえの取材・証拠の壁
今回の件がラオスで起きた可能性があるという点も、報道されにくい理由の一つです。
海外での取材は簡単ではなく、現地の警察や政府の協力がなければ確実な裏付けが取れないため、報道判断が難しくなります。
SNSと報道の役割の違い
SNSは「問題提起」の場であり、報道は「検証された情報を社会に伝える」ことが役割です。この違いから、たとえSNSで多くの人が注目していても、報道がすぐに動くとは限りません。
「報道されない=虚偽」ではありません。むしろ、報道できない“構造的な壁”があるからこそ、市民による発信の意味や、私たち一人ひとりの問題意識が大切になってくるのだと私は感じました。
三崎優太(みさき ゆうた)プロフィール

- 生年月日:1989年3月29日
- 出身地:北海道札幌市(その後、北見市で成長)
- 職業:実業家・YouTuber・タレント・投資家
- 通称:「青汁王子」— 健康食品のネット通販で成功した後、メディア露出が増えてついたニックネーム
主な経歴
- 学歴と起業の始まり
- 高校を数回退学 → クラーク記念国際高等学校卒業
- 高校時代にアフィリエイトで成功。月収400万円を超え、2007年「メディアハーツ」創業
- フルーツ青汁で成功
- 2014年〜美容系通信販売を展開
- 「すっきりフルーツ青汁」で爆発的成長。2017年には通販売上高131億円を記録
- 脱税による逮捕と復活
- 2019年、法人税法違反により脱税容疑で逮捕。同年、有罪判決(懲役2年・執行猶予4年、罰金4600万円)
- 保釈後、SNSで「贖罪寄付」を行うなど話題にj
- 再起と多方面での活躍
- 「三崎未来ホールディングス株式会社」を2024年設立し代表取締役
- YouTubeやXなどを通じ、投資・ビジネス・アイドル育成など多彩な活動を展開
その他の情報
- 家族背景:父親は歯科医、母親は専業主婦
- 活動の多様性:YouTubeチャンネル、テレビ、CM出演、ホスト経営、アイドルグループの立ち上げなど、幅広い領域で挑戦中
まとめ
今回の一連の問題は、海外で起きた出来事として片づけるには、あまりに多くの示唆を含んでいます。
子どもが搾取の対象となっているかもしれないという現実、そこに日本人が関与している可能性、さらに信頼される職業に就く人々の関与が指摘されたこと——その一つひとつが、私たちの社会が抱える課題を映し出しています。
SNSというツールは、声にならなかったものを可視化し、広く社会に投げかける力を持っています。
その一方で、情報の受け止め方や発信の仕方には、冷静さや慎重さも必要です。三崎優太さんの投稿が多くの共感と波紋を呼んだことは、問題の根深さと、私たちの中にある「何かがおかしい」という感覚を浮かび上がらせたのではないでしょうか。
この問題を前に、私たち一人ひとりができることは、決して小さくありません。
たとえば、日常の中でモラルについて語り合うこと。子どもたちに正しい情報と安心できる環境を与えること。そして、社会全体で「どんな立場の人でも、間違った行為は許されない」という共通認識を持つこと。
「知ってしまった以上は、無関心でいられない」。
そんな思いを持った人が少しずつ増えていけば、私たちの社会は確実に変わっていくはずです。

コメント