近年、全国のドラッグストアや衣料品チェーンで「万引き被害」が深刻化しており、その被害総額は年間3,000億円を超えるとも言われています。
特に外国人グループによる組織的な犯行が目立ち、企業の損害は想像以上に大きなものです。そんな中、ユニクロを展開するファーストリテイリングが、万引犯に対して民事で損害賠償請求を行う方針を発表しました。
本記事では、その背景や他企業への波及、そして私たちがこの問題をどう捉えるべきかを、一般市民の目線で分かりやすく解説します。
はじめに
社会問題化する万引被害の実態とは
近年、全国の小売業界では「万引」による深刻な被害が続いています。
特に衣料品チェーンやドラッグストアなど、生活に身近な店舗がターゲットとなることが多く、被害額は年間で約3千億円を超えるとも言われています。
店頭で気軽に手に取れる商品が狙われやすく、防犯カメラの設置や警備員の巡回など、各店舗は対策を講じているものの、根本的な解決には至っていません。
こうした中、外国人による組織的な万引事件が相次ぎ、警察庁のデータでは摘発された外国人の5〜7割がベトナム人という報告もあります。
中には、日本とベトナムを行き来しながら、報酬を得て特定の商品を狙う「指示型」のグループ犯も存在しています。
大阪・東京・兵庫などで連続して被害を与えていたベトナム人グループによる事件では、被害総額が1,200万円以上にのぼるとされました。
ユニクロが打ち出した「民事での賠償請求」とは
このような状況を受け、衣料品大手の「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング社は、犯人に対して“民事での賠償請求”を行う新たな対応を打ち出しました。
これまでは警察に被害届を提出し、刑事処分を待つだけの企業が大半でしたが、ファーストリテイリングは盗まれた商品や防犯対応の費用など、すべての損害を加害者に請求する姿勢を明確にしています。
この方針は、全国790以上の店舗を持つ同社の経営判断としても注目されており、「安心して買い物ができる環境を守る」という強いメッセージと受け取られています。
これにより、被害企業が泣き寝入りせずに実損回復を求める動きが広がる可能性があると、業界団体やNPO法人も注目しています。
1.外国人グループによる万引の現状
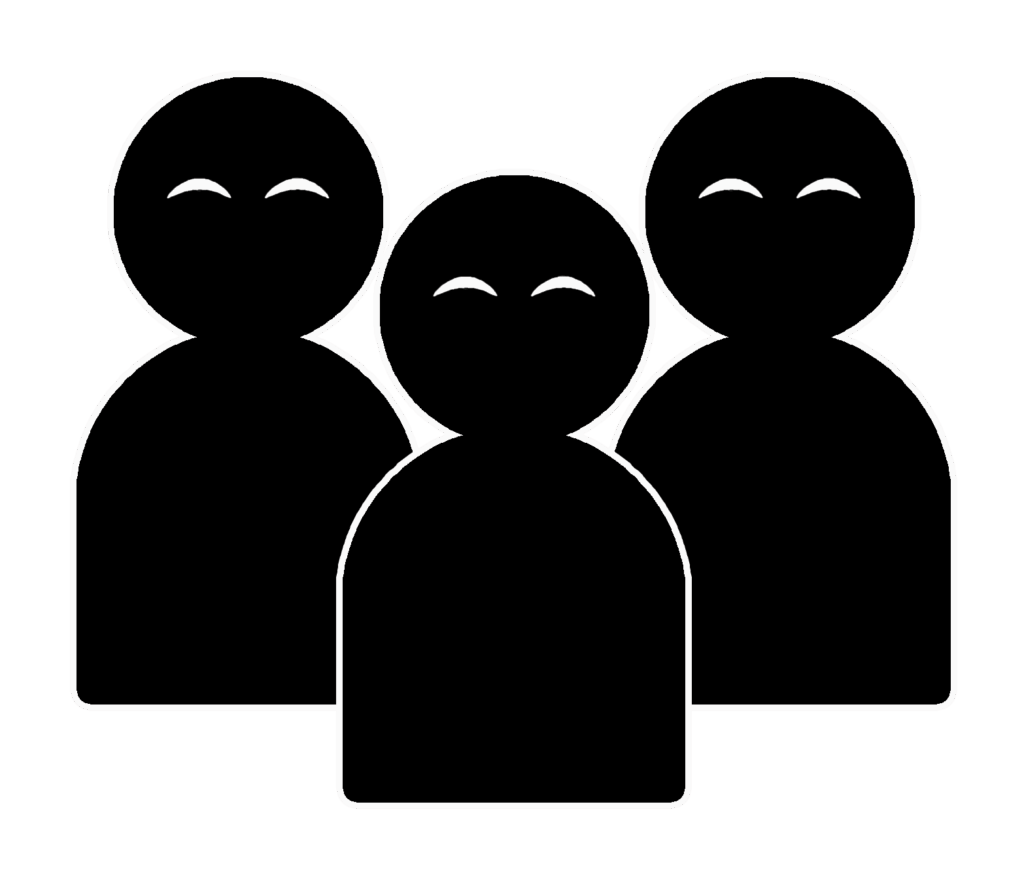
ベトナム人グループによる組織的犯行の実態
近年、日本国内で相次いで摘発されている万引事件の中でも、特に目立つのがベトナム人によるグループ犯行です。
大阪市のユニクロ店舗で逮捕された30代から40代のベトナム人女性3人は、衣料品の万引を繰り返していたことが判明。
彼女たちは「ベトナム国内にいる人物から指示を受けた」と供述しており、単なる個人の犯行ではなく、背後に組織的な関与があることがうかがえます。
このグループは日本とベトナムを頻繁に行き来しており、1回の渡航で17万~21万円の報酬を受け取っていたとされています。
つまり、日本に来て特定の商品を万引し、それを転売することで生活費を稼ぐ「ビジネス」としての万引が成立していたというのです。
こうした事例は、一般的なイメージの“軽犯罪”という枠を超え、深刻な経済犯罪として捉える必要が出てきています。
全国各地で相次ぐ摘発と被害金額
ベトナム人による集団万引事件は、特定の地域にとどまりません。
ユニクロを中心に、東京・大阪・兵庫・福岡など全国8都府県で被害が確認されており、その被害額は約2,000万円にも及びます。
中には、わずか数カ月の間に複数店舗で合計37件もの犯行を重ねていたケースもあり、警察は組織的な手口として重点的に捜査を進めています。
2023年には福岡県警がベトナム人男女4人を逮捕し、集団で衣料品を盗んでいたことが明らかになりました。
被害総額は1件あたり数十万円にのぼるケースも珍しくなく、特に高額な防寒着やブランド商品が狙われる傾向があります。
こうした広域的かつ反復的な犯罪行為は、警察だけでなく企業側にとっても深刻な負担です。
背後にある指示役や報酬制度の存在
さらに問題となっているのが、犯人たちの背後に存在する「指示役」の存在です。
ベトナム国内にいる人物がLINEなどの通信アプリを通じて盗むべき商品を指定し、万引に成功すれば報酬が支払われるという仕組みが確認されています。まさに“窃盗版のフードデリバリー”のような構図です。
これにより、金銭的に困窮している外国人が日本に来て犯行に加担するケースが増加。
中には「生活のためにやった」と話す人もおり、経済的背景や国際的な格差が万引の温床になっている現実も無視できません。
こうした背景を理解したうえで、単なる犯人逮捕だけでなく、抜本的な対策が求められています。
2.企業側の対応とユニクロの方針
ファーストリテイリングの断固たる姿勢
万引被害が全国で深刻化する中、ファーストリテイリング(ユニクロ運営会社)は2025年6月、これまでにない強い姿勢を示しました。
これまでは警察への被害届や刑事告訴が中心でしたが、同社はそれに加え、窃盗によって発生したあらゆる損害を犯人に対し民事で請求する方針を打ち出したのです。
たとえば盗難による商品損失にとどまらず、防犯強化にかかった費用や営業への影響など、実質的な損害すべてが請求対象となります。
ユニクロのこうした方針は、全国に約790店舗を展開する大手企業ならではの影響力を持ち、他の小売企業にも波紋を広げています。
ユニクロ広報は、「安心して買い物できる店舗環境を守るため、断固とした対応を取る」と発表。これは、被害を泣き寝入りせず、加害者に“きちんと責任を取らせる”という企業姿勢の表れでもあります。
民事請求に踏み切った理由と背景
ユニクロが民事請求を本格化させる背景には、現行の刑事処分だけでは企業側の実損が回復しにくいという問題があります。
犯人が有罪判決を受けたとしても、盗まれた商品が戻るわけではありませんし、再発防止への抑止効果も限定的です。特に今回のような組織的・広域的な犯行においては、刑事罰だけで済ませるには企業側の負担があまりに大きいのです。
また、同社は防犯カメラやAI技術を使った万引検知システムの導入を進めてきましたが、それでも被害が後を絶たない現状に危機感を持っていたといいます。
加えて、社会的責任を果たすという観点からも、毅然とした対応が求められていました。こうした背景から、ファーストリテイリングは「訴訟も辞さず」という姿勢を明確にしたのです。
他企業への波及と業界団体の反応
このユニクロの方針表明を受けて、同様の被害を受けているドラッグストアやホームセンターなどの小売企業でも、民事請求を視野に入れる動きが出始めています。
実際、全国の小売業者で構成されるNPO法人「全国万引犯罪防止機構」によれば、「民事請求を行っている」と回答した企業はまだ1割程度にとどまっていますが、今後は増加する可能性が高いとされています。
業界団体の関係者は「これまで請求の仕方がわからなかったり、時間やコストがかかるために断念していた企業も多い」と語っており、ユニクロの行動が“風穴”になるとの期待も寄せられています。
特に、他企業も連携し、共通の手続きフローや法的支援体制を整えることができれば、より多くの企業が被害回復の一歩を踏み出すことができるかもしれません。
3.万引被害と賠償請求をめぐる課題

年間3千億円を超える被害の実態
万引による被害は、単なる店舗の損失にとどまらず、日本全体の小売業に大きな影響を与えています。
全国万引犯罪防止機構の試算によると、その年間被害額は実に約3,460億円。
これはコンビニエンスストアチェーン1社分の年間売上に匹敵する金額であり、いかに重大な損失であるかがわかります。
しかも被害は目に見える商品だけではありません。従業員の心理的負担や防犯設備への投資、営業時間の短縮など、見えないコストも膨大です。
中小の小売店にとっては経営を揺るがす要因となり、最悪の場合は廃業に追い込まれるケースもあります。こうした万引被害が慢性化することで、地域経済の衰退や雇用の減少といった波及効果も無視できません。
賠償請求が広がらない理由とは
こうした被害にもかかわらず、実際に加害者に対して民事で損害賠償を請求している企業はまだ少数派です。
令和6年の調査では、「賠償請求を行っている」と回答したのはわずか10.9%(29社)にとどまっています。背景には、請求手続きが煩雑であったり、法的知識が必要であったりすることへの不安があります。
さらに「裁判沙汰になると企業イメージが悪くなるのではないか」という懸念や、「どうせ支払われないだろう」という諦めムードも一因とされています。
特に中小企業では、法務担当者や顧問弁護士を持たないところも多く、請求のハードルは高いままです。実際、万引犯が外国人の場合、強制送還されることもあり、損害賠償の実行はさらに難しくなります。
今後求められる法的・社会的整備
こうした現状を打開するには、法的・社会的な整備が欠かせません。
たとえば、被害企業が簡易的に損害請求できるような制度や、NPO法人や行政による手続き支援の仕組みが求められています。
さらに、加害者の支払い能力に応じて分割納付を認めるなど、現実的な回収方法の確立も課題です。
また、学校教育や地域の啓発活動を通じて「万引はれっきとした犯罪である」という意識を広めることも必要です。
特に若年層や外国人労働者向けに、日本の法制度や文化を正しく理解してもらう取り組みは、犯罪の抑止につながります。万
引を単なる店舗内の問題ではなく、社会全体の課題としてとらえ、官民が連携して取り組む体制の構築が今こそ求められています。
📊 日本人 vs 外国人:万引き犯罪の比率
✅ 万引きにおける共犯率の違い
警察庁の令和2年データによると、
- 来日外国人における万引きでの共犯率は約40.1%
- 日本人はわずか約3.1% にとどまっています。
つまり、外国人の万引き事件は組織的な手口(グループでの犯行)が圧倒的に高く、日本人の約12.9倍の共犯が確認されています。
🧍♂️ 万引き全体に占める日本人・外国人の割合
2021年~2023年におけるドラッグストアの万引き事件(警察庁資料)では、
- 日本人容疑者:約19,423件
- 外国人容疑者:約3,938件
1件当たりの被害額は、日本人が約1万774円に対し、外国人は約7万8936円と、外国人事犯の方が高額傾向にありました。
削減すれば、外国人は総件数に対して割合から見ると約17%程度を占めると推定されます。
✔️ 比較まとめ
| 指標 | 日本人 | 外国人 |
|---|---|---|
| 共犯率(万引き) | 約3.1% | 約40.1% |
| 件数比率(ドラッグストア例) | 約83% | 約17% |
| 1件あたりの平均被害額 | 約1万8千円 | 約7万9千円以上 |
📝 補足情報
- 来日外国人全体では、すべての刑法犯に占める割合が 約5% 程度。日本人と比較して特別著しく高いわけではないとされます。
- 同時に、来日外国人の犯罪では組織的な傾向がある一方、日本人は個別犯が多いという特徴もあります。
まとめると:
- 万引きにおける 共犯の多さ と 高額被害 といった点で、外国人事犯は日本人とは異なる傾向があります。
- ただし 数としては日本人のほうが圧倒的に多く、全体像では外国人が犯罪の中心ではありません。
🔍 外国人犯罪の国籍別構成比(令和2年/刑法犯)
- ベトナム人:約30.8%
- 中国人:約29.9%
- つまり ベトナムと中国だけで、来日外国人による刑法犯の約 6割 を占めています 。
窃盗犯罪に限ると、万引きでは特にベトナム人の割合が高いとされています(侵入盗は中国・韓国、万引きはベトナム人が多い)。
🧍♂️ 検挙された外国人の内訳(例:日本国内に滞在中の来日外国人)
| 国籍 | 構成比(刑法犯全体) |
|---|---|
| ベトナム人 | 約31% |
| 中国人 | 約30% |
| その他 | 残り約40% |
ただし、この数値は来日外国人全体(永住者・特別永住者を除く)による刑法犯の構成比であり、万引きに特化したデータではありません。ただ、万引き犯罪においては特にベトナム人の比率が高い傾向が見られます。
✅ まとめ
- 外国人犯罪のうち、ベトナム人と中国人で全体の約6割を占める。
- 万引きに限ると、ベトナム人の検挙割合が特に高い。
- 他国籍も一定割合を占めますが、窃盗系犯罪においてはこの2国が中心です。
業態別:外国人による万引きの実態
ドラッグストア(薬局・化粧品・日用品店)
警察庁の指針によると、令和5年(2023年)中の万引き認知件数は約13,870件(過去最多)で、全体に占める割合は約15%に上ります。そのうち、外国人グループによる組織的な大量万引き事案が目立ち、防犯対策の強化要請が出されています。
国籍別で見ると、ドラッグストアでは中国やベトナム出身者の割合が高く、被害商品は化粧品や医薬品など高額で換金可能なものが中心です。
スーパー・コンビニ・書店など
全国万引犯罪防止機構の調査では、スーパーが全体の37%、書籍・文具店が20%を占めており、これら業態での万引きも多発しています。ただし、業態別の国籍比率までは明示されていませんが、店舗の構造上、中小業態でも一定の頻度で被害が起きています。
🌍 地域別の傾向
具体的な都道府県ごとの国籍別統計は公開されていませんが、警察庁資料では全国的に外国人犯罪の検挙件数の“共犯率”が高い地域や都市部ほど、組織的な万引事案も多いと分析されています。
また、首都圏を含む大都市・観光都市ほど、来日外国人による万引きも多く、被害額や組織性が特に問題視されています。
📌 国籍別特徴まとめ(万引きに関わる外国人犯罪)
| 業態・地域 | 特徴 |
|---|---|
| ドラッグストア | 外国人グループによる組織的な大量万引き、化粧品・医薬品が狙われる |
| 大都市圏(東京・大阪など) | 来日外国人の比率が高く、グループによる広域犯も報告される |
| その他の小売店舗 | 防犯設備の差異や情報共有の不足が課題 |
✅ まとめ
- ドラッグストア業態では、外国人グループによる万引きが社会的に注目されている。
- 大都市や観光地など外国人客が多い地域で、検挙数・被害額・組織性の高い事案がみられる。
- 業態別・地域別のデータは限られているものの、「金額の大きさ」「組織的犯行」「共犯性」は、外国人による万引き犯罪の特徴として浮き彫りになっています。
まとめ
外国人グループによる組織的な万引事件の増加は、もはや一企業や一地域の問題ではありません。ベトナム人による指示型の犯行や広域的な摘発事例が続く中、ユニクロを運営するファーストリテイリングが打ち出した「民事での賠償請求」は、これまで見過ごされてきた“泣き寝入り”の常態を変える大きな一歩となる可能性を秘めています。
ただし、実際には多くの企業が賠償請求に踏み切れていないのが現状です。法的手続きの複雑さ、企業イメージへの配慮、費用対効果への不安など、乗り越えるべき課題は山積しています。しかしながら、万引による被害額が年間3千億円を超える今、企業が立ち上がらなければ被害は拡大し続ける一方です。
今後は、企業単位での対策にとどまらず、法制度の整備、行政やNPOによる支援、そして消費者を含む社会全体の意識改革が不可欠です。万引が「軽い罪」ではないこと、そして被害者である企業には回復の機会と仕組みが必要であることを、私たち一人ひとりが理解し、支えていくことが求められています。

コメント