SNSで4万件以上の“いいね”を集めた「熊串焼き」投稿。青森の道の駅「よこはま」で販売されたツキノワグマの串焼きが注目を集めています。
マトンに似たホロホロ食感と、臭みのない美味しさに驚く声も多数!
同時に「駆除された熊を無駄にしない」ジビエ活用の流れにも関心が高まっています。
本記事では、話題の食レポから法的課題、そして“食べて応援”の意義まで詳しく解説します。
はじめに
クマ肉ブーム到来?SNSで話題の「熊串焼」
「ツキノワグマの串焼きを食べた!」という投稿が、SNS上で大きな話題を呼んでいます。
発端は、青森県の道の駅「よこはま」で販売された2本800円の“熊串焼き”。投稿者のヤギさん(@manunusan)が「臭みがなくホロホロで美味しかった!」とコメントしたことで、一気に注目が集まりました。
見た目はゴツゴツとしてワイルドですが、味は意外にもマトンに近く、柔らかくジューシーだったとのこと。焼肉のタレ風の味付けが食欲をそそり、「ビールに合いそう」「スパイスで炒めても美味しそう」といった声も多く寄せられています。
「#青森グルメ」とともに投稿されたこのツイートは、なんと4.3万件以上の“いいね”と8,000件超のリポストを記録。
中には「食べてみたい!」「固くないんだ」と驚く声や、「山形で食べたクマのすき焼きも絶品だった」と共感する声も多く見られました。
クマ被害とジビエ活用の関係性とは
一方で、背景には深刻な“クマ被害”の問題があります。全国各地で農作物の被害や人身事故が相次ぐ中、やむを得ず駆除されたクマの命を無駄にしないため、「ジビエ(野生鳥獣肉)」として活用する取り組みが広がっています。
熊肉は古くから高級食材として珍重されてきましたが、一般の食卓に並ぶ機会は少ないものでした。
しかし近年は、地域の道の駅やイベントで販売されるケースも増え、観光資源としての側面も注目されています。
この流れは単なるグルメトレンドではなく、自然と人間社会の共存を模索する新しいアプローチでもあります。
「駆除される命を無駄にせず、食べて支える」——そんな考え方が、今静かに広がりつつあるのです。
1.ツキノワグマの串焼きが注目された背景
青森・道の駅「よこはま」で販売された熊串肉
今回話題になったのは、青森県の道の駅「よこはま」で販売された「熊串焼」。価格は2本で800円とお手頃で、観光客にも購入しやすい設定でした。
この串焼きは、地元で駆除されたツキノワグマの肉をジビエとして調理したもの。青森県内では、農作物への被害や人身事故の増加を背景に、駆除個体を廃棄するのではなく「地域資源」として再活用する試みが進められています。
販売された熊肉は、しっかりと下処理が施されており、独特の臭みがほとんどないと評判。
道の駅スタッフによると「食べやすいように特製のタレに漬け込んでから焼き上げている」とのことで、観光客だけでなく地元の人からも好評を得ているそうです。
一見すると珍味のように感じるクマ肉ですが、地域ぐるみの新しい「食の循環」としても注目されています。
投稿者ヤギさんが語る「臭みのないホロホロ食感」
実際に食べたヤギさん(@manunusan)は、「ホロホロと柔らかく、まったく臭みがなかった」と感想を語っています。
「焼肉のタレ風の味付けがされていて、マトンのような風味でした。クミンなどのスパイスで炒めたらさらにおいしくなりそう」と語り、ジビエに馴染みがない人でも挑戦しやすい味だったようです。
ジビエ料理はしばしば「硬い」「臭い」と敬遠されがちですが、今回の串焼きはそのイメージを覆すほどの出来栄え。SNSの投稿写真からも、こんがりと焼けた肉がジューシーに輝き、見るだけで食欲をそそります。
ヤギさん自身も「下処理や調理法が素晴らしかったからこそ、こんなに美味しかったんだと思う」と話しており、現地の技術力と工夫が多くの共感を呼びました。
SNSで4万件超の“いいね”を集めた理由
この投稿がここまで拡散したのは、「珍しい体験」×「美味しそうな見た目」×「社会的背景」の3拍子がそろったからでしょう。
まず、クマ肉という“非日常”の食材が注目を集めたこと。
さらに、投稿者の率直でポジティブなコメントが共感を呼び、「自分も食べてみたい!」という声が殺到しました。
加えて、昨今のクマ出没ニュースが増える中で、「駆除されるなら食べて活用すべき」という考え方が広がっていたタイミングでもありました。
コメント欄には、「命を無駄にしない取り組みとして素晴らしい」「ジビエが地域の収入につながるのはいいこと」といった意見も多く見られました。
結果として、この一つの投稿が「クマ肉ブームの火付け役」となり、地域のジビエ振興にも光を当てることになったのです。
2.クマ肉ってどんな味?実際の食レポと反応
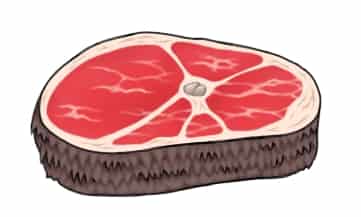
「羊肉に似てる」「ビールに合う」など多様な感想
実際に食べた人の声で多かったのは「羊肉(マトン)に近い」という感想でした。
香りはほどよく、噛むとホロホロほどける柔らかさ。味付けは焼肉のタレ風で、濃すぎず甘辛バランスがよく、「これはビールに合う」との声も。
一方で、「スパイスで炒めてもおいしそう」「串焼きなら初めてでも挑戦しやすい」といった意見も多く、食べ方のアイデアが広がっていました。
珍しい食材でも、親しみのある“串”という形と手頃な価格(2本800円)が、ハードルを下げた印象です。
下処理の工夫でおいしさが変わる理由
「臭みがない」と評価された背景には、丁寧な下処理があります。例えば、
- 余分な脂や血の部分を取り除く
- 低温でゆっくり火を入れて硬くしない
- タレに漬けて旨みをなじませる
といった基本的な工夫だけでも、風味がぐっと食べやすくなります。
実際に「下処理や調理法が素晴らしかったから、こんなにおいしかった」との感想もあり、調理側の気配りが味の決め手になっていることが分かります。
家庭で試す場合も、強火で一気に焼き固めず、中まで温めるイメージで火加減を調整すると柔らかさを保ちやすく、スパイス(クミンなど)を合わせると香りの相性も良好です。
ネット上のリアルな声と食文化としての可能性
SNSでは「食べてみたい」「思ったより柔らかい」という驚きと興味の声が目立ちました。中には「山形で食べたクマのすき焼きが絶品だった」と、地域の食体験を共有するコメントも。
こうした口コミが広がることで、クマ肉が“珍味”から“身近なご当地グルメ”へと認識が変わる可能性があります。
観光のきっかけになったり、イベント出店で地域の売り上げに貢献したりと、食の楽しみと地域振興の両面でポジティブな循環が生まれつつあります。
大事なのは、“話題性”だけで終わらせず、丁寧な調理と安全な提供を続けること。リアルな感想が積み重なれば、「また食べたい」「別の料理でも試したい」という次の一歩につながります。
3.駆除された熊を“食べて応援”という発想

被害防止と資源活用を両立するジビエの意義
全国でクマによる被害が相次ぐ中、「駆除された個体を廃棄せず、食材として活かす」という考え方が広まりつつあります。
山間部では農作物の被害や人身事故が増加しており、年間で数千頭のクマが駆除される地域もあります。
本来であればその多くが処分されてしまうところを、「ジビエ(野生鳥獣肉)」として活用することで、食害対策と地域経済の両立を目指す動きが活発になっています。
たとえば北海道ではエゾシカ、九州ではイノシシ、そして東北地方ではツキノワグマが地域の新たな資源として注目されています。
青森や秋田では、捕獲したクマを冷凍保存し、専門業者が衛生基準を満たした上で加工・販売を行う仕組みが整いつつあります。
このように「被害動物」だった存在が、今や「地域の食文化を支える素材」へと変化しつつあるのです。
ヤギさんの言葉にあった「少しでも食べて応援できれば」という思いは、まさにこの新しい流れの象徴といえるでしょう。
クマの胆嚢や肉の流通に関する法的課題
一方で、クマ肉やその副産物を扱うには法的なルールも存在します。
特に注目されるのが、漢方薬として高値で取引される「熊の胆(くまのい)」です。これは肝臓に付随する胆嚢から得られる成分で、古くから滋養強壮や鎮痛効果があるとされてきました。
しかし現在、野生動物の取引には「鳥獣保護管理法」や「食品衛生法」など複数の規制が関係しており、正規の流通ルート以外での販売は違法となります。
そのため、地方自治体や猟友会では、捕獲から加工・流通までを一元管理する体制づくりを進めています。
具体的には、
- 捕獲個体を検査して寄生虫やウイルスを確認する
- 加工施設を認定制にして衛生基準を明確化する
- 流通ルートを追跡できるトレーサビリティ制度を導入する
といった取り組みが行われています。
こうした体制整備が進むことで、安心して「合法的に食べられるクマ肉文化」が根付きつつあるのです。
ヤフコメに見る「命を無駄にしない」議論
今回の話題を受けて、ヤフーニュースのコメント欄ではさまざまな意見が寄せられました。
多かったのは、「駆除されるならせめて有効活用を」という前向きな声です。
「命を無駄にしない」「自然の恵みとして感謝して食べたい」といった意見が多く、単なるグルメ記事を超えた“倫理的議論”として注目されています。
一方で、「安易に商業化すべきではない」「野生動物との距離感を見誤ると危険」といった慎重派の意見も。特に近年、住宅地へのクマの出没が増えていることから、「共存のあり方」を問い直すきっかけにもなっています。
いずれにしても、“食べる”という行為を通じて、自然とのつながりや命の尊さを考える機会になったことは間違いありません。
「食べて応援する」という小さな一歩が、地域社会や環境との関係を見つめ直す大きなきっかけとなりつつあるのです。
まとめ
青森の道の駅「よこはま」で販売された“熊串焼(2本800円)”をきっかけに、ツキノワグマのジビエが一躍注目を集めました。
実食の声では「マトンに似た風味」「ホロホロで柔らかい」「ビールに合う」といった具体的な感想が並び、丁寧な下処理と火入れ、タレ漬けなどの工夫が“臭みの少なさ”と“食べやすさ”を生んだことが分かりました。
珍しい食材でも、串焼きという親しみやすい形や手頃な価格がハードルを下げ、SNSの拡散(4万超の“いいね”)が「自分も食べてみたい」というムードを後押ししました。
同時に、各地で深刻化するクマ被害を背景に、「駆除された命を無駄にせず食で活用する」という発想が広がっています。
エゾシカやイノシシと同様に、ツキノワグマも地域資源としての可能性があり、イベント出店や観光と結びつけば、地域経済の一助にもなり得ます。
一方で、流通・提供は法令と衛生基準の順守が前提です。
熊の胆嚢(熊の胆)を含め、正規ルート以外での売買は違法となり、加工施設の認定や検査、トレーサビリティの整備が不可欠です。
ヤフコメでは「命を無駄にしない」という賛意と、「安易な商業化は慎重に」という意見の双方が示されました。
結論として、ツキノワグマのジビエは“話題の珍味”にとどまらず、被害抑止と資源活用、食文化の育成を同時に進める取り組みになり得ます。
私たちができることは、正規・安全な提供を選び、現地のルールに従って「食べて応援」すること。小さな一歩の積み重ねが、自然との向き合い方と地域の未来を少しずつ良い方向へ動かしていきます。
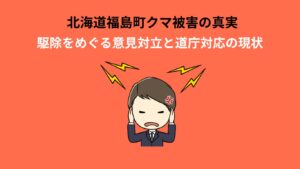


コメント