今回は「クレジットカードによる表現規制」という、ちょっと難しそうに聞こえる問題についてお話ししますが、実は私たちの身近なところにも関係している話なんです。
「好きな作品が買えない」「急にサイトでカードが使えなくなった」…そんな経験、ありませんか?
実はそれ、国際的なクレジットカード会社や決済代行会社が、ある種の“見えないルール”で表現をコントロールしているからかもしれません。
この記事では、その背景や実際に起きている事例、そしてなぜオタク業界が巻き込まれているのかを、わかりやすく整理していきます。
はじめに
表現の自由と民間企業の判断が交錯する時代に
最近、ネット上で「この作品が買えなくなった」「決済が通らない」という声を見かけたことはありませんか?
それは、クレジットカード決済にまつわる“見えない規制”が関係しているかもしれません。
たとえば、成人向けコンテンツを扱っていた同人誌販売サイトが、決済代行会社から「特定の言葉を含む商品を削除しないと契約を解除する」と警告を受けたり、実際に利用停止されたりするケースが起きています。
中には、性的表現とはまったく関係のない婚活サイトが、理由も告げられずにカード決済を止められた例もありました。
これは単なる一企業の判断で済ませてよい問題でしょうか? 誰が、どんな基準で、表現の可否を決めているのか──その構造がいま問われています。
クレジットカードによる「見えない検閲」が社会問題化
このような動きの背景には、米国を中心に強まるポルノ規制や訴訟リスクの影響があります。
国際ブランドであるVisaやMastercardは、「表現規制はしていない」と主張している一方で、決済代行会社が自主的に“過剰対応”している構図が見えてきました。つまり、明確なルールがないまま、リスクを恐れた中間業者がコンテンツを勝手に選別してしまっているのです。
とくに、表現の自由に敏感な「オタク」業界では、Steamやニコニコ動画など大手プラットフォームにも波及する兆しがあり、ファンやクリエイターにとって深刻な問題となっています。
もはやこれは一部ジャンルだけの話ではなく、インターネット文化全体が左右される「見えない検閲」の時代に突入しているのかもしれません。
1.クレカによる表現規制とは何か
決済代行会社がコンテンツを“選別”する仕組み
インターネット上の多くのサービスは、クレジットカードを使った決済に依存しています。
しかし、その裏には、利用者には見えない「フィルター」が存在しています。
たとえば、「Aというカード会社では問題なく決済できたのに、Bでは拒否された」といった違いがあるのは、このフィルターの設定が各決済代行会社によって異なるためです。
決済代行会社は、クレジットカードブランド(VisaやMastercardなど)との契約に基づき、一定の“取扱基準”を守らなければなりません。
これには、違法性のある商品だけでなく、社会的・道徳的に問題視されるコンテンツも含まれます。
しかし、その“基準”は明文化されていないことが多く、判断は各社の「社内ポリシー」によって大きく左右されているのが現状です。
その結果、本来は合法であり、かつ多くの人に支持されているコンテンツですら、「リスクがある」と判断されれば、決済サービスの対象外とされてしまうことがあります。
「禁止語句」による契約解除の実例
実際に起きた例として、ある同人誌通販サイトが決済代行会社から「このキーワードを含む作品はすべて削除してください」と通告され、対応しなければクレカ決済を止めると警告されたというケースがあります。
問題となったのは、「女子高生」や「催眠」といった言葉を含む作品。これらは法律で禁止されているわけではなく、表現としても創作物の範囲内で使われていました。
しかし、決済代行会社は「未成年に関連する性的表現」とみなし、該当作品の排除を要請。最終的にサイトはそれらの作品を削除するか、クレカ決済の導入を断念せざるを得なくなりました。
こうした「禁止語句」のリストは一般に公開されておらず、クリエイターや運営者がどの表現がNGなのかを事前に知ることは難しいのです。
婚活サイトも標的に?範囲が拡大する規制
さらに衝撃的なのは、成人向けとはまったく関係のないジャンルにも規制が及びはじめていることです。
とある婚活マッチングサイトでは、利用者が「性的な意図で他者にメッセージを送った可能性がある」という曖昧な理由で、カード会社との契約を一方的に打ち切られたと報告されています。
このような対応が繰り返されれば、決済が通らないことによってサービスの継続が困難になる中小の事業者が増えることは避けられません。
「問題があるかどうか」ではなく、「問題になりそうかどうか」でサービスが停止される――これが、いま現実に起きていることです。
2.誰が“規制”しているのか

Visa・Mastercardのスタンスと責任の所在
クレジットカードによる表現規制が問題視される中で、多くの人が気になるのは「いったい誰がその判断をしているのか?」という点です。
実は、VisaやMastercardといった国際ブランド自身は、「私たちは表現規制をしていない」と公式に表明しています。
つまり、直接的に「このコンテンツはダメ」と指示を出しているわけではないという立場をとっているのです。
しかし、実際にはそれらのブランドが定めた「加盟店規約」や「取扱基準」をもとに、決済代行会社が運用を行っており、その解釈が問題の根本になっています。
つまり、表面上は「規制していない」と言いながら、間接的には強い影響を与えている構図があるのです。
たとえば、Mastercardは2021年以降、アダルト系サイトに対して“年齢確認の厳格化”や“コンテンツ精査”を強化しており、これが決済業者の対応に拍車をかけた一因とも言われています。
決済代行会社による過剰反応の実態
決済代行会社は、VisaやMastercardからの信頼を失わないよう、自社の取引先(サイト運営者など)に対して過剰ともいえる対応を取ることがあります。
たとえば「このワードを含む作品があるなら、契約を解除します」といった通知を突然送り、即時対応を求めるケースも。運営側にとっては、予告もなく収益源が断たれるリスクを抱えることになるのです。
問題は、こうした決済代行会社の判断が透明ではない点にあります。
企業によってNG基準が異なり、明確なガイドラインも存在しないため、クリエイターや販売者は「どこまでがセーフでどこからがアウトか」を事前に把握できません。これにより、同じ内容でも「A社ではOKだが、B社では決済停止」といったケースが後を絶たないのです。
中には、いったん審査を通過していた商品が、突然の社内方針変更によって販売不可になることもあります。「そのときの担当者の判断次第」とさえ言われる状況は、表現の自由に対する重大な脅威と言えるでしょう。
「見えない圧力」とブラックボックス化した判断基準
この問題がさらにやっかいなのは、誰がどの段階で「圧力」をかけているのかが非常に不透明だということです。
VisaやMastercardは規約を示すだけで、現場の細かい判断は決済代行会社に任されています。
加えて、実際に取引を断られたサイトに対しても、その理由を明かさないまま「契約上の判断です」「基準に満たないため」といった一言で片づけられることが少なくありません。
こうした“ブラックボックス”の存在が、業界全体に萎縮をもたらしています。誰もが「これは大丈夫だろうか?」と過剰に自主規制をするようになり、結果として表現の幅がどんどん狭くなっていく。
表現者側が抗議しても「契約の自由」という法の壁に阻まれ、問題提起すら難しい現状があります。
クレジットカードという、生活にもビジネスにも欠かせないインフラが、こうした「見えない圧力」のもとで機能している。その現実が、今あらためて問われているのです。
3.なぜオタク業界が狙われるのか
国際的なポルノ規制強化と訴訟リスクの影響
近年、アメリカを中心にポルノや性的表現に対する規制が厳しくなっており、それが国際的なクレジットカードブランドにも影響を与えています。
背景には、未成年の保護を目的とした世論の高まりや、オンライン上の性犯罪への懸念があり、特にアダルト系サイトに対しては厳しい監視と基準の適用が進んでいます。
この流れを受け、VisaやMastercardはアダルトサイト運営企業に対して「実在モデルの年齢確認」や「違法コンテンツ排除の徹底」を求めるようになりました。
2020年には、アメリカの有力紙による告発記事をきっかけに、某大手アダルト動画サイトの決済機能が一時停止されたことも話題になりました。
こうした動きは、決済リスクを最小限にしたい決済代行会社にも波及し、必ずしも違法ではないが“訴訟リスクの高そうな”表現にまで規制が及ぶようになっています。
そしてその対象として、アニメや漫画、ゲームといった“オタク”文化の作品が含まれているのです。
国内作品も規制対象にされる背景
問題は、こうした国際的な動きが、法的には問題のない国内作品にも波及していることです。
たとえば、フィクションの登場人物であっても「未成年に見えるキャラクター」「制服姿のキャラ」などが含まれると、それだけで“NGコンテンツ”と判断されてしまうケースがあります。
この判断基準は、あくまで決済代行会社側のリスク回避に基づくものであり、実際の日本国内の法律や倫理とは必ずしも一致していません。
結果として、合法かつ表現の自由の範囲内で制作された作品が、国際ブランドの規約や、業者の“独自判断”によって販売停止に追い込まれてしまうという構図が生まれています。
とくに同人誌やインディーズゲームなど、小規模な表現者にとっては、クレジットカード決済が使えないことは“死活問題”です。これは単なる表現の問題ではなく、経済的な制裁として機能してしまっているのです。
Steam・ニコ動・同人サイトへの波及
こうした規制の影響は、個人の創作活動だけでなく、大手プラットフォームにも広がっています。
2025年には、ゲーム配信プラットフォーム「Steam」が決済代行業者の規約に則り、一部の成人向けゲームの販売制限を強化する可能性が報じられました。
また、ニコニコ動画では、海外発行のクレジットカードが利用できなくなるという対応が話題となり、「ついに日本国内サービスにも波が来た」と警戒する声が高まりました。
さらに、同人誌やイラスト投稿サイトでも「クレジットカード対応をやめる」「電子マネーのみ対応」といった方針変更が相次いでおり、今後ますます選択肢が狭まる可能性があります。
表現の場が奪われることで、創作文化全体が萎縮してしまう懸念はぬぐえません。
つまり、オタク業界が狙われているのではなく、リスクを避けたい企業の判断が“結果として”この業界を直撃している――その現実が、私たちの創作環境をじわじわと侵食しているのです。
まとめ
クレジットカードによる表現規制の問題は、もはや一部のアダルトサイトや過激な表現に限った話ではなくなっています。
決済インフラを握るクレカ会社や決済代行業者の“見えない判断”によって、合法であっても販売や発信の機会を奪われる表現が急増しています。
しかも、その判断基準は曖昧かつ不透明で、抗議や見直しを求める術さえ限られているのが現実です。
とくに、アニメや同人誌、ゲームといったオタク文化は、その創作性の豊かさと一部ジャンルの過激性ゆえに、真っ先に“リスクがある”と判断されやすい領域です。
本来であれば守られるべきフィクション表現の自由が、国際的なポルノ規制の延長線上で無差別に巻き込まれている構図には、大きな危機感を抱かざるを得ません。
今後、私たちにできることは、電子マネーや銀行振込など多様な決済手段を確保することに加え、こうした動きに対して声を上げていくことです。
「誰が、どの基準で、なぜ規制しているのか」を問い続ける姿勢こそが、自由で多様なネット表現を守る第一歩になるはずです。
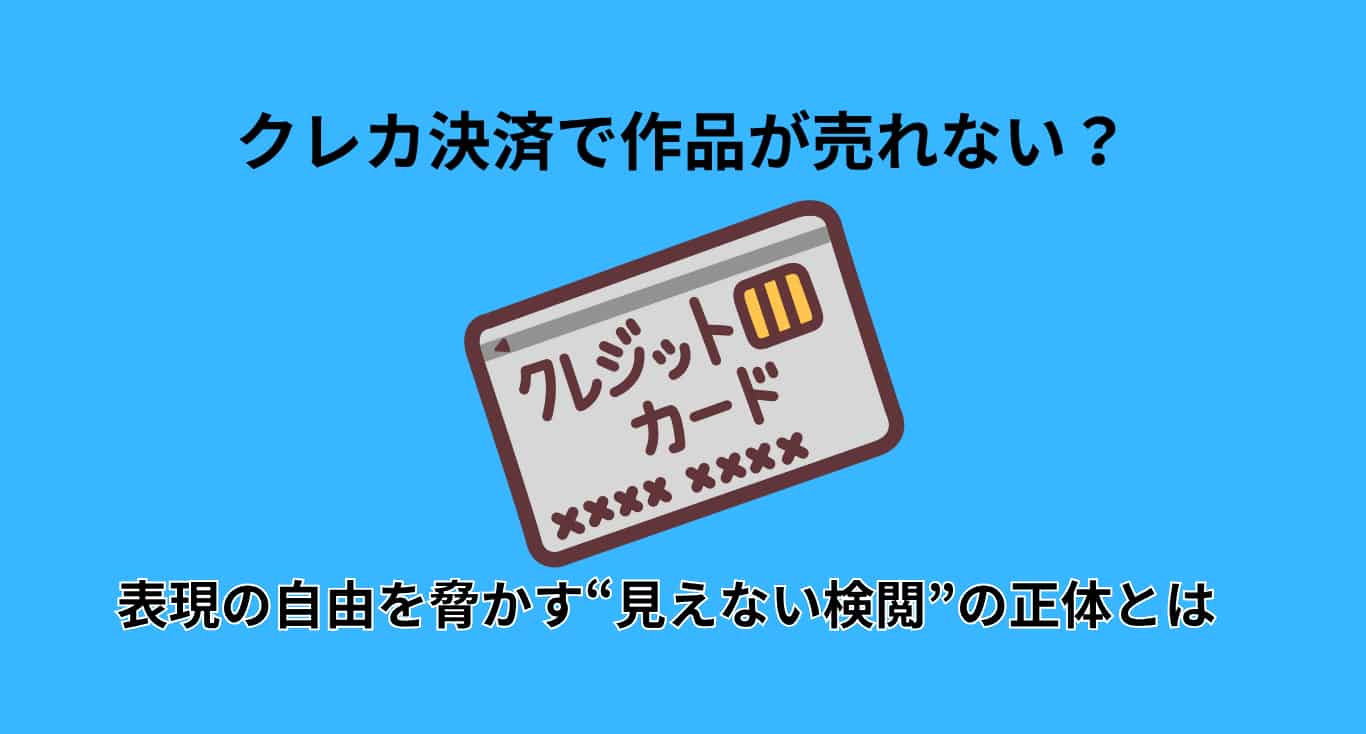
コメント