精神科病院での入院を「強度行動障害のある人は原則対象外」とする方針を厚生労働省が示し、大きな議論を呼んでいます。
急性期の患者は入院対象となる一方、慢性的に自傷やこだわり、睡眠障害などが続く人は「訪問看護や地域支援で対応」とされる方向です。
しかし、実際に24時間対応を担う家族や地域の現場からは「本当に支えられるのか」「受け皿が足りない」といった不安の声が相次いでいます。
本記事では、この新方針の背景、強度行動障害の特徴、そして現場からの課題や解決への道筋を、わかりやすく整理しました。
はじめに
精神科医療をめぐる新たな議論
近年、日本の精神科医療は「入院中心」から「地域支援」へと大きな転換点を迎えています。
厚生労働省は、急性期の治療を必要とする人を中心に入院を位置づけ、強度行動障害を抱える人については地域や施設での支援に移行する方針を示しました。
たとえば、自傷や他害のリスクがある人に対して、従来は病院に長期的に入院させることが多かったのですが、今後は訪問看護や福祉サービスを組み合わせて生活を支えていく仕組みが重視されます。
これは、医療費の抑制や患者の人権尊重といった観点からは前向きな取り組みにも見えますが、一方で現場や家族からは「地域だけで本当に支えられるのか」という強い疑問も投げかけられています。
強度行動障害と入院対象外方針の背景
強度行動障害とは、知的障害や自閉症のある人に見られる自傷行為や極端なこだわり、睡眠の乱れ、異食といった行動が頻発する状態を指します。
現在、国内には数万人規模で該当者がいるとされ、障害者施設での受け入れが困難な場合、精神科病院に長期入院せざるを得ないケースもあります。
厚労省がこうした人たちを「入院対象外」としようとしている背景には、精神科病床の削減方針があります。つまり「病院ではなく地域で支える社会」を目指しているのです。
しかし、在宅で家族が24時間対応する現実を考えると、訪問看護だけで支えきれるのか不安の声は根強いです。
例えば、暴力的な行動や夜間の不眠などに対して短時間の訪問看護で十分な支援ができるのかは、まだ具体的な見通しが示されていません。こうした議論が今、精神科医療をめぐって熱を帯びています。
2.強度行動障害とは何か
定義と判定基準
強度行動障害は、日常生活に大きな影響が出るほど行動上の困りごとが続いている状態を指します。
対象になるのは主に知的障害や自閉スペクトラム特性のある人で、「困りごと」の強さや頻度を点数化して判断します。
判定では、たとえば「自傷がどのくらいの頻度で起きるか」「夜間にどれくらい眠れているか」「同じ行動への強いこだわりがあるか」などをチェックし、合計点が一定以上(例:24点中10点超)で該当とされます。
具体的には、家族や支援者が1週間の様子を振り返り、起こった行動を記録。医療や福祉の担当者が一緒に評価して、「どの場面で」「どのくらいの強さで」困りごとが出るのかを可視化します。
これにより、支援の優先順位(安全の確保/睡眠の調整/日中活動の整えなど)を決めやすくなります。
行動特徴(自傷・異食・こだわりなど)
現場でよく見られる行動としては、以下のようなものがあります。
- 自傷行為:頭を打ちつける、皮膚を噛む・引っかくなど。痛みや不安、感覚の過敏さが背景にあることも多いです。
例)夕方の騒がしい時間帯に耳をふさぎながら頭を叩く。静かな部屋に移ると落ち着く。 - 異食:食べ物ではないものを口に入れる。感覚刺激を求める行為や不安の高まりがきっかけになることがあります。
例)衣類のタグをかじるので、タグを外す・代わりに口寂しさを満たす咀嚼グッズを用意する。 - 強いこだわり:同じ順番・同じ道順・同じ容器でないと不安が高まる。
例)通所先へ行く道が工事で通れないとパニックに。視覚的に「別ルートの地図」を示して事前に練習すると通過できる。 - 睡眠の乱れ:夜間覚醒や早朝覚醒が続き、昼夜逆転になる。
例)夕方以降の刺激(明るい照明、ゲーム)を減らし、寝る前のルーティン(ぬるめの入浴→静かな音楽→就寝)を固定する。 - 他害・物壊し:混雑や予定変更など、環境の負担が重なると起きやすい。
例)スーパーの混雑が苦手 → 利用時間を朝一に変更/ノイズを減らすイヤーマフを使用。
どの行動も“本人が困っているサイン”であり、叱責や力で止めるだけでは長続きしません。環境を調整し、安心できるやり方を一緒に探すことが土台になります。
支援が必要とされる理由
強度行動障害では、安全の確保と生活の安定を同時に進める必要があります。家族だけで24時間対応し続けるのは現実的ではなく、次のような理由から専門的な支援の仕組みが欠かせません。
- 命と健康を守るため:自傷や夜間の徘徊、誤飲などはすぐに危険につながります。短時間でも専門職が入ることで、事故のリスクを下げられます。
例)入浴中の見守り方法や、誤飲を防ぐ収納の工夫を訪問時に一緒に確認。 - 家族の“休む権利”を守るため:慢性的な夜間対応や力仕事は、介護者の体調不良や離職につながります。
例)週末だけ短期入所を利用し、家族が睡眠を確保。翌週のトラブルが減るケースは少なくありません。 - “うまくいくやり方”を積み重ねるため:薬だけに頼らず、環境・コミュニケーション・活動量の調整を繰り返し試すことで、行動の安定が進みます。
例)「待つ時間に不安定化→視覚スケジュールで“あと5分”を見える化」「外出前に好きな曲を1曲だけ聴く」など、再現可能な工夫を蓄積。 - 地域で暮らし続けるため:学校・福祉事業所・医療機関・自治体が同じ地図を持ち、役割分担を決めることで、入院が“最後の安全弁”として機能します。
例)月1回の合同カンファレンスで、通所先からの気づき(混雑回避の時間帯)や、訪問看護の所見(入眠儀式の効果)を共有し、支援計画を更新。
こうした理由から、「判定→支援メニュー化→定期見直し」という流れを地域で回し続けることが、本人の安心と家族の持続可能性の両方を支える鍵になります。
3.現場からの声と課題
精神科医・専門家の見解
現場の医師や研究者は、「入院以外の選択肢を増やす方向性」そのものには賛同しつつも、地域で支えるための中身がまだ足りないと指摘します。
たとえば、強いこだわりや自傷が続く人を支えるには、短時間の訪問だけでなく、日中の活動先・短期入所・夜間の相談窓口がひとつの計画としてつながっている必要があります。
具体例:退院直後の3か月は、週3回の訪問看護(夕方)、週5日の通所、月2回の家族面談、必要に応じた週末ショートステイを“セット”で提供。さらに、支援がうまく回らない時に即日調整できる連絡網(担当医、訪問看護、通所、家族)が機能することが重要だと述べられます。
家族や支援者が抱える負担
家族の負担は想像以上に重く、夜間の覚醒対応や身体介助、見守りの連続で睡眠不足になりやすいのが実情です。支援者(学校や福祉事業所のスタッフ)も、予定変更や感覚過敏に伴う行動の変化に毎日向き合います。
具体例:
- 平日は母親が深夜2時まで見守り、父親が2時〜6時を担当。仕事のパフォーマンスが落ち、離職が現実味を帯びる。
- 通所先では、混雑時間帯の外出で不安定化。「買い物は開店直後」「イヤーマフを常備」などの工夫が効果的だったが、家族だけでは発想しにくかった。
こうした背景から、家族には“休む権利(レスパイト)”を計画的に保障し、支援者には実地研修や緊急時のバックアップを確実に用意することが求められます。
施設整備・地域連携の必要性
地域で暮らしを支えるには、使える資源の層を厚くすることが前提です。訪問看護の拠点だけでなく、短期入所のベッド、夜間も相談できる窓口、行動面に詳しい専門職(行動支援、作業療法、言語・心理)の配置が欠かせません。
具体例:
- 週末に不安定化しやすい家庭のため、金曜夕〜日曜夕のショートステイ枠を地域で確保。月1回は家族まるごと休める日を固定。
- 月1回の定期カンファレンス(医療・福祉・教育・家族)で「うまくいった工夫」を共有し、支援計画を小さく更新。
- 市区町村は、相談支援専門員のコーディネートに加え、緊急時の“駆け込みベッド”や送迎支援を備える。
薬で行動を抑えるだけでは長続きしません。環境調整・コミュニケーション支援・活動設計を組み合わせ、入院は「安全を守る最後のカード」として機能させる――そのための施設整備と連携の仕組みが、地域全体で急ぎ整えたい課題です。
認知症の行動障害(BPSD)は対象になるのか?
障害を持つ子の親の問題だけでなく、高齢者の親を持つ者にも将来、親が認知症になった場合を想定する必要があります。認知症による行動障害が家庭で介護できなくなった場合はどうなるのでしょう?
厚労省が今回示した「精神科入院の対象外とする方針」で中心に議論されているのは 強度行動障害(知的障害や自閉スペクトラムのある方に多い行動特徴) ですが、実は「認知症に伴う行動障害(BPSD=周辺症状)」も密接に関わってきます。
- 急性期の場合は入院対象
認知症で幻覚や妄想が強く出て、自傷や他害の危険が高いとき、または急に生活が成り立たなくなったときは、精神科入院の対象になります。これは「本人と周囲の安全を守るために一時的に必要」という考え方です。 - 慢性期・長期は対象外に近づく
しかし、長期間にわたり落ち着かない行動(徘徊・夜間不眠・暴言など)が続く場合は、精神科病院ではなく、介護保険サービス(特養・グループホーム・小規模多機能型施設など)や、在宅+訪問看護・ショートステイで支える方向にシフトさせたい、というのが国の方針です。

現場での課題
- 実際には「介護施設で対応困難」として精神科病院に入院しているケースが多いのが現状です。
- 家族も夜間の徘徊や幻覚への対応に疲弊し、施設も人手不足から受け入れを拒むことが少なくありません。
- そのため、「認知症の行動障害を精神科で長期に預かってもらう」という現実があり、今回の方針がその受け皿不足をさらに浮き彫りにしています。
まとめると
- 認知症による行動障害(BPSD)は 急性期は入院対象、しかし 慢性期は地域や介護サービスで支えるべき という方針です。
- ただし、現場では介護サービスが追いつかず、精神科病院に長期入院せざるを得ないケースが多数あります。
- 結果として「理念と現実のギャップ」が、強度行動障害と同じように認知症の分野でも大きな問題になっています。
強度行動障害と認知症の行動障害(BPSD)の違い
| 項目 | 強度行動障害 | 認知症に伴う行動障害(BPSD) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 知的障害・自閉スペクトラムのある人 | 高齢者(アルツハイマー型など認知症の方) |
| 行動特徴 | 自傷(頭を叩く・噛む)/異食/強いこだわり/睡眠障害/他害・物壊し | 徘徊/暴言・暴力/幻覚・妄想/昼夜逆転/拒食・過食 |
| 原因背景 | 感覚過敏・不安・環境変化への対応困難 | 脳の変性による認知機能の低下・混乱 |
| 判定方法 | 行動チェックリストで点数化(例:24点中10点以上で該当) | 診断後に症状の有無を観察(BPSDは診断基準に含まれないが臨床的に評価) |
| 入院対象 | 急性期のみ(強い自傷・他害のリスクがあるとき) → 慢性期は地域支援へ移行方針 | 急性期は対象(安全確保や身体合併症治療が必要なとき) → 長期は介護施設や在宅支援を基本 |
| 主な支援 | 精神科訪問看護・短期入所・通所支援・家族レスパイト | 介護保険サービス(特養・グループホーム・デイサービス)・訪問介護・訪問看護 |
| 現場の課題 | 受け入れ施設不足/家族の24時間対応負担/専門職不足 | 介護現場の人手不足/精神症状の強い人の受け入れ拒否/家族の介護疲れ |
まとめ
厚労省が示した方向性は、「長期入院で暮らしを支える」から「地域の仕組みで暮らしを守る」への転換です。
強度行動障害は“問題行動”ではなく“助けを要するサイン”であり、判定→支援メニュー化→定期見直しを地域全体で回すことが要になります。
そのためには、訪問看護の拠点強化だけでなく、短期入所・日中活動・夜間相談・家族の休息(レスパイト)をひとつの計画に束ね、月1回の合同カンファレンスで小さく更新していく運用が不可欠です。
薬だけに頼らず、環境調整とコミュニケーション支援を組み合わせることで、入院は“最後の安全弁”として機能します。現場の不安(家族の過負担、夜間対応、受け皿不足)を直視し、使える資源の層を厚くすることが、制度を実体化させる最短ルートです。
明日からできるミニチェックリスト
- 判定の“見える化”:1週間の行動記録(自傷・睡眠・こだわり・誘因)を家族と支援者で共有
- 支援の束ね方:訪問看護(夕方)+通所(平日)+週末ショートステイ+夜間相談の連絡網を一本化
- 家族の休む権利:月1回“家族がまるごと休める日”を先にカレンダーに固定
- 環境調整の基本セット:視覚スケジュール/イヤーマフ/混雑回避の時間帯/就寝ルーティン
- 月例カンファレンス:うまくいった工夫を1個ずつ採用し、次月の目標を“小さく具体的”に設定(例:「入眠まで30分短縮」)
合言葉は「面で支える」。拠点化した訪問看護をハブに、医療・福祉・教育・家族が同じ地図で動けば、入院に頼らない安心の土台は現実になります。
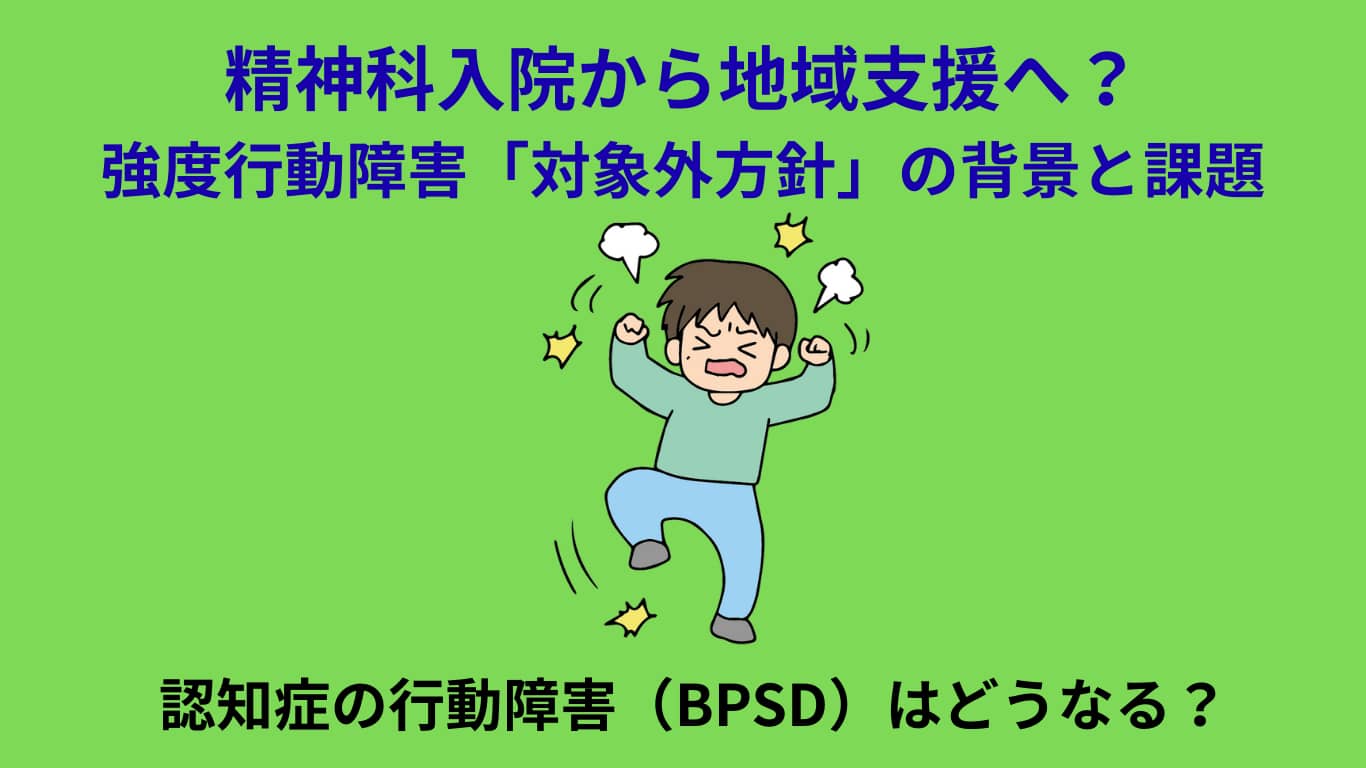
コメント