2025年8月22日、神戸市の22歳職員が診断書や領収書を偽造し、合計55日の虚偽休暇で懲戒免職となりました。併せて同僚の財布からの窃取で停職処分も公表され、2,000件超の反応が集まっています。
本記事では、発覚の流れや市の声明をやさしく整理し、「なぜ起きたのか」「私たちの暮らしに何が起きるのか」を、チェック体制や再発防止の具体例とともに解説します。
はじめに
事件の要旨と配信日時(2025年8月22日)
2025年8月22日(金)15:32、神戸市の22歳の女性職員が、医師の診断書や病院の領収書を偽造して休暇を申請し、合計55日間も仕事を休んでいたとして懲戒免職になった、というニュースが配信されました。
配属は行財政局の税務部で、上司が産業医に相談するため書類を確認したところ、不自然な点が見つかり発覚したとされています。
本人は当初「偽造していない」と説明していたものの、市は「公務員のみならず社会人としてあるまじき行為」として、最も重い処分を決定しました。
同時に、垂水区の男性職員が同僚の財布から合計1万5千円を盗んで停職3カ月となった事案も明らかになり、コメント数が2,000件超にのぼるなど大きな反響を呼んでいます。
具体的には「55日間もどうやって見逃されたのか」「税金で成り立つ職場でのルール違反は許されない」といった声が目立ちました。
本記事の焦点:公務員の不正行為が市民の信頼に与える影響
本記事では、「なぜ一人の不正が、職場だけでなく市民生活にも響くのか」をやさしく解きほぐします。
たとえば、税務窓口での相談が長引いたり、還付の確認に時間がかかったりすると、日々の暮らしに小さな不便が積み重なります。
「証明書は本物か」を必要以上に疑われる空気が生まれれば、正しく休むべき人まで肩身の狭い思いをします。
また、公務員への信頼は「税金を安心して預けられるか」と直結します。
今回のような偽造や窃盗が続けば、「役所は大丈夫なのか」という不安が広がり、真面目に働く多くの職員まで疑われかねません。
本記事では、具体例(休暇の申請手順の見直し、抜き打ち確認のやり方、窓口での説明の仕方など)を交えながら、信頼を取り戻すためにできる現実的な手立てを考えていきます。
1.神戸市職員・虚偽休暇と懲戒免職の全体像
虚偽休暇55日と診断書・領収書の偽造手口
対象となったのは、神戸市・行財政局税務部法人税務課に所属する22歳の一般職員です。
2023年度から2024年度にかけて、健康支援休暇や病気休暇を取るために、医師の診断書や病院の領収書を偽造して申請を繰り返し、結果として55日間も欠勤していました。
偽造といっても特別な専門技術が必要とは限りません。
たとえば、①ネットで拾った書式に自分の名前を打ち込む、②実在の領収書画像の金額や日付をスマホで書き換える、③同じ印影(ハンコの模様)を何度もコピペする――といった、素人でも思いつく方法が使われがちです。
実際に偽造書類では、フォントの大きさが診療科名だけ微妙に違っていたり、領収金額と点数の整合が取れていなかったり、QRコードが読み取れないなど“細部のズレ”が手掛かりになります。
「55日」もの休暇が取れてしまった背景には、書類を“信じること”を前提に回る日常業務があります。
担当者は、提出された診断書が本物かどうかを毎回医療機関に確かめるわけではありません。だからこそ、形式上もっともらしい書類がそろっていると、最初の関門は通ってしまいます。
発覚の経緯:上司の疑義と産業医相談による書類精査
不自然なほど休む日が増えたため、上司は「念のため産業医にも相談しよう」と考え、申請一式を見直しました。
ここで、日付や金額の並び、印影の形、病院の名称表記など、いくつかの“よくある引っかかり”が見つかります。
たとえば、別日付なのに同じ領収書番号が続いている、病院名の正式表記が院の看板と違う、日曜診療が無いはずの病院の発行日が日曜日になっている――といった点です。
上司は、産業医と相談しながら事実確認に必要な範囲で関係部署と連携し、申請履歴を時系列で洗い直しました。
提出書類の画像データを拡大して余白のにじみや境界線の不自然さを確かめ、同じ印影の“使い回し”の可能性もチェックします。
本人からは当初「偽造していない」という説明がありましたが、書類上の矛盾は解けず、最終的に市は「公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為」として懲戒免職を決定しました。
こうした流れは、どの現場でも起こり得ます。だからこそ、申請が集中する繁忙期でも、最低限の“おかしさサイン”を見逃さない仕組みづくりが欠かせません。
2.派生事案と組織リスクの分析
併発事案:同僚の財布から計1万5000円窃取・停職3カ月
同じ発表の中で、垂水区の男性一般職員が2023年6月~10月にかけて、同僚の財布から2回にわたり合計1万5000円を抜き取っていたことも公表されました。
発覚は「ことし1月」。上司との別件の会話の中で本人が2023年の行為を口にし、事実関係の確認につながったとされています。本人は「財布が落ちていて、1万円札が多く入っていたので1枚取ってもばれないと思った」と説明したとのこと。
職場で起きる窃取は、派手な犯行ではなく「ふとした油断」を突く形で起きがちです。たとえば、
- 昼休み、会議室の椅子にかけた上着のポケットに財布を入れっぱなし
- ロッカーのカギを同僚と“とりあえず共有”してしまう
- デスク周りの来客が多いのに、置きっぱなしのバッグを死角に置く
といった、ごくありふれた状況が引き金になります。金額が少額でも、被害者は長く不信感を抱きますし、周囲の士気も下がります。今回のように「停職3カ月」という処分は重く感じられるかもしれませんが、被害が金銭だけにとどまらず、職場の空気やチームワークを傷つける点を考えると、組織として見過ごせない行為です。
内部統制の脆弱性:勤怠・証憑の真正性確認の穴
2つの事案に共通するのは、「忙しさ」と「信頼」を前提にした運用が、確認の目を甘くしてしまう点です。具体的には次のような“穴”が見受けられます。
- 書類の丸のみ:診断書や領収書は「医療機関の書式だから大丈夫」と思い込み、発行日の曜日や領収書番号の連番、印影の不自然さを見落とす。
- 単独承認の偏り:休暇や経費の承認が特定の担当者に集中し、体調不良や繁忙期にはチェックの深さが日によってブレる。
- 記録の分散:勤怠システム、紙の申請、メール連絡などがバラバラで、後から時系列を追うのに手間がかかり、矛盾点の発見が遅れる。
- 私物管理の曖昧さ:個人ロッカーの鍵管理や来庁者の導線管理が曖昧で、財布やスマホなど小物の保管が自己流になりがち。
たとえば、休暇申請のピーク(年度末・長期連休前)に、提出物の画像ファイルをそのまま受け付け、原本の提示や医療機関名の正式表記まで確かめない、といった運用は珍しくありません。
また、フロアの入退室管理が「名札の色で見分けるだけ」といった簡易ルールだと、来庁者や業者の出入りが多い日にはデスク周りの見張りが手薄になります。
こうした“穴”は、誰か一人の注意不足ではなく、仕組みの組み合わせで生まれます。だからこそ、チェックの目を増やす工夫(例:二重承認やランダム抽出の確認)や、証拠の扱い方をそろえる工夫(例:原本提示のルール化、提出物のチェックリスト化)が、次の一歩になります
3.世論の反応と専門家の見解
主なヤフコメ傾向:厳罰支持・不心得者への怒り・真面目な職員への感謝
今回のニュースには2,000件を超える反応が集まり、目立ったのは「厳しい処分を支持する」という声でした。
理由はシンプルで、①診断書や領収書の“偽造”は偶然のミスではなく意図的な行為、②公費(税金)で成り立つ職場の信用を傷つける――この2点が大きいからです。
実際のコメント傾向をかみ砕くと、次のような具体例が並びます。
- 「55日も通ったのが信じられない」:仕組みの穴を心配する声。
- 「偽造は悪質。最も重い処分は当然」:処分妥当論。
- 「大半の公務員は真面目。少数の不心得者が足を引っ張る」:現場へのエールと同時に、再発防止の期待。
- 「被害は市民にも及ぶ」:窓口の遅れや、正当な休暇への疑いの目など“二次被害”への懸念。
こうした反応は、単なる私刑感情ではなく、「公的サービスの安心をどう守るか」という生活感覚に根ざしています。だからこそ、処分だけで終わらせず、手続きの点検結果や改善策を市民向けにわかりやすく発信することが、信頼回復の近道になります
「公務員の世界は弛んでいる」vs「意欲ある職員もいる」二極化の視点
コメント欄では、「チェックが甘い=組織全体が弛んでいる」という見方と、「忙しい現場でも踏ん張っている職員は多い」という評価が並びました。どちらにも生活者としてうなずける理由があります。
たとえば、弛んでいる派は、「原本確認をせず画像で受け付ける」「同じ承認者に手続きが集中して見落としが出る」といった“運用の甘さ”を問題視します。
一方で、意欲ある職員派は、災害時の窓口増設や確定申告期の延長対応、困りごと相談の付き添いなど、現場の粘り強い対応を経験的に知っています。
二つの見方を橋渡しするには、感覚論ではなく見える化が有効です。
- 手順の公開:休暇申請の確認項目(発行日の曜日、領収書番号、印影の一致など)を市民にも示す。
- 抽出検査の導入:税金と同じく“抜き打ち”でチェックする仕組みを宣言し、実施状況を四半期ごとに公表。
- 現場の努力を伝える:繁忙期の応援体制や窓口の改善例を広報に載せる。
危機管理の専門家からも、今回のような偽造は悪質性が高く、抽出検査が抑止に効くとの指摘があります。処分の厳格化と、現場の支え方の両輪を同時に回すことが、市民の「役所は大丈夫」という安心感につながります。
まとめ
今回の一件は、「偽造書類で55日欠勤」と「同僚の財布からの窃取」という、性質の異なる2つの不正が同時に露出したことが大きな衝撃でした。
共通点は、忙しさに紛れて“書類を信じる”“人を信じる”運用が続き、最低限の確認が抜け落ちたこと。市民の信頼を取り戻すには、処分で終わらせず、日々のやり方を具体的に変えることが近道です。
たとえば次のような手当ては、どの職場でも今日から実行できます。
- 原本確認+簡易チェック表の徹底
発行日の曜日、病院名の正式表記、領収書番号の連番、印影の一致、QRコードの読取可否――“見るポイント”を1枚のチェック表に。画像提出のみは原則不可、原本提示を基本に。 - ランダムな抜き打ち確認の導入
月に数%でもよいので、提出書類を無作為抽出して深掘り確認。「抽選で確認する」こと自体が抑止力になります。結果は四半期ごとに件数だけ公開。 - 二重承認で“見落とし”を分散
所属内の承認で終わらせず、別部署の目も通す。繁忙期は臨時の承認サポート班を設け、1人に負担を集中させない。 - 記録の一本化
勤怠、申請書、メールのやり取りを同じ台帳(一覧)に時系列でひもづけ。後追いの点検が一気に楽になります。 - 私物管理のルール明文化
鍵付きロッカーの配備、鍵の貸し借り禁止、席を離れる時はバッグを持ち歩く、来庁者の導線から死角を作らない――を“当たり前の約束”として周知。 - 匿名で相談できる窓口の周知
早期相談が一番の予防。「報告者に不利益なし」をはっきり掲示し、連絡方法を庁内ポスターやイントラで常時表示。 - 市民向けの“見える化”
休暇申請で何を確認しているか、抜き打ち確認をいつどれくらい実施したかを、図解で公開。透明性は不信感の鎮静剤になります。 - 正しく休める環境も同時に整える
病欠の申請手順をやさしい言葉でまとめた案内、上司面談のフォロー体制、過度に疑う言動を控えるルールづくり。真面目に働く多くの職員を守ることが、結果的に不正の芽を摘みます。
“厳正な処分”と“日々の運用改善”は車の両輪です。小さな確認を積み重ね、結果を市民にわかりやすく伝える――その地味な繰り返しこそが、「役所は大丈夫」という安心感を少しずつ取り戻していきます。
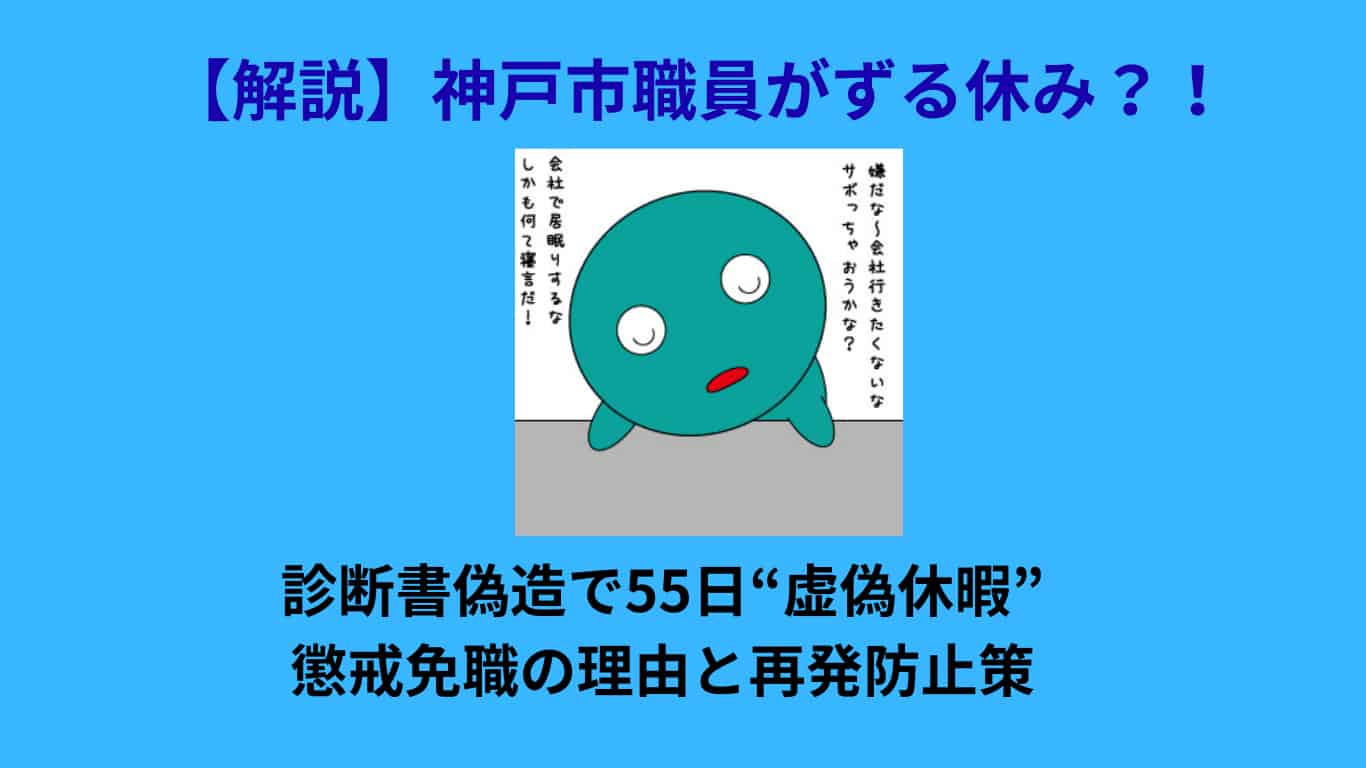
コメント