政府が長年続けてきた減反政策を終わらせ、コメの増産に舵を切りました。
背景にはコメ不足や価格高騰がありますが、現場の農家からは「高齢化で担い手が足りない」「急な増産は難しい」といった声があがっています。
本記事では、この政策転換の背景、農家や流通現場の実情、そして今後の日本農業の課題をわかりやすく解説します。
はじめに
政府の米政策転換の背景
長年、日本ではコメの生産量を調整するために「減反政策」が続けられてきました。
これはコメが余って価格が下がることを防ぐ目的で行われ、農家は水田の一部を休耕地にすることで補助金を受け取ってきました。
しかし、ここにきて政府は一転、「コメ不足」を認め、増産を呼びかけています。
この急転換の背景には、天候不順や需要の変化、流通の停滞といった複数の要因が重なり、消費者の食卓に並ぶコメの価格が高騰したことがあります。
現場からあがる怒りと困惑
今回の政策変更は、農家や流通業者に大きな戸惑いを与えています。たとえば、鹿児島県のコメ農家では「高齢化で担い手がいない」「荒廃した農地をすぐに復活させるのは難しい」といった声が上がっています。
また、創業100年を超える米店では「店頭に十分なコメを並べられない」「そもそもコメ不足は以前から感じていた」と不満を漏らしています。
現場の実情を無視した急な政策転換に対し、怒りや不安が広がっているのです。
1.減反から増産へ 急転換の経緯
長年続いた減反政策とは何だったのか
減反政策は、コメの作りすぎによる価格下落を防ぐため、1970年代から始まりました。
農家は水田の一部を休耕地にし、その見返りとして補助金を受け取る仕組みです。
結果として、生産量は安定し、米価はある程度守られてきました。
しかし長年の実施により、一部の農地は耕作をやめたまま荒廃し、農業機械や施設の規模も縮小されたままになっていました。こうした背景が、今回の急な増産指示に対応できない理由のひとつとなっています。
コメ不足を認めた政府の説明
政府はこれまで「国内のコメは足りている」と説明していましたが、2025年夏、ついにその見通しの誤りを認めました。
天候不順による収量低下や物流コストの上昇、外食需要の回復など複数の要因が重なり、コメ不足と価格高騰を招いたのです。
石破総理は「生産量の不足があったことを真摯に受け止める」と発言し、方針を転換。減反政策を事実上終了させ、増産を進める考えを示しました。
価格高騰と市場への影響
この方針転換の背景には、消費者の生活への影響もあります。店頭価格は1年で10〜20%上昇し、特に地方の小規模なコメ店では「仕入れ価格が高く、店頭に並べる量を制限せざるを得ない」という声が出ています。
片岡米穀店のように100年以上続く店でさえ十分な量を確保できず、常連客に謝りながら対応する状況です。こうした現場の混乱が、急な増産方針への不安と不満を一層強める結果となっています。
2.現場農家と流通業者の苦悩
高齢化で担い手不足が深刻化
現在、日本の農業現場では高齢化が進み、コメ作りの担い手が不足しています。
鹿児島県伊佐市のコメ農家・亀割浩介さんは「増産と言われても人がいない」と語ります。
地域の多くの農家は70代、80代が中心で、若い後継者が少ないのが現状です。過去に減反政策で農地を休ませた結果、そのまま荒れてしまった田んぼも多く、今から耕作を再開するには人手も時間もかかります。
この担い手不足が、増産指示にすぐ対応できない大きな理由になっています。
設備投資リスクと農家の戸惑い
コメを増産するには、田植え機や乾燥機などの設備を増やす必要があります。
しかし、これらは高額で、規模を広げるためには数百万円単位の投資が必要です。しかも、今後の価格が下がれば投資を回収できなくなるリスクもあります。
ある中部地方の農家は「設備をそろえても来年余ったら意味がない」と不安を口にしています。長年の減反政策で小規模経営に慣れた農家にとって、急な大規模化は非常にハードルが高いのです。
コメ店・流通業者の不安と課題
流通業者や米店も、急な増産方針に戸惑っています。
創業100年を超える片岡米穀店では「仕入れ価格の上昇で十分な在庫を確保できない」と悩んでいます。
さらに、仮に増産でコメが一気に市場に出回った場合、今度は価格が暴落し、在庫を抱えた業者が大きな損失を被る恐れがあります。
現場では「今は足りないが、将来余るのでは」というジレンマを抱え、先行きの見えない状況が続いているのです。
3.増産政策の将来と懸念
供給過多による価格崩壊リスク
政府が呼びかける増産が進めば、一時的なコメ不足は解消される可能性があります。
しかし、その後に供給過多となれば価格が急落し、農家の経営を直撃する恐れがあります。
過去にも、豊作の年に米価が大幅に下がり、農家が赤字に転落する事例がありました。
片岡米穀店の店主も「やりすぎれば、またコメ余りになる」と懸念を口にしており、現場は将来的なリスクに敏感になっています。
日本産米輸出の限界と課題
余ったコメを輸出で捌くという考え方もありますが、これには課題があります。
日本産米は高品質で人気がありますが、その分コストが高く、海外市場では価格競争力に欠けます。
例えばアジア諸国ではタイ米やベトナム米が主流で、日本産米は高級品として限られた層にしか売れません。
さらに輸出体制の整備や販路開拓にも時間がかかり、すぐに解決策となるわけではないのです。
農家の意欲を支える政策の必要性
長期的に安定した米生産を続けるには、農家が安心して生産に取り組める環境が不可欠です。
小泉農水大臣は「一律で増産を求めない」としつつ、農家の意欲を高める支援を強調しました。
例えば担い手育成のための教育支援や、設備投資への補助金、販路拡大のための輸出サポートなどが考えられます。農家が未来を描ける仕組みを作らなければ、今回の政策転換も一時的な対応で終わってしまうでしょう。
まとめ
政府が長年続けてきた減反政策をやめ、一転して増産を求めた今回の方針転換は、現場に大きな混乱をもたらしています。
農家は高齢化と担い手不足に直面し、設備投資を伴う急な増産には対応しづらい状況です。
さらに、増産による供給過多が価格崩壊を招く可能性や、輸出拡大の難しさといった長期的課題も残っています。
一方で、小泉農水大臣が語ったように「農家が意欲を持てる環境整備」は希望の光でもあります。
担い手育成や設備投資支援、輸出体制の強化などを組み合わせ、農家が安定して生産できる仕組みをつくることが重要です。
今回のコメ不足と急転換は、日本の農業政策全体を見直すきっかけとも言えるでしょう。
消費者もまた、コメを当たり前に食卓で楽しむために、農業を支える社会の仕組みに目を向ける時期に来ています。
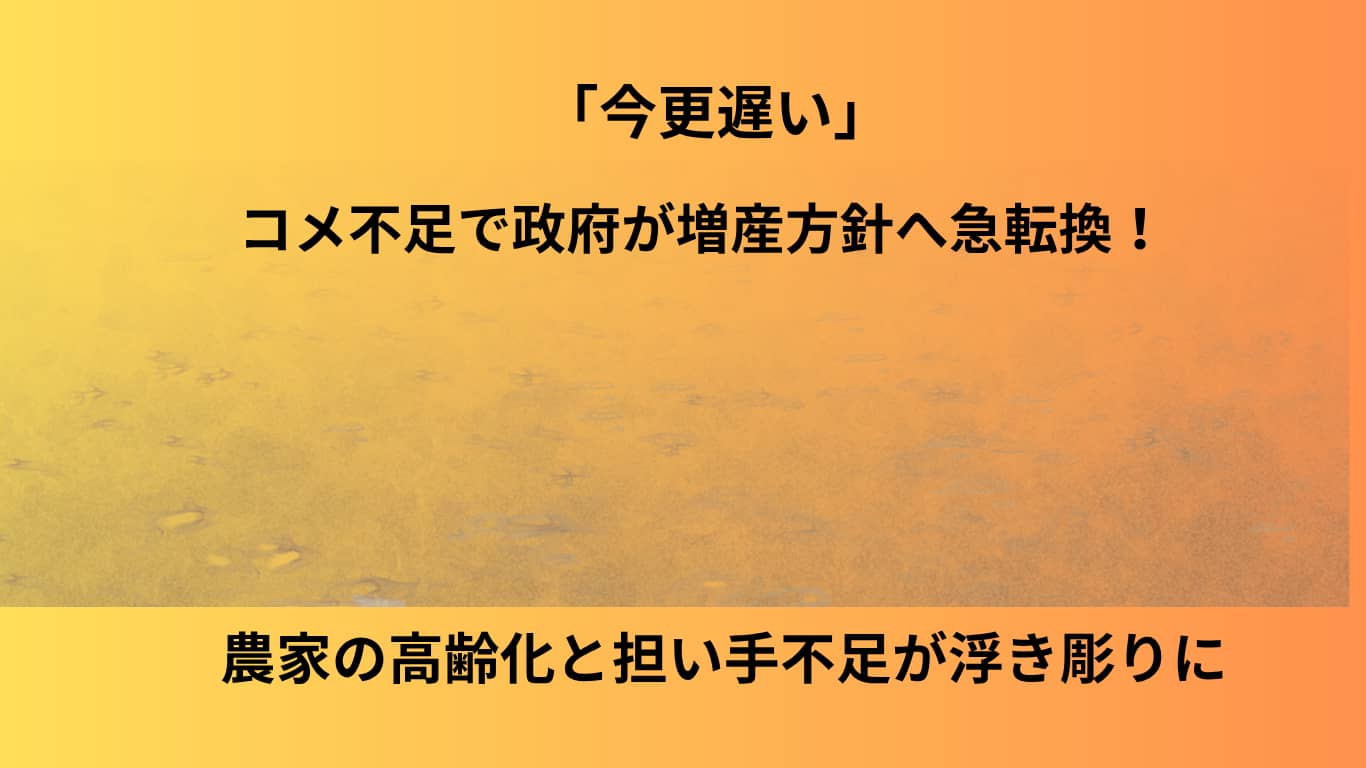
コメント