山口県の瀬戸内海に浮かぶ笠佐島で、中国資本による土地取得が進み、島民の不安が高まっています。
別荘目的とされる土地利用は一見平和的に見えますが、近くには海上自衛隊呉基地や米軍岩国基地など安全保障上重要な拠点もあり、懸念は深刻です。
本記事では、笠佐島での中国資本の動向だけでなく、外国人土地法の廃止に至る歴史的経緯や、現在の土地規制法制の課題をわかりやすく解説します。
はじめに
中国資本による日本不動産買収の現状
近年、中国資本による日本国内の不動産買収が各地で話題になっています。
特に自然豊かな地域や観光地にある土地が注目され、別荘や投資目的で購入されるケースが増えています。
山口県の瀬戸内海に浮かぶ笠佐島もそのひとつです。
この島では中国人による土地取得が行われ、林道が整備され電柱が敷かれるなど、生活環境の整備が進んでいます。
島民からは「このままでは島全体が中国資本に占められてしまうのではないか」という不安の声も上がっています。
瀬戸内海・笠佐島が注目される理由
笠佐島は周防大島の小松港から約2キロの距離にあり、自然豊かで静かな環境が魅力の島です。
周辺には海上自衛隊呉基地や旧陸軍の砲台跡など歴史的・戦略的に重要な施設が点在し、潜水艦や護衛艦が日常的に行き交います。
こうした場所に別荘用地を求める中国人が増えており、東京都や埼玉県に住む中国人や中国本土からの視察団が訪れる姿も珍しくありません。
さらに、連絡船でわずか1時間程度で広島市や松山市にアクセスできる便利さも人気を後押ししています。
1.笠佐島で進む中国人による土地取得

購入された土地の概要と規模
笠佐島では、2017年から2018年にかけて中国人3名による土地購入が行われました。
購入されたのは2筆で計3,651平方メートルの土地で、いずれも海に面した場所です。
正面には野島、左側には周防大島が望める風光明媚な立地で、クルーザーや連絡船を係留するのに適した条件を備えていました。
この土地は地元の不動産業者がインターネットに掲載した「分譲情報」をきっかけに問い合わせが入り、複数回の商談を経て売却に至ったといいます。
別荘建設や生活環境整備の進展
購入者は上海で日本企業に勤務した経験のある中国人男性とその家族で、「別荘を建てたい」という理由から土地を取得しました。
実際に林道(町道)が整備され、真新しい電柱が並び、島内での生活環境が整いつつあります。
島の反対側に向かう林道を歩くと、伐採された森林の跡地に重機が置かれ、建設準備が進んでいる様子が見て取れます。
さらに、桟橋を建設したいという希望も語られており、将来的には海を活用した移動やレジャーが想定されていると考えられます。
島民が抱く不安と現地の声
一方で、島の住民の間には不安の声が広がっています。「このままでは島全体が中国人に買い占められるのではないか」「有事の際に外国資本の土地がどう扱われるのか」といった懸念が多く聞かれます。
実際に、都内に住む中国人家族が高級車で訪れ、島内を長時間視察する姿が見られるなど、外部からの関心の高さを実感する機会が増えています。
島民の中には、景観や自然の変化だけでなく、安全保障上の影響を危惧する声も少なくありません。
特に海上自衛隊呉基地や旧軍の砲台跡などが近くにあることから、土地利用の目的や今後の動向に注目が集まっています。
笠佐島とは
笠佐島を含む瀬戸内海エリアの地理的な位置が分かる地図です。山口県・周防大島町の小松港から西へ約2kmに位置する笠佐島の場所が確認できます。

地図を参照しながら、以下の特徴をご理解いただくと内容がより明確になります:
- 笠佐島は、周防大島(屋代島)から西に約2km離れた場所に浮かぶ小さな有人島です。
- 瀬戸内海の中央部に位置し、近隣には広島や山口、香川など複数の県にまたがる島々が点在しています 。
- 瀬戸内海エリア全体が穏やかな海域であることから、観光や別荘地として人気がある一方、米軍岩国基地や海上自衛隊呉基地など、日本の安全保障に関わる主要施設にも近い地域となります。
2.中国資本が瀬戸内海に注目する背景
中国人観光客・別荘購入者の増加
瀬戸内海エリアは、穏やかな海と点在する島々の景観が魅力で、国内外から観光客が訪れる地域です。
近年は特に中国からの観光客が増え、観光目的だけでなく別荘用地を購入する動きも見られます。
笠佐島では、東京都や埼玉県に住む中国人が高額で土地を購入したり、中国本土の大連などから視察に訪れる団体が見受けられました。
こうした背景には、インターネットを通じた不動産情報の拡散や、手軽に船で移動できる瀬戸内海ならではの利便性が大きく影響しています。
中国系不動産業者の仲介と購買パターン
この流れを後押ししているのが中国系の不動産業者です。
東京や大阪で中国人が経営する不動産会社が仲介役となり、中国本土に住む人々へ日本の物件を紹介しています。
笠佐島での土地取引も、地元業者がインターネットに掲載した分譲情報をきっかけに中国から問い合わせを受けたことが始まりでした。
購入者は、かつて日本企業に勤めた経験があるなど、日本への理解があるケースもありますが、投資目的や将来的な開発計画を視野に入れている可能性も指摘されています。
このように、個人の別荘利用から企業的な開発志向まで、購買パターンは多様化しています。
安全保障上のリスクと懸念
しかし、この動きには安全保障上の懸念も伴います。笠佐島は海上自衛隊呉基地や旧軍施設に近く、有事の際の戦略的重要性が高い地域です。
中国では国防動員法や国家情報法により、国内外の中国人や企業が政府に協力する義務を負うとされます。
そのため、平時には観光や別荘利用であっても、将来的に土地がどのように使われるか予測しにくいという指摘があります。
島民からは「気付いたときには島全体が外国資本に占められていた」という事態を懸念する声もあり、こうした不安は瀬戸内海全域に広がりつつあります。
3.日本の法制度と課題
外国資本に開放された不動産取引の現状
日本では、外国人が土地や建物を購入することに大きな制限はありません。
これは1994年に署名した世界貿易機関(WTO)の「サービスの貿易に関する協定(GATS)」によって、日本人と外国人を平等に扱うことが定められた結果です。
そのため、多くの国で導入されている外国人向けの購入制限や追加課税、日本人への転売条件などは日本では存在せず、誰でも同じ条件で不動産を取得できます。
実際に、観光地や過疎地などでの外国人による土地取得は年々増加しており、今回の笠佐島での事例もその流れの一環と言えます。
重要土地等調査法の限界と課題
こうした状況を受け、日本政府は2022年に「重要土地等調査法」を全面施行しました。
この法律は、自衛隊基地や原子力施設、国境離島など安全保障上重要とされる地域の土地や建物の利用状況、所有者を調査できるようにしたものです。
しかし、その調査対象範囲は施設の周囲およそ1キロ圏内に限定されており、調査にとどまるため、土地の取得そのものを制限する実効力はありません。
このため、一部では「ザル法」と批判され、外国資本による土地の買収を根本的に防ぐ手段にはなっていないと指摘されています。
今後必要とされる政策対応
今後は、重要地域における土地取引の透明性を高め、リスクを早期に察知する仕組みづくりが求められています。
たとえば、外国資本が土地を取得する際の事前届け出制度の導入や、軍事拠点や国境離島における外国人の所有制限などが検討課題として挙げられます。
また、地方自治体と国が連携し、現場レベルでの監視体制を整えることも重要です
。笠佐島のような小規模な島では住民の不安を軽減しつつ地域活性化につなげるバランスの取れた政策が求められており、単に規制するだけでなく、観光や交流を活かした地域づくりと並行して進めていく必要があります。
補足:外国人土地法とその施行令廃止の背景
笠佐島での土地取得問題を考える際、過去に存在した「外国人土地法」もよく話題になります。
この法律は1925年に制定され、外国人や外国法人が日本で土地を取得する際に制限を設けられる内容でした。しかし、この法律を具体的に運用するための「施行令」は1945年に廃止され、その後再び制定されることはありませんでした。
なぜ施行令は廃止されたのか?
1945年の敗戦後、日本は連合国軍(GHQ)の占領下に置かれました。
当時のGHQは、戦前の統制的・差別的な制度を改めることを重視しており、外国人の土地取得を制限する施行令は「差別的」と見なされる恐れがありました。
加えて、占領政策の一環として日本経済の自由化と国際的な開放が強く求められ、外国資本を受け入れる体制づくりが進められました。
これにより、施行令は廃止され、日本は土地取引において外国人と日本人をほぼ同等に扱う開放的な制度へと転換したのです。
戦後の占領政策と現在の法制度への影響
この戦後の方針は現在の制度にも影響を残しています。
日本では外国人の土地取得に大きな制限はなく、住宅用地や観光地、さらには今回の笠佐島のような離島においても、外国資本による取得が法的に可能な状態が続いています。
確かに2022年に施行された「重要土地等調査法」によって、自衛隊基地や国境離島周辺での土地利用状況を調査する仕組みは導入されましたが、これはあくまでも“調査”にとどまり、取得そのものを制限する強い規制にはなっていません。
つまり、戦後に形作られた自由主義的な土地制度は、現在でも維持されており、外国資本による土地取得問題の背景にはこの歴史的経緯が色濃く影響しているのです。
まとめ
笠佐島で起きている中国資本による土地取得は、瀬戸内海全体で広がりを見せる動きの一部に過ぎません。別荘や観光目的といった平和的な利用が前提とされているものの、海上自衛隊基地など戦略的に重要な地域に近いことから、不安の声は根強く残っています。
日本は外国人が土地を購入することをほとんど制限しておらず、世界的に見ても開放的な制度を持っています。しかし、この制度は安全保障上のリスクを伴い、現在の「重要土地等調査法」では十分な歯止めがかかっているとは言えません。
今後は、外国資本の土地取得に対する監視体制を強化し、地域住民の不安を軽減しつつ、地域活性化と両立できる政策を検討することが求められます。笠佐島の事例は、日本が今後どのように土地管理や安全保障に取り組むべきかを考える重要なきっかけとなっています。
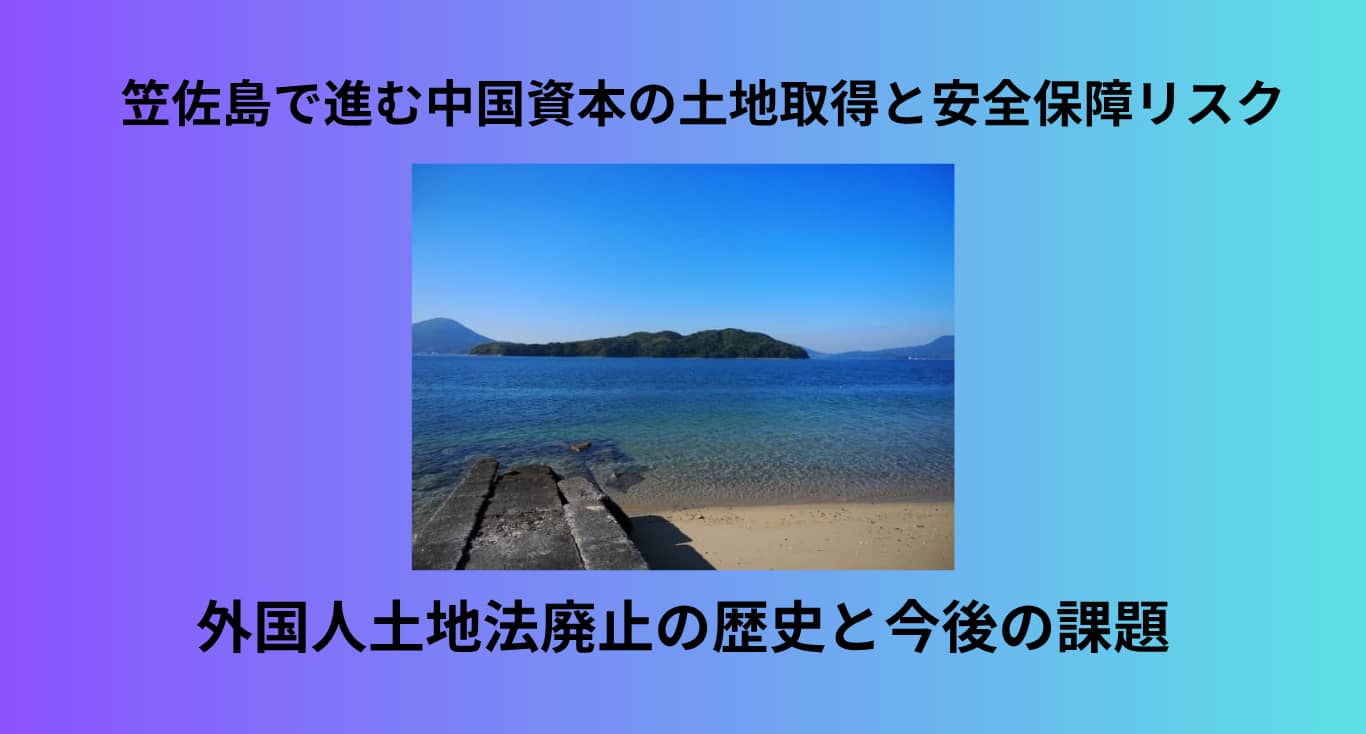
コメント