「かかりつけ医って、こちらが勝手に決めてもいいの?」——SNSで話題になったこの疑問、私も同じところでつまずきました。
実は“登録して固定”ではなく、日常の不調や薬の調整、検査結果の相談を継続してお願いできる身近な先生のことを指します。
さらに2025年からは、各医療機関の体制が「かかりつけ医機能」として公表され、普段の診療(1号機能)や時間外・在宅対応(2号機能)の有無が見えやすくなります。
本記事では、まず「かかりつけ医」の基本をやさしく整理し、次に新制度のポイントをチェック。最後に、通いやすさ・話しやすさ・連携体制など、失敗しない選び方のコツを具体例つきで紹介します。
読み終えるころには、「この人に任せたい!」と思える先生を自信を持って選べるはず。今日からあなたの暮らしに合う“頼れる拠点”を一緒に見つけていきましょう!
はじめに
SNSで話題になった「かかりつけ医」投稿とは
私もこの話題をSNSで見てドキッとしました…。最近、「未だによくわかんないんだけど、“かかりつけ医”ってこっちが一方的に決めていいの?」という投稿がSNSで広く共有されました。たとえば――
- 風邪で近所のクリニックに2回行っただけなのに、「うちがあなたのかかりつけです」と言われて戸惑った。
- 花粉症の薬を毎年もらうために同じ医院に通っているけど、正式に“かかりつけ”って名乗っていいのか不安。
- 逆に、別の病院を受診したら「まずはかかりつけ医へ」と言われて困った。
こんな“あるある”が次々と語られ、「どの時点で“かかりつけ”になるの?」という素朴な疑問が一気に可視化されました。
「一方的に決めていいの?」という疑問が生まれる背景
私の周りでも、まさにこういう場面で迷う人が多いです。疑問が生まれる背景には、日常の具体的な場面があります。
- 薬の継続:高血圧やアレルギーなどで同じ薬を出してもらうとき、毎回同じ先生に診てもらう方が安心。でも「まだ数回しか行ってないのに“関係が重い”感じにならない?」と心配になる。
- 紹介状の話:専門外来に行きたいとき、「まずはかかりつけ医に相談を」と案内されがち。そもそも自分の“かかりつけ”が誰なのか曖昧だと、一歩目でつまずきます。
- ライフスタイルの変化:転勤や引っ越し、勤務時間の変更で通い先を変えたいとき、「前の医院に失礼? 新しい所で“初診からかかりつけ”ってアリ?」と迷う。
- 気まずさの不安:「何回か診てもらっただけで“患者ヅラしてる”と思われない?」という心理的ハードル。これは“恋人ヅラ”の比喩がバズった背景でもあります。
本記事の「はじめに」では、このモヤモヤを前提に、読者が等身大でつまずきやすい場面を具体例で共有しました。
以降の章では、そもそも“かかりつけ医”とは何か、近々はじまる“見える化”の仕組み、そして実際にどう選べばいいのかまで、順にやさしく整理していきます。
1.かかりつけ医とは何か

登録制度ではなく「継続的に診てもらう関係」
私自身も最初は「どこかに登録しないといけないの?」と思っていましたが、違いました。 「かかりつけ医」は、役所に登録して“関係が固定される”ものではありません。
実際は、体調の相談や薬の調整、検査の結果説明などを同じ先生に継続してお願いする関係を指します。
たとえば、花粉症の時期だけ毎年同じクリニックで薬をもらう、風邪を引いたらまず近所の内科で診てもらう、健康診断の再検査や生活習慣の相談を同じ先生に続けて相談する――こうした積み重ねで「この先生が自分のことを一番わかってくれている」という状態になります。
ポイントは回数より中身の連続性。2回でも、薬や体調の変化を覚えていてくれて、次に活かしてくれるなら、十分“かかりつけ”に近づいています。
厚生労働省と日本医師会が示す定義と役割
公的な説明でも、私が「なるほど!」と思ったのは、かかりつけ医が何でも最初に相談できる窓口であることです。
- 初期対応:発熱や腹痛など、まずは原因の当たりをつけて必要な検査や治療につなぐ。
- 全体を見る視点:過去の病気、飲んでいる薬、仕事や生活リズムなどを踏まえて無理のない治療を一緒に考える。
- 連携のハブ:専門的な検査や手術が必要なら、適切な病院・科を紹介し、治療後はふたたび日常のケアに戻してくれる。
- 予防と生活支援:ワクチン、健康診断、食事・睡眠・運動の相談、介護や在宅医療の窓口にもなる。
たとえば「血圧が少し高い」「胃の調子が安定しない」といった“グレー”な状態でも、「まず相談する先」として機能してくれるのが、かかりつけ医の大きな役割です。
患者の自由意志で選ぶ「身近な医師」という考え方
ここがいちばん安心したポイントです! 誰を“かかりつけ”にするかはあなたが決めてよいものです。宣言や契約は必須ではありません。
選び方のイメージはシンプルで、通いやすい・話しやすい・説明がわかりやすいが基本軸。たとえば、
- 仕事帰りに寄れる時間帯に開いている。
- 症状の説明を最後まで聞いてくれて、専門用語を噛み砕いてくれる。
- 必要なとき、スムーズに他院を紹介してくれる。
こうした実体験が積み重なり、「困ったらまずこの先生に相談しよう」と思えた時点で、その医師はあなたにとっての“かかりつけ医”と呼べます。
気まずさを心配する必要はありません。あなたの体と生活を守るための“頼れる拠点”を自分で選ぶ――それが、かかりつけ医という考え方です。
2.かかりつけ医機能報告制度の概要
制度の目的と導入時期(2025年4月施行)
制度のニュースを見て、私も「これは助かる!」と思いました。 この制度は一言でいえば、「そのクリニックが“どこまで何ができるか”を見える化する仕組み」です。
これまでは、夜間対応や在宅診療、専門医への紹介体制などがクリニックのHPや口コミだけでは分かりにくく、「行ってみないと実情が見えない」状況がありました。
制度が始まると、医療機関が自院の体制を毎年、都道府県に報告し、整理された情報が住民向けに公表される想定です(施行は2025年4月)。
具体的なイメージ:
- 夜に発熱した子どもを診てもらいたい親御さんが、近隣で時間外の相談窓口がある小児科を探せる。
- 独居の高齢者を支える家族が、在宅医療(訪問診療)に対応できる内科を絞り込める。
- 慢性疾患のフォローを続けたい人が、生活習慣病の継続管理が得意で、必要時に専門病院へスムーズに紹介してくれる医師を選びやすくなる。
つまり、「どの時点で“かかりつけ”になるの?」という不安に対し、“頼れる先を選ぶための客観情報”が増えるのがこの制度のねらいです。
医療機関が報告する「1号機能」と「2号機能」
この分け方も、生活者としてイメージしやすいです。報告内容は大きく二段階に分かれます。専門用語を避けて、ざっくり機能の“中身”で説明します。
① 1号機能(基本セット)
「日常の不調をまず診て、継続して面倒を見る力」があるかを示す項目です。
たとえば:
- 風邪・胃腸炎・花粉症・生活習慣病(高血圧・糖尿病など)への初期対応と継続管理
- 検査結果や薬の調整をわかりやすく説明し、次回へ活かす継続フォロー
- 専門医や病院への紹介ができ、治療後は逆紹介で普段のケアに戻せる連携
例)「○○内科」は、花粉症と血圧管理の両方を定期的に診てくれて、必要な検査は地域の総合病院へ依頼、結果説明は同院で実施――この一連の“面倒見”が1号機能の中心です。
② 2号機能(拡張オプション)
「基本セット」に上乗せされる機能で、生活や緊急時まで視野に入れた体制です。
たとえば:
- 時間外や休日の相談・診療(地域の当番制への参加などを含む)
- **在宅医療(訪問診療・往診)**の提供
- 退院後の生活を支える入退院支援・多職種連携(訪問看護・介護事業所との連携)
- 急変時にどこへ連絡し、どう動くかの案内体制
例)「□□クリニック」は、日中の外来に加えて月・木は19時まで相談を受け、要介護の方には在宅で薬の調整や点滴も対応。入院が必要になれば地域中核病院と連携し、退院後はまた□□で普段のフォロー、という流れを整えています。
ポイントは、1号=“まず診る・続けて診る”の基礎体力、2号=“時間外・在宅・介護まで含めた拡張力”という分け方。
あなたが情報を見比べるときは、ふだんの受診目的に合う1号機能が整っているかをまず確認し、生活や家族事情に応じて2号機能が必要かを検討すると、ミスマッチを減らせます。
3.かかりつけ医を選ぶ基準
通いやすさ・話しやすさ・信頼関係の重要性
私も子育てや仕事の合間に受診することが多いので、ここは超・現実的に見ます! まずは通いやすさ。
体調が悪い日に1時間かけて行くのは現実的ではありません。自宅や職場から徒歩・自転車・通勤動線で行けるかが大切です。
例)「発熱した子どもを抱えてタクシー必須」より、「徒歩10分でベビーカーでも行ける」ほうが続けやすい。
次に話しやすさ。初診で「説明が長くても遮られない」「質問しても嫌な顔をされない」は重要なサイン。
例)腹痛の原因を“ストレス”の一言で終わらせず、食事・睡眠・仕事の状況まで聞いてくれる先生は、次回以降の診療が楽になります。
最後に信頼関係。診断や薬の理由を図や紙にメモして渡してくれる、他の選択肢も示す、迷ったら「いったん様子見」ではなく再診のタイミングを決めてくれる――こうした積み重ねが安心感につながります。
診療の幅・連携体制・継続的サポート
診療の幅は、“よくある不調”をどれだけカバーしているかが目安。風邪・花粉症・胃腸炎・皮膚トラブル・生活習慣病など、日常で起こりがちな相談に一つの窓口で対応できると便利です。
例)花粉症の相談で受診→血圧測定もしてくれ、家庭での計測方法や塩分の目安まで教えてくれた…など。
連携体制は、“必要なときに専門へつなげる力”。画像検査や高度な治療が必要なら、紹介状を即日で用意し、結果が出たら元のクリニックに戻して継続フォロー(逆紹介)――この往復がスムーズだと、負担が減ります。
例)慢性的な肩の痛みで整形外科を紹介→MRI後の説明は元の内科で生活アドバイスも含めて実施、という分担。
継続的サポートは、次回予約や再診の目安を一緒に決めること、検査結果を過去と並べて比較してくれること、体調メモを受け取って見てくれること。
例)「3週間後に血圧手帳を見せて」「体調が崩れたらこの番号に連絡を」など、次の一歩が明確だと続けやすい。
「この人に任せたい」と思えるかどうかの判断軸
最終的には相性です。私もここは妥協しません…! チェックのコツを具体化します。
- 説明のわかりやすさ:難しい言葉を置き換え、メリット・デメリットを1分で要点化してくれるか。
- 選択の尊重:薬を増やす/生活改善を優先する――あなたの価値観に合わせた提案になっているか。
- 再現性:毎回の診察で方針がぶれないか。カルテの情報がきちんと共有され、誰が見ても同じ説明になる体制か。
- 緊急時の道筋:夜間は「#7119(救急相談)」や地域の当番医など、もしもの連絡先を具体的に案内してくれるか。
- 通院ストレス:待ち時間、予約方法(電話・Web・LINE)、決済(カード・QR)、受付スタッフの雰囲気まで含めて無理がないか。
小さな違和感は放置しないでOK。「近いけど説明が早口で伝わらない」より、「少し遠いが納得して帰れる」ほうが、長い目で見ると満足度が高くなります。
迷ったら、風邪・花粉症・健康相談など軽い用件で2〜3回受診し、“説明の一貫性”や“相談しやすさ”を確かめると、自然に「この人に任せたい」が育っていきます。
まとめ
ここまで読んでくださってありがとうございます! 「かかりつけ医」は、誰かに“指名される”ものではなく、あなたが選び、継続して相談する関係のこと。回数よりも、症状の変化を覚えて次につなげてくれる連続性が大切です。
2025年からは各医療機関の体制が「かかりつけ医機能」として見える化され、普段の不調を診て継続フォローできる1号機能、時間外や在宅医療などを含む2号機能の有無が分かりやすくなります。
これにより、夜間対応や在宅対応の有無、専門医との連携度などを事前に比較しやすくなります。
選ぶときは、
- 通いやすさ・話しやすさ・信頼感があるか
- 診療の幅と連携体制、継続的サポートが実感できるか
- 「この人に任せたい」と思える相性があるか
をシンプルに確認。
迷う場合は、風邪や花粉症など軽い用件で2〜3回受診し、説明の一貫性や相談しやすさを体験して決めましょう。
“気まずさ”を心配する必要はありません。あなたの生活に合う“頼れる拠点”を、自分の意思で選ぶ――それが、かかりつけ医という考え方です。
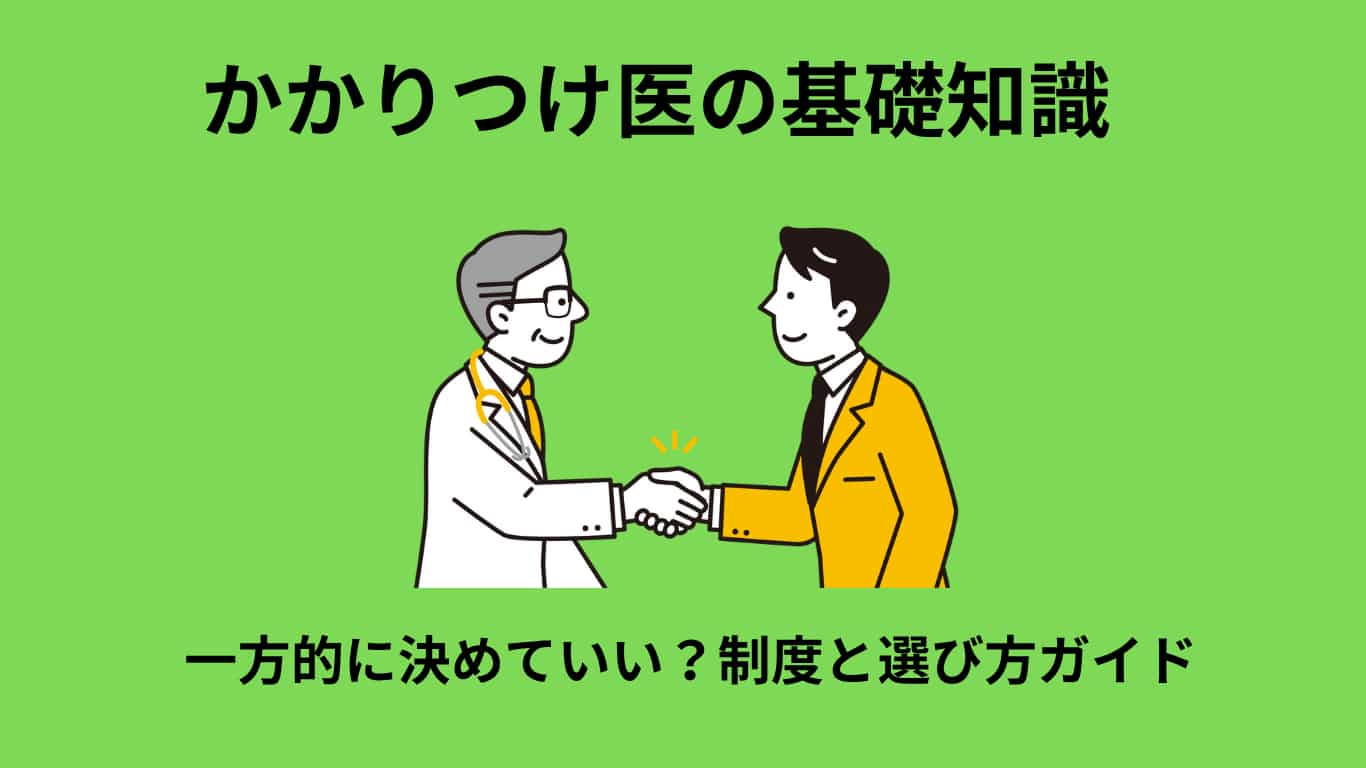
コメント