2025年の参院選では、過去2番目の多さとなる152人の女性候補が立候補しました。
女性の政治参加が進んでいるように見えますが、実は“当選の壁”はいまだに高いままです。
「なぜ女性候補は好まれているのに勝ちにくいのか?」
この記事では、最新の研究が明らかにした「戦略的差別」や「無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)」に注目し、その背景にある投票行動の心理をやさしく解き明かしていきます。
はじめに
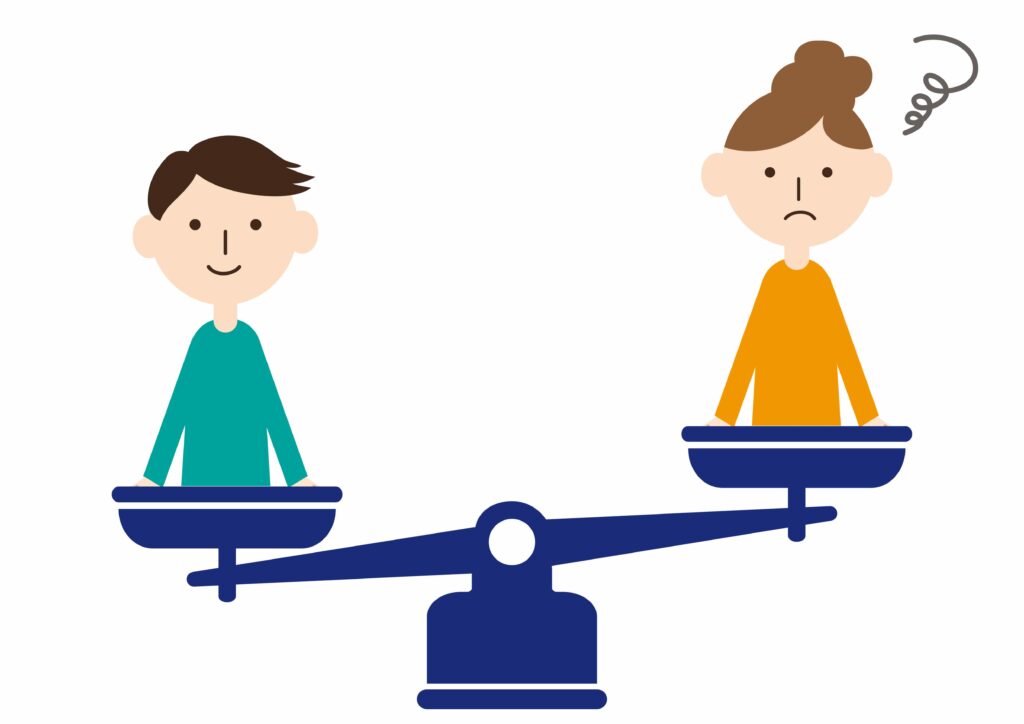
女性候補は“好まれる”けれど“勝ちにくい”?という不思議なズレ
2025年の参院選では、女性候補の数が152人と、過去2番目の多さを記録しました。これは「女性の政治進出が進んでいる」とも受け取れる一方で、当選となると話は別です。
明治大学の加藤言人氏が行った実験では、多くの有権者が「女性候補のほうが望ましい」と思っているにもかかわらず、「選挙で勝ちそうなのは男性」と考えている傾向が明らかになりました。つまり、個人的には応援したくても、“どうせ勝てない”と思い込んでしまっているのです。
このような意識のズレは、実際の投票行動にも影響を与えかねません。「勝ちそうな人に投票したほうが一票がムダにならない」と考える有権者が多くいるのは、現実的な判断のように見えますが、その背景には私たち自身の中にある“思い込み”が潜んでいます。
戦略的差別や無意識の偏見が女性の政治進出を妨げている現実
「戦略的差別」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは「本当はこの人を支持したいけれど、当選しそうにないから他の候補に投票する」といった行動を指します。
今回の研究によれば、こうした投票行動が、女性候補の当選を阻む大きな壁になっている可能性があるといいます。
さらに問題なのは、こうした思い込みは有権者だけでなく、候補者を選ぶ政党側にも存在しているという点です。「政治家といえば男性」というイメージが無意識のうちに根付いていることで、女性がリクルートの段階で除外されてしまう──このような“アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)”が、政治の場における女性の存在感を薄めているのです。
このブログでは、女性候補がなぜ“勝ちにくい”と見られてしまうのか、またその背後にある有権者の心理や社会構造について、できるだけ分かりやすく解きほぐしていきます。
1.増える女性候補者と見えない壁
女性候補の立候補数が過去2番目の多さに
2025年の参院選では、立候補者数522人のうち、女性候補は152人。これは過去最多に次ぐ記録であり、女性比率も高水準に達しています。
女性の社会進出が進む中で、政治の場でもその動きが広がってきたことは一見ポジティブな変化に見えます。
しかし、こうした数字の伸びに比して、当選率がそれに追いついていない現実があります。
つまり「立候補する女性は増えているが、当選には結びついていない」のです。候補者の数が増えれば当然チャンスも広がるはず──そう考えるのは自然なことですが、現実はそう単純ではないようです。
“女性候補は望ましいが勝てない”という有権者の意識
多くの人が「女性候補は清潔感があり、丁寧で誠実な印象」とポジティブなイメージを持っています。実際、明治大学の加藤言人氏による調査でも、有権者は女性候補を「望ましい」と考える傾向が見られました。
ところが一方で、同じ有権者に「どちらの候補が選挙に勝ちそうか」と尋ねると、今度は「男性候補の方が勝ちそうだ」と答える人が多数派になります。
この“望ましさ”と“勝ちやすさ”のズレこそが、女性候補の当選を難しくしている原因の一つと考えられています。
これは単なる印象の問題ではなく、実際の投票行動に直結する可能性があります。
いくら望ましく思っていても、「どうせこの人は当選しない」と思えば、支持は表に現れません。結果として、実力や人柄で評価されるはずの候補者が、見えない壁に阻まれるのです。
明治大学・加藤言人氏による選好―期待ギャップの研究
加藤氏の研究では、このズレを「選好―期待ギャップ」と呼び、2つの質問を使った実験でその存在を証明しました。1つ目は「どちらの候補が望ましいか」、2つ目は「どちらが当選しそうか」という問いです。
この実験により、有権者の多くが「女性候補を望ましいと思っているが、当選しそうだとは思っていない」という心理傾向が明らかになりました。
さらに注目すべきは、このギャップがリベラルな思想を持つ人や女性自身により強く見られたという点です。つまり、女性候補を積極的に支持したいと考えている層ほど、「他の人はそう思っていないかもしれない」と感じてしまうのです。
この“他人の目”を意識した判断が、結果として「戦略的に男性候補を選ぶ」という投票行動につながる可能性もあります。加藤氏は、このギャップを認識すること自体が、私たちの思考を問い直す第一歩になると語っています。
2.“戦略的差別”とは何か

好ましい候補より「勝てそうな候補」に投票する心理
選挙という場では、私たちはつい「勝ちそうな人」に投票しがちです。本当はAさんの考えに共感していても、「どうせ当選しないから」とBさんに票を入れる──これが「戦略的差別」と呼ばれる行動です。
加藤言人氏の研究では、この心理が女性候補に対して特に働きやすいことが示されました。
たとえば、有権者の中には「女性候補の主張は好きだけど、現実的に当選は難しい」と考えてしまう人が多くいます。
すると、その人の支持は実際の票にならず、結果として「支持はあったのに落選する」現象が起きるのです。
このような判断は、自分の一票を“無駄にしたくない”という思いから来ていますが、その判断が積み重なることで、女性候補の活躍の場を狭めているのかもしれません。
リベラル層・女性により強く現れる期待とのギャップ
特に興味深いのは、リベラルな価値観を持つ人や、女性自身がこの“戦略的差別”の傾向を強く持っているという点です。これは一見矛盾しているように思えるかもしれません。
女性の社会進出を支持している人たちが、実は「女性は勝てない」と思い込んでしまっている──この心理的なズレは、研究の中で「選好―期待ギャップ」として示されました。
加藤氏の分析によれば、リベラル層の有権者は「女性候補が望ましい」と強く感じている一方で、「でも現実には男性候補のほうが勝つ」と思い込んでいる傾向があります。
このギャップは女性の回答者にも見られ、「自分は応援したいけれど、世の中の大半はそう思っていないはず」と感じてしまうのです。
有権者の“思い込み”が生む投票行動の変化
こうした“思い込み”が広がると、投票行動自体が変わってきます。
「勝てそうな候補に投票するのが現実的」という考えが一般化すればするほど、マイノリティや新しいタイプの候補者が当選しにくくなります。
心理学では「同調圧力」や「空気を読む」といった日本独特の社会的傾向が知られていますが、まさにこの「勝ち馬に乗る」ような投票行動も、その延長線上にあるのかもしれません。
周囲が男性候補に注目している雰囲気を感じると、「やっぱりこっちかな」と無意識に選択を変えてしまう──それが“戦略的差別”を生み出す土壌となっているのです。
つまり、私たちが「どうせ当選しない」と思い込むことが、実際にその候補者を“当選しにくくする”という現象を生み出してしまっているのです。
3.無意識のバイアスと変わるきっかけ
女性自身が“女性候補は不利”と感じてしまう理由
女性候補が「自分は不利だ」と感じてしまう背景には、長年染みついた“社会の常識”があります。
実際、多くの人が子どもの頃から「政治家=男性」というイメージを見て育ちます。ニュースや国会中継で映る政治家の多くが男性であることが、無意識のうちに「政治は男の世界」という刷り込みになっているのです。
加えて、「どうせ女性だから通らない」と自分でブレーキをかけてしまう女性候補も少なくありません
。これは“自己選抜”とも呼ばれ、能力があっても最初から諦めてしまう心理的な壁です。「子育て中だから」「家庭の支援がないから」「目立つのが怖いから」など、女性が抱える生活上の制約も、その不利感を強めています。
政党側にも根強く残る「男性優位」の思い込み
バイアスは候補者自身だけでなく、候補者を選ぶ政党側にも存在しています。
政党の幹部に男性が多いと、候補者選びでも無意識に「男性のほうが有権者にウケがいい」「地元の支持が得やすい」などと判断してしまうことがあります。
こうした偏見は、数字や根拠に基づいたものではなく、あくまで“過去の経験則”や“思い込み”から来ている場合が多いのです。
たとえば、「30代の女性候補より、50代の男性候補のほうが票が取れる」といった発言が、候補者選定の場で平然と出るケースもあります。
選挙に勝ちたいというプレッシャーが強いからこそ、過去の“勝ちパターン”にすがりたくなるのでしょう。しかし、それが新しい可能性を閉ざしていることに、どれだけの人が気づいているでしょうか。
モデルケースとSNS発信がバイアスを揺さぶる力に
では、どうすればこの無意識の偏見を乗り越えることができるのでしょうか。
ひとつの鍵となるのが「モデルケース」の存在です。たとえば、東京都の小池百合子知事や、上川陽子外相など、実際に活躍している女性政治家の姿を見ることで、「女性でも政治家になれる」という意識が広がっていきます。
さらにSNSの力も見逃せません。候補者自身が、日々の活動や思いを発信することで、有権者に「この人なら信頼できそう」と思ってもらえるチャンスが生まれます。
また、他の女性たちにとっても、「こんな生き方があるんだ」と背中を押されるきっかけになるでしょう。
実際に、若い女性候補がInstagramで政策をわかりやすく解説したり、TikTokで日常の活動を共有するなど、新しい形で政治にアプローチする動きが出てきています。
こうした取り組みが、これまで“見えなかった女性候補”を身近に感じさせ、バイアスの修正につながるのです。
まとめ
2025年の参院選では、女性候補者の数が過去2番目の多さを記録しました。
しかし、その数に比例して女性が当選しやすくなっているわけではありません。
むしろ「望ましいとは思うが勝てそうにない」という有権者の意識、つまり“選好―期待ギャップ”が、女性候補の当選を阻む大きな要因となっていることが、加藤言人氏の研究で明らかになりました。
このギャップは、リベラル層や女性自身の中でも強く表れているという点で、単純な男女差別の問題を超えた“心理の壁”といえます。
「どうせ当選しないだろう」という思い込みが「戦略的差別」という形で投票行動に影響し、それが現実の結果をさらに強化してしまう──まさに“自己成就的予言”のような現象です。
また、無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)は有権者だけでなく、政党や候補者自身にも深く根付いています。
だからこそ、今必要なのは「自分の中の思い込みに気づくこと」。そして、小さくても着実に社会の空気を変えるために、モデルとなる女性政治家の発信や、新しい世代の挑戦を応援していくことではないでしょうか。
この研究が示すのは、女性が政治に参加しやすい環境を整えることは、特別な“優遇”ではなく、見えない“偏り”をフラットに戻すということ。
次の一票を投じるとき、あなたのその一票が、未来の常識を変える力になるかもしれません。
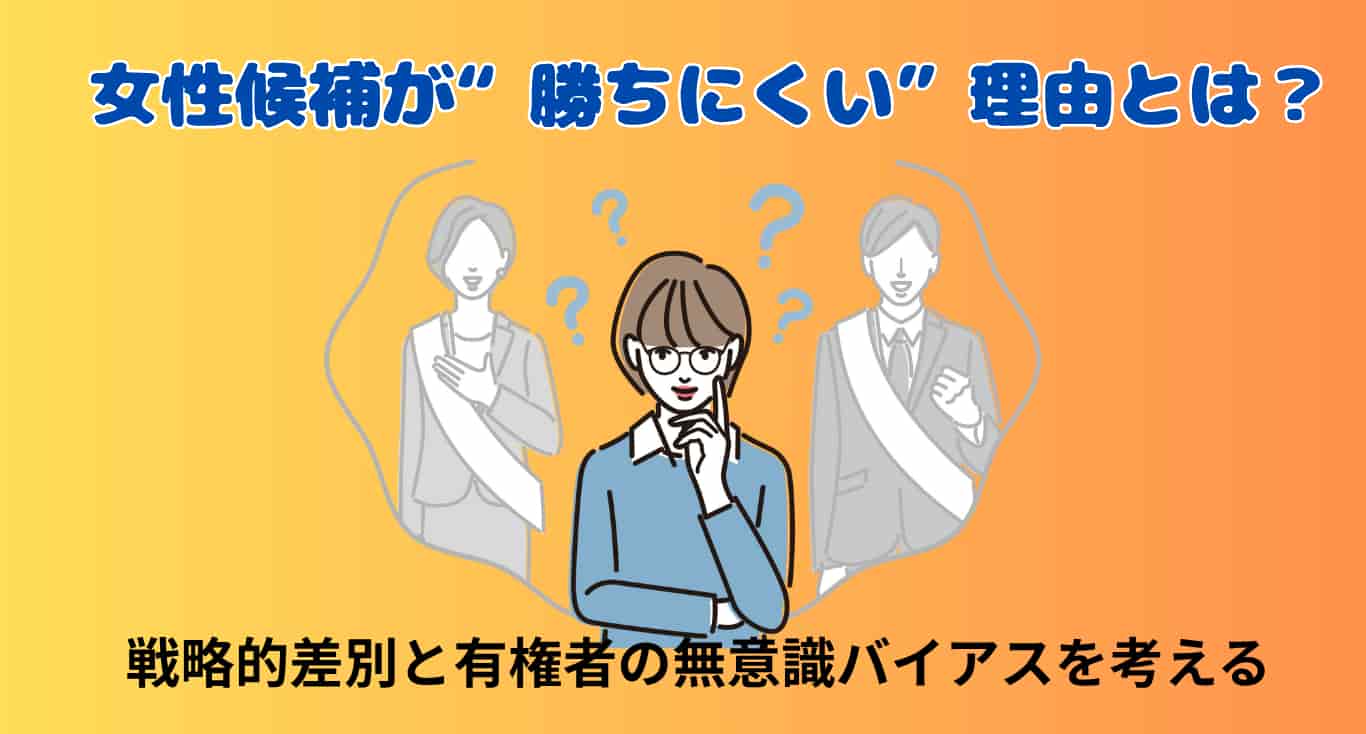
コメント