教師による盗撮事件や広島のわいせつ未遂事件など教育現場の安全性を根本から問う深刻な出来事が多発しています。これらの事件をきっかけに注目を集めているのが、2026年度中の施行が予定されている「日本版DBS制度」です。
この制度では、教員や保育士など、子どもと関わる職業に就く際に、性犯罪歴の有無を事前に確認できる仕組みが導入される予定です。
すでにイギリスやオーストラリアなど多くの国で導入されている同様の制度と比べて、日本版はどのような特徴があるのでしょうか?
本記事では、事件の経緯から制度の必要性、導入の背景、メリット・デメリット、今後の課題までをわかりやすく解説します。
日本版DBS制度の概要
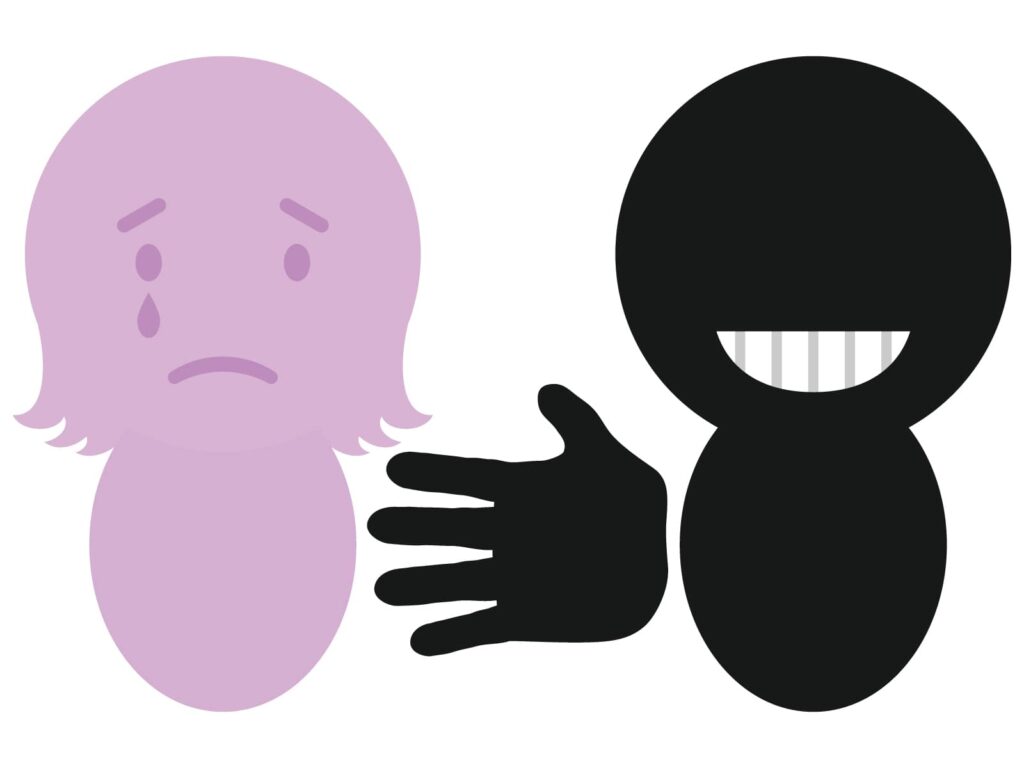
2024年6月、「こども性暴力防止法」が成立し、日本でもついに性犯罪歴の確認制度=日本版DBS(Disclosure and Barring System)の導入が決まりました。
この制度は、子どもと関わる職業に就く前に、過去の性犯罪歴の有無を国を通じて照会し、必要に応じて制限や配置転換を行うものです。
日本版DBS制度は「義務対象」と「認定対象」の2つに分けられます。
義務対象(法律上の確認義務あり)
- 小学校・中学校・高校
- 幼稚園・認定こども園
- 保育所(認可・認証)
- 児童養護施設
- 放課後等デイサービス
認定対象(国の認定を受けた場合)
- 学習塾
- スイミングスクール
- 学童クラブ
- ダンス教室
- スポーツクラブ等
制度対象外
- 家庭教師(個人)
- 個人ベビーシッター
- 個人ボランティア
| 分類 | 対象事業例 | DBS照会の義務 |
|---|---|---|
| 義務対象 |
・小学校・中学校・高校 ・幼稚園・認定こども園 ・保育所(認可・認証) ・児童養護施設 ・放課後等デイサービス |
あり(法律上の義務) |
| 認定対象 |
・学習塾 ・スイミングスクール ・ダンス教室・習い事教室 ・学童保育(民間) ・スポーツクラブなど |
あり(認定事業者に限る) |
| 対象外 |
・家庭教師(個人) ・ベビーシッター(個人) ・個人ボランティア ・非認定の小規模教室など |
なし(現時点では制度外) |
🔍 確認対象となる犯罪
日本版DBSでは以下の「特定性犯罪」が照会対象とされます:
- 不同意性交罪・不同意わいせつ罪
- 児童ポルノ禁止法違反
- 痴漢・盗撮など条例違反
ただし、下着窃盗やストーカー規制法違反、不起訴処分などは対象外。今後、付帯決議での拡大も検討中です。
📋 性犯罪歴照会の流れ
日本版DBSでは、以下のような流れが想定されています:
確認書の内容と措置:確認書には氏名は記載されず、申請番号・確認日・特定性犯罪該当の有無のみが記載されます。性犯罪歴が確認された場合、事業者には「子どもと関わらない業務への配置転換」や、条件を満たせば「解雇」も可能とされています。ただし合理性や社会通念上の妥当性のある対応が求められます。
事業者が照会申請:雇用予定者について、事業者が「こども家庭庁」に申請を行う。
本人の戸籍情報提出:就労希望者本人が戸籍情報などを提出(事業者には渡らない)
法務省への照会:こども家庭庁が法務大臣に性犯罪歴の有無を照会。
照会結果と対応:
前歴なし → 事業者に「犯罪事実確認書」が交付される。
前歴あり → まず本人に事前通知、2週間以内に訂正請求や内定辞退ができる。辞退がない場合は、事業者に確認書が交付される
🗓 制度開始のスケジュール
- 法律成立:2024年6月19日
- 施行予定:最大2年6か月以内(2026年度中)
- 現職対応:施行後3年以内に確認完了が必要
認定事業者は認定から1年以内に全職員の確認が求められます。また、急な補充には「特例期間内の照会」制度も設けられます。
✅ DBS制度のメリットとデメリット
DBS制度のメリット(利点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 子どもの安全確保 | 採用前に重大な性犯罪歴がある人を排除することで、子どもにとって安心できる教育・保育環境を実現できます。 |
| 採用判断の透明性向上 | 客観的な照会により、雇用主の個人的な判断だけに依存せず、安全性を可視化した人材選びが可能になります。 |
| 再発防止と抑止効果 | 既に前歴がある人の再就職を制限し、また「監視がある」ことで不適切な志願者の応募自体を防ぐ効果も期待されます。 |
| 保護者・社会の信頼向上 | 制度があることで「社会として子どもを守っている」という姿勢が可視化され、教育や保育現場への信頼感が高まります。 |
⚠ DBS制度のデメリット・課題
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ⚠ プライバシー・人権の問題 | 犯罪歴というセンシティブな情報を扱うため、「過剰な監視」や「名誉回復の機会が奪われる」といった懸念もあります。 |
| ⚠ 誤情報・不正確な登録の恐れ | 登録ミスや過去の軽微な違反が誤って扱われると、不当に職を失う・就けないケースも生まれる可能性があります。 |
| ⚠ 再チャレンジの妨げ | 一度過ちを犯した人が反省・更生していても、「一律で排除される仕組み」は社会復帰の妨げになるという指摘もあります。 |
| ⚠ 照会対象の線引きが難しい | どこまでの過去を、どの程度まで確認するか(例:10年前?不起訴?)という点で制度設計が非常に難しい側面があります。 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 子どもの安全と信頼性が高まる | 更生の機会を奪うという意見がある |
| 採用判断の透明性が向上 | 個人情報の取り扱いが慎重を要する |
| 再犯防止や抑止力が期待される | 軽微な違反の対象化への懸念 |
| 保護者・地域の信頼が制度で担保される | 制度の線引きや複雑な運用課題 |
制度に対する意見のまとめ
賛成意見
- 子どもを守るためには不可欠
- 教職員の資質保証につながる
- 採用前のチェックで保護者が安心できる
懸念・反対意見
- 更生者の社会復帰を妨げる恐れ
- 情報漏洩や誤登録リスク
- プライバシー侵害の懸念
- 教職人材不足が悪化する可能性
バランスある制度設計の必要性
制度を導入する目的は「子どもや弱者を守ること」ですが、それだけでなく、
- 個人の更生や再挑戦を可能にする道
- 情報管理の正確性と透明性の担保
- 過剰な差別や社会的排除の防止
などの観点も欠かせません。
日本版DBS制度に望まれること
- 段階的な制度導入と運用の見直し
- 対象職種・確認範囲の透明な定義
- 情報照会に関する本人通知・異議申立ての制度整備
- 支援付きの更生者支援策との併存
🌍 イギリスDBS制度との比較
🇯🇵 日本版DBS制度と🇬🇧 イギリスDBS制度の主な違い
| 項目 | 日本版DBS制度(2026年導入予定) | イギリスDBS制度(2002年施行) |
|---|---|---|
| 対象者 | 学校、保育施設などの職員・職業従事者(国が定めた施設・職種) | 子ども・高齢者・障がい者と接するすべての職種(公私問わず広範囲) |
| 確認の内容 | 一定の性犯罪歴(性暴力関連)に限定 | 性犯罪歴に限らず、暴力、窃盗、詐欺、薬物など広範囲の犯罪歴 |
| 確認の主体 | 採用側(施設・学校など)が「こども家庭庁」などを通じて国に照会 | 本人が自らDBSに申請し、証明書を取得して就職先に提示 |
| 確認の義務 | 該当施設には確認義務が課される予定 | 雇用者によって義務化されており、本人申請が前提 |
| 就業制限 | 国が就業制限措置を検討可能(制度設計中) | 「バリング制度」により就業制限・禁止対象に指定されると再就業不可 |
| 照会の対象となる過去の期間 | 確認可能な犯罪歴の「年数制限」がある方向で議論中 | 有罪判決は基本的に生涯対象(内容に応じて自動消去の条件あり) |
| 制度の法的位置付け | 「こども性暴力防止法」に基づく独立制度 | 「Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006」などに基づく包括制度 |
主な違いの解説
1. 確認範囲の狭さ(日本)
日本では「性暴力関連の犯罪」に絞って確認が行われる予定です。一方イギリスでは、性犯罪だけでなく、暴力や財産犯罪など幅広い前歴がチェック対象になります。
2. 本人申請か事業者申請か
イギリスでは基本的に本人が自分で申請し、証明書を職場に提出する仕組みです。これに対して、日本では事業者が採用前に国に照会をかける形式が想定されており、本人が証明書を持ち歩く必要はないとされています。
3. 照会できる期間や情報の制限
日本では「過去◯年以内の有罪判決のみ照会可能」など、確認対象に年数制限が設けられる可能性が議論されています。イギリスでは原則として有罪判決は照会可能で、削除には厳格な基準があります。
現時点での総評
- 日本版DBS制度は「性犯罪歴の確認に特化した限定的な制度」としてスタートします。
- イギリスの制度は「脆弱な立場の人々を守るための包括的な安全確認制度」という色合いが強いです。
- 日本ではまずは子どもを対象に制度を設計し、その後「高齢者介護」や「障がい者支援」などへ対象を広げる可能性もあります。
| 比較項目 | 日本 | イギリス |
|---|---|---|
| 対象職種 | 教職・保育限定(開始時) | 教育・福祉・医療等広範囲 |
| 対象犯罪 | 一部性犯罪に限定 | 性犯罪+暴力・薬物・財産犯罪など |
| 就業制限 | 配置転換・任用努力義務 | バリング(就業禁止)制度あり |
| 申請方式 | 事業者が国に申請 | 本人が証明書を取得・提出 |
| 法施行 | 2026年度予定 | 2002年〜(2012年DBS移行) |
📈 イギリスDBS制度の成果・効果
1. 大規模な運用実績
- 年間約 700万件の照会(DBSチェック)が行われており、約 1万2千件の就業制限(バリング)案件が検討されています 。
- 現在では、 99,500人以上が禁止リスト(Barring List)に登録されており、子どもや弱者と関わる仕事への就労が法的に制限されています 。
2. 雇用ルールの改善とリスク回避
制度導入により、雇用主は候補者の前歴を把握し、より安全な採用判断ができるようになりました。特に、教育や福祉など、子どもと接する職種においては不適切な人材を事前に排除する仕組みとして機能しています 。
3. 制度運用の効率性と透明性
- DBSは処理の迅速性と費用対効果(Value for Money)に注力しており、申請者の約95%が8週間以内に承認を受ける体制が整っています。
- 内部監査や独立レビューによって改善点が提言されており、制度運用の透明性と効率性が高い評価を得ています 。
| 成果・効果項目 | 内容 |
|---|---|
| 照会件数とバリング件数 | 年間700万件以上のDBS照会、12,000件以上の就業禁止判断 |
| 禁止リスト登録者数 | 約99,500人がバリング対象として登録 |
| 採用安全性の向上 | 事前に不適切な候補者を排除できる仕組みにより、安全性向上 |
| 処理スピードと効率性 | 約95%が8週間以内に承認取得、迅速な照会対応 |
| 制度監査とレビュー体制 | 定期的な独立レビューにより改善と透明性が維持されている |
イギリスDBS制度は、子どもや弱者と関わる職種における採用安全性を高める上で大きな役割を果たしていると評価できます。就業禁止リストへの登録など具体的な措置が制度として定着し、多くの職場で活用されています。
ただし、犯罪発生率の減少など直接的な効果を示す統計的なデータは公表されていないため、制度全体の抑止力を定量的に評価することは難しいとされています 。
✅ 日本版DBS制度に期待される効果(イギリス制度との比較視点)
イギリスのDBS制度で得られた成果を踏まえて、日本版DBS制度に期待される効果と、制度導入にあたって検討すべき課題をわかりやすく整理しました。
| 期待される効果 | 内容 |
|---|---|
| 子どもを守る体制の強化 | イギリス同様、性犯罪歴のある人が教職や保育職に就くことを未然に防ぎ、安心できる教育・保育環境を実現。 |
| 採用段階での事前確認の仕組み | 雇用側(学校・施設等)が国を通じて確認を行うことで、制度的に「安全性のフィルター」をかけられる。 |
| 社会的抑止力の強化 | 「チェックがある」と知られることで、不適切な経歴を持つ者が職に応募すること自体を抑止する効果が期待される。 |
| 国民的な理解と信頼の醸成 | 制度が整うことで、保護者や市民が教育・保育現場をより信頼できるようになる(イギリスではDBS証明書が採用基準に)。 |
⚠ 日本版DBS制度の課題と今後の検討ポイント
| 検討課題 | 解説 |
|---|---|
| 確認対象の範囲が狭い | イギリスは性犯罪に限らず、暴力・薬物・財産犯罪も確認対象。日本では当面「性犯罪歴の一部」に限定される予定。 |
| チェック対象者の範囲 | 学校・保育園などに限られており、学習塾・スポーツクラブなど民間教育サービスは対象外の可能性が高い。 |
| バリング制度(就業制限)の明確化 | イギリスでは「働いてはいけない職業」が明確に設定されているが、日本ではまだ「任用しない努力義務」にとどまる可能性あり。 |
| 再チャレンジの権利とのバランス | 犯罪歴がある人への社会復帰の道も大切。何を「確認対象」とするか、期間をどう区切るかの議論が必要。 |
| プライバシーと情報保護の調整 | 個人情報としての前歴を扱うため、第三者が不当に知ることがないように、制度運用の厳格さと透明性が求められる。 |
🔍 補足:日本とイギリスの制度の導入目的の違い
| 国 | 制度の目的の中心 | 備考 |
|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 子どもへの性暴力の防止 | スタートは限定的な範囲で慎重な制度設計 |
| 🇬🇧 イギリス | 脆弱な立場のすべての人の保護(包括的) | すべての子ども・高齢者・障がい者と接する職に義務付け |
✏ 今後の検討の方向性(提言)
保護者・市民への制度周知と情報公開の透明性強化
対象職種・施設の拡大(学童・塾・放課後デイなど)
就業制限の強制力を持たせる法整備
一定期間を経た人の再評価手続きの設計
本人の意向確認や不服申し立て手続きの整備
- 年間約700万件の照会、12,000件の就業制限実施
- 約99,500人が「禁止リスト」に登録済み
- 採用の安全性と抑止効果が実証されている
- 迅速な運用(95%が8週間以内に処理)
海外の類似制度(抜粋)
イギリス以外の国でも、教育・保育・福祉などの分野で働く人に対して前歴(特に性犯罪歴)を確認する制度が導入されている国があります。ただし、制度の名称や運用の仕組みは国ごとに異なります。
以下に、代表的な国の例を挙げてご紹介します。
| 国名 | 導入年・制度名 | 導入の背景 |
|---|---|---|
| 🇬🇧 イギリス | DBS(2002→2012) | ソーハム事件(教員による児童殺害) |
| 🇦🇺 オーストラリア | WWCC | 州単位の導入、保護者の声 |
| 🇳🇿 ニュージーランド | Children’s Worker Checks | 教育福祉の不祥事対策 |
| 🇨🇦 カナダ | Vulnerable Sector Check | 教会・学校での事件防止 |
| 🇫🇷 フランス | 犯罪歴証明書 | 採用時の前歴隠し対策 |
| 🇸🇪 スウェーデン | 無犯罪証明制度 | 子ども対象の暴力根絶政策 |
共通点と特徴
| 共通点 | 解説 |
|---|---|
| ✅ 子ども・高齢者・障がい者など「支援が必要な人」と接する職に限定 | 教育、保育、医療、福祉、送迎サービスなどが対象になることが多いです。 |
| ✅ 採用前の確認が義務化されている | 多くの国で「採用前チェック」が義務。雇用主・行政の責任が明確です。 |
| ✅ 一定期間ごとの再チェック制度あり | 更新制のチェックや、定期的な再確認制度が設けられている国も多く存在します。 |
日本との違い(参考)
- 日本はまだ制度が始まっていない(2026年施行予定)
- 確認対象が性犯罪歴に限定される方向
- 本人の申請ではなく、事業者が照会する方式
→ 海外は「申請者本人が証明書を取得して提出する」形式が多く、透明性や自衛意識の促進にもつながっています。
- イギリス以外にも、オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・アメリカ・フランス・北欧など、多くの国が類似制度を導入。
- 制度名や範囲は異なりますが、目的は「子どもや弱者を守る」ことに共通。
- 日本も国際的な流れに沿って、制度の導入とともに今後の制度設計を柔軟に見直していくことが期待されます。
🌍 各国の制度導入経緯まとめ
| 国名 | 導入年/制度名 | 導入のきっかけ・背景 |
|---|---|---|
| 🇬🇧 イギリス | 2002年「CRB(旧DBS)」→2012年「DBS」に統合 | 2002年、ソーハム事件(Soham murders)により、 学校職員による児童殺害事件が発生。 加害者は過去に性犯罪歴があったにもかかわらず、 学校が把握できていなかった。社会的衝撃から「DBS制度」が構築。 |
| 🇦🇺 オーストラリア | 2000年代以降 各州で順次「WWCC」導入 | 複数の州で児童福祉関係者による性加害・暴力事件が相次ぎ、 保護者や市民から「採用段階の透明性と監視の強化」を求める声が拡大。 州ごとに独自の制度が形成される。 |
| 🇳🇿 ニュージーランド | 2014年「Children’s Worker Safety Checks」 | 虐待事件や不適切な保育対応をきっかけに、 「子どもと関わるすべての職種での安全確認が必要」とされ、 包括的な制度化が法制化された。 |
| 🇨🇦 カナダ | 1990年代後半〜(Vulnerable Sector Check) | 学校・福祉施設・教会での性加害事件が複数報道され、 警察の前歴情報を用いた事前確認制度が州単位で制度化された。 |
| 🇫🇷 フランス | 2000年代初期〜 無犯罪証明書制度の拡充 | 教育機関の職員による犯罪歴隠しが発覚。 「前歴がある者を国家資格で雇うのは不適切」との議論が高まり、 教員・医療職などに無犯罪証明の提出を義務化。 |
| 🇸🇪 スウェーデン | 2010年前後 教育・保育職での証明書提出義務化 | 北欧全体で「子どもに対するあらゆる暴力を排除する」政策方針が強まり、 予防的観点からの採用スクリーニング制度が拡充された。 |
導入の共通背景
- 重大な事件の発生
→ 子どもや障がい者、高齢者などの弱い立場の人への犯罪行為が、制度の不備の中で起きていた。 - 採用前の情報不足
→ 過去の犯罪歴やトラブル歴が共有されず、「知らずに雇っていた」事例が続出。 - 市民の声と報道の影響
→ 保護者や地域社会から「事前確認は当然」「国家が責任を持つべき」という声が高まった。 - 人権とプライバシーとのバランスへの配慮
→ 「確認は必要だが、差別になってはならない」との視点から、情報の取り扱いに厳格なルールを導入。
🇯🇵 日本との比較ポイント
| 項目 | 海外(特にイギリス) | 日本(こども性暴力防止法に基づく制度) |
|---|---|---|
| 導入きっかけ | 重大事件(ソーハム事件など) | 市民団体・被害当事者の声、メディア報道、政治家の問題提起 |
| 立法タイミング | 事件から比較的早期に法整備 | 課題提起から10年以上かけて2024年に法制化 |
| 対象職種の範囲 | 非営利・民間・ボランティア含む広範な職種 | 当面は学校・保育所など限られた施設が中心 |
| 社会的理解・運用の成熟度 | 制度の定着と市民認知が進んでいる | 制度開始前段階(2026年度予定)、今後の啓発が課題 |
- 多くの国が「事件→制度の不備→制度導入」という流れでDBS制度を構築しています。
- 日本は制度としては遅れての導入となりますが、先行国の事例をもとに慎重かつ着実な運用設計が可能です。
- 導入後は「民間教育機関への拡大」「更新制度」「就業制限の明確化」など、段階的な整備がカギとなります。
まとめと今後への期待
日本版DBS制度は、教育や保育の現場における信頼回復と子どもを守るための一歩です。制度導入により、採用段階でのスクリーニングが可能になり、保護者や市民の安心感が高まることが期待されます。
制度の本格運用に向けては、「対象範囲の拡大」「就業制限の明確化」「本人への手続き周知」など、継続的な見直しが重要です。イギリスのように実効性と透明性のある制度運用が、日本でも定着することが望まれます。

コメント