ここ数年、映画や小説、ゲームの世界で「事故物件」を題材にした作品が大きな注目を集めています。
そんな中、実在する事故物件を舞台にした異色のホラーゲーム『日本事故物件監視協会』が登場しました。
本作は、プレイヤーが“夜間監視員”となり、深夜の物件に設置されたカメラを通じて「異常」を発見・報告するという内容。
実写映像による圧倒的なリアリティと、公式サイトまで作り込まれた世界観は、まるで現実と虚構の境目に迷い込んだような感覚を与えてくれます。
この記事では、そんな話題のホラーゲームを実際にプレイした体験を交えながら、その魅力と特徴を徹底解説していきます。
はじめに
ホラーゲーム市場で高まる「事故物件」ブーム

ここ数年、ホラーコンテンツの世界では「事故物件」を題材にした作品が次々と登場しています。
映画『事故物件 恐い間取り』や、ネットで話題になった小説『変な家』などはその代表例です。また、全国の事故物件を公開している「大島てる」というウェブサイトは、多くの人が実際に閲覧し「こんな場所が身近にあるのか」と驚かされています。
事故物件とは、殺人事件や自殺、火災などが原因で人が亡くなった住居のことを指し、現実の重さと不気味さが人々の興味を強く惹きつけています。
こうした背景から、ホラーゲームでも「事故物件」を取り入れた作品が注目を集めるようになっているのです。
『日本事故物件監視協会』という異色タイトルの登場
そんな流れの中で登場したのが、『日本事故物件監視協会』というゲームです。
タイトルだけを聞いても、「え、本当にそんな団体があるの?」と一瞬疑ってしまうほどリアルなネーミング。本作はプレイヤーが“夜間監視員”として深夜0時から朝5時まで事故物件を監視し、異常を見つけて報告するという内容です。
しかも、舞台となるのは実在する事故物件で、映像には3Dモデルではなく本物の建物を使用。
これにより、プレイヤーはまるで本当に監視業務をしているかのような緊張感に包まれます。
さらに、公式サイトには団体の概要や求人情報まで用意されており、まるで実在する協会のような徹底した作り込みも話題を呼んでいます。
こうしたユニークな仕掛けが、ただのホラーゲームにとどまらない“新しい恐怖体験”へとプレイヤーを誘っているのです。
1.『日本事故物件監視協会』とは?
ゲームの基本設定とプレイヤーの役割
『日本事故物件監視協会』は、プレイヤーが「夜間監視員」として深夜0時から朝5時まで事故物件を見張るという設定のホラーゲームです。
操作方法はとてもシンプルで、監視カメラを切り替えながら「異常」を見つけ、すぐに報告することが任務。
例えば、廊下に突然光の玉(オーブ)が現れたり、家具の配置が変わったりといった小さな違和感を探すのがプレイヤーの仕事です。
業務に失敗すると「給与ゼロ」で終了してしまうため、緊張感を持ってカメラを見続ける必要があります。単純なルールながらも、深夜の静けさと相まって強烈な恐怖体験を味わうことができます。
実在する事故物件を使用した圧倒的リアル感
本作の最大の特徴は、実際に存在する事故物件が舞台になっている点です。
秋田県の古民家や奈良県の山間部にある神社、岐阜県の老舗旅館など、どれも不気味な雰囲気を持つ場所ばかり。
しかも映像は3Dグラフィックではなく、本物の建物を撮影した実写映像。そのため、ただ画面を見ているだけでも背筋がゾクゾクするような臨場感を味わえます。
霊障の内容も実際の報告を基に作られているため、虚構のホラーとは違う“現実感”が恐怖を倍増させているのです。
架空団体の公式サイトや求人ページなどの徹底した世界観
さらにユニークなのは、ゲームの外側まで広がる徹底した世界観です。公式サイトには「一般社団法人 日本事故物件監視協会」という架空の団体が紹介され、業務内容や調査実績、さらには理事長の挨拶まで掲載されています。
求人情報まで用意されており、「現地調査員は月給44万円」「夜間監視員は時給2,970円」といった妙にリアルな待遇が書かれているのも面白いポイントです。
応募ボタンを押すとSteamのストアページにつながる仕掛けまであり、プレイヤーをゲームの世界に完全に引き込む工夫が随所に見られます。
この“現実と虚構の境界を曖昧にする演出”が、他のホラーゲームにはない強烈な魅力となっています。
2.ゲームプレイの流れと恐怖体験
カメラ切り替えで「異常」を発見するシステム
ゲームが始まると、プレイヤーは監視カメラの前に座り、複数の映像を交互にチェックすることになります。
カメラは「広間」「廊下」「外観」など物件の各所に設置されており、ボタン操作で切り替えが可能。
普段は静まり返った映像が映るだけですが、ふとした瞬間に「さっきまでは無かったはずの白いオーブ」や「急に閉まった扉」といった異変が出現します。
プレイヤーはそれを見つけ、対象箇所をクリックして「報告」しなければなりません。
まるで“間違い探し”のようですが、背後にあるのはただの遊びではなく、実在の事故物件を舞台にした生々しい恐怖。だからこそ、ほんのわずかな変化でも見逃せない緊張感が続きます。
異常報告と業務失敗の条件
報告システムには厳しいルールがあります。異常を4回も見逃すと即「業務失敗(ゲームオーバー)」となり、給与はゼロ。
逆に、異常がない場所を5回連続で誤って報告しても失敗扱いです。特別手当(ハードモード)では、そのミス許容量が3回に減るため、より集中力が求められます。
例えば、プレイヤーが廊下の物音を聞き逃してしまうと、そのまま「未報告」としてカウントされるのです。
緊張で手汗をかきながらカメラを切り替える中で、「次の一瞬こそ何かが出るのでは」と心臓がバクバクする──そんなプレッシャーがプレイヤーを強烈に追い込みます。
実写映像と静寂が生む没入感と孤独感
本作の恐怖をさらに高めているのは、実写によるリアルな映像と、ほとんど音楽が流れない環境設定です。
聞こえるのは、わずかな環境音や突然の物音、そして自分の心臓の鼓動だけ。
周囲には誰もいない深夜の事故物件を、たった一人で監視している感覚に陥ります。
実際、プレイ中に「カメラを切り替えた瞬間に知らない顔が映り込む」といった現象に出会うと、反射的に声を上げてしまうほどの恐怖が走ります。
これは単なるゲームというよりも、孤独な業務体験をそのまま再現したような没入感。静寂とリアル映像が合わさり、プレイヤーは「もうやめたいのに目が離せない」状態へと引き込まれていきます。
3.特徴的な仕掛けと他作品との違い
リアルイベントやコラボレーションによる没入演出
『日本事故物件監視協会』は、ゲーム内の恐怖体験だけにとどまらず、現実世界とのリンクを意識した仕掛けが随所に盛り込まれています。
たとえば、事故物件を実際に買い取り宿泊体験を提供している団体「暗夜-ANNYA-」とのコラボレーション。彼らが手掛けた物件がゲーム内の隠しステージとして登場するため、プレイヤーは「現実とゲームがつながっている」という感覚を強く抱きます。
さらに、X(旧Twitter)での告知は数万の「いいね」を獲得し、130万ビューを超えるなど、SNSでの注目度も抜群。このような“リアルと虚構の融合”は、ただのゲームプレイを超えて「体験そのもの」に進化させています。
心霊・オブジェクト系など多彩な異常現象
ゲームに登場する異常現象はバリエーション豊かです。
家具の位置が変わる、扉が開閉するといった「オブジェクト系」の異常に加え、白いオーブや人影、さらには明らかに人外の存在が映り込む「心霊系」の現象も用意されています。
中でもプレイヤーを驚かせるのが“顔にゅ~”と呼ばれる、カメラを切り替えた瞬間に画面いっぱいに現れる異常現象。心臓が止まりそうになるほどの衝撃で、多くのプレイヤーが悲鳴を上げたと言われています。
さらに、うめき声や壁を叩く音など「音による異常」もあり、映像と聴覚の両面から恐怖が迫ってくるのが特徴です。こうした多彩なパターンにより、繰り返し遊んでも飽きることなく、新しい恐怖に出会える仕組みになっています。
『Observation Duty』系作品との差別化ポイント
監視カメラを題材にしたホラーゲームはこれまでも存在しており、代表的なのが『I’m on Observation Duty』シリーズや『Spectator』です。
しかし、『日本事故物件監視協会』が際立っているのは「実在する事故物件を使用している点」と「徹底的なリアリティ演出」にあります。
海外作品が架空の空間や3Dモデルを舞台にしているのに対し、本作は実写映像を使い、現実に存在する建物を舞台とすることで没入感を極限まで高めています。
さらに、求人ページや団体紹介といった公式サイトの仕掛けも、他作品にはないユニークな要素です。
つまり本作は、ジャンプスケア頼みの恐怖だけではなく、「本当に存在するのでは?」と錯覚させるリアルさこそが最大の武器となっており、監視カメラ系ホラーの新たなスタンダードを提示していると言えるでしょう。
まとめ
『日本事故物件監視協会』は、ただのホラーゲームにとどまらない“体験型コンテンツ”として強烈な印象を残します。
実在する事故物件を舞台にした実写映像のリアリティ、異常を報告するという緊張感あふれるシステム、そして公式サイトやコラボイベントを通じた徹底的な世界観の作り込み。
どれもが相互に作用し、プレイヤーを現実と虚構の境界線へと引き込みます。
類似作品と比べても一線を画すリアルさがあり、ジャンプスケアが苦手な人でも「監視業務」というゲーム性のおかげで自然に恐怖を受け止められる工夫が施されています。
価格も手ごろであり、夏の夜に背筋を凍らせるにはぴったりの一本。ホラー好きはもちろん、普段ホラーをあまり遊ばない人にもぜひ試してもらいたい作品です。
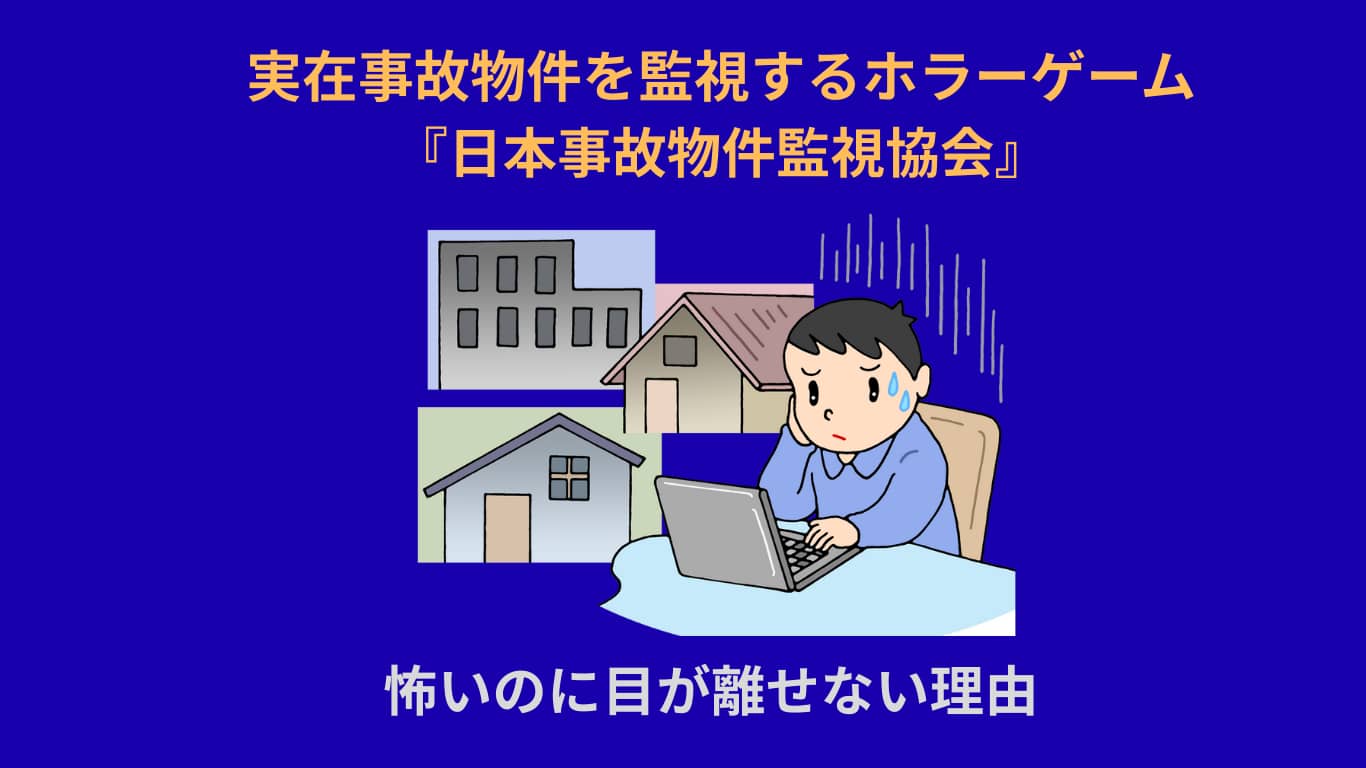
コメント