2025年の自民党総裁選には、小泉進次郎氏・茂木敏充氏・高市早苗氏・小林鷹之氏・林芳正氏の5人が立候補しました。
次期総理を決める選挙として注目されるなか、それぞれの演説スタイルには大きな違いがあります。
印象に残るフレーズで注目を集める小泉氏、データで裏付ける実務派の茂木氏、理念を強く訴える高市氏、生活者目線を重視する小林氏、調整型で安定感を示す林氏──本記事では5人の演説傾向を比較し、強みと弱みを整理しました。
はじめに
自民党総裁選2025の注目度
2025年の自民党総裁選は、日本の次期リーダーを選ぶ重要な選挙として大きな関心を集めています。テレビや新聞だけでなく、SNSでも連日候補者の発言が取り上げられ、一般市民の間でも話題になっています。
とくに、日常生活の不安や将来への期待に直結する経済政策や外交姿勢は、国民が注目する大きなポイントです。普段は政治にあまり関心がない人でも、「次の総理大臣は誰になるのか」「どんな言葉で日本を導くのか」という点に自然と関心を持つようになっています。
候補者の演説スタイルを比較する意義
政治家の演説は、政策の中身だけでなく、言葉の選び方や伝え方からも人物像が浮かび上がります。
同じ「経済成長」を語っても、数字を並べる人もいれば、わかりやすい比喩で説明する人もいます。言葉の調子や表現の強さによって、有権者の受け止め方は大きく変わるのです。
演説スタイルを比較することで、「誰が発信力に優れているのか」「誰が具体的な政策を説明できるのか」「誰が共感を呼びやすいのか」といった違いを整理できます。こうした視点は、候補者の能力やリーダー像を見極めるうえで重要なヒントになります。
1.小泉進次郎|印象に残る抽象的フレーズ
リズム感ある言い回しで耳に残る
小泉進次郎氏の演説は、耳に残るフレーズの多さが特徴です。
たとえば「今のままではいけない。でも、これまで通りでいいわけではない」といった言い回しは、一見すると矛盾しているように感じますが、リズム感があり強い印象を残します。
短く切ったフレーズを繰り返すことで、内容よりも“聞いたときのインパクト”を優先している点がわかります。こうしたスタイルはテレビのワイドショーやSNSで拡散されやすく、多くの人の記憶に残る要因になっています。
抽象的で中身が薄いと批判されやすい
一方で、小泉氏の演説は「具体策が見えにくい」と批判されることも少なくありません。
たとえば環境大臣時代に語った「セクシーな環境政策」という発言は、耳目を集める一方で「結局どういう政策なのか分からない」と国民に受け止められました。
抽象的な表現が多いため、政策論争の場では「中身が薄い」「質問に正面から答えていない」という評価を受けることもあります。こうした点は、首相候補としての説明責任を果たす上での課題となっています。
若さと発信力で政治に無関心層にも届く
ただし、若さと発信力は小泉氏の大きな強みです。政治に関心が薄い層にも響きやすい言葉を選ぶことで、これまで政治に無関心だった若者や主婦層に関心を持たせるきっかけを作っています。
SNSで「進次郎構文」と揶揄される発言が拡散するのも、逆に言えば注目度の高さの証です。内容の薄さを批判する声がある一方で、メディアを通じて広く存在感を発揮できる点は、小泉氏が持つ稀有な資質といえるでしょう。
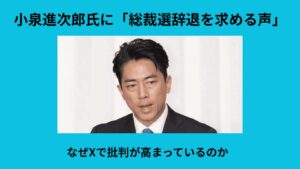
2.茂木敏充|データと交渉力で実務派
データや交渉事例を示す具体性
茂木敏充氏の演説は、数字と具体例が出発点です。
たとえば「物価上昇率」「実質賃金」「中小企業の設備投資額」といった分かりやすい指標を最初に提示し、そこから政策の優先順位を説明します。聞き手は“今どこに問題があるのか”を数字で把握でき、話の先をイメージしやすくなります。
また、通商分野の話では、自由貿易協定の交渉経験を例に、関税の引き下げ幅や発効までの工程、国内産業への支援策までをセットで語るのが特徴です。
単に「輸出を伸ばす」と言うのではなく、「こういう条件で合意を取り付け、どの業界にどういう利益が出たのか」を具体的に示すため、実務の手触りが伝わります。
さらに、中小企業の海外展開支援や、認証・規格の統一といった細かな論点も取り上げるため、現場の課題と政策を橋渡しする説明になっています。
論理的で整理された説明力
茂木氏の話し方は、結論→根拠→対策→効果の順で進む「型」が安定しています。
たとえば賃上げのテーマなら、まず「賃上げを継続させる」ことを結論として掲げ、その理由として企業収益や生産性の推移を示し、具体策として税制優遇や取引の適正化を挙げ、最後に家計消費や地域経済への波及を説明する——という具合です。
各段階が短い文で区切られ、要点ごとに話がまとまるため、聞き手は迷子になりにくくなります。
さらに、反対意見への先回りもよく見られます。たとえば「財政負担が増える」といった懸念に対しては、歳出の重点化や無駄の削減、政策の実施時期をずらす案などを併せて提示します。
これにより、単なる理想論ではなく、実行段階まで視野に入れた“段取りのある説明”になっている点が、茂木氏の演説の強みと言えるでしょう。
3.高市早苗|理念を力強く打ち出す
国家観や防衛政策を断定的に提示
高市早苗氏の演説は、最初の一文から立場が明確です。
たとえば「国を守るのは政治の最優先」と言い切り、「抑止力を高め、国民の命と暮らしを守る」と続けます。言い回しは短く、主語と動詞がはっきりしているため、聞き手は迷わず主張の芯をつかめます。
安全保障を語る際は、ミサイル防衛、領域警備、サイバー対策など、具体的な領域名を並べて優先順位を提示します。
たとえば「サイバーは今この瞬間も攻撃されている分野。官民連携で防御を固める」といった具合に、日常の危機感と結びつけて説明します。
経済政策でも同じ調子で、「電力の安定供給が物価の土台」「中小企業の賃上げには取引適正化」と、生活に近い言葉へ落とし込みます。断定的な語調は支持層に安心感を与え、「この人は迷わない」という印象を生みます。
数値を交えた説得力ある演説
高市氏は、主張を数字で支える場面が多く見られます。
代表的なのは防衛費の目標で、「GDPの2%以上」という具体的な基準を掲げ、装備の更新周期や人員確保の費用感に触れながら必要性を説明します。
たとえば「老朽化した装備を更新し、弾薬を確保し、隊員の処遇を改善する——この三つを同時にやるには、1年限りの増額では足りない」と段階的に示すため、聞き手は“どこにお金が使われるのか”をイメージできます。
家計に直結するテーマでも、数字の使い方は同様です。電気料金なら「燃料価格が家計にどれだけ響くか」、賃上げなら「物価上昇率と実質賃金の差」を示し、「企業の価格転嫁を後押しする仕組み」「中小への支援枠」など対応策を列挙します。
数値と手立てをセットで語ることで、主張が“願望”で終わらず、“計画”として受け止められるのが強みです。
一方で、断定的な言い回しは賛否を分けやすく、反対意見への橋渡しが不足すると議論がかみ合いにくくなることもあります。
数字で裏付ける姿勢を保ちながら、懸念点への答えや代替案にも一言添える——そのひと工夫が、より広い層に届く鍵になります。
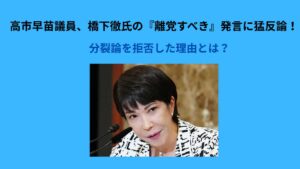
4.小林鷹之|生活者視点と政策のバランス
暮らしの実感に寄り添う言葉
小林鷹之氏の演説は、専門用語よりも生活に密着した表現を使う点が特徴です。
たとえば「光熱費が高くて家計が厳しい」という市民の声を取り上げ、それに対して「エネルギー政策の見直しが必要」とつなげていきます。
抽象的なスローガンではなく、日常の悩みを起点に話を進めるため、聞き手は「自分たちの声が届いている」と感じやすくなります。
抽象語と政策語彙のバランス
小林氏は抽象的な理念と具体的な政策語彙を組み合わせるのが得意です。
たとえば「未来への安心」という抽象的なフレーズの後に、「公定価格の見直し」「財政規律の確保」といった具体策を続けます。
この構成によって、聞き手は大きな方向性をイメージしながら、同時に実行手段も理解できます。
小泉進次郎氏のように印象重視に偏るわけでもなく、茂木敏充氏のように数字一辺倒になるわけでもない、バランス型のスタイルです。
知名度不足で存在感に課題
一方で、小林氏の課題は知名度の低さにあります。
大臣経験はあるものの、テレビ出演やメディア露出は限られており、一般市民にとっては「まだよく知らない候補」の印象が強いでしょう。
演説そのものは誠実で分かりやすいのですが、大きな舞台での発信力に欠けるため、総裁選のように注目度の高い場では埋もれてしまう危険性があります。今後は、自らのメッセージを広く届ける戦略をどう築くかが課題になりそうです。
5.林芳正|調整型で慎重な発言
不適切発言の撤回と柔軟な対応
林芳正氏は、発言に誤解が生じた場合でもすぐに修正や謝罪を行う柔軟さを持っています。
たとえば「自分ならやらなかったかもしれない」と給付策を評価した発言が批判を受けると、すぐに撤回とお詫びを表明しました。
この対応は、責任ある立場としての誠実さを印象づける一方で、強いリーダー像を期待する層には物足りなく映ることもあります。
官房長官として培った調整力
林氏の強みは、長年の官僚的な調整力です。
外務大臣や官房長官として、国際交渉や与党内の意見調整に取り組んできた経験から、物事を円滑に進めるスキルを持っています。
演説でも、極端に振れることなく「現実的にできること」を意識した言葉選びが目立ちます。そのため派閥や党内関係者からの信頼は厚く、組織運営に強い候補と言えるでしょう。
強烈なメッセージ性に欠ける点
ただし、林氏の演説は無難にまとまる分、強烈な印象を残しにくいという弱点もあります。
小泉進次郎氏のようなキャッチーなフレーズもなく、高市早苗氏のような理念訴求の迫力もないため、一般市民には「地味」と映ることがあります。
安定感を重視する層には好印象ですが、カリスマ性を求める有権者には響きにくいのが課題です。

自民党総裁選 主要5候補の発言比較表
| 候補者 | 発言サンプルの特徴 | 抽象語の多さ | 政策語彙の多さ | 全体傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉進次郎 | 「今のままではいけない。でも、これまで通りでいいわけではない」 | ◎ 高い | △ 低い | 印象重視・リズム感のある抽象的表現が中心。聴衆の耳に残りやすいが、中身が薄いと批判されやすい。 |
| 茂木敏充 | 「経済再生にはデータと科学的根拠に基づく政策判断が必要だ。FTAやEPAの交渉で日本がリーダーシップを発揮してきた」 | △ 低め | ◎ 高い | データ・交渉・制度など具体的な政策語彙が多く、実務派。情緒性は弱いが国際交渉力を示せる。 |
| 高市早苗 | 「国を守る気概を持たなければならない。防衛費をGDPの2%以上にするのは最低限の責務」 | ○ 中程度 | ○ 中〜高 | 理念と数字を織り交ぜる。断定的な語調で支持層に強く響くが、分断リスクもある。 |
| 小林鷹之 | 「暮らしが良くならないという声を多く聞いた。公定価格を引き上げ、安易な赤字国債発行は避ける」 | ○ 中程度 | ○ 中程度 | 生活者目線を重視しつつ、財政・経済語彙を織り交ぜる。安定・堅実な印象。 |
| 林芳正 | 「給付策について『自分ならやらなかったかもしれない』と述べたのは不適切だった。誤解を招いたことをお詫びし、撤回する」 | △ 低め | ○ 中程度 | 調整型で慎重。謝罪・撤回など柔軟さを示す一方、強いメッセージ性は弱い。 |
- 発信力・印象派 → 小泉進次郎
- 実務派・交渉型 → 茂木敏充
- 理念訴求型 → 高市早苗
- 生活者視点+政策語彙のバランス → 小林鷹之
- 安定調整型 → 林芳正

まとめ
自民党総裁選2025に立候補した5人の演説スタイルを比較すると、それぞれに明確な個性と課題が浮かび上がります。
小泉進次郎氏は耳に残るフレーズで注目を集め、政治に無関心な層にもリーチできる一方で、政策の中身の薄さが指摘されます。
茂木敏充氏はデータと交渉実績を武器に実務力をアピールできますが、情緒的な訴えが弱く、国民の心に響きにくい点が課題です。
高市早苗氏は理念と断定的な言葉で力強さを示し、支持層には強烈に響きますが、分断を招くリスクを抱えています。
小林鷹之氏は生活者目線の言葉と政策をバランス良く取り入れ、誠実な印象を与えますが、知名度や発信力の不足が弱点です。
そして林芳正氏は調整力と安定感を備えた発言で信頼感を築けますが、強いメッセージ性に欠け、大衆の印象に残りにくい傾向があります。
総理大臣に求められる資質は一つではありません。発信力、実務力、理念、生活者視点、調整力──どの要素を最重視するかによって、有権者の選択は変わります。
演説の言葉は、その候補者の政治姿勢やリーダー像を映し出す鏡です。総裁選を通じて、私たち一人ひとりが「どんなリーダーを日本に望むのか」を考えることこそ、投票行動につながる大切なステップになるでしょう。

コメント