映画『チェンソーマン ロゼ編』のエンディング曲「JANEDOE」。米津玄師さん×宇多田ヒカルさんの豪華コラボに加え、MVの“地下鉄”がどこなのかも話題です。
本記事ではジョージア・トビリシ地下鉄が有力と考える理由を、車両の見た目・ベンチの形・壁や天井の意匠など、ぱっと見で分かるポイントに絞ってわかりやすく解説します。
はじめに

本記事の目的と結論要約(トビリシ地下鉄が有力)
本記事の目的は、「JANEDOE」MVに登場する地下鉄シーンのロケ地を、映像のディテール比較から分かりやすく示すことです。
結論はシンプルで、ジョージア(グルジア)・トビリシ地下鉄(Line 1)で撮影された可能性が非常に高いというもの。
根拠は、①旧ソ連製81-717系に特徴的な車体形状と配色、②ホーム中央の超ロング木製ベンチ+石の背もたれ+金属支柱という造作、③壁面の灰色石タイルに半円アーチの描画、④天井の連続ライトボックス(乳白パネルの長い帯)といった、複数の要素が同時に一致しているためです。
駅名は映像に文字情報がないため未確定ですが、Isani~Samgori 区間がもっとも整合します。
この記事で扱う検証範囲と“推定”の位置づけ
本記事は、MVの地下鉄シーンに限定して検証します。
使用する材料は、スクリーンショットや公開映像の見た目の一致点(車両の“顔”、ベンチの素材と形、壁の模様、天井と床のパターン)で、難しい専門用語は避け、「どこがどう似ているか」を写真の見どころレベルで説明します。
制作サイドから公式クレジットは現時点で未掲出のため、ここでの結論は高精度の“推定”として扱います。
また、天井パネルが砕ける描写は撮影用パネル+VFXの演出と見なし、設備破壊ではない前提で触れます。最終的な駅名や技術クレジットが公表された場合は、事実に合わせて更新する方針です。
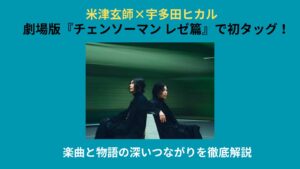
1.JANEDOE MVの地下鉄シーン概要
主要カットの特徴(ホーム・車両・天井ライト)
MVの地下鉄シーンは、①ホーム中央に“延々と続く”木製ロングベンチ、②ホームを通過・停車する旧型の濃緑車両、③頭上を帯のように走る乳白色のライトボックス、の3点で構成されています。
とくにベンチは木の座面+石の背もたれ+金属支柱という珍しい組み合わせで、一本の長椅子が画面の奥行きを強調。
車両は角張った窓枠と太い窓縁が目立ち、走行時のモーター音が“重め”に響くのも印象的です。
天井のライトは切れ目の少ない連続パネルで、カメラの移動に合わせて光の帯が流れるように映り、クライマックスではパネルが粉砕する演出が入ります。
画としての統一要素(色調・素材・配置)
全体の色調は濃いグレー(壁・床)×深い緑(車両)×木の茶(ベンチ)×乳白(天井光)で統一。
石材のマットな質感と木の温かみ、金属の冷たさが同居し、画面に“古いけれど強い”コントラストを作ります。
配置面では、ベンチがほぼ画面センターの軸になり、壁面の半円アーチ模様がリズムを刻むことで、カットが変わっても“同じ場所にいる”というつながりを保っています。
人物が入るショットでは、この軸に沿って前後左右の距離感をはっきり見せるため、観る側は自然と奥行き→人物→光源の順で視線が流れます。
注意点(公式クレジット未掲出と検証の前提)
このセクションは映像から読み取れる事実を土台にまとめています。現時点で制作側の公式クレジットにロケ地の明記はありません。
したがって、以降の検証(車両の型・ベンチの造作・壁や天井の意匠からの照合)は、“映像比較に基づく推定”として扱います。また、天井パネルが割れるカットは安全素材の差し替え+視覚効果(VFX)による演出と考え、実際の駅設備を破壊していない前提で読み解きます。
2.なぜトビリシ地下鉄と言えるのか(一致ポイント検証)
車両:旧ソ連製81-717系の外観・配色の一致
まず目につくのは車両の“顔つき”です。角ばった大きめの窓、太い窓枠、ドアの位置関係、屋根肩の丸み——これらは旧ソ連製「81-717系」グループの定番ディテールです。
MVの車体色は深いオリーブ系の緑で、窓まわりはアイボリー寄りの明るい縁取り。この配色は、近年のトビリシ地下鉄(Line 1)で実在する塗装とよく合います。
走行シーンでは、加速時に車体側面の“窓列のリズム”が強く出て、編成の古さと重さが画面に乗る——ここもトビリシの実車イメージと重なります。
ベンチ/壁:木×石×金属+半円アーチ模様の一致
ホーム中央には、とても長い木製ベンチが一本物のように続きます。
背もたれは石でできており、それを等間隔の金属支柱で固定。日本や西欧ではあまり見ない組み合わせで、コーカサス地域の駅で見られる造作に近いのがポイントです。
さらに、背面の壁は灰色の石タイル仕上げで、その上に半円アーチのライン模様が“描き”として回り込んでいます。
石の冷たさと木の温かさ、金属の無機質感——この素材ミックスは、トビリシの駅写真と並べても違和感がありません。
天井/床:連続ライトボックスとタイル縁取りの一致
天井は、乳白色のパネルが帯状に連なるライトボックス。切れ目が少なく、カメラが動くと“光の川”のように見えるのが特徴です。
クライマックスでパネルが砕け散る演出が入りますが、基礎の形状は実駅の天井意匠と一致します。
床は濃いグレーの石タイルに、明るい縁取り(ボーダー)を回すデザイン。ベンチの足元ラインと相まって、画面にまっすぐな遠近の軸を作ります。
ライトの“水平帯”+床の“縦のボーダー”+ベンチの“長い直線”が三位一体で、トビリシのホームで感じる奥行き感をそのまま再現しているのが分かります。
3.駅の絞り込みと残る不確定要素
候補区間:Line1「Isani~Samgori」が最有力な理由
候補をこの区間に絞る決め手は、“3つの並び”がそろうことです。
1) 天井の帯状ライト……一本の大きな光の帯がホーム中央をまっすぐ貫く。
2) 床の明色ボーダー……濃い石タイルの中に細い“縁取り”が走り、遠近感を強調。
3) 超ロング木製ベンチ……座面が長く続き、石の背もたれを金属支柱で固定。
この三点セットに、灰色石タイルの壁+半円アーチ模様が加わると、見え方がIsani〜Samgori付近のホーム写真と非常に近くなります。
とくに、ベンチの“座面の連続感”と、天井帯の“幅と位置”のバランスが、他区間よりもこのセクションによく似ています。
決め手となる情報(駅名標・サイン・脚部形状)の不足
最終確定には駅名標(ジョージア文字)が必要です。
- Isaniは「ისანი」、Samgoriは「სამგორი」。この綴りが柱や壁に写れば一発で決まります。
- ほかにも、ベンチ台座の断面形(石台の厚みや角の面取り)、壁アーチの間隔、床ボーダーの幅といった“寸法の癖”が比較材料になります。
今回は看板のアップが映っていないため、駅名までは断言せず、路線・区間レベルの特定にとどめます。
天井破砕シーンの解釈(プロップ+VFXの可能性)
公共設備を実際に壊すことは現実的ではありません。
- 割れるパネルだけを安全素材(樹脂等)の撮影用パーツに差し替える
- 飛散量や破片の軌道、光の反射をVFXで増強する
というハイブリッド演出がもっとも自然です。実際、割れる直前と直後で光の反射や破片の“数”に差があり、物理破壊+合成の併用が推測できます。
駅そのものの形(ライト帯の位置・幅)はMV全体で一貫しているため、“本物の駅の意匠”に合わせて作られた差し替えパネルを使った、と考えるのが妥当です。
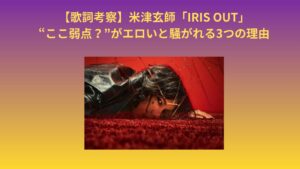
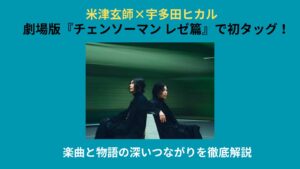
まとめ
本記事では、「JANEDOE」MVの地下鉄シーンを映像の一致ポイントから検証し、ジョージア・トビリシ地下鉄(Line 1)で撮影された可能性が高いという結論に至りました。
決め手は、①旧ソ連製81-717系相当の車両外観と配色、②木製ロングベンチ+石の背もたれ+金属支柱という独特の造作、③灰色石タイル+半円アーチ模様の壁、④乳白色の連続ライトボックスという天井意匠の“同時一致”です。駅名は断定していませんが、Isani~Samgori 区間が最有力です。
ロケ地の公式クレジットは未掲出のため、本稿の結論はあくまで高精度の推定として扱います。
天井パネルの破砕は、撮影用パネル+VFXのハイブリッド演出と見るのが妥当です。
今後、制作側から正式なロケ地情報や技術クレジットが公開された際は、内容を即時アップデートします。読者のみなさんが気づいた一致点(駅名標の断片、柱の形状、床ボーダーの幅など)があれば、コメントでお寄せください。検証の精度をさらに高めていきます。
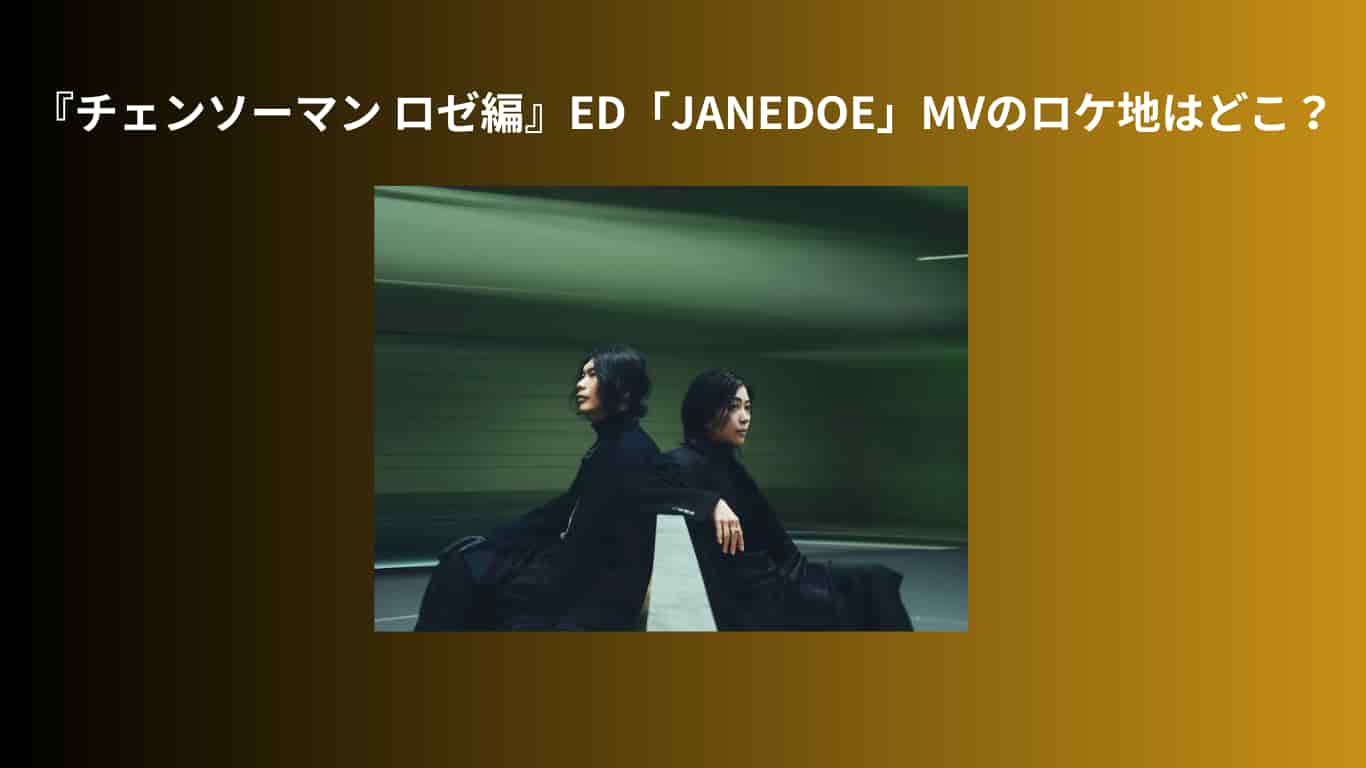
コメント