スーパーでお米を買うたびに、「あれ?また少し高くなった?」と感じること、ありませんか?
私もそう思っていた矢先、ニュースで石破首相が「お米の増産に転換する」と発表したと聞いて、正直ちょっとびっくりしました。
でも、実際のところ、すでに田植えは終わっていて、夏の暑さで収穫量も減りそう…。そんな中で「増産します!」って言われても、現場の農家さんはどう感じているんだろう?
このブログでは、ひとりの主婦として、お米の価格や供給のこれからについて、わかりやすくまとめてみました。難しい話は抜きにして、「私たちの食卓にどう影響するのか?」を一緒に考えてみませんか?
はじめに

食料自給率とコメ政策の転換に注目が集まる理由
日本の食卓に欠かせない「お米」。その安定供給をどう確保していくかは、わたしたちの生活に直結する大きなテーマです。
特にここ最近は、ウクライナ情勢や円安などの影響で、輸入に頼る小麦や油の価格が上昇し、改めて「国産の主食をどう守るか」に注目が集まっています。
そんな中、石破首相が掲げたのは、コメの増産政策への転換。これまでの“過剰生産を防ぐ”方向性から一転し、“もっと作っていこう”という新たなスタートです。
背景には、日本の食料自給率がカロリーベースで約38%(2022年度)という先進国では異例の低さであることが関係しています。
とくにコロナ禍以降、物流の混乱や価格変動が起きるたびに「食料の国産化を強化すべきだ」という声が高まってきました。お米は日本の気候に合っていて、全国の農家が栽培し続けてきた作物です。
だからこそ、増産に本腰を入れる政策の転換は、多くの国民にとって関心の高い話題となっています。
石破首相が打ち出した新たな「増産方針」とは
2025年(令和7年)産のコメから、政府は増産を本格的に進める方針を示しました。
石破首相は、米の価格が一時的に高騰した背景には、収穫量の見通しが立てづらかったり、流通構造の不透明さがあったことを認め、それらを改善するための具体策を次々と発表しています。
たとえば、農家が安心して生産を増やせるように、政府は買い取り制度を見直し、小売業者に直接販売できるルートを整備。
また、「作況指数」という収穫の予測指数の公表をやめ、実際の収穫量を重視した新しい仕組みへと統計も見直されています。
これらの政策は、単に米の供給量を増やすだけでなく、農家の所得を守りつつ、消費者が安定価格でお米を手に入れられるようにする“バランス重視”の姿勢が特徴です。
石破首相は、小泉農林水産大臣を中心に、関係省庁が一丸となって取り組むよう呼びかけています。
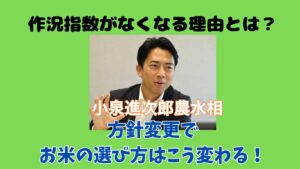
1.米価格高騰と政府の初期対応
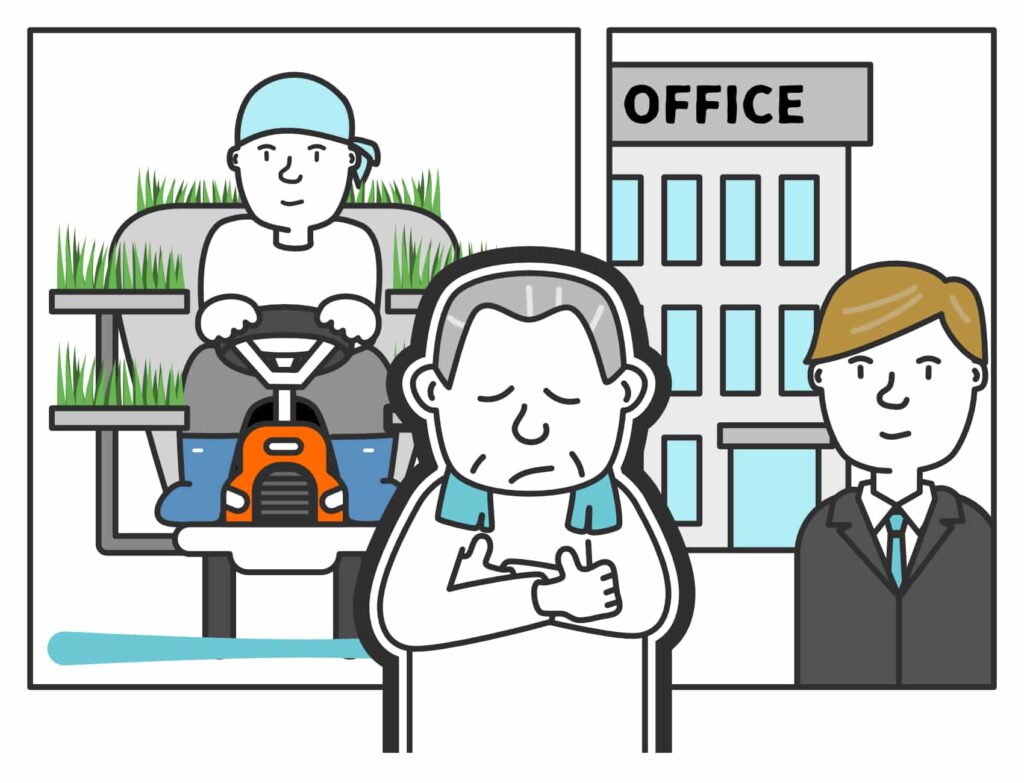
販売店舗拡大と価格水準の安定化
コメの価格が上昇した背景には、天候不順や生産量の減少に加え、流通経路の限定など複数の要因が重なっていました。
これに対し政府は、迅速に備蓄米の流通ルートを見直し、販売店舗の拡大に取り組みました。
これまで、備蓄米は特定の業者を通じて販売されていたため、消費者の手元に届くまでに時間がかかり、価格にもばらつきが生じていました。
そこで、政府は新たな販売ルートを確保し、スーパーやドラッグストアといった日常的に利用される小売店舗に迅速に備蓄米を届ける体制を整えました。
その結果、米1袋(5kg)の平均価格は一時4000円台を超えていたものの、現在は3801円と、3000円台に戻るまでに落ち着いています。
家計を直撃する米価格の上昇に歯止めがかかったことは、多くの家庭にとって安心材料となりました。
随意契約・買戻し要件の撤廃の影響
販売ルートの多様化を支えたのが、「随意契約の導入」と「買戻し要件の撤廃」という2つの制度改正です。
従来は、政府が定めた条件を満たす業者としか契約できず、流通に時間と手間がかかっていました。これを見直し、より柔軟な契約ができるようにすることで、必要な時に必要な量を市場に供給できるようになったのです。
また、これまで備蓄米の販売には「一定期間内で買い戻す」という条件が付き、業者側にとっては負担が大きいものでした。
この要件が撤廃されたことで、小売業者が在庫リスクを気にせずに販売できるようになり、結果的に店舗数や取扱量の増加につながりました。
特に地方の中小スーパーでは、これまで備蓄米の扱いが難しかったのが、制度の柔軟化によって仕入れが可能になり、地域住民の生活を支える一因となっています。
小売事業者への直接売渡しの成果
さらに注目すべきなのが、政府が小売事業者へ直接米を売渡す制度を取り入れた点です。
これまで流通の中間に複数の業者が入ることで価格が上乗せされるケースもありましたが、政府と小売業者が直接やり取りできるようになったことで、中間マージンが削減され、販売価格の抑制にもつながっています。
たとえば、ある全国チェーンのスーパーでは、この制度を活用して安価な政府米を自社ブランドとして提供し、5kgあたり3500円以下で販売したところ、消費者の反応は上々で、売上も安定して伸びたといいます。
このような一連の初期対応は、急激な価格変動を最小限に抑えるとともに、今後の増産体制の下支えとなる重要なステップとなりました。
2.価格高騰の要因と統計の見直し
流通構造の可視化と全事業者調査の意義
米の価格が一時的に急騰した背景には、実際の需給バランスを把握するための情報が不足していたことが大きな要因とされています。
特に、農家から消費者に届くまでの流通経路が複雑で、「どこでどれだけ在庫が滞っているのか」や「価格がどこでどのように決まっているのか」が不透明でした。
この問題を改善するため、政府は全国の届出事業者すべてを対象にした大規模な調査を実施。
流通構造を「見える化」し、どの業者がどの段階でどれだけの米を扱っているかを明らかにしました。これにより、「在庫があるのに出回らない」といったミスマッチを把握し、流通のボトルネックを特定することが可能になりました。
たとえば、一部の大手卸業者が過剰な在庫を抱えていた一方で、地方の小売業者は仕入れができずに販売機会を逃していたケースもあったことが調査で判明しました。
このような実態を把握することで、今後の対策に活かされることが期待されています。
作況指数の廃止と収穫量の把握方法の変更
これまで農業の現場では、毎年の作柄を示す「作況指数」が指標として使われてきました。
しかし、実際の収穫量とは必ずしも一致しないこの指数に基づいて市場が動くことで、米の供給量や価格が不安定になることが課題視されてきました。
そこで政府は、作況指数の公表を廃止し、より現実的な「収穫量の実数」に基づいた統計に切り替えることを決定しました。
今後は、農家から直接得られる収穫報告や、流通実績データなどをもとに、より正確な需給の把握を目指します。
たとえば、同じ「平年並み」の作況指数であっても、地域によって収穫のばらつきが大きく異なることがあります。
このばらつきが市場に反映されず、予想外の価格変動を招くケースも少なくありませんでした。新たな統計方法によって、こうした「実態と乖離した情報」の解消が期待されています。
生産者アンケートによる意向調査
今後の米の増産を円滑に進めていくためには、現場で生産を担う農家の「やる気」や「不安の有無」をしっかり把握する必要があります。
そこで政府は、生産者を対象としたアンケート調査を実施し、どの地域でどの程度の増産が見込めるのか、また障壁となっている問題は何かを明らかにしようとしています。
このアンケートでは、たとえば「農機具が老朽化していて増産は難しい」「後継者がいないため生産面積を増やせない」など、現場からの率直な声が集められました。
一方で、「価格が安定するなら生産量を増やしたい」「販路が確保されるなら挑戦してみたい」といった前向きな意見も多く、政府の政策判断に反映されています。
こうした生産者の声を政策に反映させることで、単なる数字の目標ではなく、実現可能で持続可能な増産体制の構築を目指すというのが、今回の新政策の大きな特徴です。
3.令和7年産からの本格的増産政策

意欲ある生産者支援と所得確保の施策
コメの生産量を増やすには、まず農家が安心して作付けに取り組める環境づくりが不可欠です。
政府は令和7年産からの本格的な増産に向けて、特に「意欲のある生産者」への支援を強化する方針を掲げました。
たとえば、コメを増産する農家には収穫量に応じた補助金や、栽培に必要な資材費の一部助成などが検討されています。
また、過去に米価の下落で打撃を受けた農家にとっては、「ちゃんと売れる」「赤字にならない」といった経済的安心感が重要です。
これに対応するため、政府は新たに「価格安定制度」の導入も視野に入れており、収入が下がった場合に補てんされるような仕組みをつくることで、増産へのハードルを下げようとしています。
さらに、若手農家や新規就農者へのサポートとして、機械の導入補助や地域での営農支援なども強化される見込みです。こうした施策が実現すれば、米づくりに再挑戦する人も増え、地域農業の活性化にもつながる可能性があります。
消費者の安定供給に向けた取り組み
消費者がいつでも安心してお米を手に入れられるようにするには、生産だけでなく「販売ルートの安定」も重要です。そのため政府は、増産されたコメが確実に市場に届くよう、需要と供給のマッチングにも力を入れています。
具体的には、学校給食や介護施設、病院など大口でお米を使用する施設への優先供給体制の整備が進められています。また、コメの品種ごとの需要予測データを共有し、生産者が「売れるお米」を選んで作れるようにする工夫も始まっています。
加えて、消費者が求める価格帯でコメを提供するため、物流コストの見直しや、JA(農業協同組合)や流通業者との連携強化も進められています。たとえば、1kg単位の小分け販売やネット注文に対応した新サービスの開発など、消費行動の多様化に合わせた対応が期待されています。
備蓄水準の回復と政府一体での推進体制
今回の政策転換において、もう一つの柱が「備蓄米の適正水準への回復」です。
備蓄米は、自然災害や急な不作時などに備える重要なストックですが、ここ数年の減産方針によって備蓄量が減少していました。これを再び一定水準に戻すことで、国全体の「食の安全保障」も強化されます。
石破首相はこの点について、林官房長官や小泉農水大臣らに対し、「関係省庁が一体となって取り組むように」と強く指示しました。内閣官房や農水省のほか、財務省や経産省、総務省も連携し、増産に必要な予算確保や地域支援策を講じていく流れとなっています。
たとえば、災害時に備えた「ローリングストック方式」での備蓄更新や、全国の地方自治体との協定による分散備蓄の検討も進められています。政府全体で計画的かつ持続的なコメ供給体制を構築することで、消費者も農家も安心できる「未来の食卓」を支えていく構えです。
とはいえ、今年の作付けはすでに春に終わっており、実際にお米を増やせるのは来年以降になります。今年の夏は全国的に猛暑が続いており、稲の実り具合にも影響が出るのではと心配されています。
そうした中で発表された「増産方針」には、「これは本当に現場を見たうえでの政策なのか?」という疑問の声も出ているようです。一部では、「選挙前のアピールでは」といった指摘もあり、やや慎重な見方も根強くあります。
増産を進めるには、補助制度や販売先の確保など、農家が実際に動き出せるような仕組みづくりが欠かせません。ただ「増やしてください」と言うだけでは、現場は動けないのです。
だからこそ、政府には見せかけではない実効性のある対策を、ひとつずつ丁寧に進めていってほしいと感じます。
まとめ
お米は、日本人の食卓にとって欠かせない存在です。だからこそ、米の価格が不安定になったり、スーパーでいつもより高い値札を見つけたりすると、「これからどうなるの?」と心配になりますよね。
今回、石破首相が打ち出したコメ増産の新しい方針は、そんな不安を払拭しようとする一歩だったのかもしれません。政府が米価の安定や流通改善、農家支援までを含めた包括的な対策を進めていることは、確かに前向きな動きだと感じます。
ただ、今すぐに増産できるわけではないというのも現実です。今年の田植えはすでに終わっており、猛暑の影響も心配されていますし、「選挙向けのパフォーマンスじゃないの?」という厳しい声が出るのも理解できます。
大事なのは、こうした政策が一過性のもので終わらず、ちゃんと現場に届いていくこと。農家が「これなら増やしても大丈夫」と思える仕組みを、消費者が「ちゃんと買える」と感じられる価格で届けられる仕組みを、地道に作っていくことが本当に必要なんだと思います。
私たち一人ひとりの生活にも関わる「お米」の話、これからも目を向けていきたいですね。
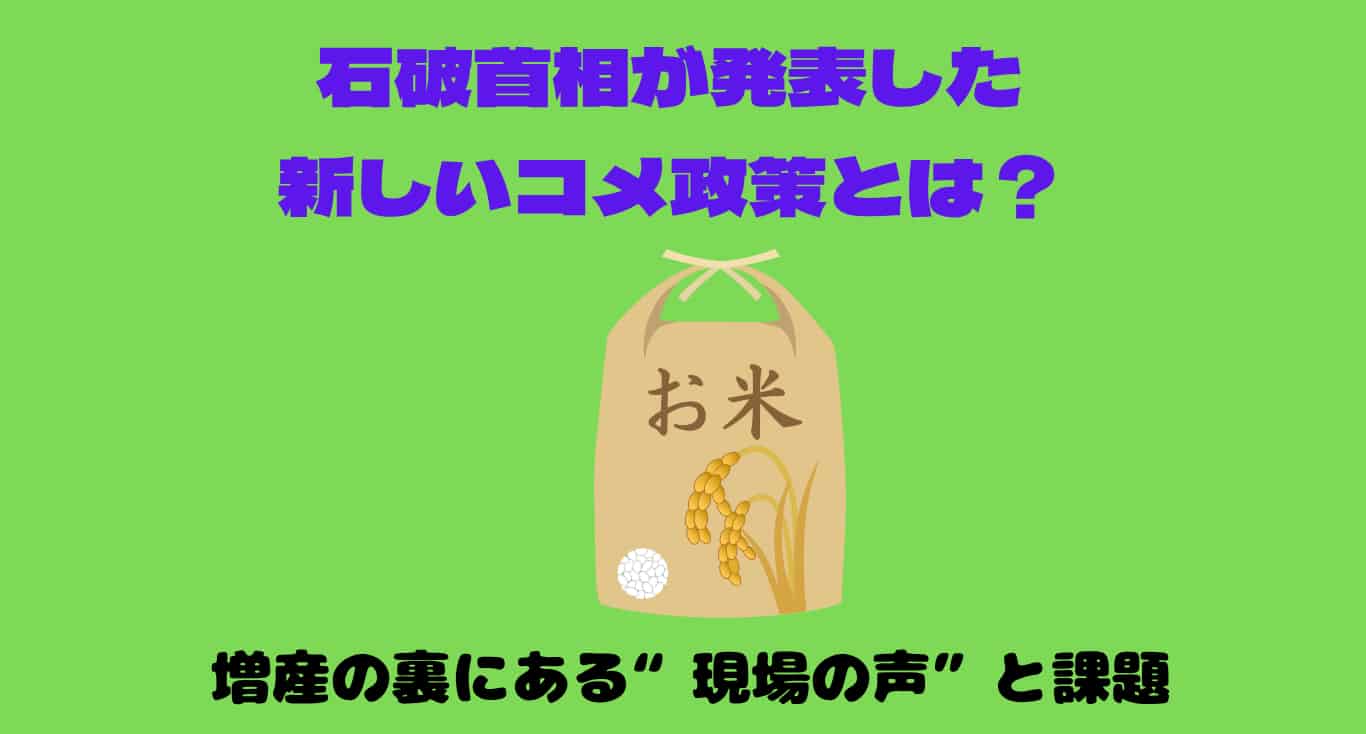
コメント