SNS上で急増している「犬笛」――特定の人物や団体への抗議や攻撃を呼びかける行為は、時に“間違った正義感”から発信され、想像以上の被害を生み出します。
本記事では、兵庫県の斎藤知事を巡るSNS騒動をきっかけに、元落語家が人生を大きく変えざるを得なくなった実例や、犬笛を吹いた本人の後悔、そして言論の自由と責任のあり方を詳しく解説します。
誹謗中傷やネット炎上の危険性を理解し、発信前に立ち止まるヒントをお伝えします。
はじめに
SNS時代に広がる「犬笛」現象とは
近年、SNS上で特定の人物や団体に対して抗議や批判を呼びかける投稿が増えています。
この行為は比喩的に「犬笛」と呼ばれ、直接的に攻撃対象を示さなくても、受け取った人々が自発的に行動するよう扇動するのが特徴です。
本来の「犬笛」は犬にしか聞こえない音を出す道具ですが、ネット上では仲間内だけが意図を汲み取り、攻撃や抗議に向かう構造を指します。
間違った正義感がもたらす誹謗中傷の連鎖
問題は、この「犬笛」がしばしば“正義感”に基づく行動として行われる点です。
発信者は自分の信じる正義のためと考えますが、結果的に他人の名誉や生活を奪うケースも少なくありません。
今回取り上げるのは、兵庫県の斎藤知事を巡るSNS上の抗議呼びかけと、それによって人生が大きく変わってしまった人々の実例です。
1.「犬笛」が生んだ標的とその影響

元落語家・月亭太遊さんが直面した誹謗中傷
2025年3月、落語家の月亭太遊さん(40)は、自身のX(旧Twitter)で「月亭太遊という名前を返上し、落語家を辞める」と発表しました。
きっかけは、兵庫県の斎藤元彦知事や、同知事を支援したNHK党・立花孝志党首を批判する投稿でした。これを受けて、SNS上で“犬笛”と呼ばれる抗議呼びかけが拡散。所属先である吉本興業や上方落語協会、さらに月亭一門へ苦情や嫌がらせが相次ぎました。
太遊さんは「事態を終息させるため、自らの意思で名前を返上し、落語家を辞めることにした」と説明。
芸名の返上は、事実上プロの落語家としての活動終了を意味しますが、「落語は自作のものを続ける」とし、発言や芸事は続ける意向を示しました。
芸名返上と落語界からの事実上の退場
Xのユーザー名も「ひょうきんなオッサン」に変更し、「ツキテイ太遊だった者です。もうツキテイでも太遊でもありません」と表明。
寄席など落語専門の舞台には立てなくなり、今後はゲスト出演や自主公演など、限られた活動範囲で生きる道を模索することになりました。
標的化による生活・仕事への打撃
この一連の経緯は、SNS時代における批判の拡散力と、犬笛行為の影響の大きさを示しています。
たった数回の投稿が、築き上げた芸歴や仕事の場を失わせ、日常生活や精神面にも深刻な影響を与えた事例となりました。
月亭太遊(つきてい たいゆう)プロフィール
- 本名:非公表
- 生年月日:1984年(昭和59年)生まれ
- 年齢:40歳(2025年時点)
- 出身地:兵庫県
- 経歴:
- 2010年、月亭遊方に入門し「月亭太遊」を名乗る。
- 上方落語協会に所属し、寄席やイベント、メディア出演などで活動。
- 自作落語や独自の舞台構成に定評があり、若手落語家として注目される。
- 所属:吉本興業(エージェント契約、2025年3月時点では公式サイトに名前が残る)
- 活動停止の経緯:
- 兵庫県・斎藤元彦知事やNHK党・立花孝志党首を批判するSNS投稿をきっかけに、“犬笛”による抗議呼びかけが拡散。
- 所属団体や一門に苦情や嫌がらせが相次ぎ、2025年3月に芸名を返上し落語家を辞める決断を発表。
- 現在の活動名:「ひょうきんなオッサン」
- 活動方針:
- プロ落語家としての活動は終了したが、自作落語や芸事、発信活動は継続。
- イベント出演や自主公演を中心に活動予定。
2.犬笛を吹いた人の動機と後悔
「こいつ許せない」感情からの衝動的行動
この「犬笛」を吹いたのは、兵庫県出身で北海道在住の「ともさん(仮名)」。
斎藤知事を応援する立場から、批判的な人物を「許せない」と感じ、「みんなで通報しよう」という気持ちで行動しました。
そこには金銭的利益やフォロワー獲得の目的はなく、あくまで自身の中の正義感が原動力だったと語ります。
ネット情報を鵜呑みにした浅はかさ
しかし、ともさんは一次情報を確認せず、ネット上で流れる情報だけを信じて行動してしまったと振り返ります。
その結果、対象となった人の仕事や人生を奪ってしまう可能性があったことに気づき、「間違った正義感」だったと後悔しました。
弁護士の指摘で気づいた誤り
転機となったのは、弁護士・大前治さんのSNSでの指摘でした。
ともさんが投稿に吉本興業や落語協会の電話番号を記載していたことは、威力業務妨害を招く可能性がある違法行為だと明言され、初めて自らの行動の重大さを自覚したのです。
3.SNS時代の言論の責任と危うさ
フェイク情報にだまされやすい心理
国際大学の山口真一准教授によると、フェイク情報を見抜けた人はわずか14.5%。
しかも「自分は大丈夫」と思う人ほど、実際にはだまされやすい傾向があるといいます。
SNS上での情報は真偽不明なものも多く、感情に流されると判断を誤る危険性があります。
「言論の自由」と「言論の責任」の両立
共同通信の太田昌克編集委員は「言論の自由には言論の責任がある」と強調します。
一時の感情や周囲の空気に流されて発する言葉は、刃物のように人を傷つけ、人生を狂わせる力を持ちます。その影響は本人だけでなく、家族にも及びます。
発信前に立ち止まるための心構え
SNSで発信する前に、その情報の真偽を確認し、自分の言葉がどのような影響を与えるかを考えることが重要です。
「正義感」という名のもとで行動しても、それが他者の権利を侵害するものであれば、法的にも倫理的にも許されません。
まとめ
SNS時代における「犬笛」は、善意や正義感が引き金となる一方で、他者の人生を破壊する危険な行為となり得ます。
情報の真偽を見極め、冷静な判断をもって発信することが、言論の自由と責任を両立させる第一歩です。
感情的な呼びかけや攻撃に加担する前に、一度立ち止まり、その行動の意味と結果を考える必要があります。
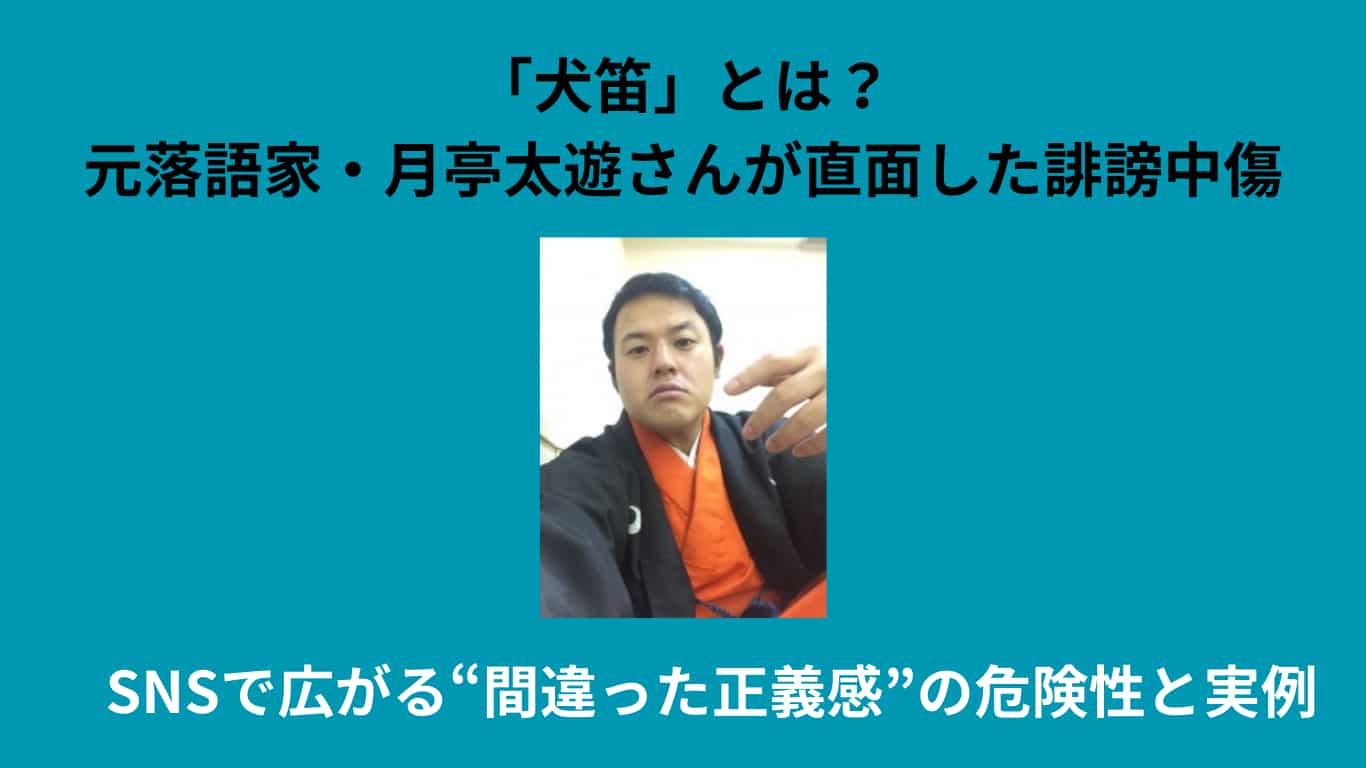
コメント