就職氷河期世代――1990年代から2000年代前半に社会に出た人たちは、バブル崩壊やリーマン・ショックなどの経済危機のあおりを受け、正社員になれず不安定な働き方を強いられてきました。
2025年現在、彼らは50代に突入し、年金や老後の生活に不安を抱える人が急増しています。
この記事では、生活保護で月13万円の生活を送りながら、都内の食料配布に足を運ぶ鈴木孝さん(仮名)の歩みを通して、就職氷河期世代が直面する厳しい現実と、公的支援の限界をわかりやすく紹介します。
政府や政党が掲げる支援策に、今後どのような改善が求められるのかも一緒に考えていきましょう。
はじめに
「失われた30年」を生きた世代が今、直面している現実
2025年5月のある土曜日、東京都庁前にできた長い行列。その先にあるのは人気イベントではなく、NPO法人などによる「無料の食料配布」でした。
横殴りの雨の中、列の最後尾に並ぶ鈴木孝さん(仮名・56歳)は、自宅から徒歩で4時間かけてやってきたと言います。
わずか数百円の電車賃すら出せず、スマートフォンを質屋に預ける日もあるという彼の暮らしは、想像以上に過酷です。
鈴木さんは、就職氷河期と呼ばれた時代に社会に出た世代のひとり。日本経済が長く停滞し、非正規雇用が常態化した「失われた30年」のただ中を生きてきた人々です。
会社の倒産、派遣切り、体調不良による離職……安定からほど遠い働き方を余儀なくされてきた彼らは、今もなお、そのツケを一人で背負わされています。
なぜ今、就職氷河期世代が注目されているのか
この氷河期世代の問題が再び注目を集めているのは、彼らが50代半ばに差しかかり、いよいよ高齢期に突入しようとしているからです。
非正規雇用や低収入のまま年を重ねてきた結果、年金額も低く、老後の生活に明るい展望を持てない人が多くいます。
政府はようやく本格的な支援に動き出し、就労支援や住まいの確保、年金制度の見直しといった政策を打ち出しています。
とはいえ、支援を受けるには「自分から」動くことが前提とされており、情報にアクセスできない人々には、制度そのものが届いていないのが実情です。
「就職できなかった自分が悪い」「自己責任だと言われ続けてきた」──そう語る氷河期世代の声に、私たちはどう向き合えばいいのか。
この記事では、鈴木さんの歩みをたどりながら、この世代が抱える課題と、今求められている支援の形を探っていきます。
1.氷河期世代・鈴木さんの歩んだ30年

バブル崩壊直後の就職活動と内定取り消しの連続
鈴木さんが大学に入学したのは1989年、バブル経済が真っ盛りだった頃です。
当時のキャンパスは、採用募集の掲示が所狭しと並び、「就職には困らない」という空気が流れていました。
しかし、就職活動を始めた頃には、景気は一転。バブルは崩壊し、企業の採用数は激減しました。
大学卒業を目前に控えた鈴木さんは、18社に応募し、3社から内定を獲得。ところが、いずれも「業績悪化」を理由に内定を取り消されてしまいました。
「本当に突然でした。会社からの連絡で、急に“ごめんなさい”と。頭が真っ白になりました」と当時を振り返ります。
そこから慌てて就職活動を再開し、ようやく地方の家具輸入会社に正社員として入社できたのは、卒業から数か月後のことでした。
正社員として働くも、倒産・派遣切りの繰り返し
しかし、その会社も安定とは程遠いものでした。入社3年目、ある朝突然、社長が夜逃げし、会社は実質的に倒産。「昨日まで普通に仕事をしていたのに、突然“明日から来なくていい”と言われました」。
鈴木さんは仕事を失い、生活の見通しを立てることも難しくなりました。
その後、知人の紹介で都内の自動車部品工場に再就職。ここでは10年ほど勤め、念願の安定した暮らしを手に入れました。
ところが、2008年のリーマン・ショックがその生活を打ち砕きます。
翌年、勤めていた工場は閉鎖され、再び職を失うことに。以後、派遣会社に登録し、金属加工や衣料品原料の工場など、職を転々とする生活が始まりました。
どの職場も一時的なもので、繁忙期が終われば「契約終了」。安定とはほど遠い日々が続きました。「30代、40代の貴重な時間を、“いつ切られるかわからない”という不安の中で過ごしていました」と鈴木さんは話します。
月13万円で暮らす現在の生活とスマホを質に入れる日常
そんな不安定な働き方が10年以上続いた結果、持病のヘルニアが悪化。手に力が入らなくなり、働くこと自体が難しくなりました。
現在は月13万円ほどの生活保護で暮らしており、その中から家賃・光熱費・医療費などを差し引くと、手元に残るのは数万円。食費を削るしかなく、業務用スーパーで27円の袋麺や88円の食パンを頼りに生きています。
「今月は足りない」と思った時は、スマホを質屋に持ち込み、7000~8000円を借りるのが習慣になっています。「スマホがないと食料配布の時間も場所も調べられないし、連絡もできなくなる。でも、食べられないよりはマシだから」と鈴木さんは語ります。
雨の中、都庁前の列に並びながら手にしたレトルトご飯と野菜入りの袋。そのわずかな支援に「ありがたい」と笑顔を見せる彼の姿に、この30年の重さがにじみ出ていました。
2.各政党・政府の支援策とその限界

政府が進める就労・ひきこもり・老後支援の枠組み
2025年、政府はようやく就職氷河期世代に対する本格的な支援策の見直しに乗り出しました。
これまでの就労支援に加え、高齢期の生活支援や住宅確保といった“暮らし全体”を視野に入れた政策が打ち出されたのです。
具体的には、65歳以上になる氷河期世代を想定し、年金だけでは生活できない人に向けた支出支援や、住まいの安定を支える制度の整備が進められています。
たとえば、生活困窮者向けに公営住宅の優先枠を拡大したり、低所得者への家賃補助の導入が議論されています。
また、就労支援としては、正規雇用への転換を促す企業に対する助成金制度の拡充や、職業訓練とセットになった再就職プログラムなどが実施されています。
しかし、こうした施策の多くは「自ら動ける人」にとっては有効でも、心身に不調を抱えていたり、社会との接点が少ない人にとってはハードルが高いままです。
実際、鈴木さんのように情報収集の手段すらままならない生活を送る人にとって、「制度がある」だけでは助けにならないのが現状です。
参院選で掲げられた各党の氷河期世代向け政策
2025年の参院選では、各政党がこぞって就職氷河期世代への支援策を公約に盛り込みました。
立憲民主党は「新しい家賃補助制度」を創設し、都市部での生活困窮を防ぐと明言。
日本維新の会は「社会保険料の軽減」を通じて実質的な手取りの増加を目指し、国民民主党は「最低保障年金制度の導入」によって、将来の不安を減らそうと提案しました。
こうした政策の方向性は評価されていますが、現場の声はどこか冷ややかです。
「選挙前だけ都合よく“支援します”と言われても、もう信じられない」と語る人は少なくありません。鈴木さんも「どうせ私たちは蚊帳の外。誰の話も自分ごとには聞こえない」と肩を落とします。
つまり、制度の“設計”だけでなく、“信頼”をどう築くかも重要なのです。数十年にわたって放置されてきた世代が、いま初めて耳を傾けてもらえると感じられるような対話の場づくりが欠かせません。
「今さらの就労支援」─当事者のため息と制度のミスマッチ
「正社員で働いた期間が短いので、将来の年金は月5万円ほど。就労支援も今さらです」──これは、鈴木さんの率直な言葉です。
現役世代だった頃に「正社員になれ」と言われ続け、ようやく安定をつかんだと思えば、会社が倒産したり工場が閉鎖されたり。そのたびに振り出しに戻され、年齢を重ねるごとに就労のチャンスは減っていきました。
政府は今、あらためて「正社員になりましょう」と言いますが、体調不良を抱える人や、長年非正規で働き続けてきた人にとって、それは現実的ではありません。
就職支援のプログラムを案内されたとしても、「面接の服を買うお金がない」「通勤ができるほどの体力がない」「職場に馴染む自信がない」と、そもそも入り口にすら立てない人が大勢いるのです。
つまり、現在の支援策は「できる人」を前提に設計されており、「もう頑張れない人」にとっては取り残される仕組みのまま。
本当に必要なのは、頑張らなくても生きられる制度。鈴木さんのような人に、「生きていてよかった」と感じてもらえる社会を、どう実現していくのかが問われています。
3.社会全体で考えるべき支援のあり方
「情報にたどり着けない人」への支援のハードル
現在の支援制度には、「知っている人しかたどり着けない」という大きな壁があります。
たとえば、就職支援セミナーや住宅支援制度、相談窓口の情報はインターネット上に多く存在しますが、それを見ることができない人も多いのです。
鈴木さんのようにスマホを質屋に預けざるを得ない生活を送っている人にとって、ネット検索や行政のウェブサイトの閲覧は、当たり前ではありません。
また、役所に足を運ぶには交通費が必要ですし、申請には印鑑や書類の用意といった煩雑な手続きがついて回ります。生活が不安定であればあるほど、こうした準備を整える余裕がなくなっていきます。
結果として、「支援の仕組みはあるけれど、届かない」現象が起きてしまうのです。
ある女性(44歳)は、都庁前の食料配布の列に並びながらこう話していました。「生活に困ってはいるけど、並ぶことに後ろめたさがあって…。自分が『支援を受けていい人』なのか、自信が持てないんです」。
情報が届かないだけでなく、心理的な壁も支援へのアクセスを妨げています。
支援の受け手に“自助”を求める仕組みの限界
政府の支援策は、どうしても「本人の努力」を前提に設計されがちです。履歴書を自分で書き、面接に行き、役所に申請する──こうした一連の行動が取れる人ならば、ある程度のサポートで立ち直れるかもしれません。
しかし、長期にわたり生活が困窮していた人にとっては、その一歩が極めて重く、難しいのです。
「自分でなんとかしてください」「動けば助けます」という仕組みは、ある意味で“選別的な支援”になっています。本当に困っている人ほど動けず、支援の輪の外に取り残されていく。
この構造そのものを見直さなければ、今後も多くの鈴木さんたちが支援にたどり着けないまま、孤立していくことになります。
支援とは、努力の先にある「ご褒美」ではなく、生きるための「土台」であるべきです。行政サービスを“利用する側の努力”に任せるのではなく、“迎えにいく支援”の発想が求められています。
声を上げにくい人々へ、支援側からの“アクセス”を
本当に困っている人ほど、「助けて」と言えません。支援の必要性を自覚していても、恥ずかしさや迷惑をかけたくないという思いから、声を上げることをためらってしまう人が多いのです。
食料配布の現場でも、そうした“沈黙”は目立ちました。
だからこそ、支援は“待つ”のではなく、“出向く”形が必要です。
たとえば、地域のスーパーやコンビニに支援情報のチラシを置く、バスの中吊り広告で制度を周知する、あるいは郵便で直接アプローチするなど、暮らしの中に自然と届く支援のかたちが求められています。
また、行政やNPOが連携し、自治体ごとに「生活困窮者を見守る担当者」を配置するような仕組みも効果的です。
SOSを出すことができない人のもとに、まず声をかけに行く。その最初の一歩が、支援と自立への橋渡しになるのです。
鈴木さんのような存在を“見つけて支える”力が、今の社会には必要とされています。支援は制度だけでは完結しません。その制度が、本当に必要な人の手元に届くかどうか──そこに、私たち全員の責任があります。
まとめ
就職氷河期世代として社会に出た鈴木さんの歩みは、個人の失敗ではなく、時代が生んだ構造的な問題を映し出しています。
企業の倒産、派遣切り、体調の悪化――そのすべてが「自己責任」という言葉で片付けられてきた結果、支援制度にすら手が届かない人が今も多く取り残されています。
政府や自治体は支援策を次々に打ち出していますが、それを「知っている人」「動ける人」だけが利用できる状況では、不公平が広がるばかりです。
支援は申請主義ではなく、生活困窮者に寄り添う“伴走型”であるべきです。食料配布の列に並ぶ人々の静かな行列の背後には、誰にも頼れず声も上げられない「沈黙した困窮」が存在しているのです。
スマホを質屋に預けて生きる鈴木さんのような人にとって、支援が届くかどうかは「生きていけるかどうか」に直結します。そうした当事者にこそ、社会が“先に手を差し伸べる”仕組みをつくっていく必要があります。
支援制度の整備だけでなく、それをどう届けるか──。その視点が、次の30年を決めていく鍵になるはずです。
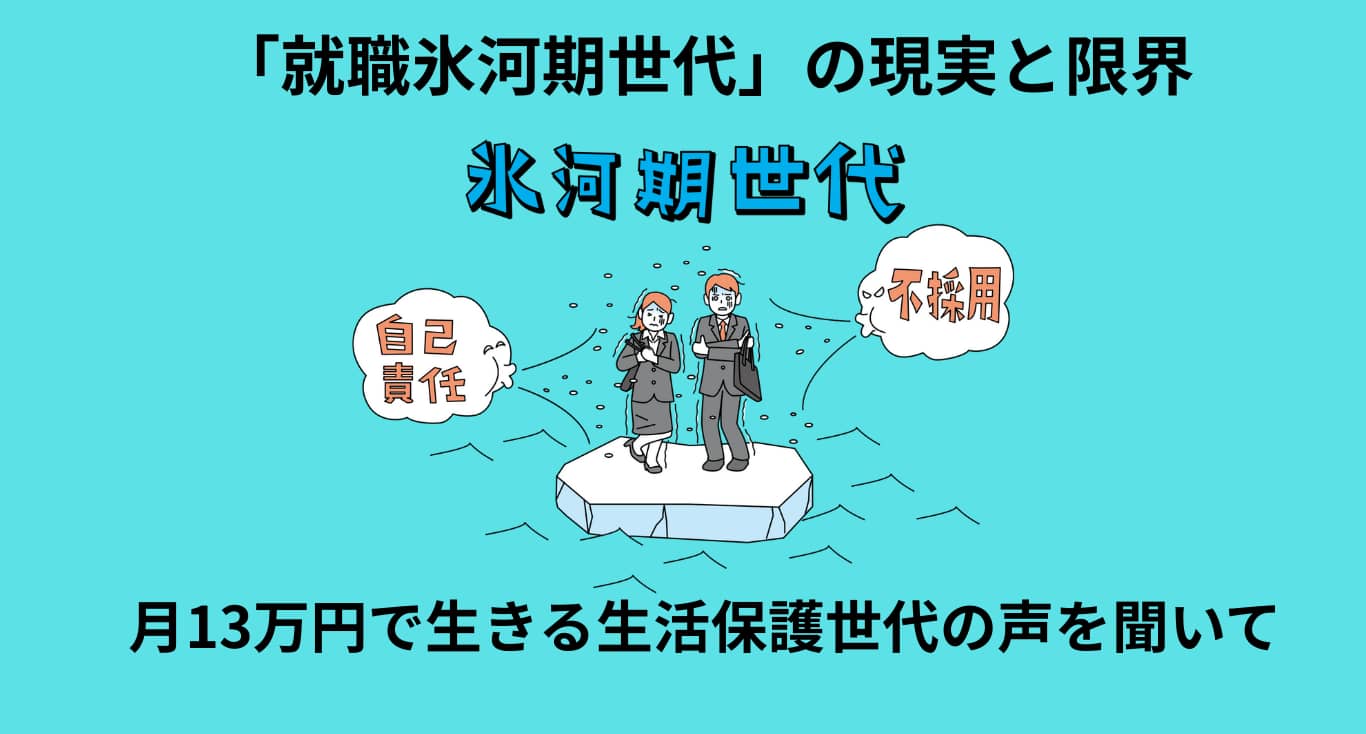
コメント