高市早苗内閣の発足直後、日本テレビのニュースで「不支持18%」と表示されていたにもかかわらず、折れ線グラフが“30%台に見える位置”に描かれていた問題。
これに「おかしいやん!」と生放送で苦言を呈したのが、保守論客として知られる ほんこん さんです。
SNSでは「印象操作では?」「テレビ大丈夫?」と批判が瞬く間に拡散。
今、特に若者層で高まる “テレビ不信” の背景を、視聴者の目線で整理します!
はじめに
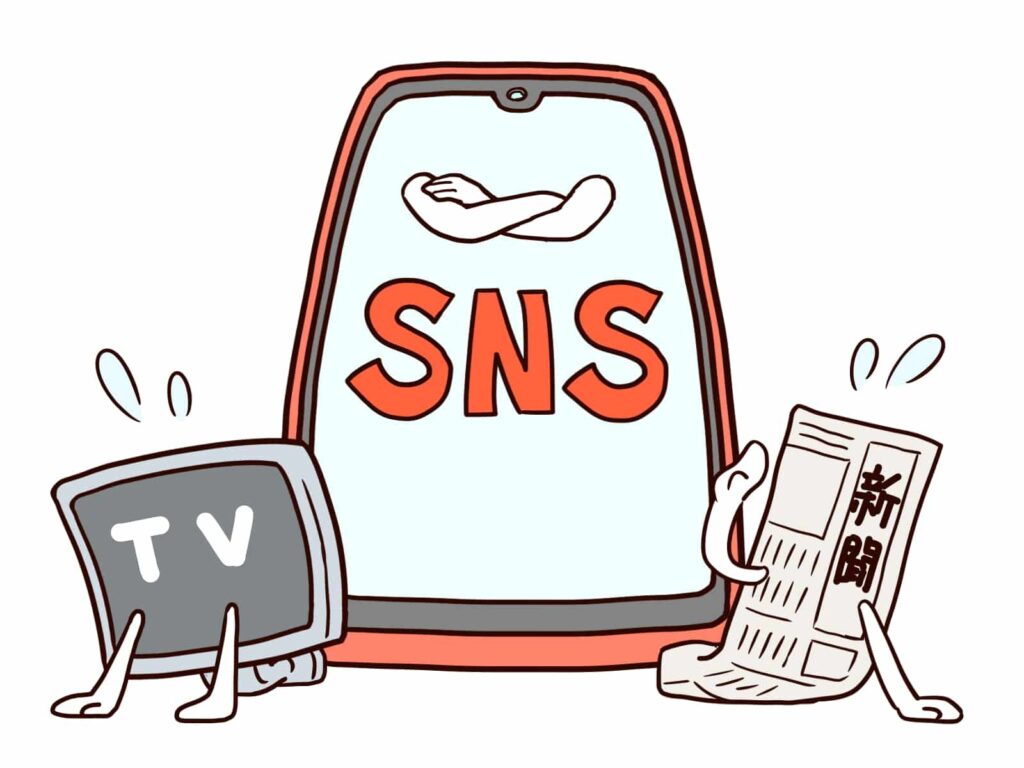
若者とテレビ報道の関係性
かつてテレビは、家庭における圧倒的な情報源でした。しかし、今の若者にとってテレビは「数ある情報源のひとつ」に過ぎません。
スマホを開けば、ニュース記事だけでなく、一般の人が投稿した現場の映像や、専門家が直接発信する解説にもすぐアクセスできます。
例えば政治ニュースを見ても、「テレビがそう言っていたから」と受け入れるのではなく、「本当にそうなのか?」とSNSで検索し、異なる意見や追加情報を確認しながら判断するのが当たり前になっています。こうした行動は、テレビの報じ方に違和感を覚えたとき、特に顕著に表れます。
SNS時代のメディアへの疑問
最近でも、内閣支持率のグラフが誤った位置に表示されていたテレビ報道がネットで瞬時に指摘され、SNS上で広く議論を呼びました。
また、ニュース映像の角度や演出が「不安を煽っているのでは?」といった批判を受けることもあります。
若者は、単なる情報の受け手ではなく、メディアを監視し、間違いを共有し、意図を読み解こうとします。
事実を自分で確かめられる環境が整った今、情報の発信側に対して「正確さ」と「誠実さ」がより強く求められているのです。
1.テレビ報道への違和感の広がり
支持率グラフの誤表示と拡散する不信感
テレビ報道への違和感が特に顕著になったのは、内閣支持率に関するニュースでした。
不支持が18%と表示されているのに、実際のグラフの折れ線は30%台に見える位置に描かれていたというものです。
視聴者は一瞬で違和感を抱き、SNSで画面を撮影した画像がすぐさま共有されました。
「間違えました」で済ませるには影響が大きく、若者は「間違いなのか、印象を操作したかったのか」と疑いの目を向けざるを得ません。
特に政治の話題では、小さな数字のズレが受け手の印象を大きく左右するため、情報に対する信頼性が一気に揺らぎます。
映像演出がもたらす印象操作の指摘
また、ニュース番組で使われる映像演出に対する批判も増えています。
たとえば、首相官邸での記念撮影が「斜め」に映されていた場面では、「不安を煽りすぎでは?」という指摘が相次ぎました。
映像の角度は視聴者の感情に影響を与えやすく、わずかな工夫で「安定していない」「危機感がある」といった雰囲気を作ることができます。
若者はその違和感を見逃しません。SNSにはすぐさま「映像が傾いていたのはなぜ?」「意図があるように見える」という投稿が並び、テレビの演出に対する警戒心が高まっています。
SNSで可視化される批判と検証文化の台頭
こうした問題が起きると、テレビの画面をスマホで撮影した写真や動画が一気に拡散され、視聴者同士が「本当のところ」を検証し始めます。
テレビ側が訂正や説明を加えるより早く、SNS上では事実の切り分けが進み、疑問点が共有されていくのです。
これまで「テレビで報じられたから正しい」とされていた時代は、すでに過去のものとなりつつあります。
若者にとって、情報は与えられるものではなく、自分で確かめる対象へと変化しました。そして、検証すればするほど、テレビ報道に対する違和感は拡大し続けています。
2.それでもテレビが持つ重要な役割

災害・緊急報道における即時性と信頼
テレビが現代においても強い信頼を保っている大きな理由のひとつが、災害や緊急事態への対応力です。
地震速報や津波警報は、テレビをつけた瞬間に情報が更新され、画面や音声で危険を知らせてくれます。
SNSでも情報は流れますが、真偽が混在し、誤った投稿が広がることも少なくありません。
一方テレビは、国や自治体などの公式発表をもとに素早くまとめ、視聴者へ確かな情報を届けます。
実際に、突然の地震でスマホが圏外になってしまい、テレビの速報で避難行動ができたという体験談も聞かれます。誰もが不安に包まれる瞬間、画面上の情報に安心感を覚える人は少なくないのです。
専門家解説や調査報道の社会的意義
もう一つ重要なのは、複雑な出来事をわかりやすく伝える能力です。
政治や経済の話題は、専門的な言葉が多く、背景事情が見えにくいもの。
テレビでは、経験豊富な専門家が解説することで、「結局どういうことなのか」を視聴者が理解できる形にしてくれます。
また、テレビ局にはジャーナリストが在籍し、現場に足を運んで問題を掘り下げる調査報道の文化があります。
SNSでは個人が重要な指摘をする場合もありますが、裏取りや責任範囲の点で限界があるため、組織的な調査力を持つテレビには依然強い期待が寄せられています。
広範な情報伝達力が果たす公共性
さらにテレビは、国民の多くに同時に情報を届けられる「公共性」を担っています。
たとえば選挙の開票速報や政府の緊急会見は、チャンネルを回せばどこでも視聴でき、年齢や居住地を問わず平等に届けられます。
アプリの操作が難しい高齢者や、SNSの使い方を知らない人にとって、テレビは今も生活に不可欠な存在です。
またニュース番組は、視聴者が関心を持っていないテーマも取り上げ、「知るきっかけ」を提供してくれます。興味が偏りやすいネット社会で、多くの話題に触れられるテレビの役割は決して小さくありません。
このように、若者を中心にテレビ批判の声は強まっている一方で、テレビには社会全体の安全と理解を支える力がまだ強く残っているのです。
3.テレビとSNSの共存に向けて
多視点と俯瞰性を両立する情報環境へ
ここまで見てきたように、テレビは「全体像を素早くつかむ」点で強く、SNSは「現場の声を細かく拾う」点で優れています。
両者の良さをつなげる工夫が進めば、視聴者はこれまでより立体的にニュースを理解できます。
たとえば選挙特番なら、テレビは開票状況や主要争点を地図や表で一望できる形にまとめ、同時に公式サイトや記者会見のフル映像、候補者の公開討論のアーカイブへ飛べるQRコードを画面に表示します。
視聴者はテレビで全体の流れをつかみつつ、スマホで一次情報にアクセスして、自分の関心領域を深掘りできるわけです。
災害報道でも同じ発想が役立ちます。
テレビは避難情報やライフラインの復旧状況を整理して示し、画面の片隅に自治体の発表、河川カメラ、交通情報のリンク集を常設表示します。
現地から届くSNSの投稿は、そのまま流すのではなく、撮影時刻と場所の確認をしたうえで「被災状況の一例」とラベルを付けて紹介する。
テレビが俯瞰を、SNSが多視点を補い合うことで、視聴者は「今、どこで何が起きているか」を誤解なく把握できるようになります。
若者が求めているのは、誰かの結論ではなく、判断に必要な材料が一式そろった“ハブ”です。
テレビがその役割を担い、SNSが個別の視点を提供する――この分業が進めば、情報との向き合い方はもっと健全になります。
誘導しない報道姿勢と透明性の必要性
共存を実現するうえで、最も信頼に効くのは「どう編集したか」を隠さない姿勢です。
具体的には、グラフなら縦軸や基準値、データの出典を画面とWeb記事の両方で明示し、映像なら編集の意図が伝わるように「再現」「過去映像」「イメージ」の表示を徹底する。
コメントやテロップでは、事実と推測をはっきり分け、「事実」「見解」「予測」といったタグを付けて区別します。
番組のWebページには使用資料の一覧、統計の原データ、カットした質疑の全記録を置き、ミスがあれば訂正履歴を残す。
たとえ手間がかかっても、こうした透明性は“印象操作ではない”ことを証明し、若者の疑いを静かにほどいていきます。
視聴者側の参加も大切です。放送中に誤りや不明点が見つかったとき、番組が用意する専用フォームやSNSの公式アカウントで指摘でき、短時間で訂正・追記が掲出される仕組みが望まれます。
たとえばニュースの「続報カード」を用意し、放送後に更新があればプッシュ通知や番組サイトの上部に反映する。
視聴者は“見っぱなし”ではなく、更新された情報で判断をアップデートできます。こうした往復運動が当たり前になれば、テレビは「一方通行の装置」から「検証可能な公共インフラ」へと印象を変えていくでしょう。
若者が本当に欲しているのは、結論を押し付けない報じ方と、後からでも確認できる透明な足跡です。
まとめ
若者は、テレビの報じ方に違和感を覚えると、SNSで別の視点や一次情報にあたり、自分の頭で確かめる習慣を身につけています。
支持率グラフの見せ方や映像の角度といった“印象を左右する演出”は、瞬時に撮影・共有され、誤りや偏りは可視化されます。
一方で、テレビには災害時の即時性、調査報道や専門家解説の厚み、全国へ同時に届ける公共性という強みが確かにあります。
だからこそ、両者は対立ではなく分業がふさわしく、テレビはデータ出典や編集意図の明示、訂正履歴の公開など透明性を高め、SNSは現場の多視点や当事者の声を提供する“拡張レンズ”として機能するのが望ましいと思います。
選択肢を示すテレビと、深掘りを助けるSNS――その組み合わせが、誰にとっても誤解の少ない情報環境をつくります。
結論を押し付けず、判断材料を丁寧に並べる姿勢こそが、揺らいだ信頼を取り戻す近道であり、私たちの情報との向き合い方を次の段階へ進めてくれるでしょう。
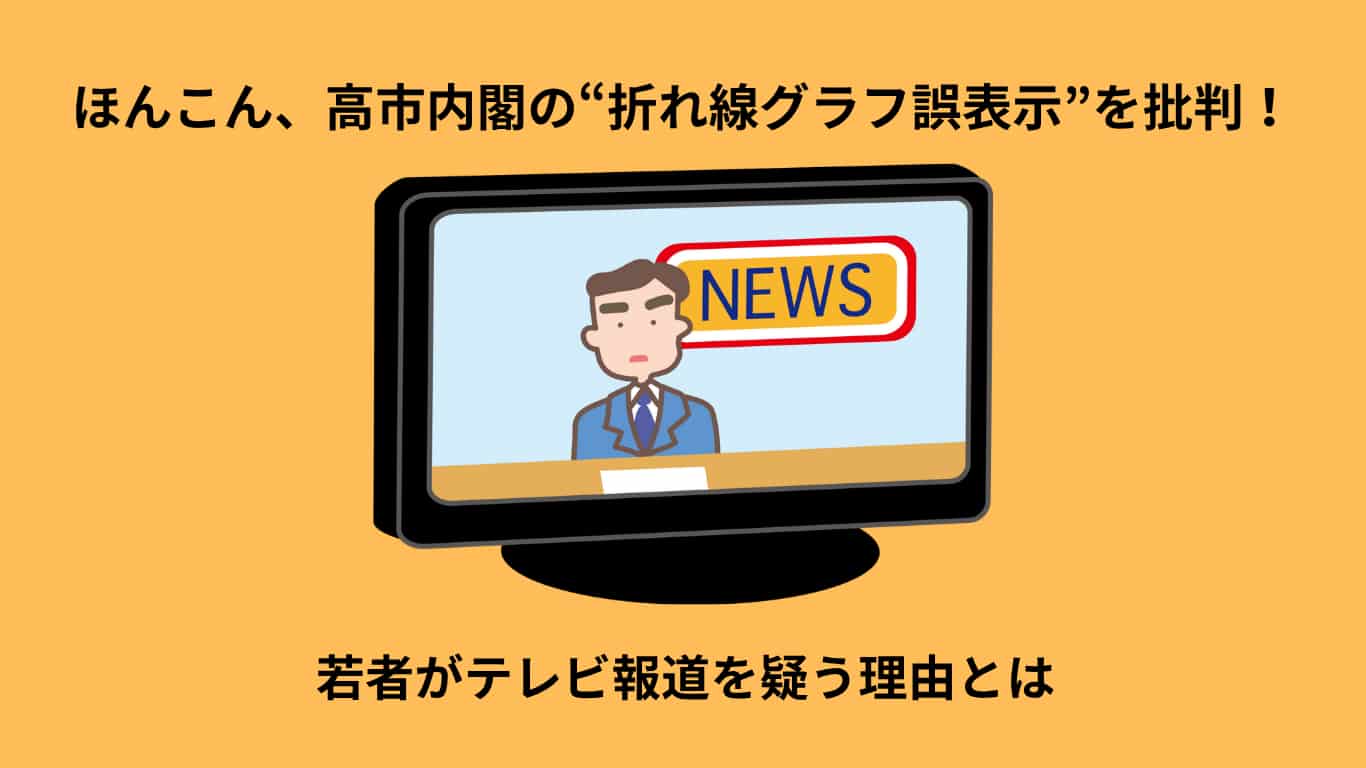
コメント