世界陸上2025東京大会で大きな話題となったのが、男子1500m準決勝で五輪王者コール・ホッカー選手が「妨害行為」で失格となった一件です。
一方で、男子3000m障害決勝では日本の三浦龍司選手が明らかな接触を受けて体勢を崩したにもかかわらず、相手選手は失格とならずレースは成立。この判定の違いに、多くのファンや視聴者が疑問を抱きました。
本記事では、世界陸連の抗議制度や過去の有名な事例を交えながら、両ケースの背景と判定の分かれ目について分かりやすく解説します。
はじめに

世界陸上で起きた判定騒動
2025年の東京世界陸上では、男子1500m準決勝で五輪王者コール・ホッカー選手が「妨害行為」で失格となり、大きな議論を呼びました。
ラスト100mで進路が狭い中を強引に抜け出そうとした際に他選手と接触し、結果として順位に影響を与えたと判定されたのです。
米国陸連が抗議を行ったものの棄却され、ホッカー選手は決勝進出を逃すことになりました。
一方、接触を受けた選手には救済措置が取られ、決勝進出が認められるという展開に。観客や視聴者からは「なぜ失格なのか」「抗議が通らなかった理由は?」と疑問の声も上がりました。
抗議制度が注目される理由
同じ大会の男子3000m障害決勝では、日本の三浦龍司選手がラストスパートの場面で前を走る選手に引っ張られるような動きを受けて体勢を崩しました。
映像を見ると「明らかな妨害」とも取れるシーンでしたが、相手選手は失格とならず、レース結果もそのまま確定しました。
この対比が多くの注目を集めたのは、抗議制度の有無や審判の判断基準によって結果が大きく変わる可能性があることを示しているからです。
陸上競技は接触や進路妨害が起きやすく、抗議制度が選手の運命を左右する場面は少なくありません。
私自身も「もし抗議があれば結果は違ったのでは…?」と感じました。そこで本記事では、世界陸連の抗議制度の仕組みや過去の事例を振り返り、今回のケースを比較しながら理解を深めていきます。
1.ホッカー失格の経緯
準決勝ラスト100mでの接触
男子1500m準決勝のラスト100メートル、五輪王者のコール・ホッカー選手は5〜6番手の位置からスパートを仕掛けました。
しかし進路は非常に狭く、左右を他の選手に挟まれる形。ホッカー選手はその隙間を強引に抜け出そうとし、すり抜ける際に肩や腕が他選手とぶつかる場面がありました。
ゴールラインを2位で通過し、本人も「決勝に行ける」と手応えを感じていた直後のことでした。
米国陸連の抗議と棄却
レース後しばらくして、大会側はホッカー選手に対し「妨害行為による失格」を通告しました。
接触によって他選手の走行が乱され、順位に影響が出たと判断されたのです。
米国陸連はすぐに抗議を提出し、「ホッカーの動きは意図的ではなく、レースの流れの中で避けられなかった」と主張しました。
しかし審判団は映像を確認したうえで抗議を棄却。「結果に影響を与えた」という基準に照らして妨害と認定された形です。この裁定に対し、米国陸連は「非常に失望した」と声明を発表しました。
救済で決勝進出した選手
一方で、接触によって不利益を被ったとされたのがドイツのロベルト・ファルケン選手です。彼は9位に終わりましたが、救済措置として繰り上げで決勝進出が認められました。
つまり、抗議そのものは退けられたものの、「妨害があった」との判断は残り、影響を受けた選手にはチャンスが与えられたのです。
このケースは「抗議があったからこそ映像が再検証され、救済が実行された」典型的な例として注目されました。
🕒 ホッカー失格・抗議の流れ(時系列)
1️⃣ レース本番(男子1500m準決勝)
- コール・ホッカー(米国)がラスト100mで狭い進路を強引に突破。
- その際、ロベルト・ファルケン(ドイツ)が接触の影響を受け順位を落とす。
- ホッカーは2位でゴール → 一旦は決勝進出を確信。
2️⃣ ドイツ陸連が抗議
- 「ファルケンが妨害を受けた」とドイツ陸連が抗議を提出。
- 審判団が映像を確認し、ホッカーの動きが「妨害」と認定される。
3️⃣ ホッカー失格が決定
- 審判団が公式に ホッカー失格処分 を発表。
- 影響を受けた ファルケンは救済で決勝進出 に。
4️⃣ 米国陸連が抗議
- 米国陸連が「失格は不当」と抗議。
- 主張:「ホッカーは故意ではなく、自然な競り合いの中で避けられなかった」
5️⃣ 抗議棄却 → 最終決定
ファルケン:救済で決勝進出
上訴審判団も含め審理 → 米国陸連の抗議は却下。
結果として、
ホッカー:失格 → 決勝進出ならず
2.三浦龍司選手のケース
3000m障害での接触シーン
男子3000m障害の決勝では、日本の三浦龍司選手がラストスパートをかけて順位を上げようとする場面で、前を走る選手の動きに巻き込まれる形となりました。
三浦選手の腕が引っ張られたように見え、一瞬大きくバランスを崩してしまいます。
観客からも「あれは妨害ではないか」という声が上がったほどで、映像でもはっきり確認できる場面でした。しかし、レースはそのまま続行され、三浦選手は崩れた体勢を立て直して完走しました。
この場面についてSNSなどで物議を醸しているが、三浦はレース後の取材で「特殊なところの1つ」と競技の特性だと強調。3000メートル障害は障害物を28回、水がたまった水濠を7回越える過酷な競技とあり「面白さも、難しさもある。最後の最後で出たのかな」と言及した。
日刊スポーツより
故意性と抗議の有無
この場面が失格につながらなかったのは、接触の故意性が明確ではなかったことが大きな理由です。
相手選手が意図的に妨害したと断定するのは難しく、自然な競り合いの一部と判断された可能性があります。
さらに、チームが正式に抗議を提出しなかった、あるいは抗議が却下された可能性も考えられます。
世界陸連のルールでは、抗議はレース結果が掲示されてから30分以内に提出しなければならず、ここで行動するかどうかが大きな分かれ道となります。
長距離・障害レース特有の判定
長距離や障害種目は接触が頻繁に起きるため、審判がすべてのケースを妨害と判定するわけではありません。
選手同士の位置取りや接触は「レースの一部」とみなされることも多く、失格処分は比較的限定的です。
特にハードルや水濠を越える障害レースでは、接触が避けられない場面が多く発生します。
三浦選手のケースも、その「競技特性」と「抗議の有無」が重なり、処分が下されなかった典型例といえるでしょう。
世界陸連(WA)はレース直後の16日午前1時過ぎの時点で、三浦の抗議は棄却されたと発表しています。
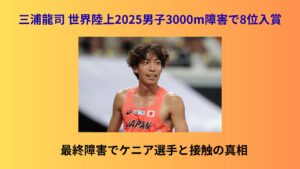
補足:準決勝と決勝で異なる抗議・救済の扱い
世界陸上の判定を考えるうえで大切なのが、「準決勝」と「決勝」というステージの違いです。ホッカー選手のケースは準決勝、三浦龍司選手のケースは決勝で起きたもので、この差が裁定の行方に影響している可能性があります。
準決勝の特徴(ホッカー選手のケース)
準決勝は「誰が決勝に進めるか」を決める大事なレースです。
このため、接触で順位に影響が出れば「決勝進出の権利」が左右されることになります。審判はより厳しく妨害を判定しやすく、影響を受けた選手に対しては「繰り上げ進出」という救済措置が適用されるのが一般的です。ホッカー選手の場合も、失格と同時にドイツのファルケン選手が救済されました。
決勝の特徴(三浦龍司選手のケース)
一方で決勝は順位やメダルが最終的に確定する舞台です。
この場合、救済で「次のラウンドへ」という措置は存在せず、審判が取れる判断は「相手選手の失格」か「結果をそのまま確定」の二択に絞られます。さらに、長距離や障害種目は接触が頻繁に起きるため、明確な故意や大きな順位変動がなければ失格処分は出にくい傾向にあります。三浦選手のケースも「自然な競り合い」とみなされ、相手選手は処分を受けませんでした。
準決勝と決勝の違いを比較
| レース段階 | 判定のポイント | 救済措置 |
|---|---|---|
| 準決勝 | 決勝進出権の有無に直結するため妨害に厳しい | 繰り上げ進出が可能 |
| 決勝 | 最終順位・メダルが確定するため慎重 | 基本は失格か結果確定の二択 |
このように、同じ「接触」でも準決勝と決勝では救済の余地や判定基準が異なり、それが今回の両ケースの違いを生んだ大きな要因となっています。
3.世界陸連の抗議制度と過去の事例
抗議の申請方法と制限時間
抗議(プロテスト)を出せるのは、選手本人ではなくチームリーダーなどの公式代表者です。
レース結果が掲示されてから原則30分以内に、専用の用紙で「種目・ラウンド」「選手名(ゼッケン)」「どの場面で何が起きたか」を簡潔に記して提出します
。証拠映像は大会側が管理しているため、代表者は“事実の指摘”に集中するのがコツです。
トラックでは接触やレーン侵害、リレーのゾーン違反、フィールドでは踏切・投擲のファウル判定などが典型的な抗議対象。
時間との勝負になるため、チームはレース直後から該当シーンの確認と方針決定を同時並行で進めます。
上訴審判団による最終判断
抗議はまず審判長(Referee)が審理し、映像・当事者確認を経て判断します。
この結論に不服がある場合は、上位機関の「上訴審判団(Jury of Appeal)」に上訴できます。こ
こが最終判断の場で、覆れば「失格撤回」や「救済(準決勝・決勝への繰り上げ、記録の回復)」などが適用されます。
判断基準は大きく二つ――①故意性(意図的か)、②結果への影響(順位や記録に明確な不利益が生じたか)。長距離や障害のように接触が日常的な種目では、同じ接触でも「レースの一部」とみなされやすく、処分は限定的になる傾向があります。
抗議で判定が覆った有名なケース
- 2012年ロンドン五輪・女子1500m:転倒選手に対し、抗議が認められて準決勝進出の救済。
- 2016年リオ五輪・女子5000m:接触転倒の2選手が抗議の結果、決勝進出を認可。
- 2019年ドーハ世界陸上・男子5000m:レーン逸脱で一度失格となった選手が、上訴で「意図なし・安全回避」と認定され撤回。
- 2021年東京五輪・女子1500m:接触で不利益を受けた選手に救済が適用。
いずれも共通するのは、チームが素早く抗議し、映像で「故意性」と「結果への影響」を説得的に示した点です。今回のホッカー選手と三浦選手の対照も、まさにこの枠組みの中で理解できます。
まとめ
ホッカー選手の失格は、狭い進路での接触が「順位に影響した」と認定され、米国陸連の抗議も棄却された一方で、影響を受けた選手には救済が適用されました。
対して三浦龍司選手のケースは、接触の故意性が不明確で、抗議の有無(または棄却)も相まって処分なしという結論に。
世界陸連の抗議制度は「30分以内の迅速な申請」「審判長→上訴審判団の二段階審理」「故意性と結果への影響」という軸で運用され、長距離・障害では接触が“競技の一部”とみなされやすい傾向があります。
結局のところ、同じ接触でも、映像で示せる因果関係とタイムリーな抗議の有無が運命を分ける――これが両ケースから見える現実です。

コメント